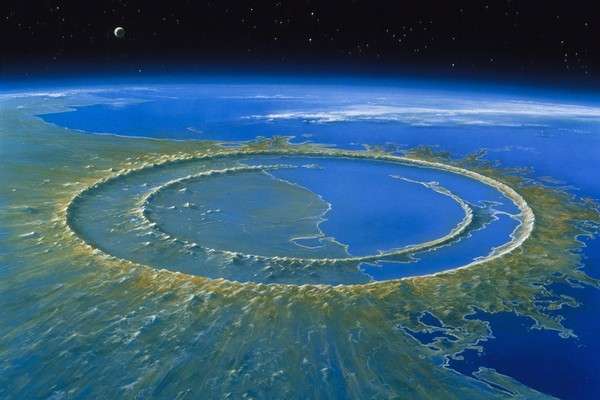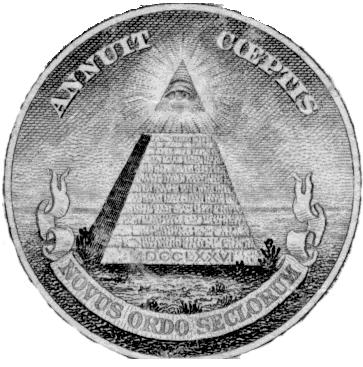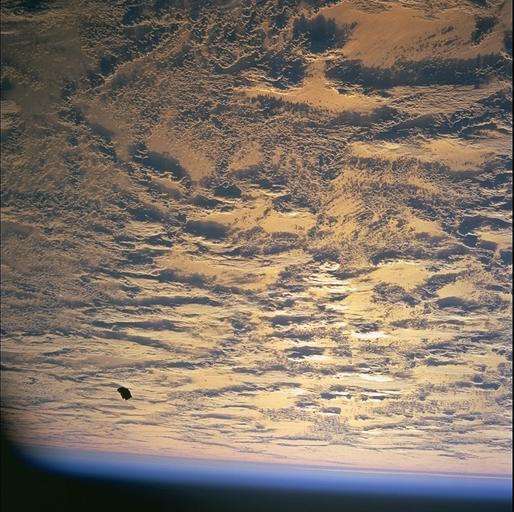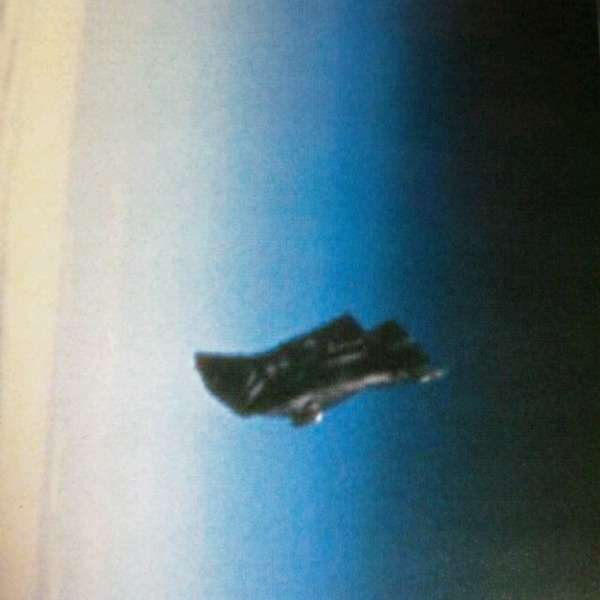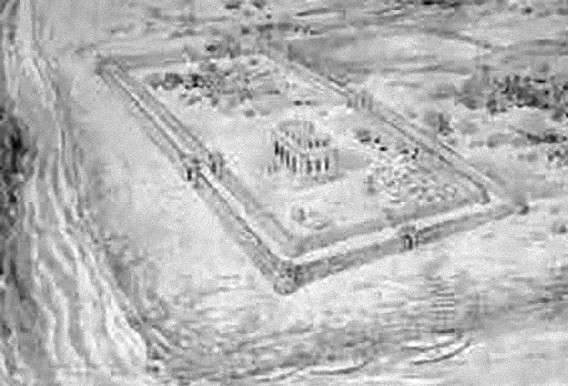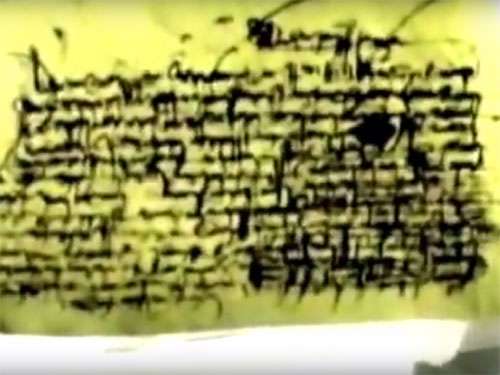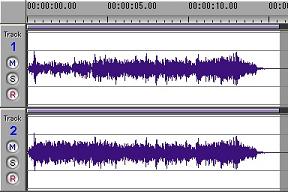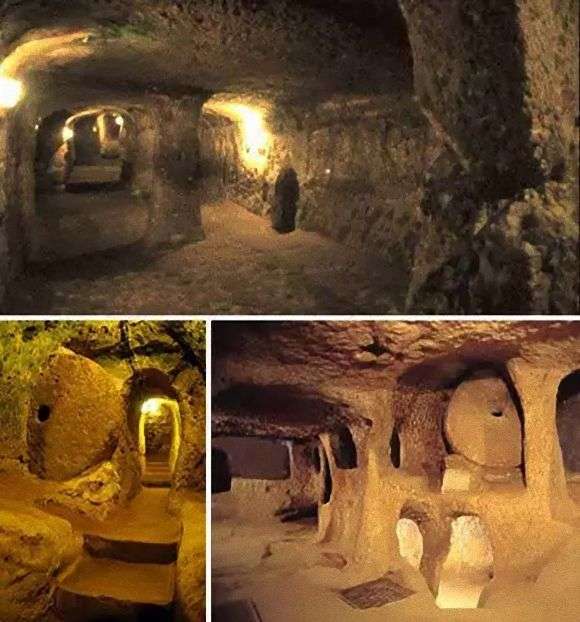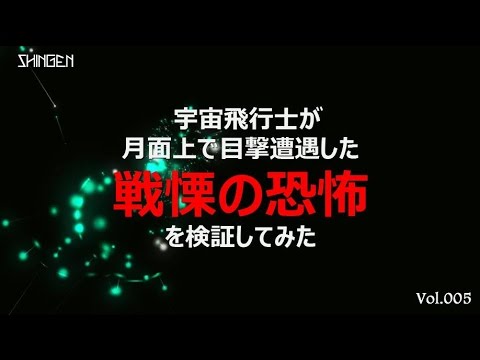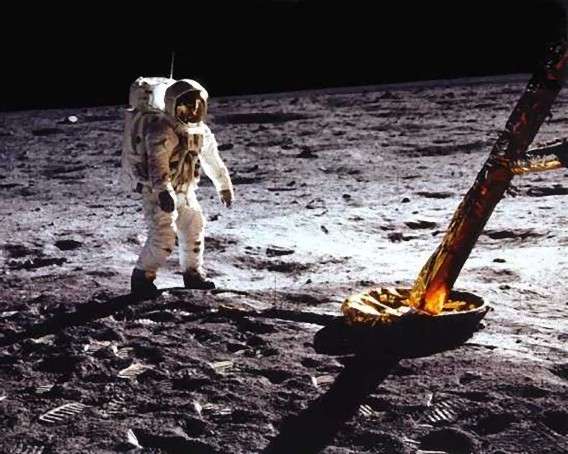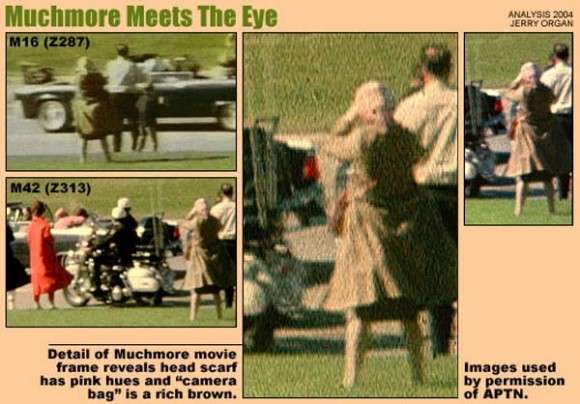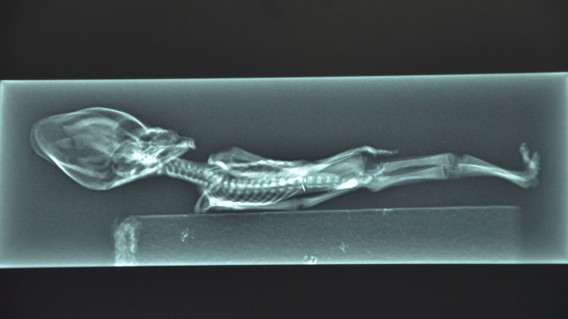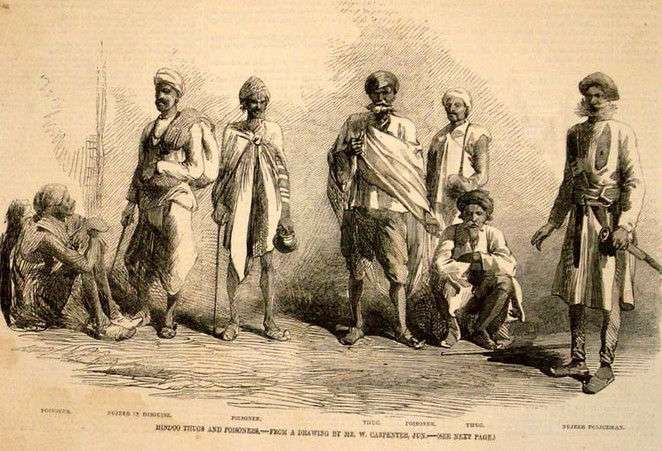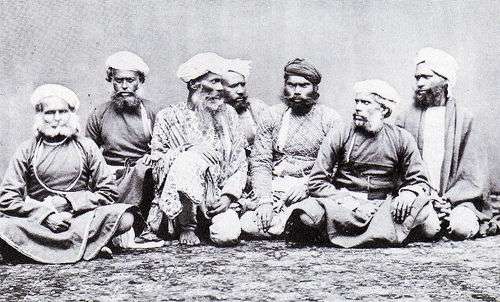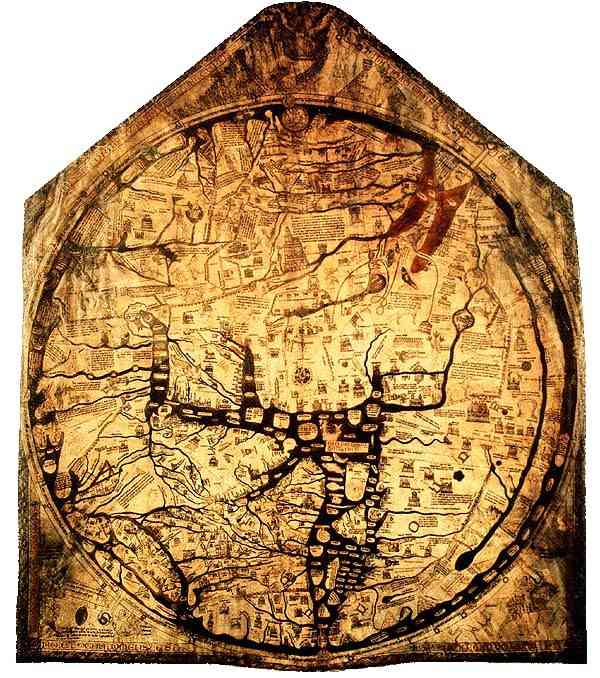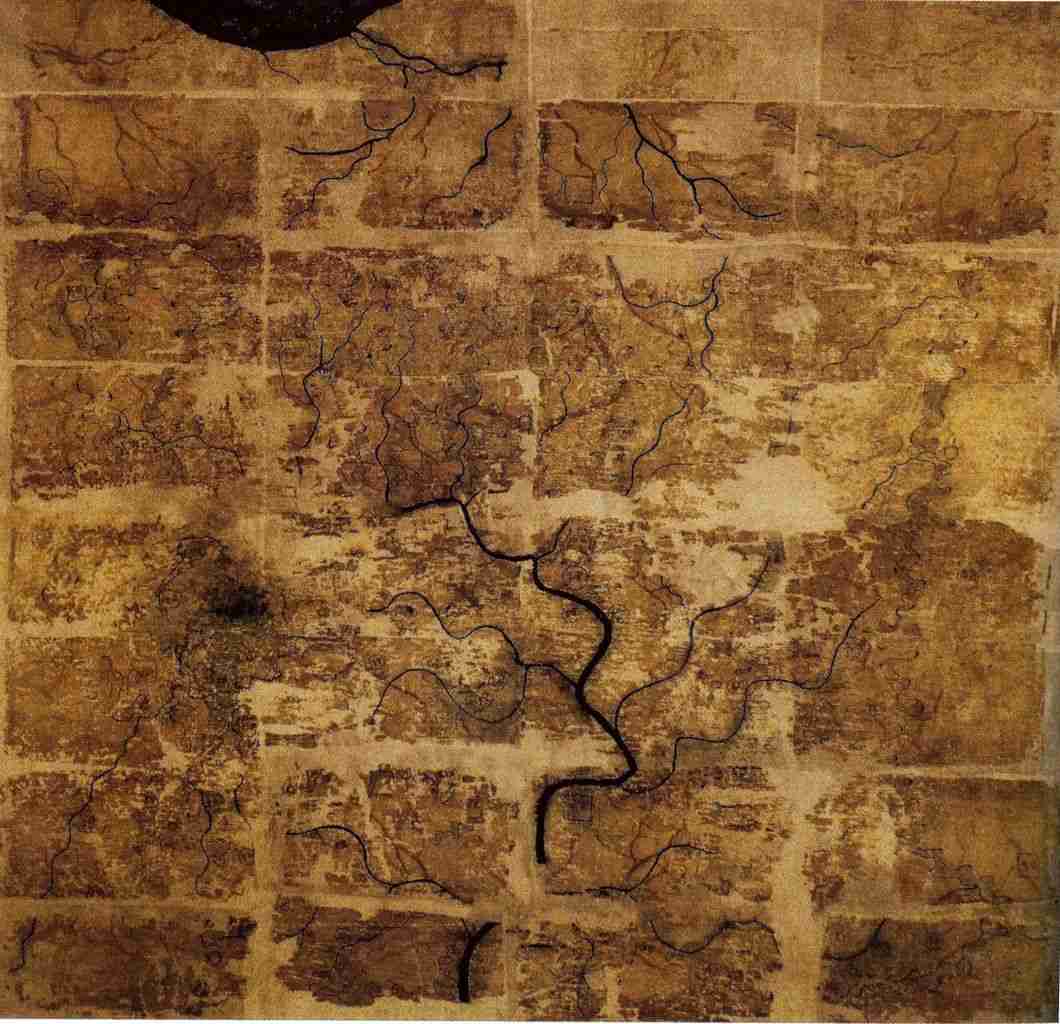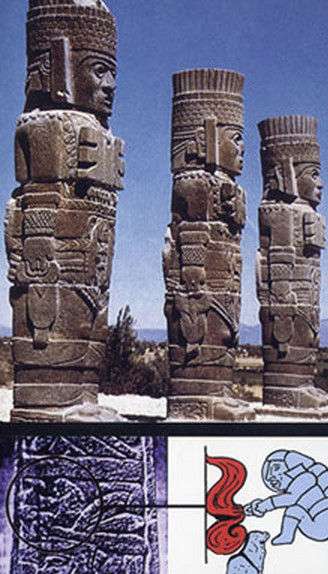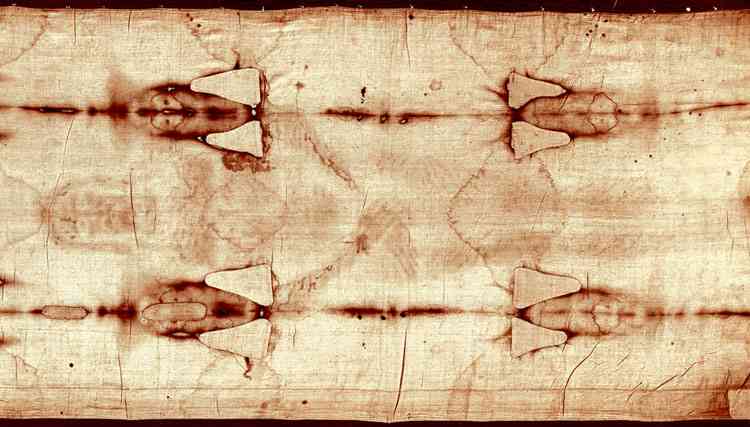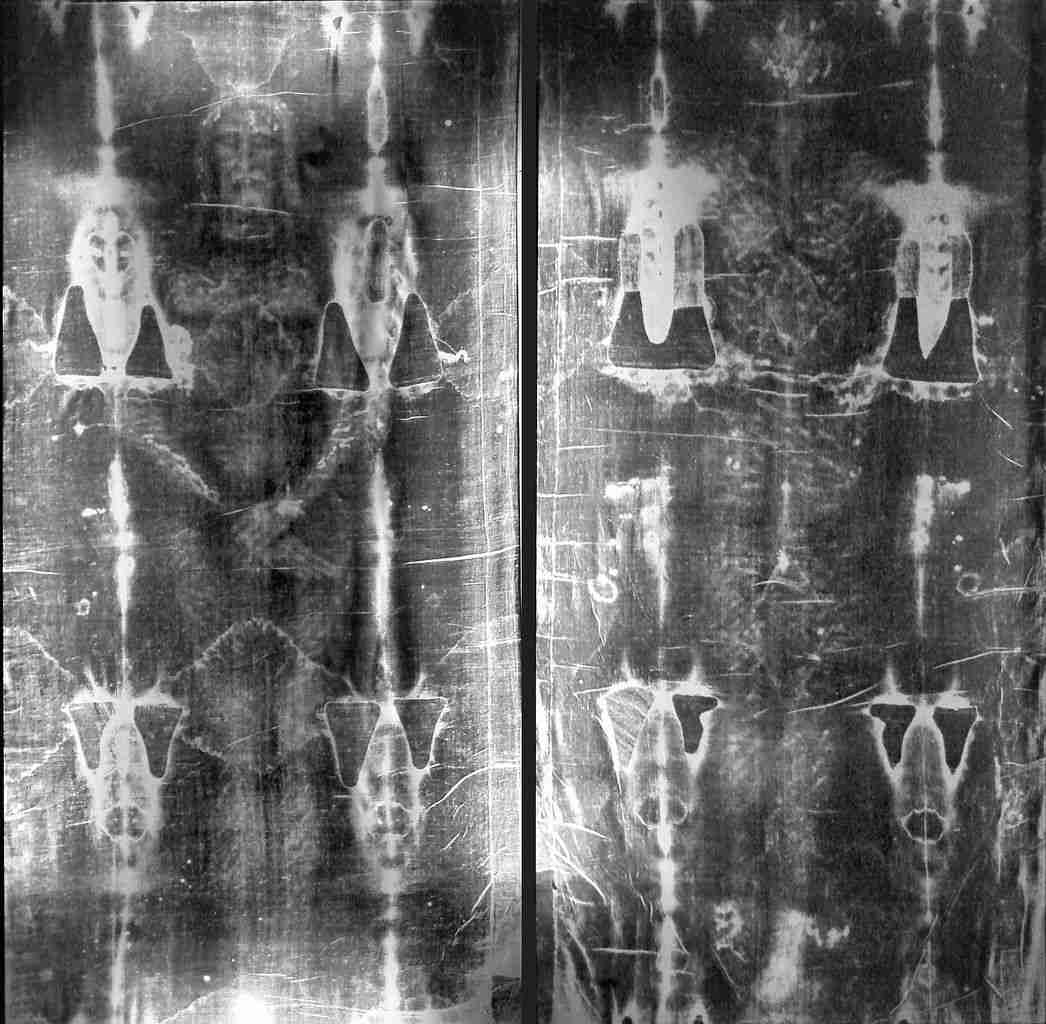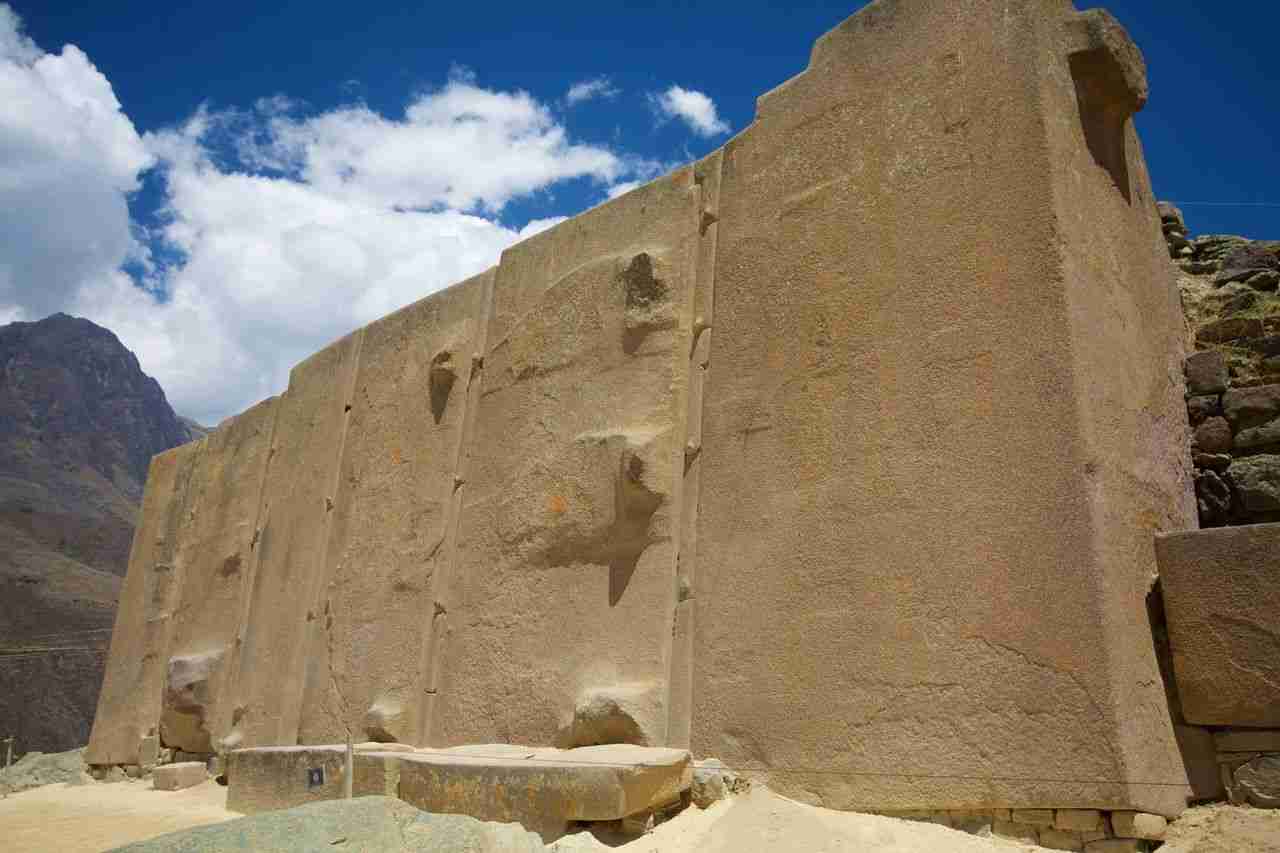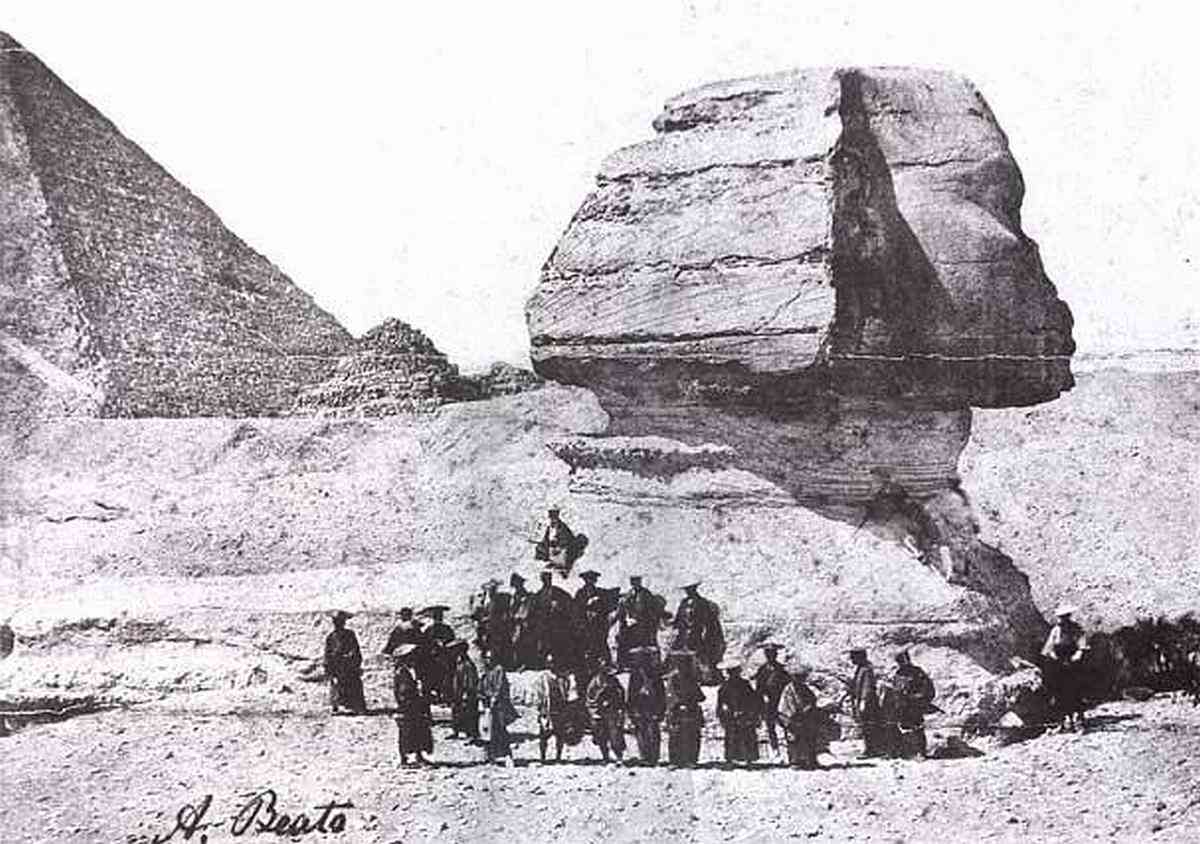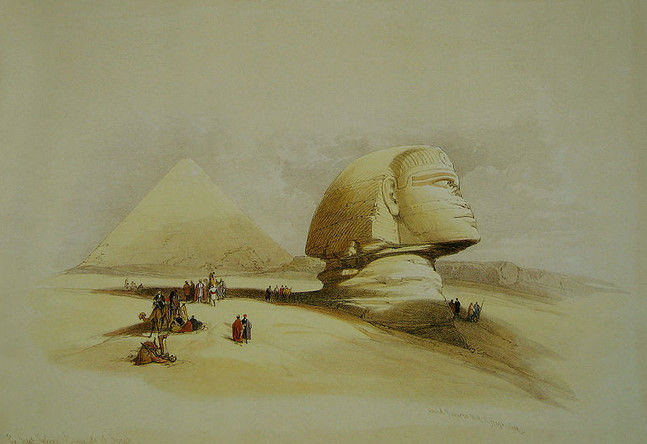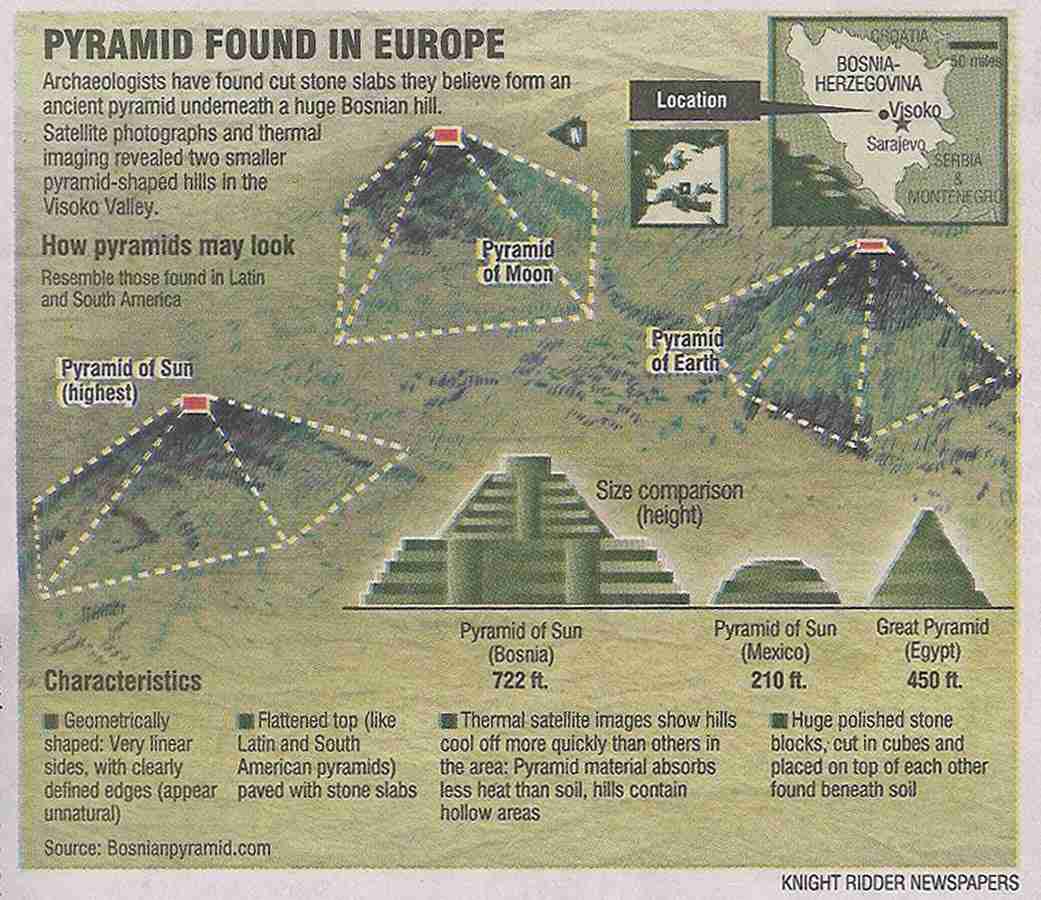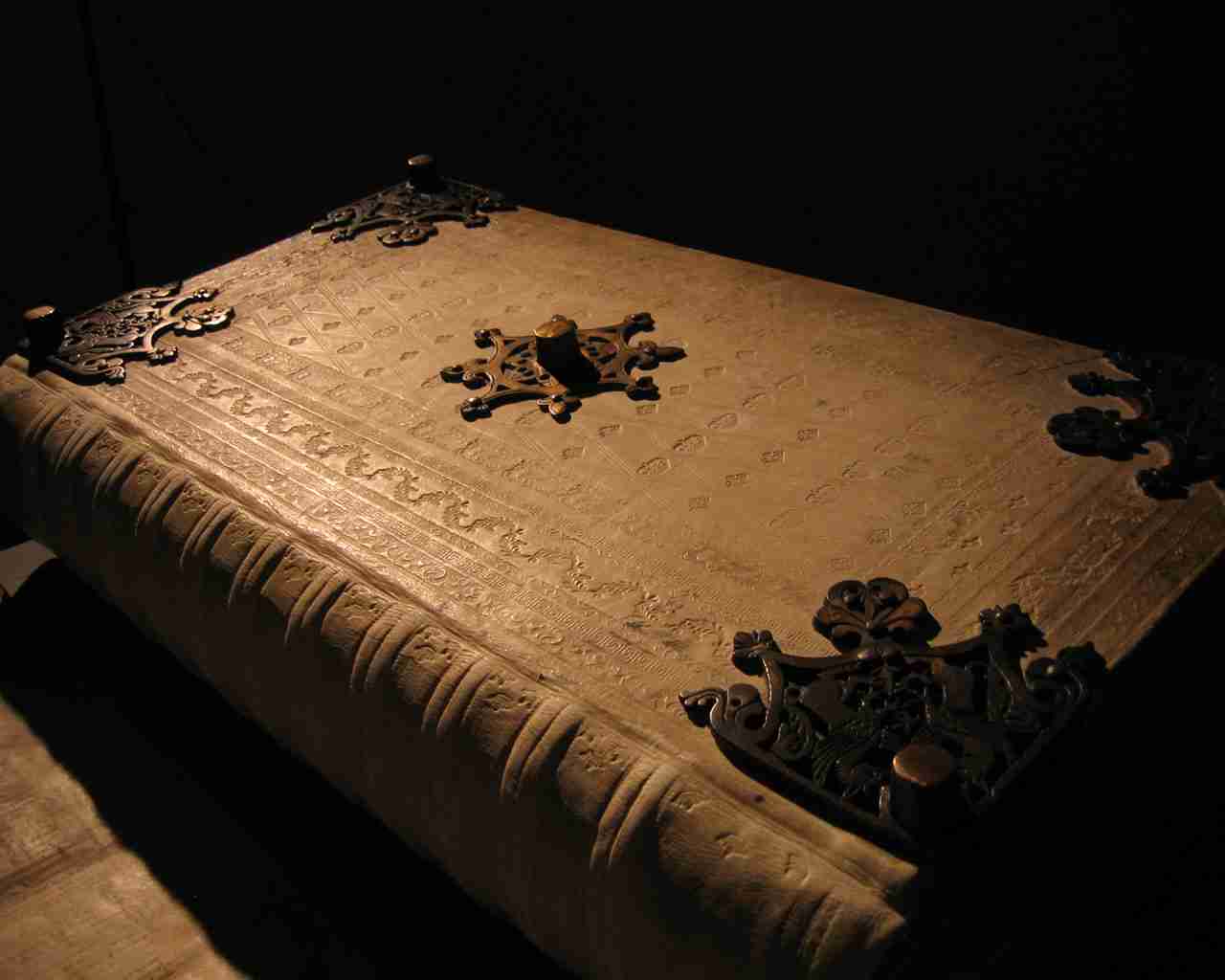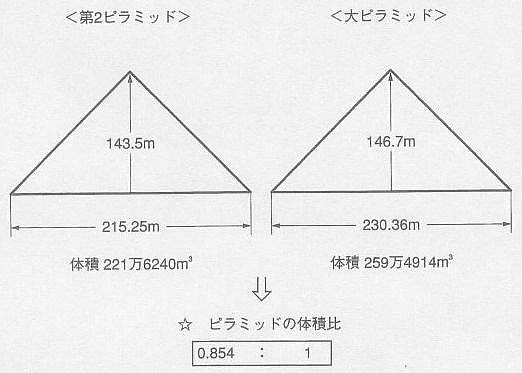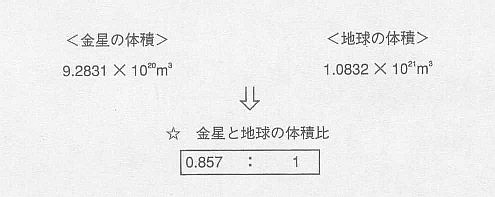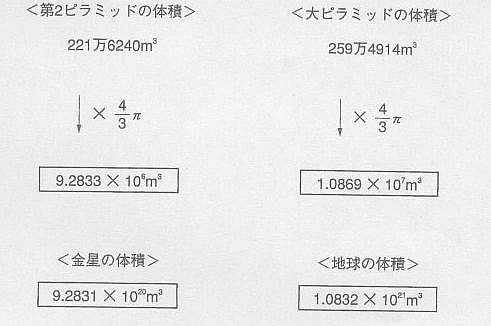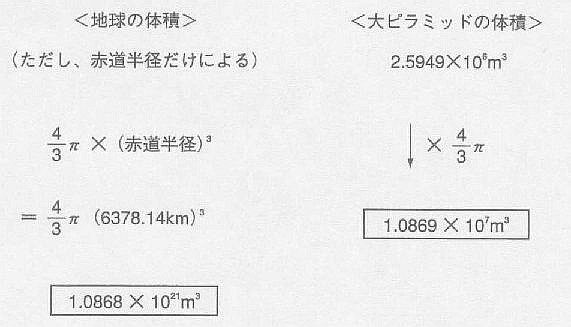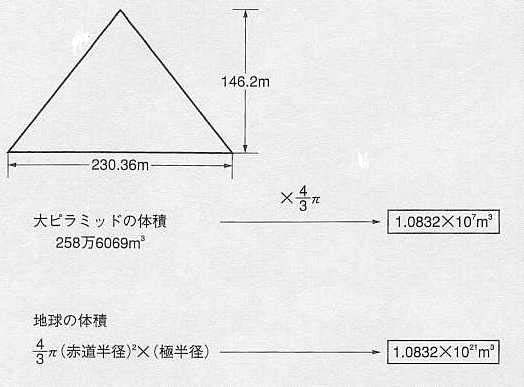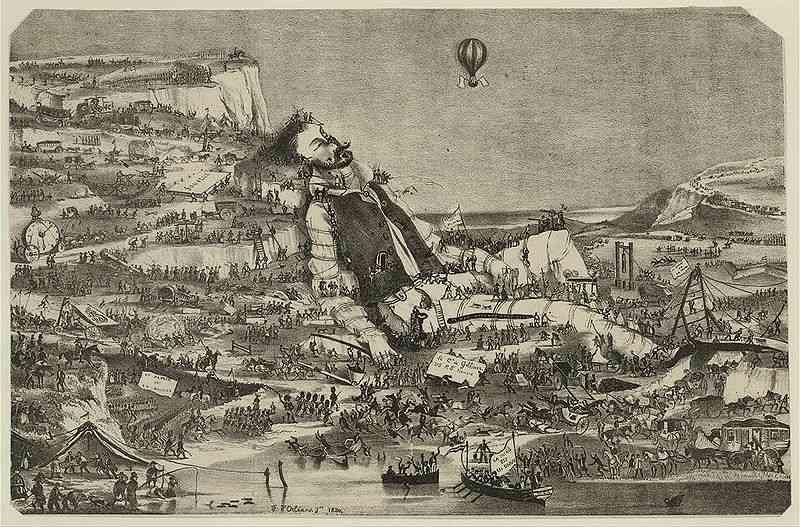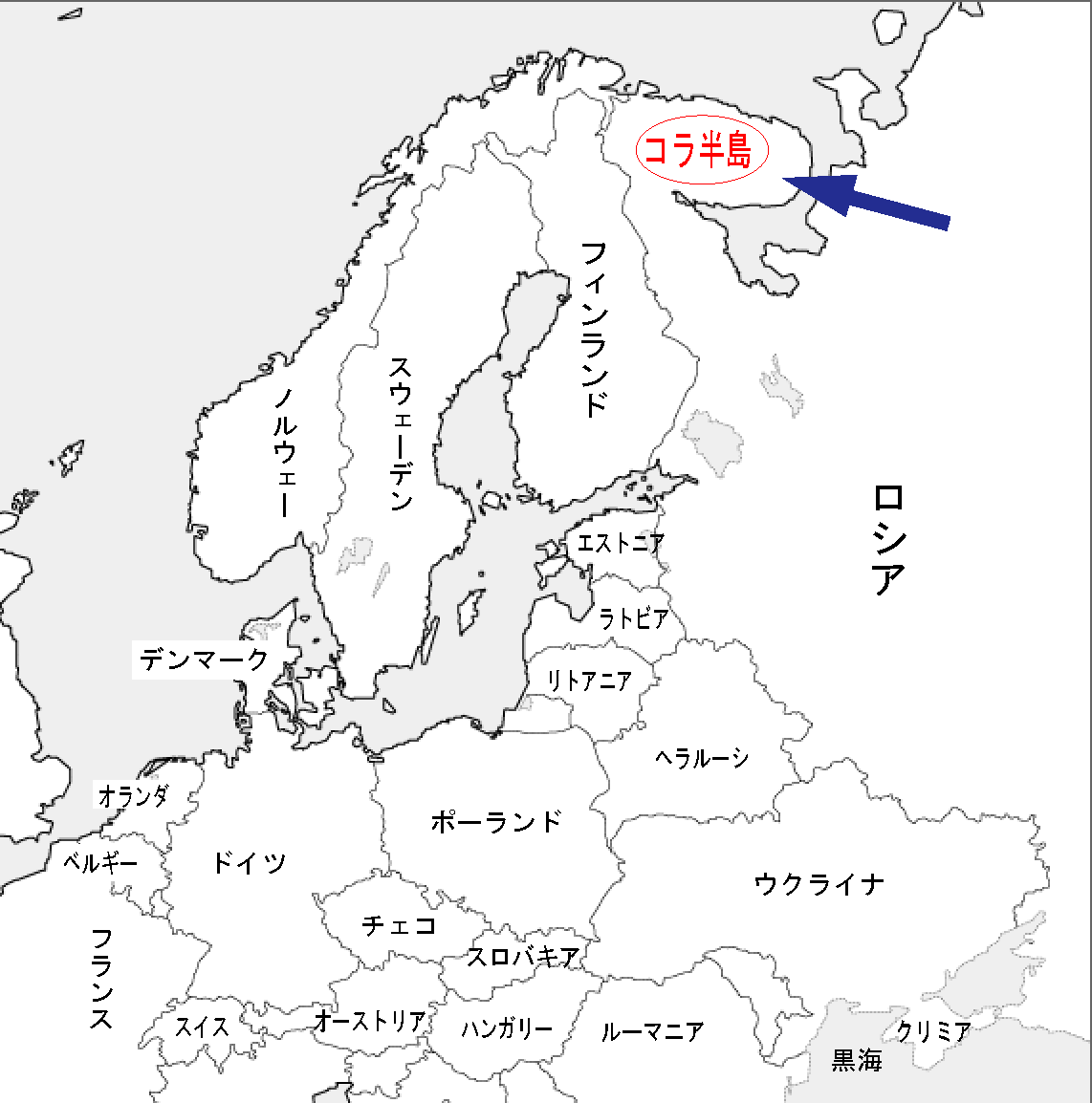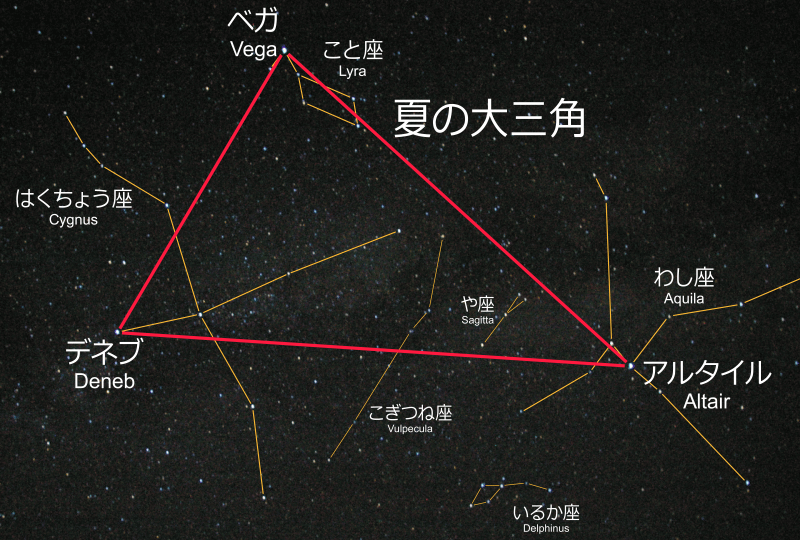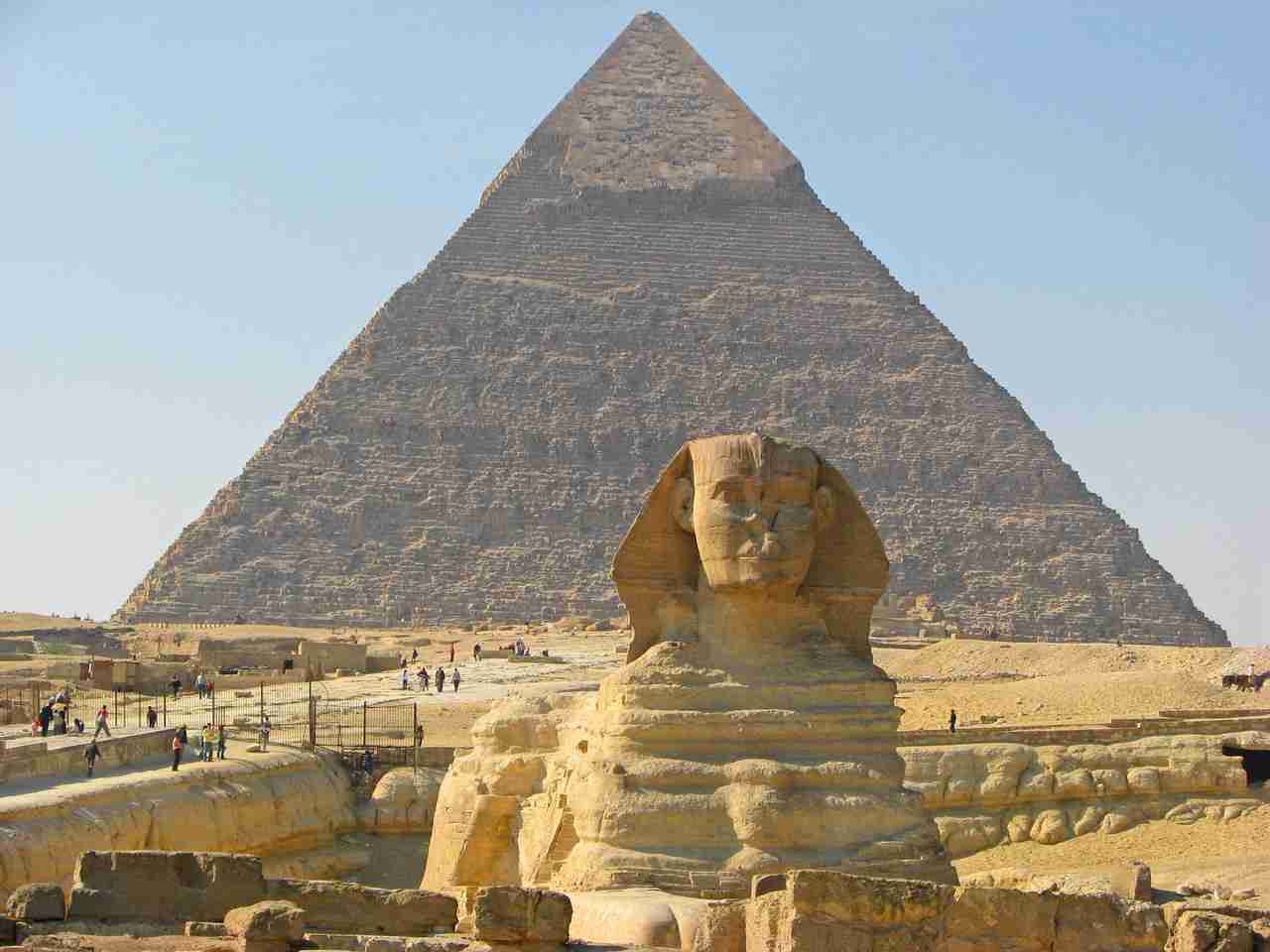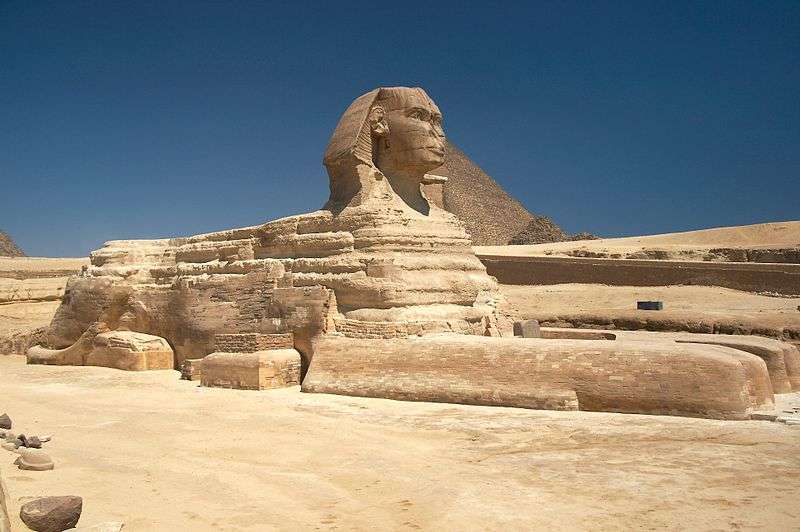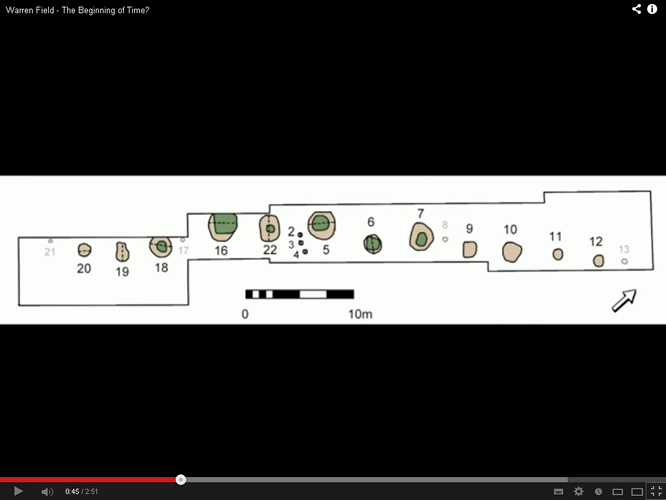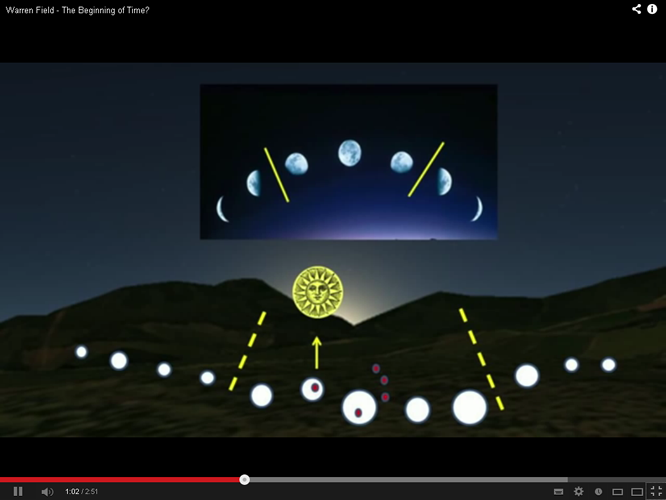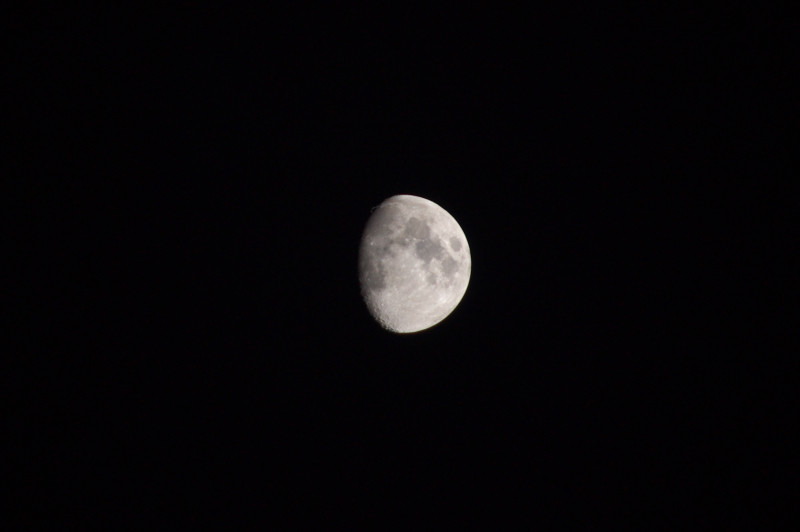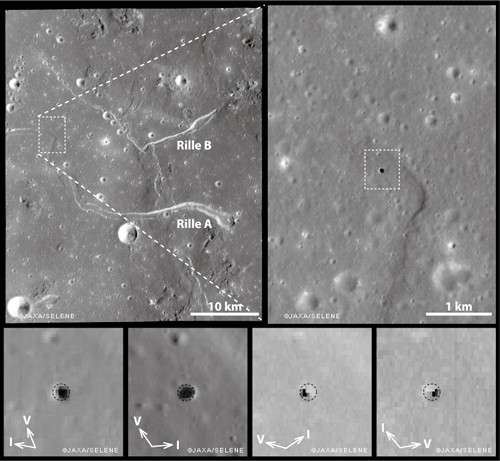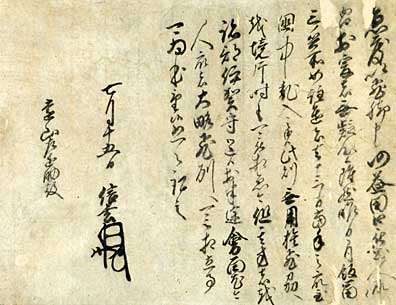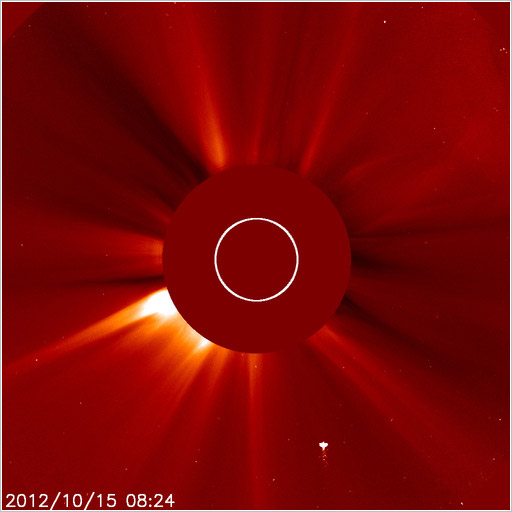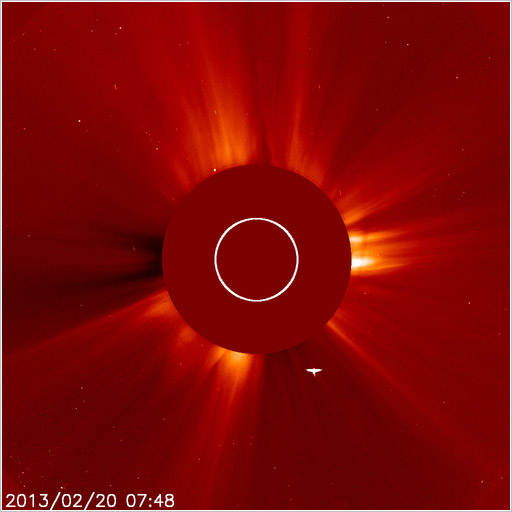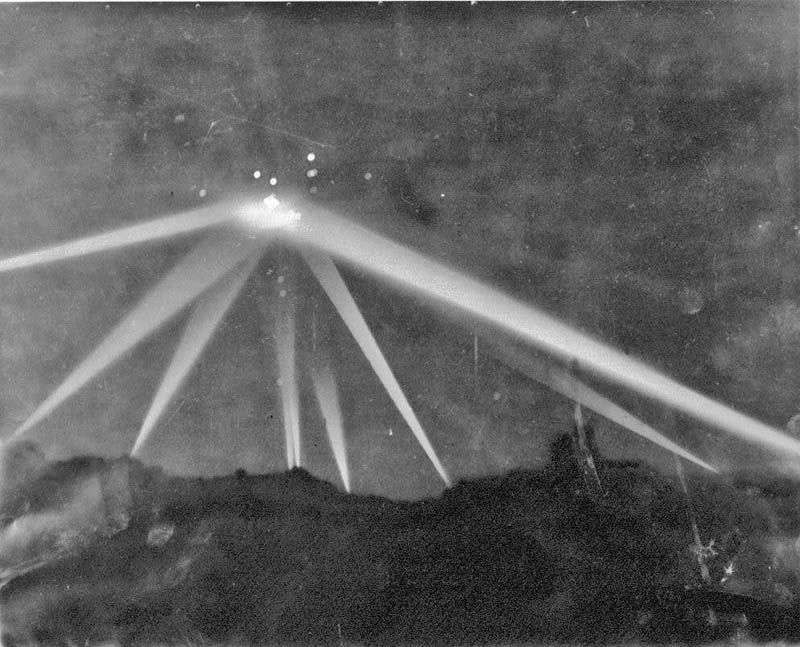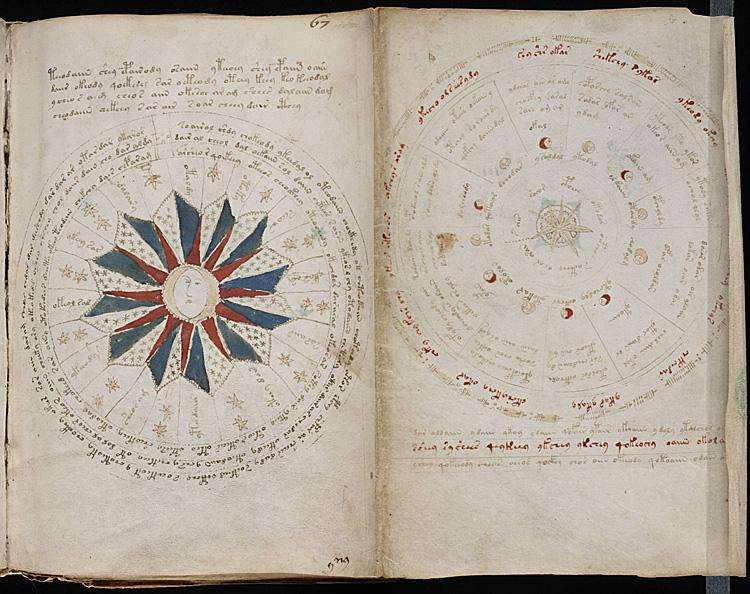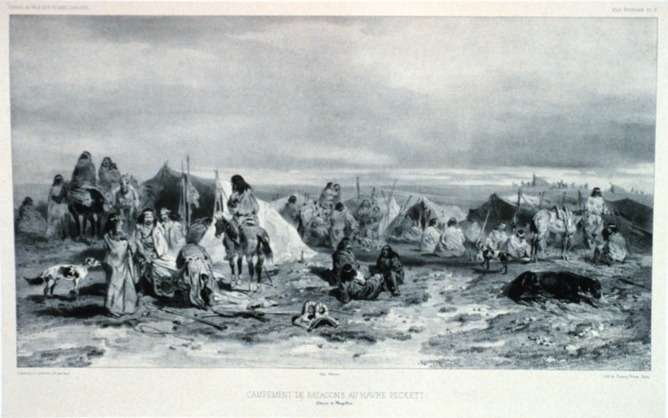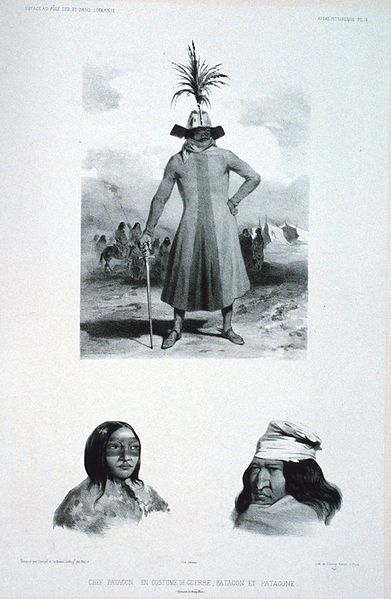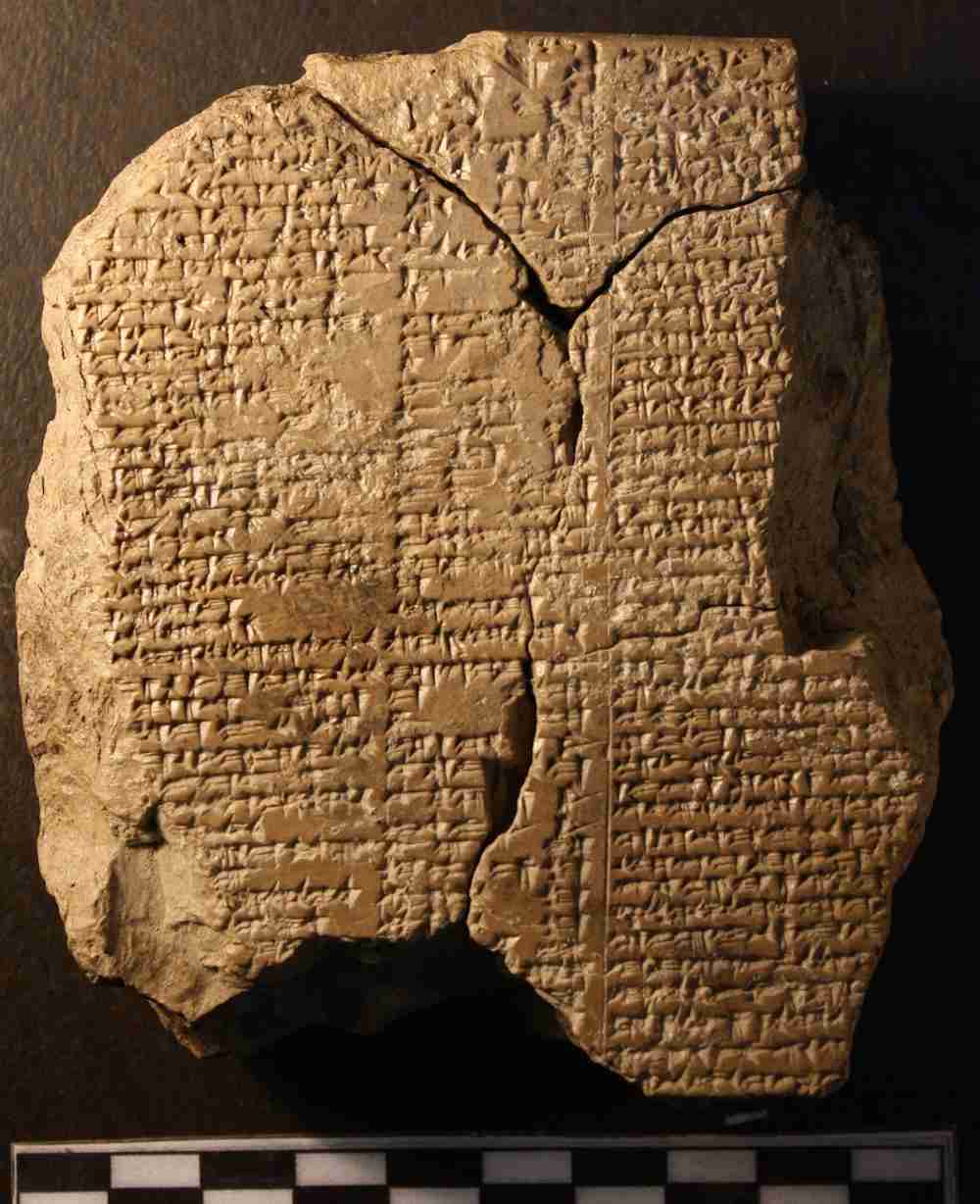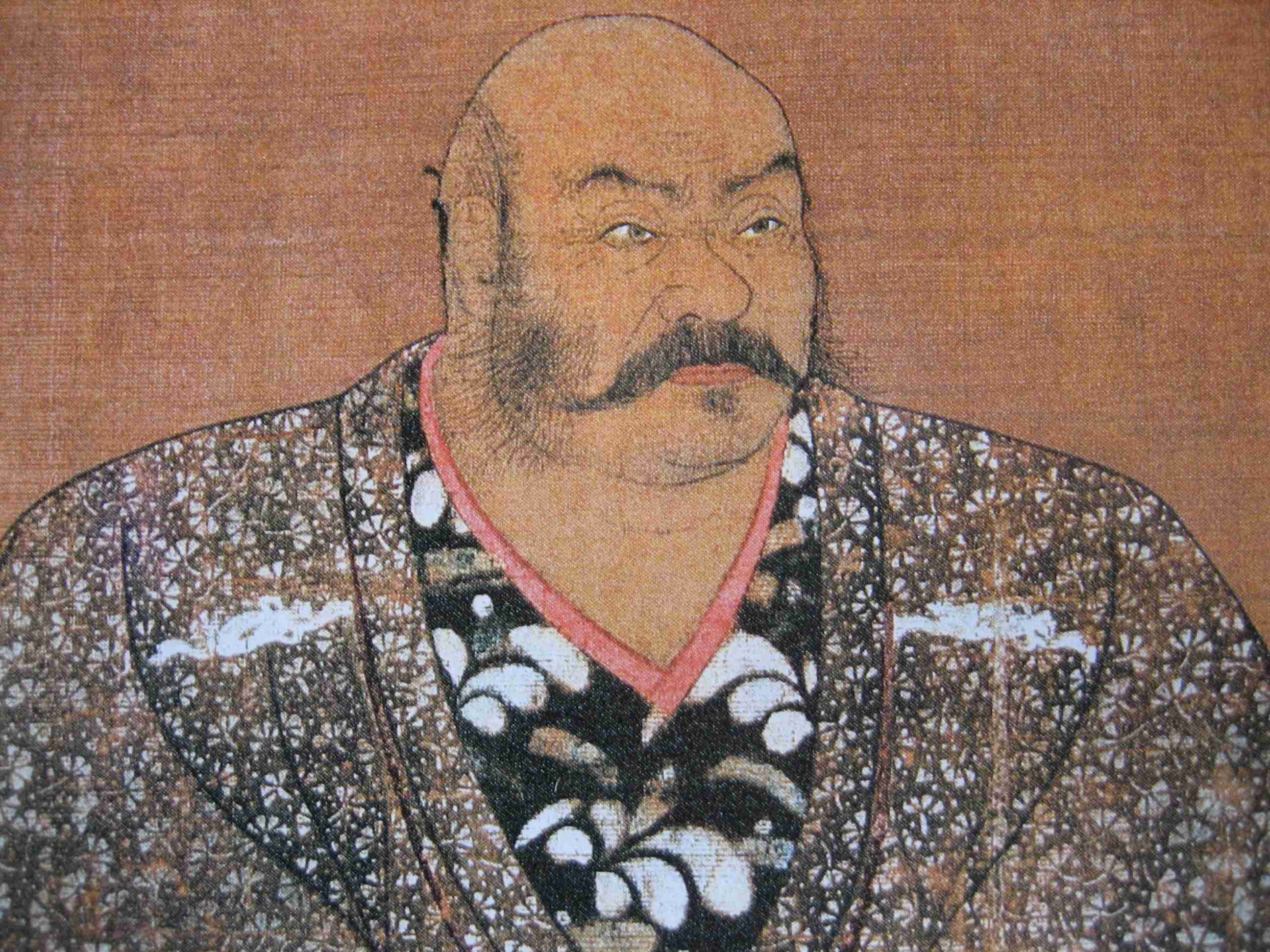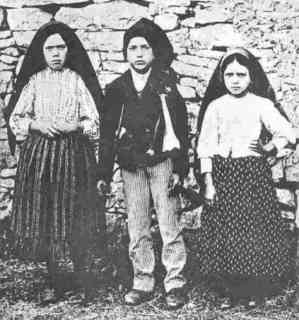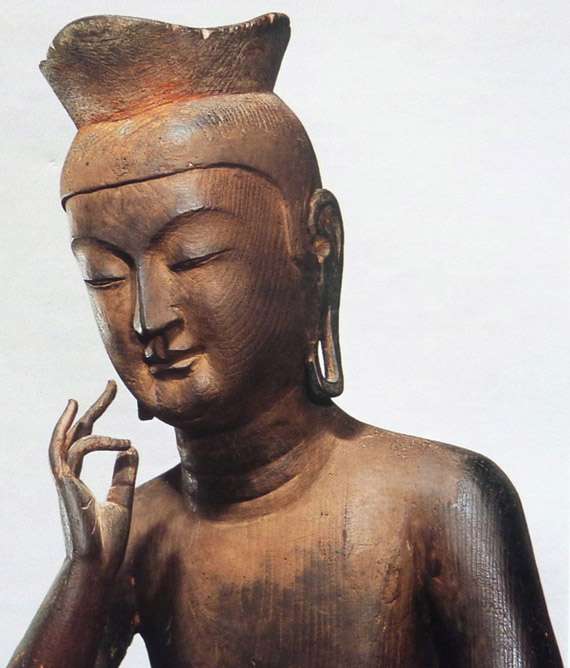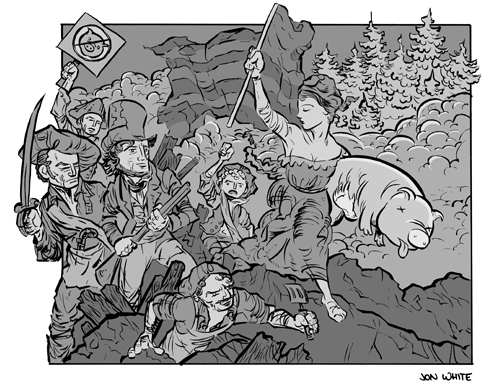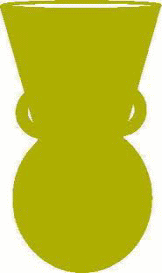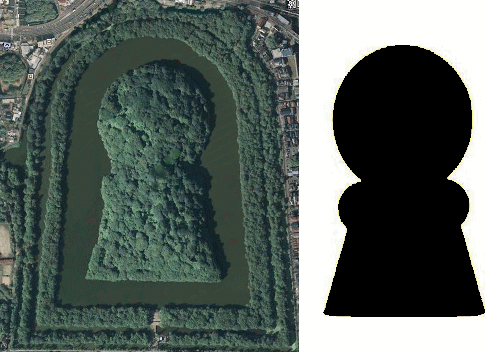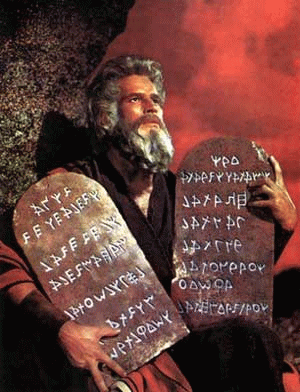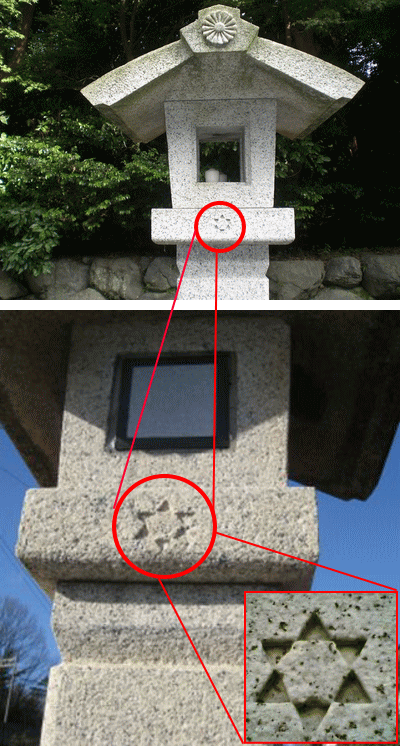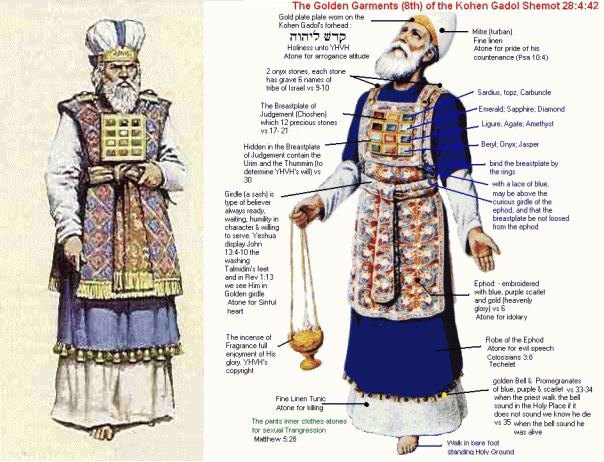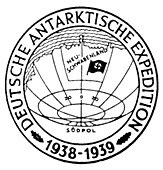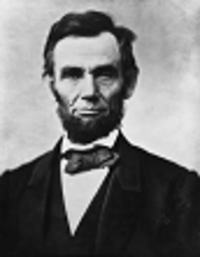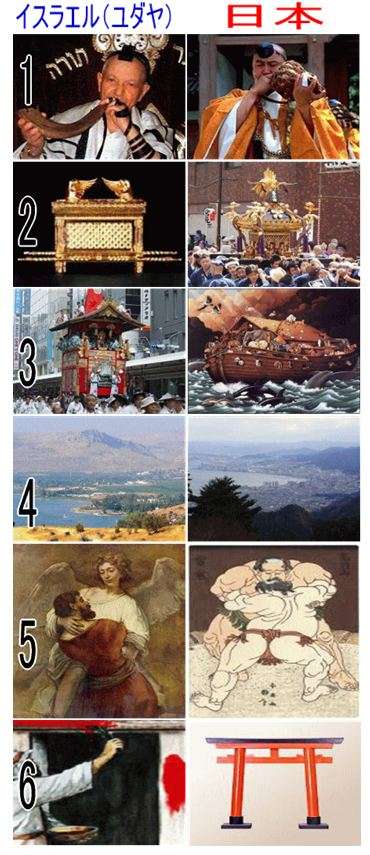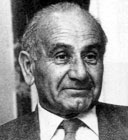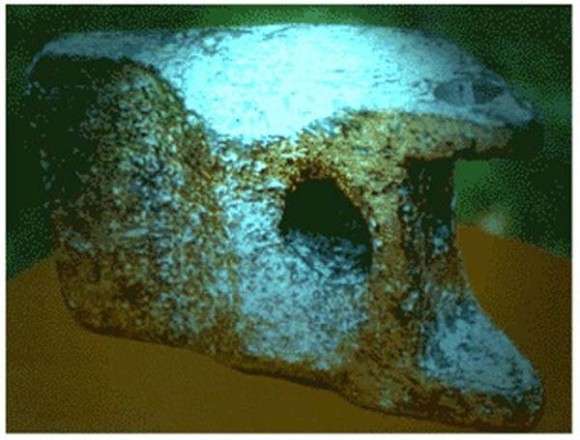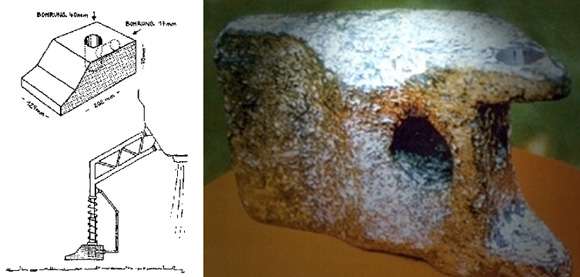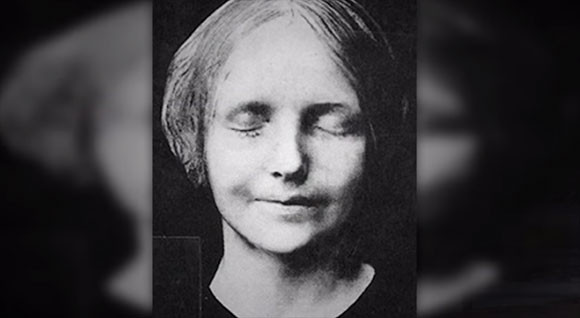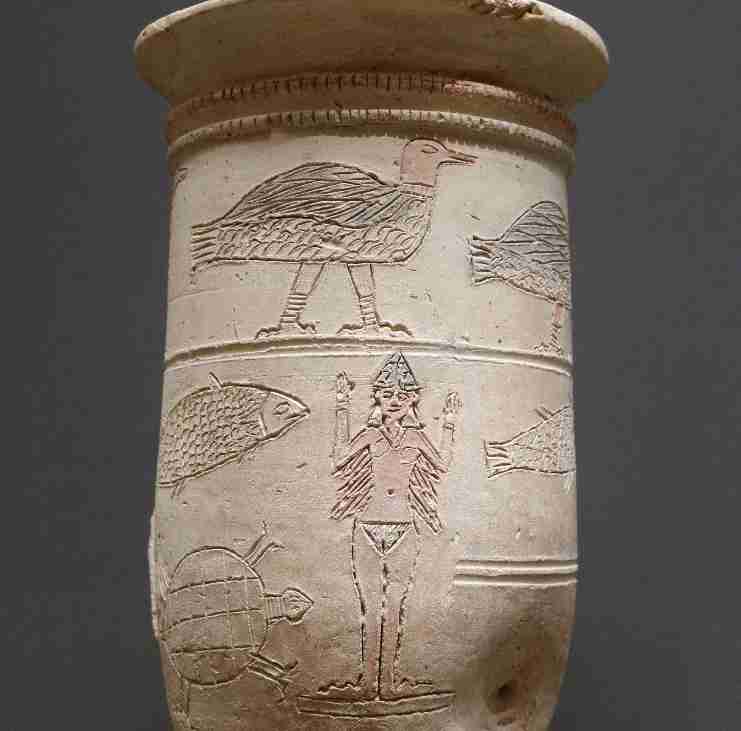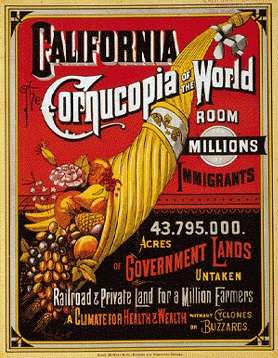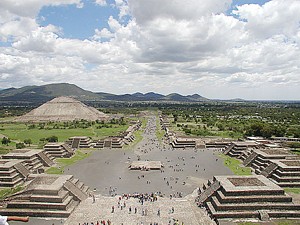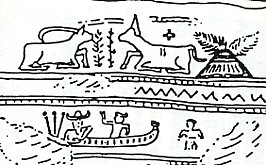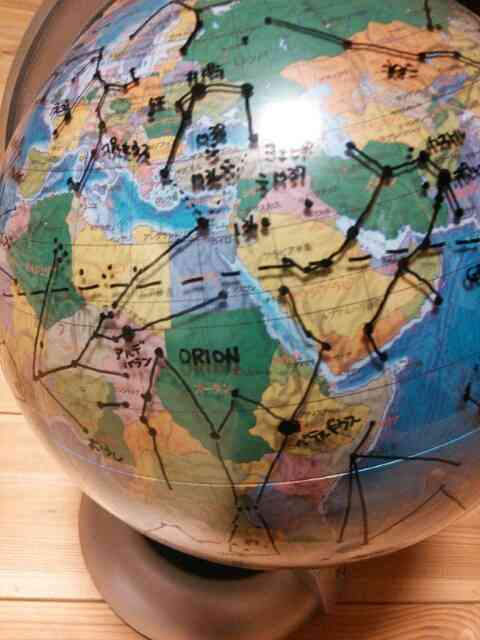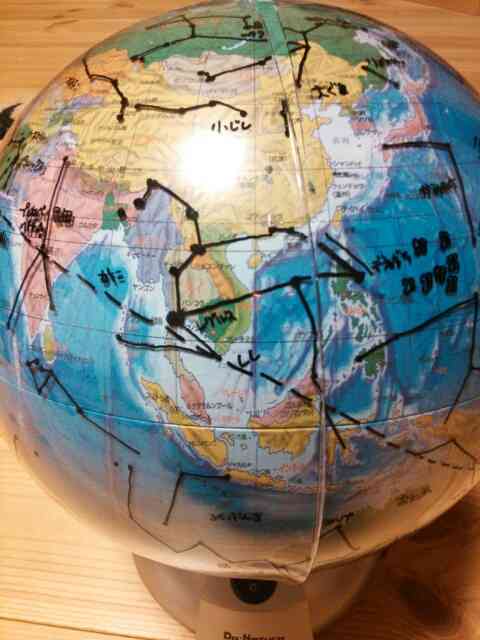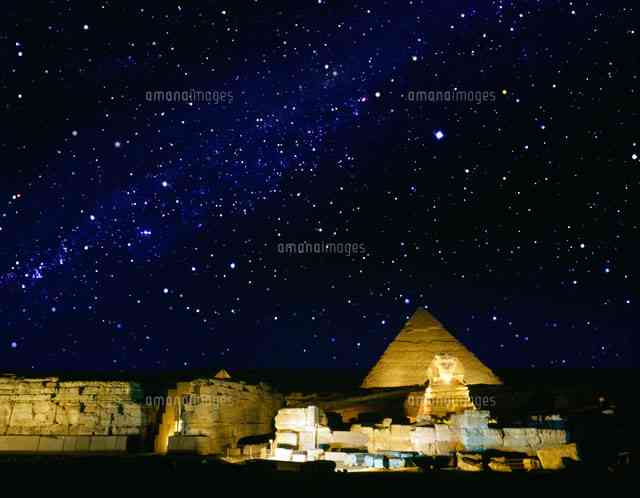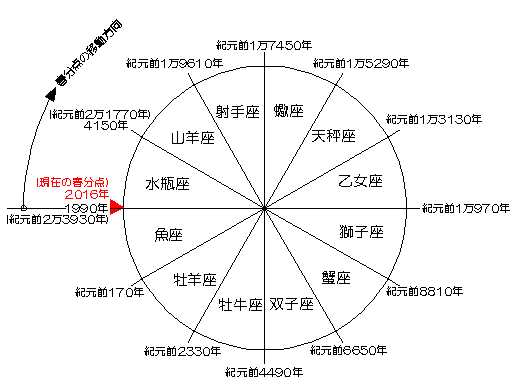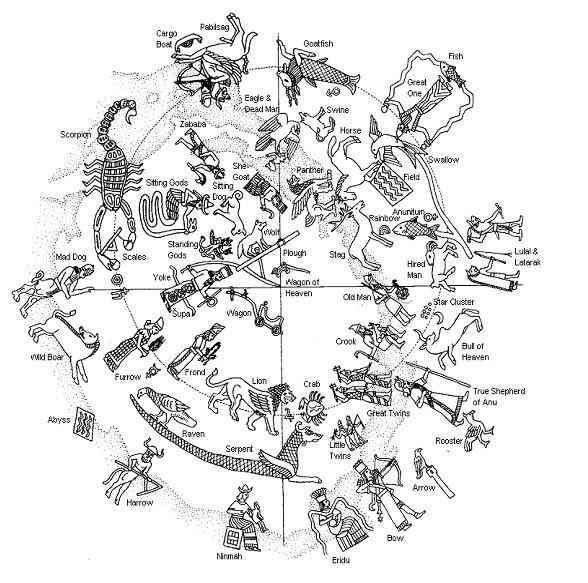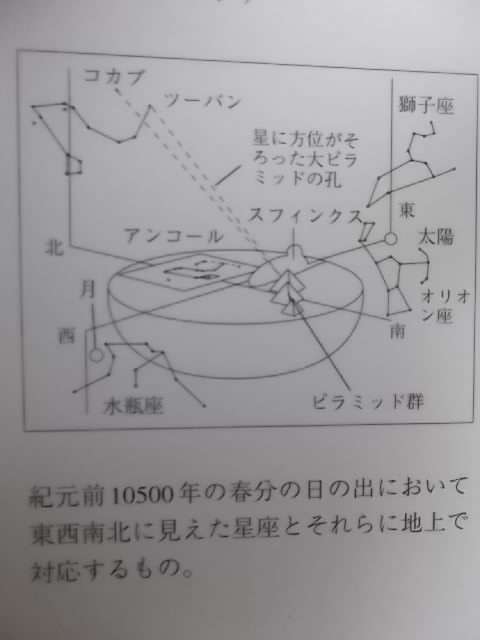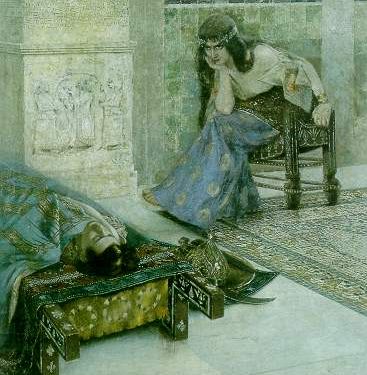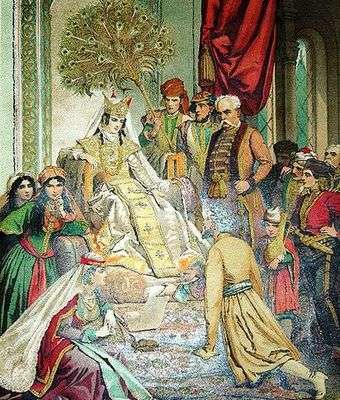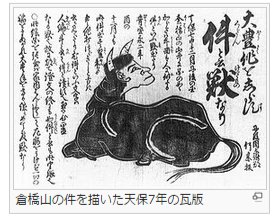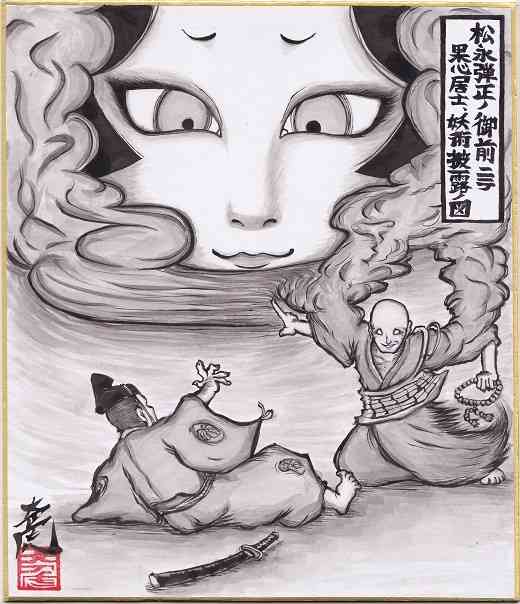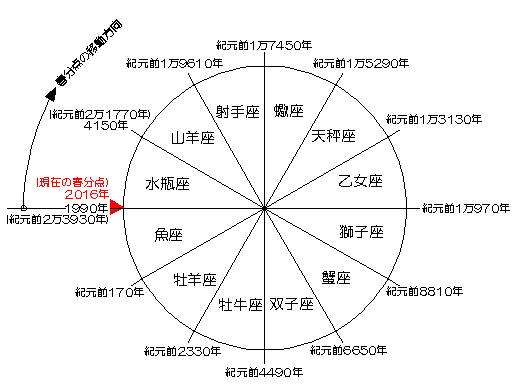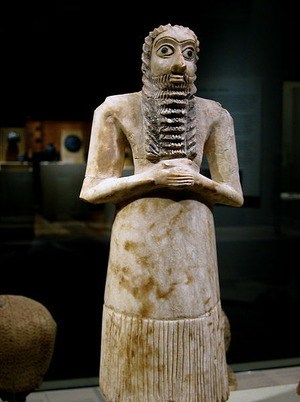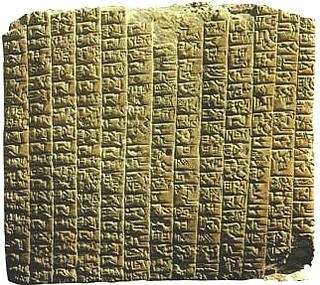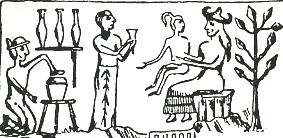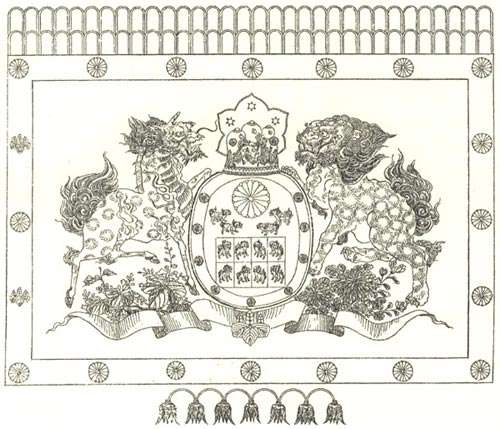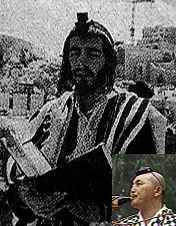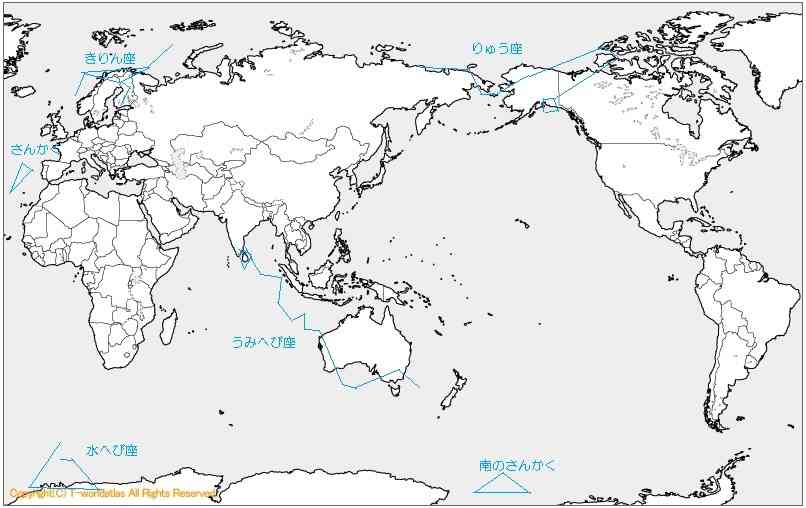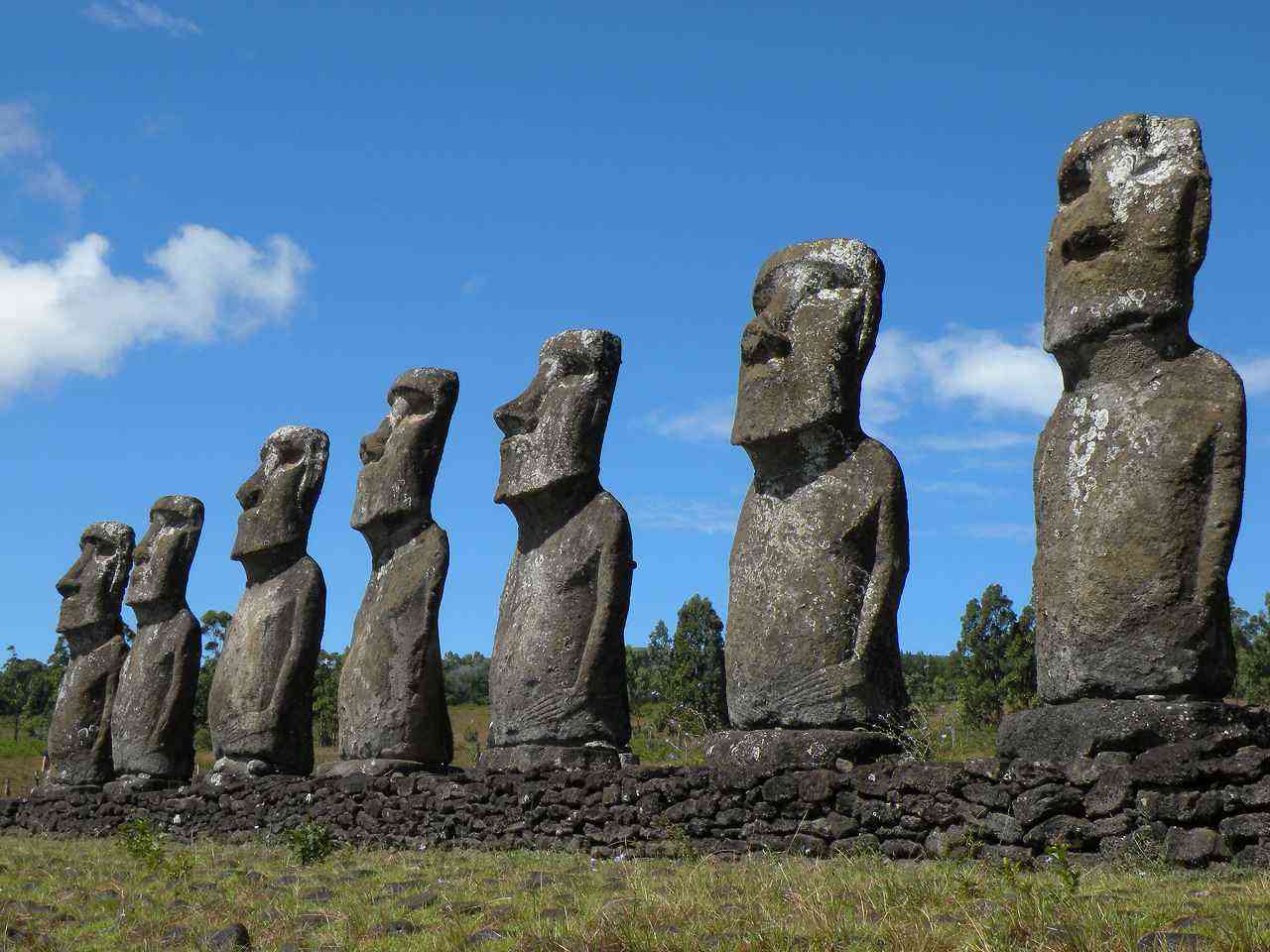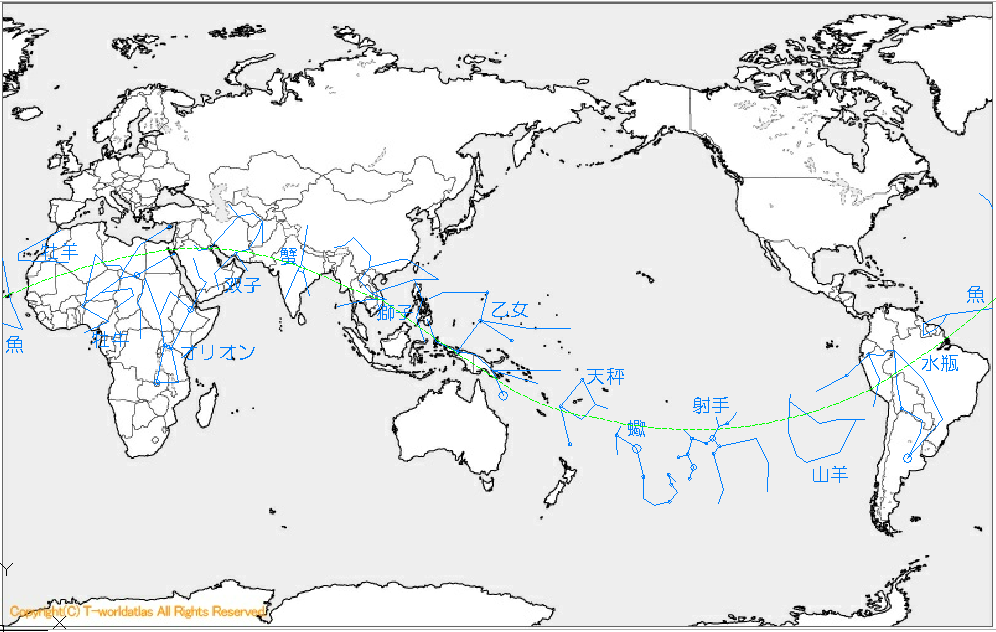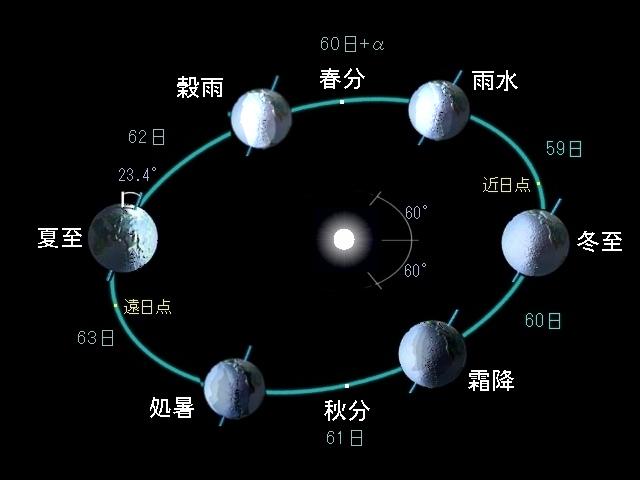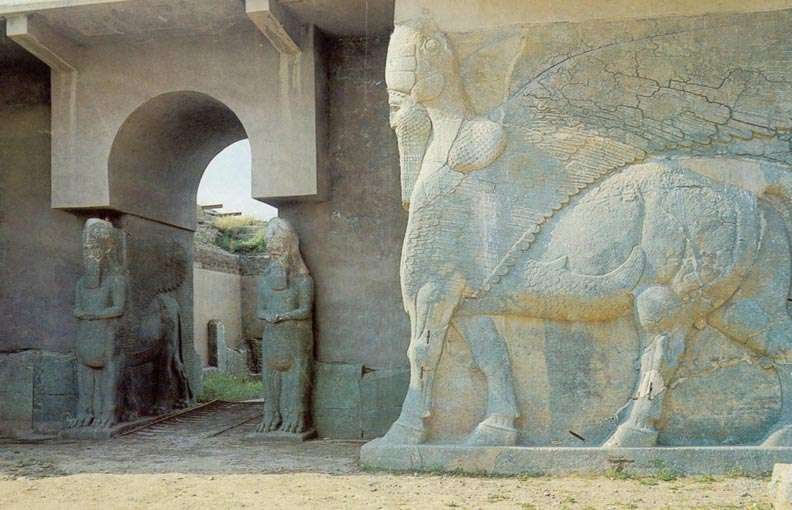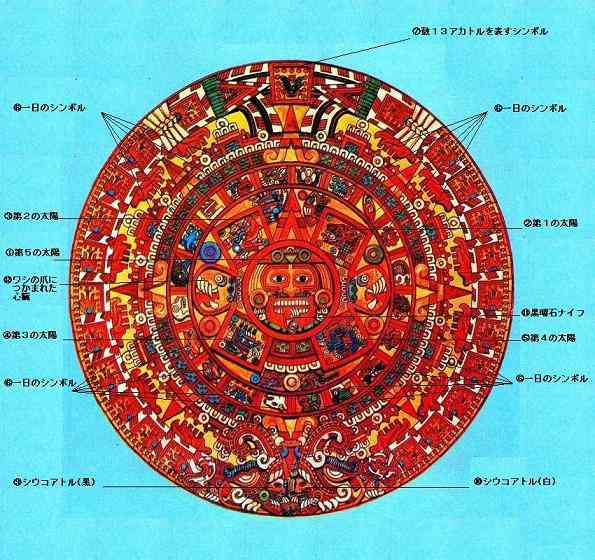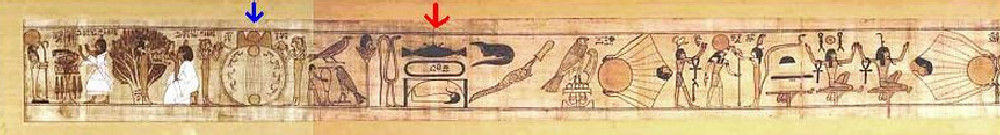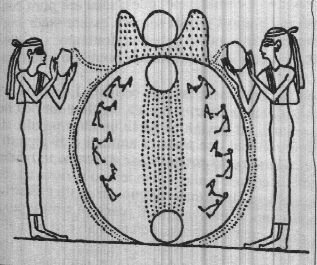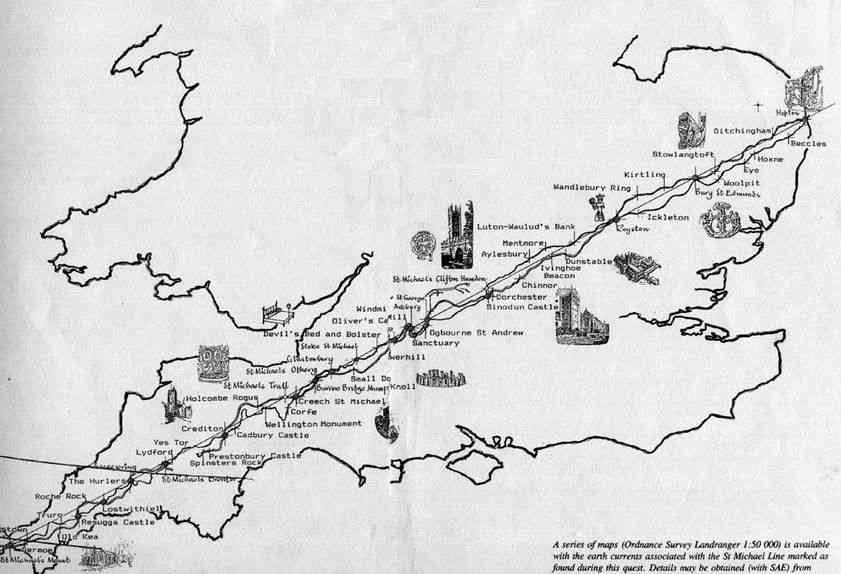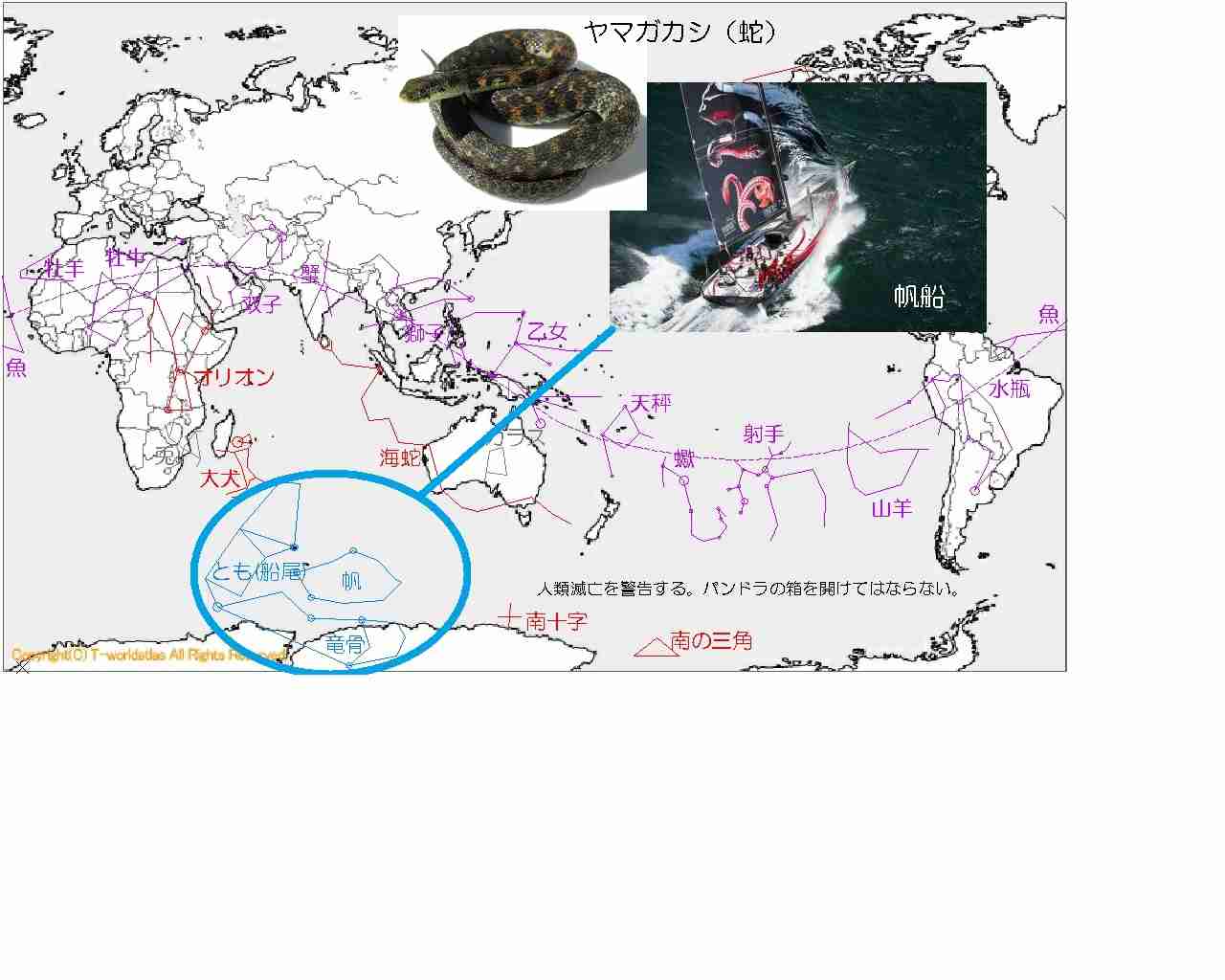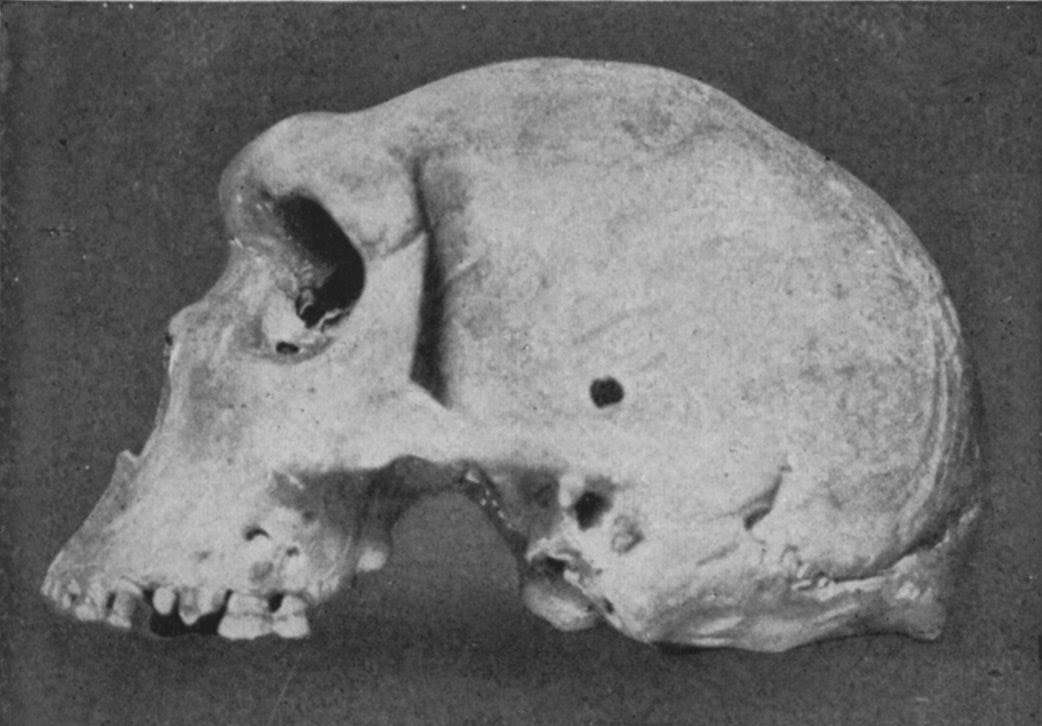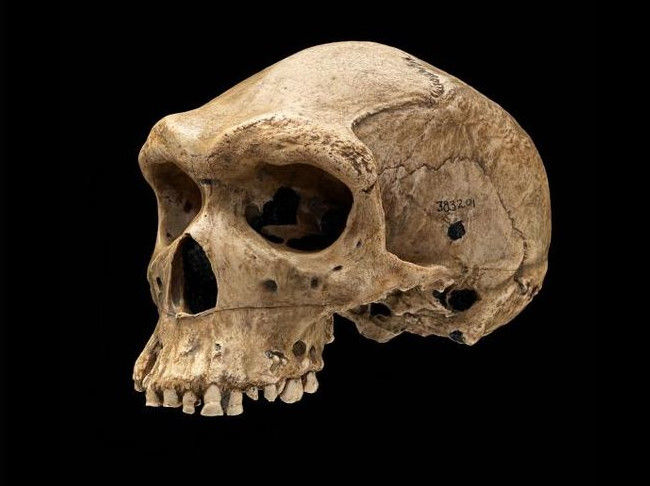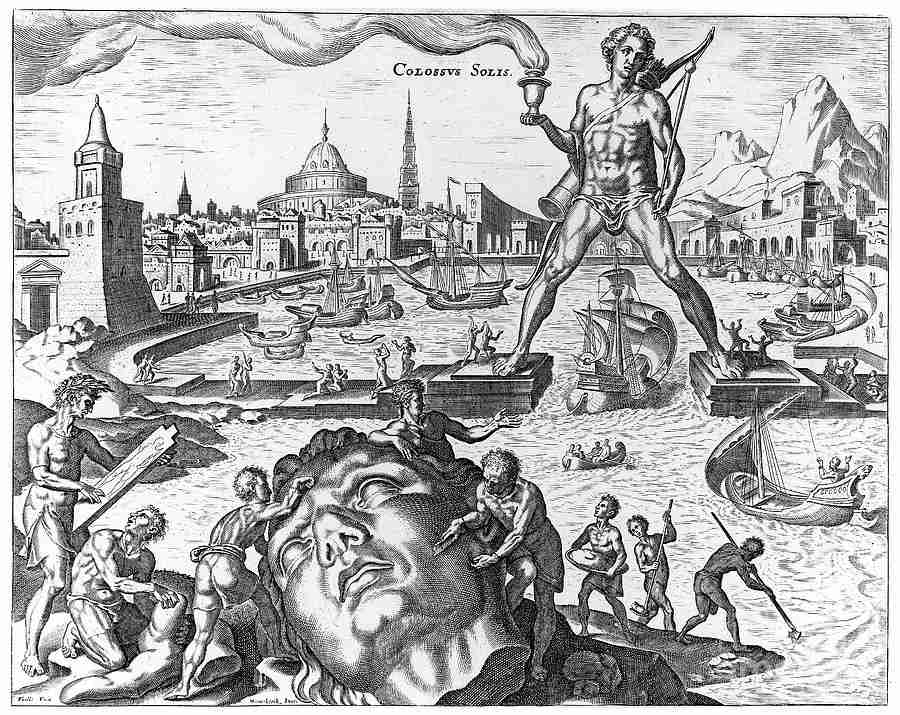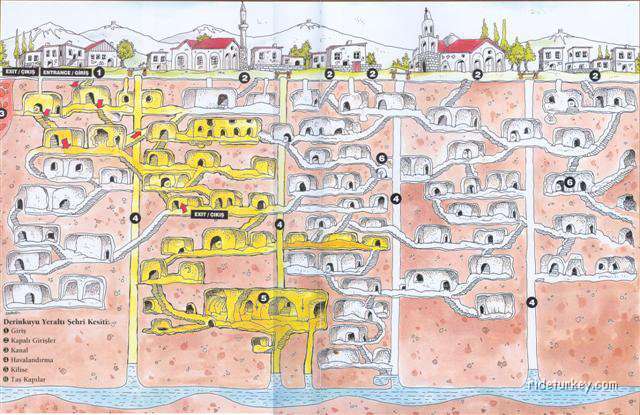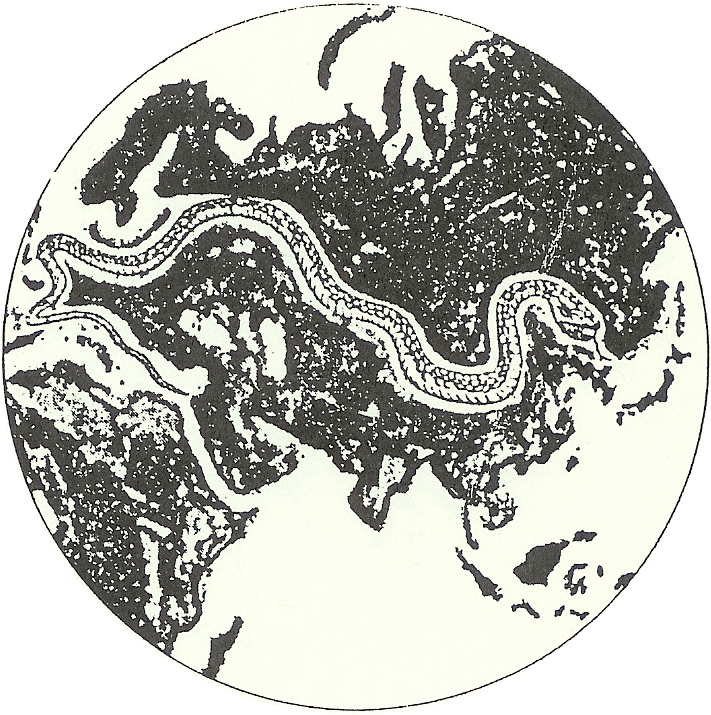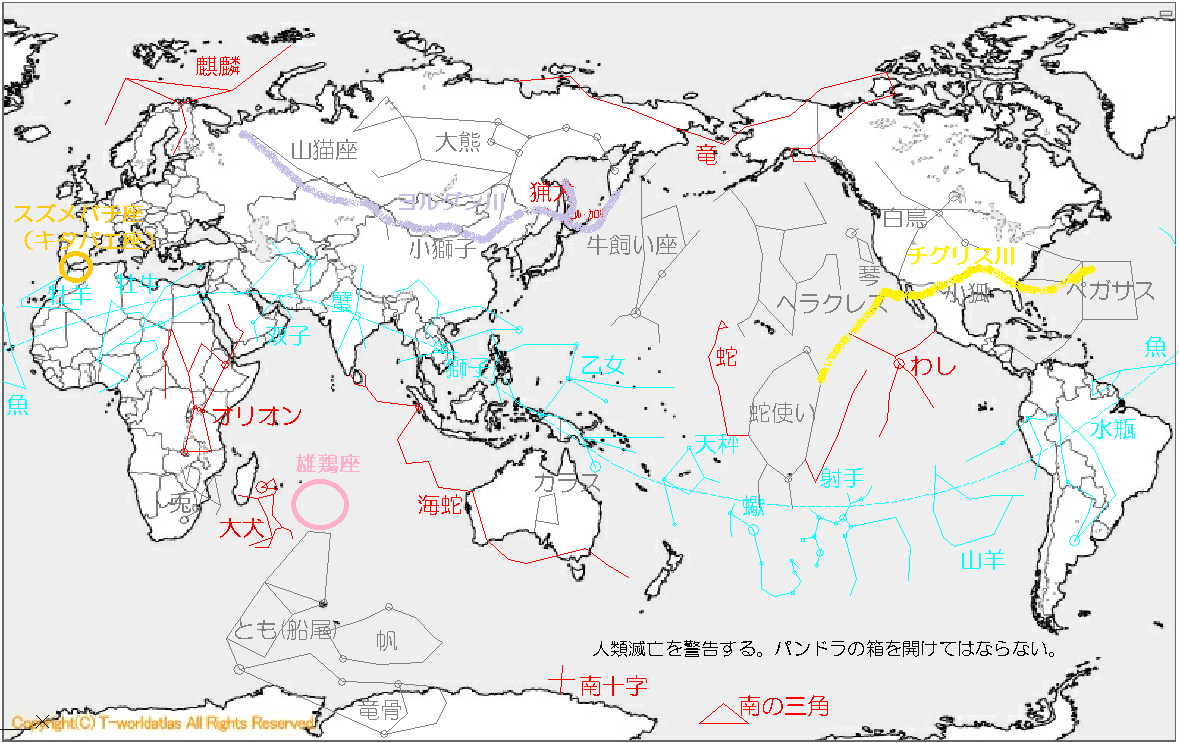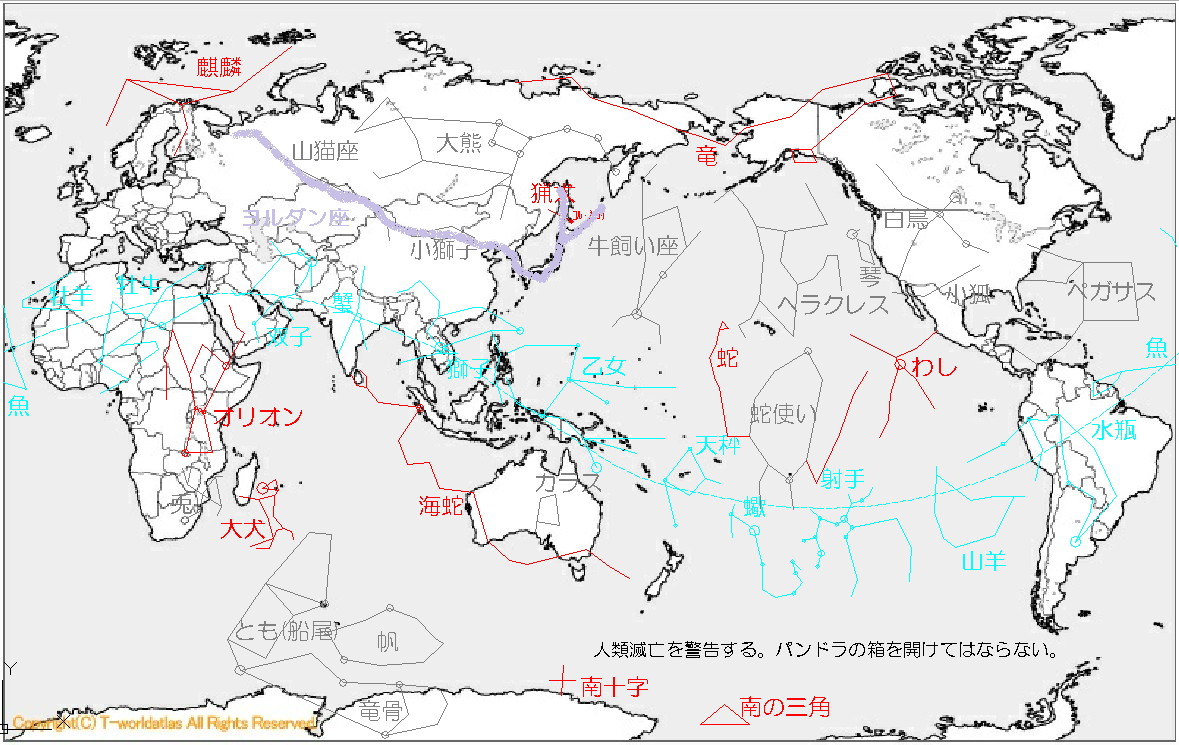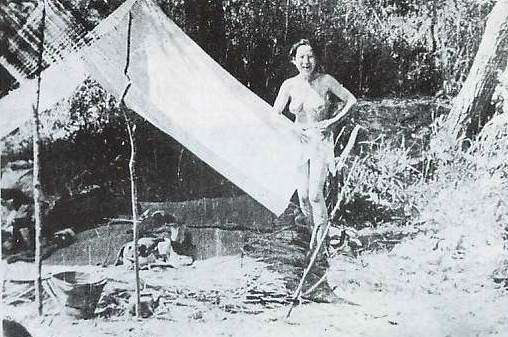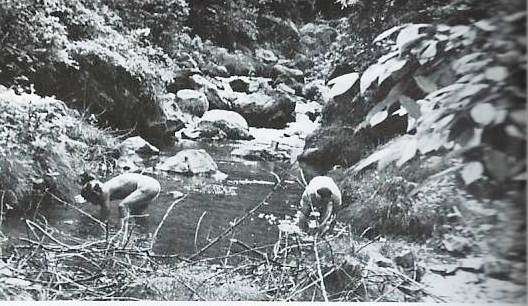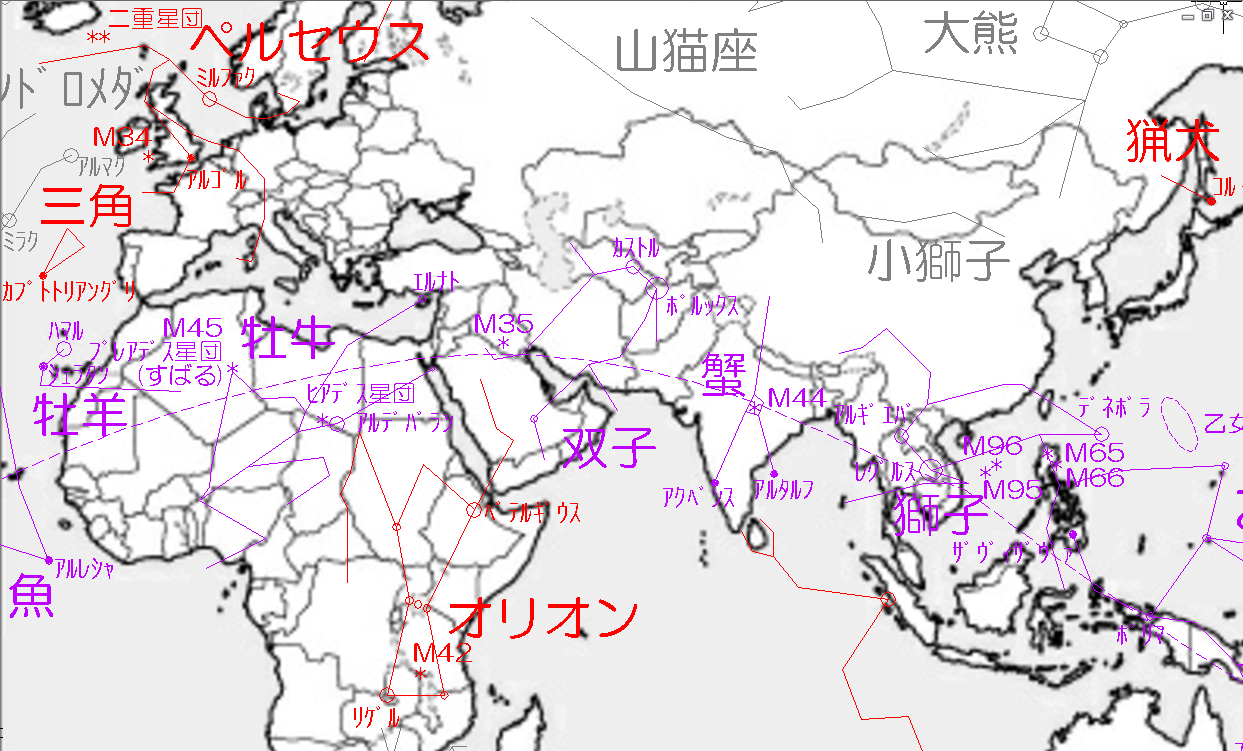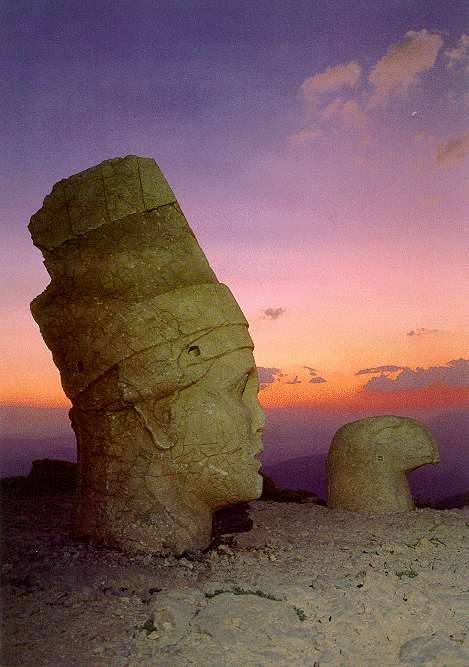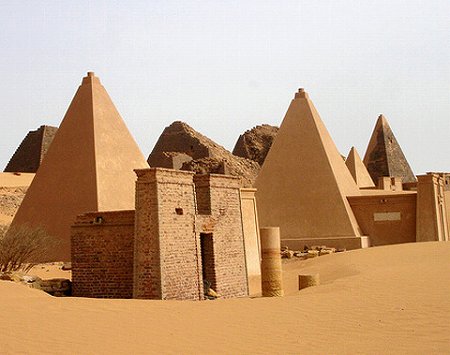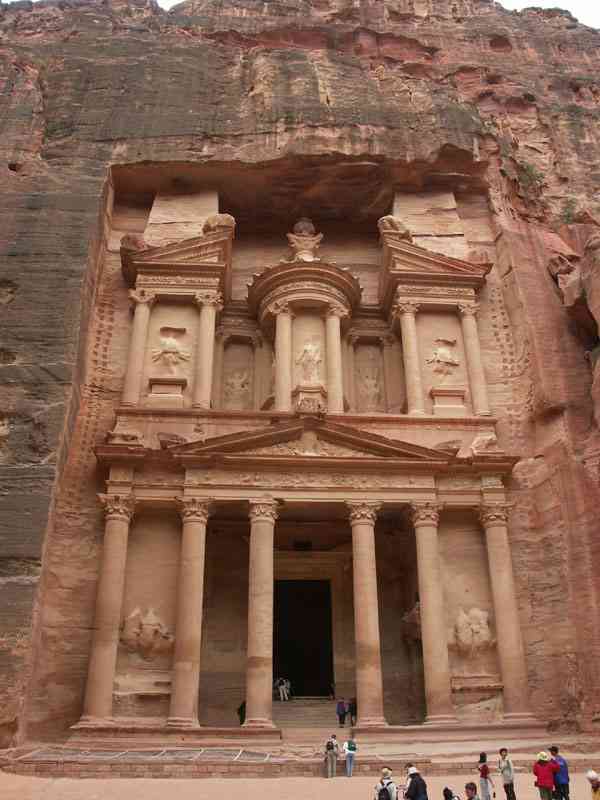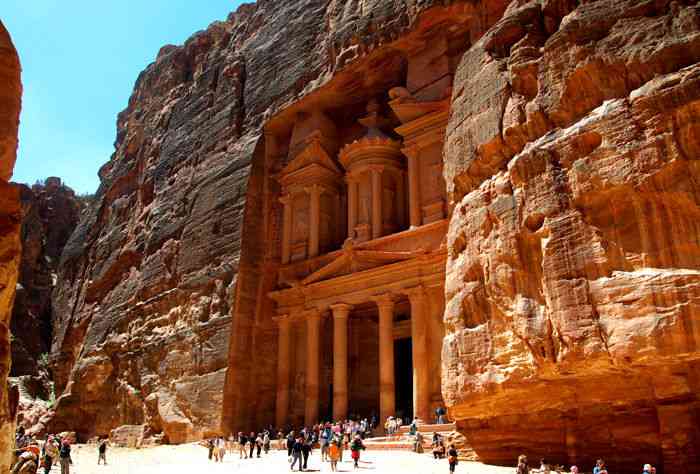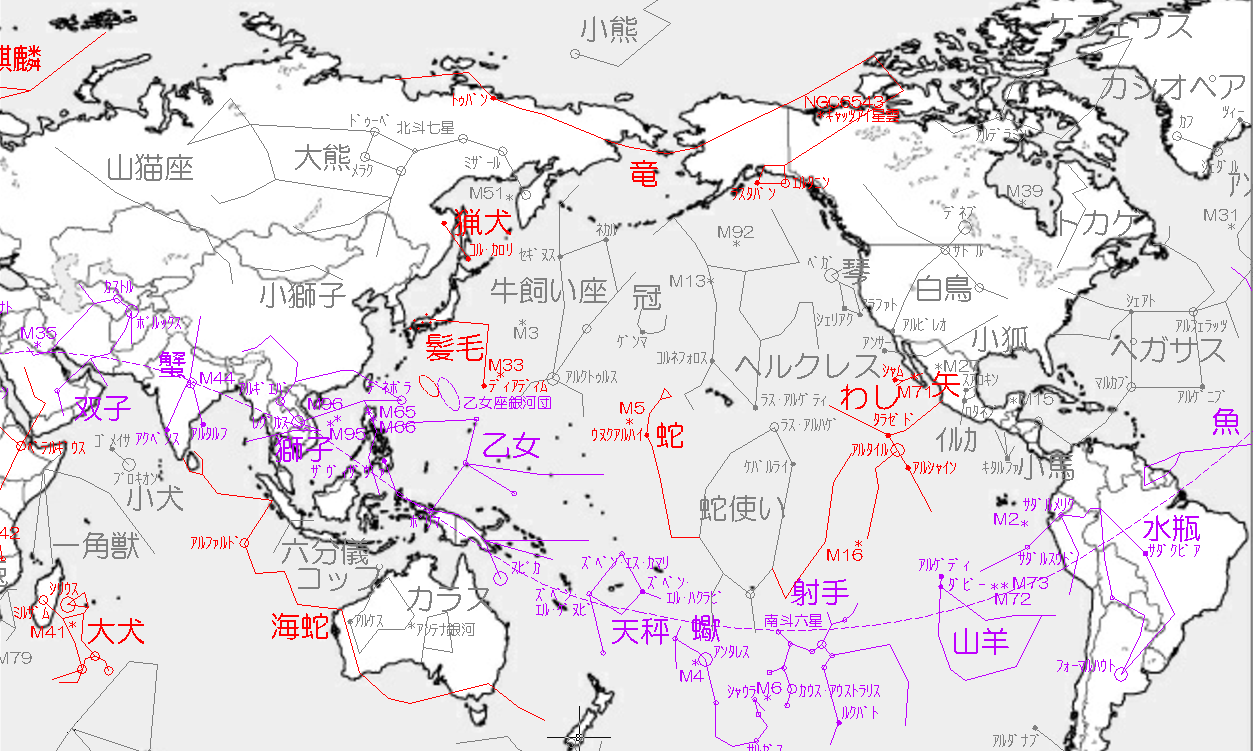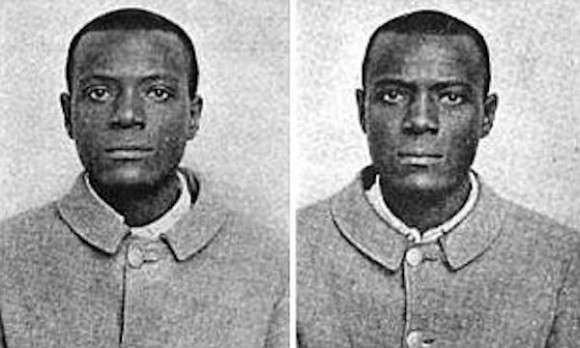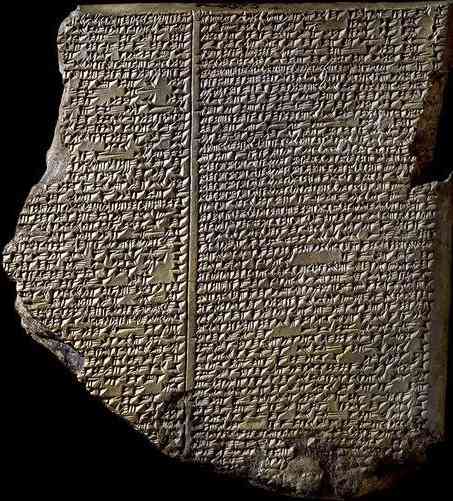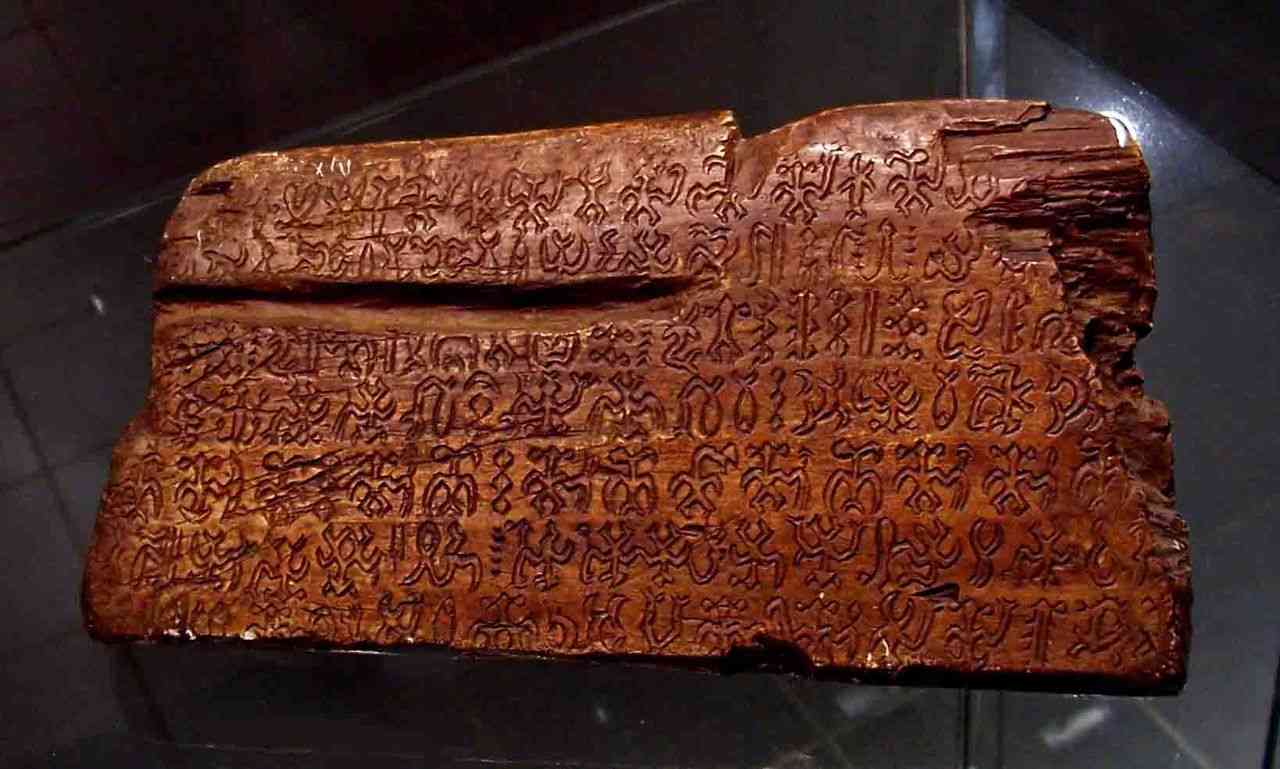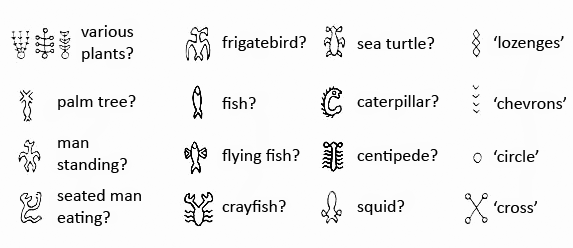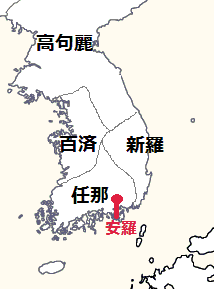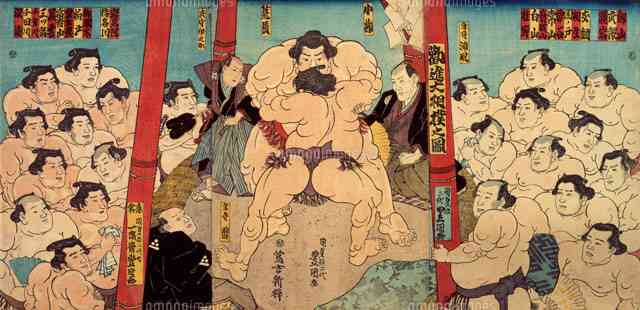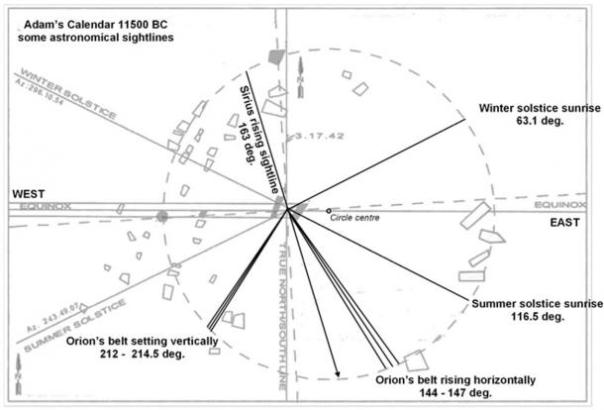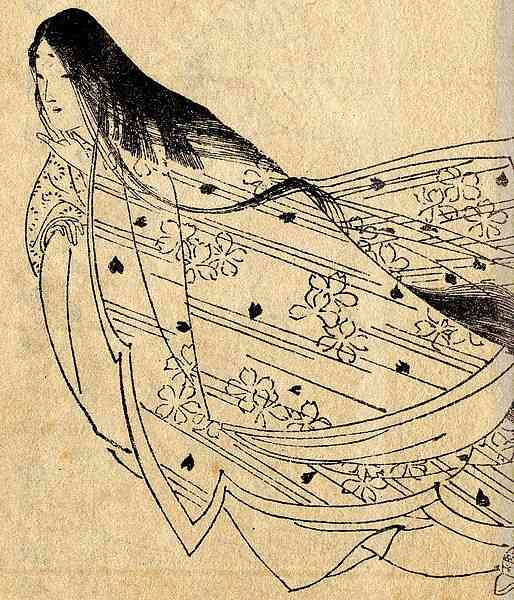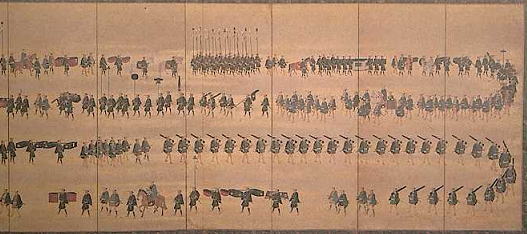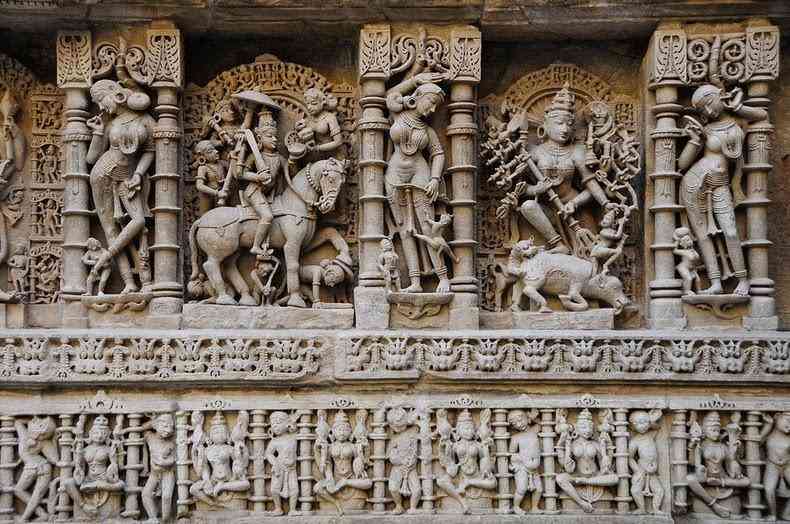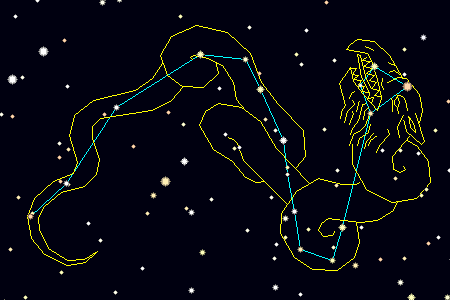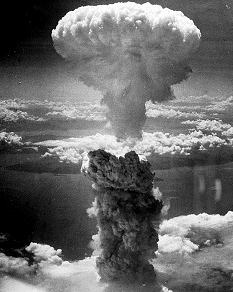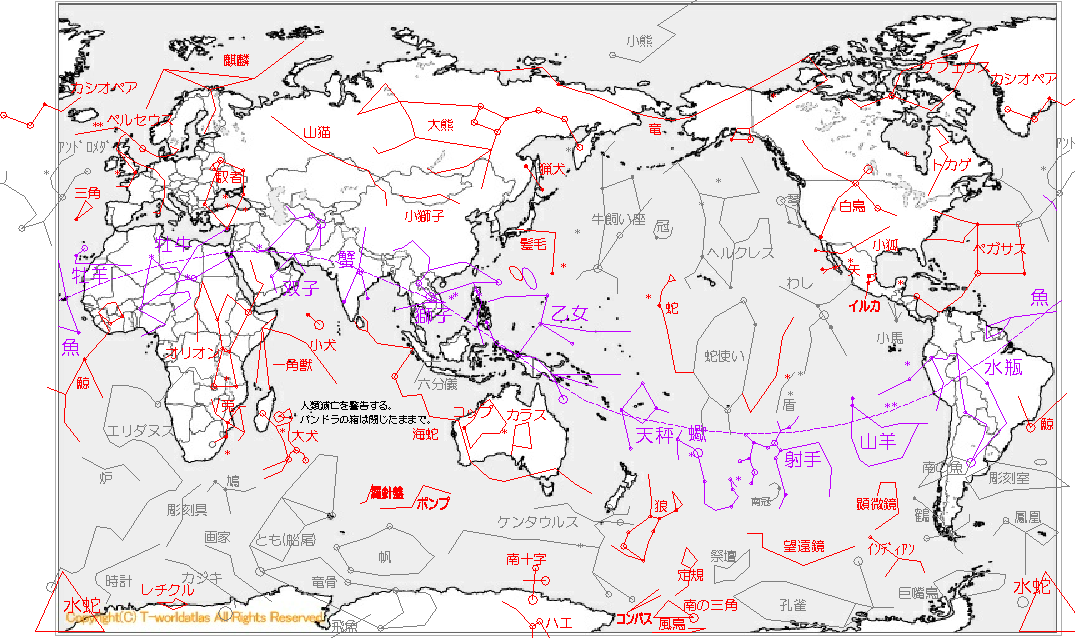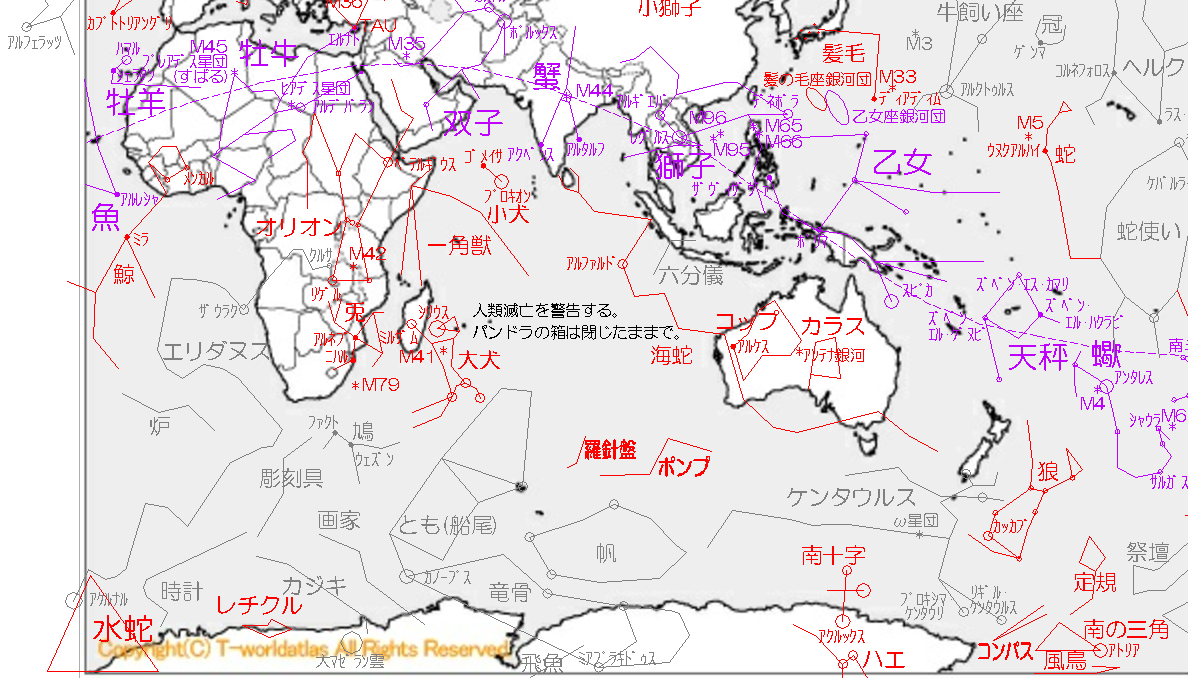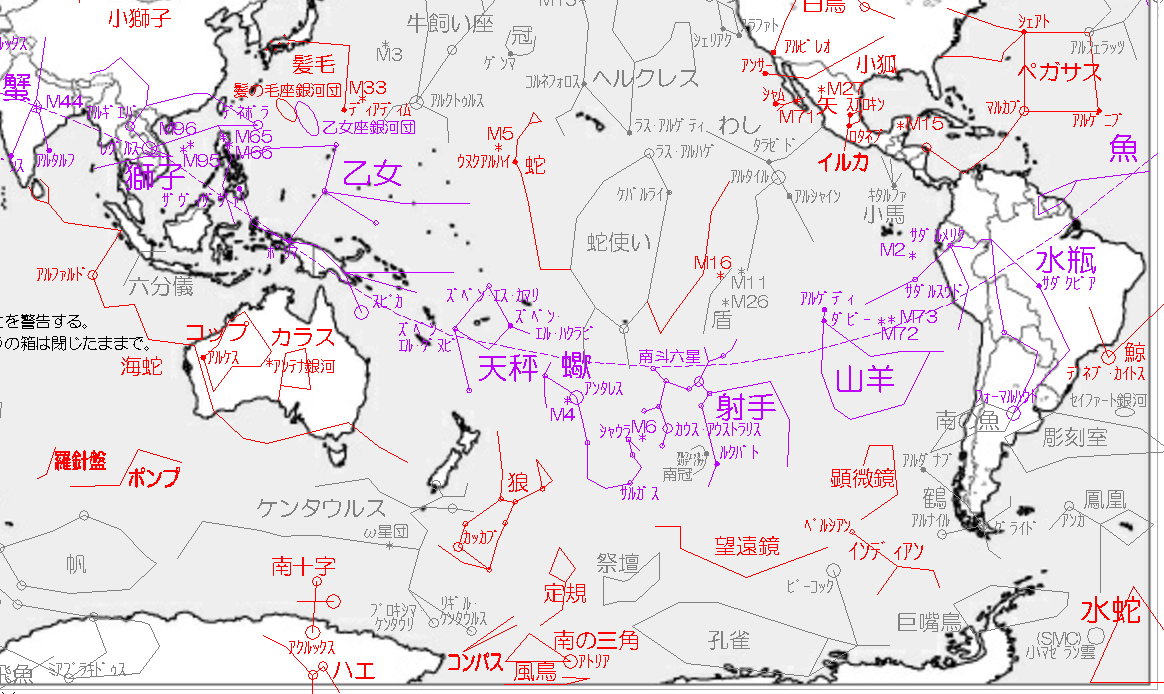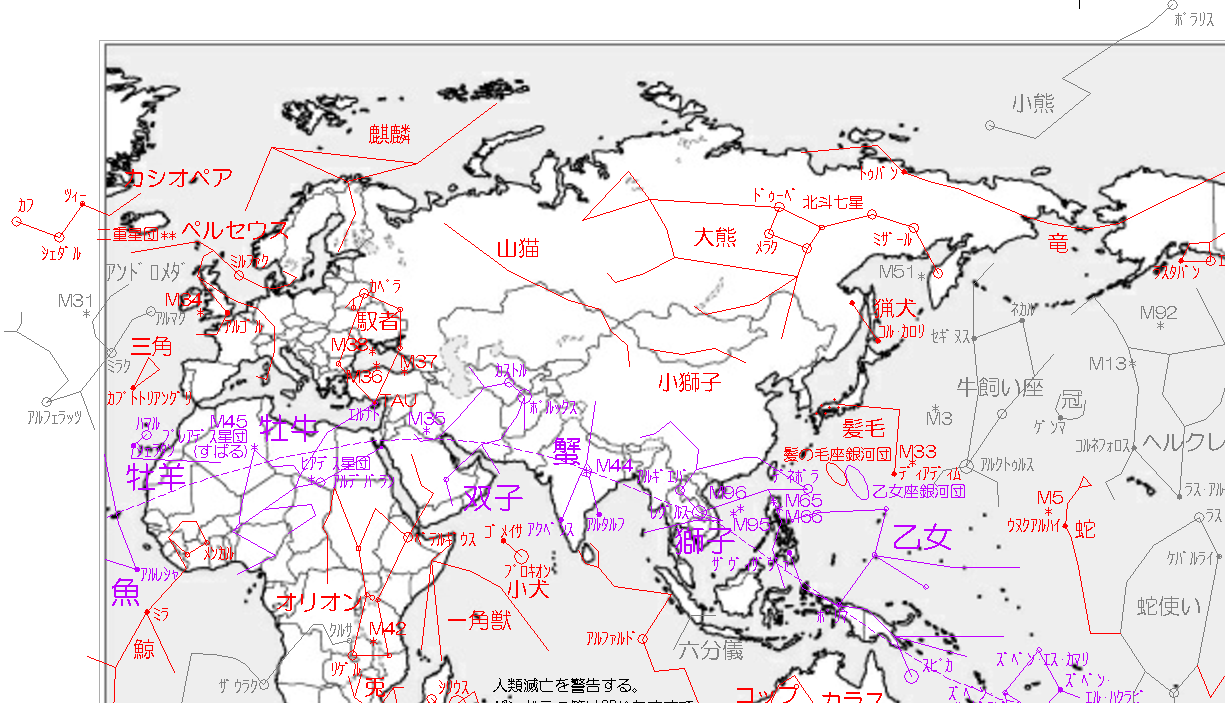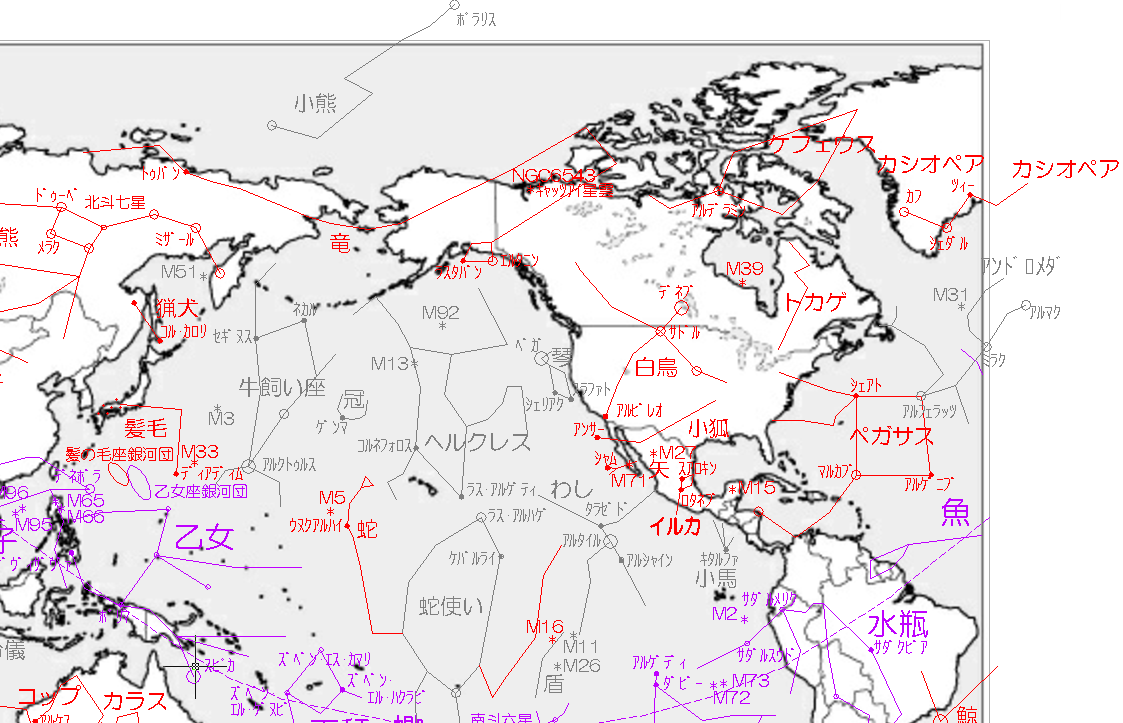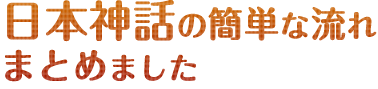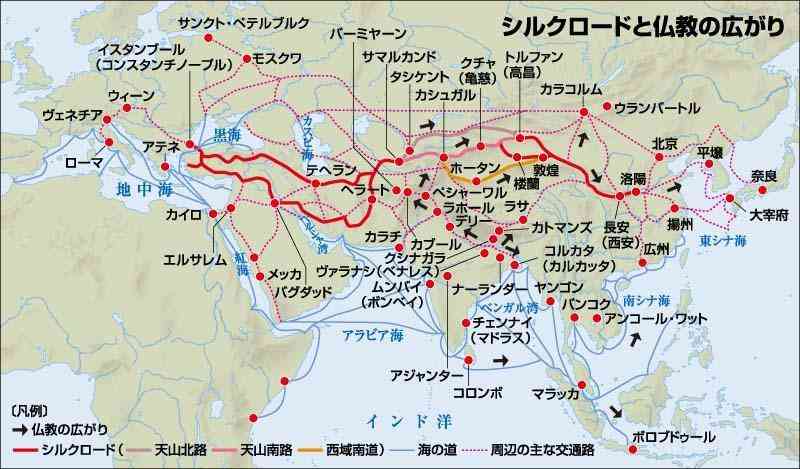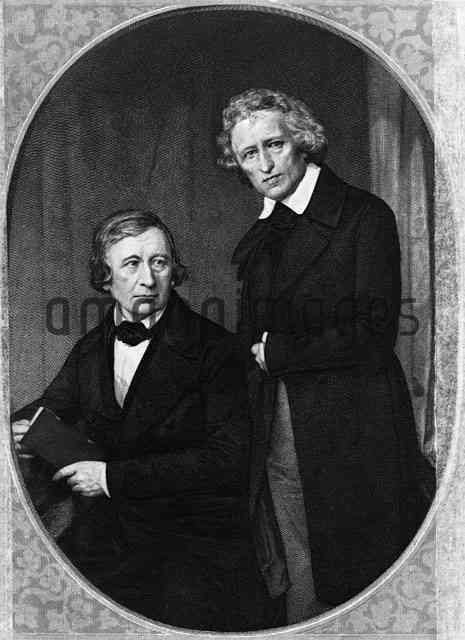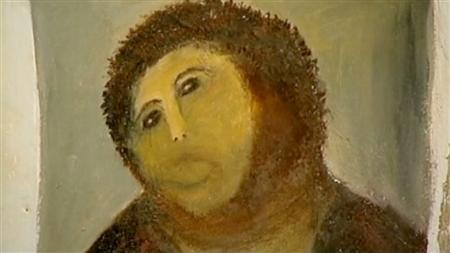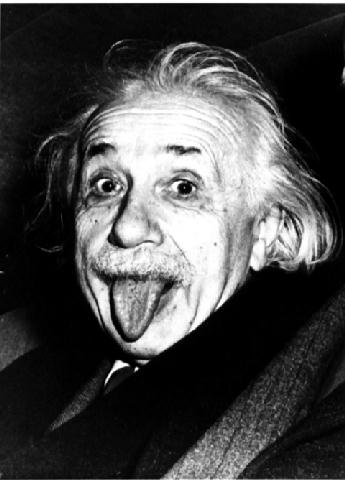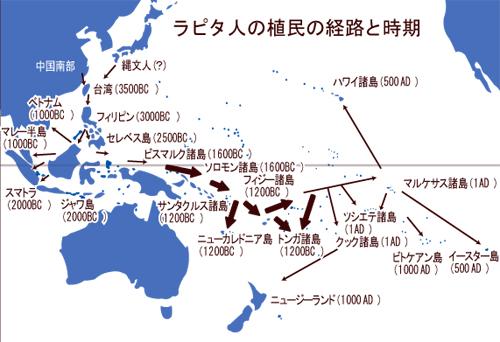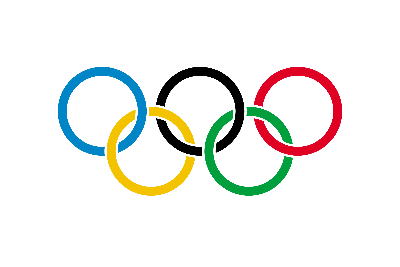-
1001. 匿名 2016/02/19(金) 11:40:07
>>977
シュメール人、目がゼイリブに出てくる人に似てる。+7
-0
-
1002. 匿名 2016/02/19(金) 11:41:33
(53319) 1999 JM8ってしってますか?
![歴史のミステリーを語ろう]() 出典:blog-imgs-42.fc2.com
出典:blog-imgs-42.fc2.com
アポロ群に属する地球近傍小惑星。1999年5月13日にリンカーン地球近傍小惑星探査 (LINEAR) によって発見されました。
1999 JM8の直径は約7kmで、潜在的に危険な小惑星 (PHA) の中では最大です。
2075年、1999 JM8は地球へ383万Kmまで接近すると予測されています。
因みに
チクシュルーブ・クレーター
メキシコのユカタン半島にある約6550万年前の小惑星衝突跡。
この衝突が、恐竜を含む大型爬虫類はじめとする多くの生物が絶滅した白亜紀末の大量絶滅(K-T境界)の、もっとも有力な原因と考えられています。
諸説ありますが、2010年にサイエンス誌に掲載された説では、小惑星の大きさは直径10-15km、衝突速度は約20km/s、衝突時のエネルギーは広島型原子爆弾の約10億倍、衝突地点付近で発生した地震の規模はマグニチュード11以上、生じた津波は高さ約300メートルと推定されています。
まさか人類滅びたりしないよね・・・
+17
-0
-
1003. 匿名 2016/02/19(金) 12:18:40
>>999大人になると特に石灰化が進んでいるらしいですね
>>994の続きです…下記は『ネイチャー』か『ナショジオ』に投稿しようかと本気で考えていたのですが、小保方さんの末路になりそうなので諦めてここで発表!
>>973さんのお帽子に注目してほしい
そしてエジプトのファラオの被り物も…
何かを連想しませんか?
そう、実は彼らはピラミッドを頭にかぶっているのです
このことからピラミッドとは人間の頭部と考えられませんか?
ベルツォーニの入口は鼻、ヴァイスの入口は口、上昇通路は鼻腔、大回廊は脳に辿り着く道筋、王の間は先ほどの”松果体”がある空間です
ちなみに女王の間はなんだろう?人体に詳しくないので、誰か考えてみてください
地下にある玄室は胃かなんかでしょう(ということは他の内臓もあるかも?)
松果体は第1の目でしたよね
ピラミッドの中には当然その第1の目があるはずです…それが王の間の石棺です(中に何か入っていたかも?)
ちなみに遠いご先祖さまには松果体の兄弟分、頭頂眼がありました
ほとんどの脊椎動物は退化した目ですが、昆虫(カマキリなど)やトカゲ類には残っているみたいです
長くなり申し訳ないですが、何が言いたかったかというと、
『ピラミッドは人間の頭部である』
という事です。
恐らくこのマークを考えた人は、このことを知っていたのでしょう+21
-1
-
1004. 匿名 2016/02/19(金) 12:20:24
オーパーツ(場違いな工芸品)に南米のクリスタルスカルがあります。
全く継ぎ目なく作られていて、当時の技術では絶対無理だという。
最近それが「偽物」とする判定が多いけど、複数ある本物がどこか一か所に集められていて、偽物とすり替えられているっていう噂もある(←まるで映画「インディージョーンズ」だけど)。
宇宙人の話は歴史に関係ないから嫌だという人もいるので、そういう方にはスルーしていただきたいのですが、それでも、歴史にはちょいちょい宇宙人が関与したとしか思えない謎のオーパーツが、たくさん遺されています。+25
-1
-
1005. 匿名 2016/02/19(金) 12:59:05
「ブラック・ナイト(黒装束の騎士)」衛星
1万3000年も前から北極上空を通過しながら地球軌道を移動している巨大人工衛星が発見されており、タイムズ誌やNASAもその存在を認めています。
「黒騎士の衛星」と名づけられているこの人工衛星の存在は、すでに54年前から確認されているのです。
(この当時、人類はまだ衛星の打ち上げに成功していない)
有名な科学者ニコラ・テスラもこの存在を知っており、この衛星から信号を受信していたという事のようです。
+25
-0
-
1006. 匿名 2016/02/19(金) 14:25:52
>>1005
やはり超古代文明があったのかな(>∀<)
もっと近くで見てみたいですよね!+24
-0
-
1007. 匿名 2016/02/19(金) 15:57:30
消えた30人のエスキモー
1930年12月、北カナダのモウンティ町から北の方へ600㎞ほど行ったところにある小さなエスキモーの村を、一人の猟師と騎馬警官隊が訪れました。
だが、不思議なことに、この村には大人と子供を合わせて30人くらいのエスキモーが住んでいたはずなのに、人っ子一人おらず、村は完全に静まり返っていました。
そして村の小屋や、テントの中には、火にかけて、食べかけの鍋の中身がそのまま残っていて、すでに凍りついていました。
また、エスキモーの人々が、寒さをしのぐアザラシの毛皮の上着もそれぞれの小屋に全部残されていたそうです。
また、エスキモーにとっては命綱とも言えるライフル銃も全て残されてあり、数十頭の犬は木につながれたまま餓死していました。
また、ソリや船もそのまま残されてあり、これら、生活にとって大変貴重な物を全て残したまま、30人全員がどこへ消えたのか今だに判明していません。
+33
-2
-
1008. 匿名 2016/02/19(金) 16:00:30
雲に飲み込まれたイギリス兵
第一次世界大戦中の、1915年8月21日。トルコのアンザックの近くにある、サル・ベイ丘。
この日、341名のイギリス陸軍・ノーフォーク連隊がその丘の方へ向かって行進していた。そして連隊が進んでいくにつれて、丘の上にかかっていた灰色の雲がだんだんと下へ降り始めてきました。
その雲はやがて丘を完全に覆い尽くし、ノーフォーク連隊の数百名はその雲の中へ向かって行進しているかのようにも見えたそうです。
しかい、雲の中へ入り込んだイギリス兵は、それから一人も姿を現さないのです。
この出来事は、イギリス軍側のニュージーランド兵22名が一部始終を見ていました。
一時間後、風が吹き始め、先ほどまで丘を覆っていた雲は、また段々と上昇し、すっかり辺りが見渡せる状態になりました。
しかし、確かにその丘に向かって行進していたイギリス兵は、一人もいなくなっていたのです。
ニュージーランド兵が見ていた場所からは数十㎞四方が広々と見えるよう場所であり、その付近に隠れるような場所など何もありません。
341名全てが行方不明になったという通報を受けたイギリス軍はただちに調査隊を送り、ノーフォーク連隊の行方を探しましたが、全く手がかりがなく、一人の死体さえ見つけることが出来ませんでした。
3年後の1918年、戦争が終結した時に、イギリス軍はノーフォーク連隊が、あの時トルコ軍の捕虜になったのではないかと思い、厳しく追及したが、やはりそのような事実はありませんでした。
あの時、雲の中へ消えた341名の兵士はいまだに行方不明のままで、帰ってきた者も、また死体が発見された者もいないのです。+32
-0
-
1009. 匿名 2016/02/19(金) 16:59:02
カンベイ湾の海底遺跡
インド・カンベイ湾にて海底に沈んだ都市遺跡が発見されました。
引き揚げた遺物を年代測定した結果、およそ9500年前と判明。
モヘンジョダロの様に巨大な人工構造物も見つかり、インド科学技術相が世界最古の都市を発見と発表したのです。
+22
-0
-
1010. 匿名 2016/02/19(金) 17:13:13
+21
-2
-
1011. 匿名 2016/02/19(金) 17:15:32
>>1007
心、内面の違いにより、違う次元に行ったらしいですよね。
よくある事らしい。つまり、こっちから見た人はいなくなった人になり、いなくなった方の人からは、こっち側の人はいなくなった人になるそうです。
ネイティブアメリカンも違う次元に行ったらしい。移住民により絶滅させられたネイティブアメリカンの方は、移住民と同じ土俵に上がってしまったかららしい。今頃、ネイティブアメリカンの人たちは悠々自適に
争いのない世界で楽しく暮らしていると思う。次元が上がったという事です。
ここで注文すべき事は、エスキモーにしてもネイティブアメリカンにしても、自然と調和した生き方をしている人達であることだと思う。+23
-4
-
1012. 匿名 2016/02/19(金) 17:21:18
>>1004
>>宇宙人の話は歴史に関係ないから嫌だという人もいるので、そういう方にはスルーしていただきたいのですが、
本当にそう思います。シュメール人にしてもどう考えても宇宙人と思います。宇宙と宇宙人との関係は、歴史上切っても切れないというか、宇宙人が文明を作るきっかけを作ったと考えています。+27
-1
-
1013. 匿名 2016/02/19(金) 17:23:53
参考までに…
銅鐸には絵画をもつものもある。シカ、イノシシ、水鳥、カメ、トカゲ、トンボ、クモ、カマキリなどの動物、狩りする人、魚をとる人、脱穀する人、舟に乗る人、争う人などの人物、そして米倉とみられる高床建物などの絵がそれである。
これぞ銅鐸である!っていう模様があったんですね
なんか意味があるに違いない+19
-1
-
1014. 匿名 2016/02/19(金) 17:27:51
>>1013
銅鐸ネタでもう一つ。
銅鐸を鋳物で同じものを作るのは非常に困難らしいです。
職人の方でも暑さ5ミリが限度なのに、本物は2ミリしか無いそうです。
ロスト・テクノロジーですね。
+26
-1
-
1015. 匿名 2016/02/19(金) 17:29:29
>>1004ですが、肝心なことを書き忘れました。
南米マヤ遺跡発掘調査などによって発見されたクリスタルスカルの中に、グレイの頭部を模ったものもあったと、以前本で読んだことがあります。
人間の頭部ならまだしも、どうしてグレイのクリスタルスカルがあったのでしょうか?
技術的にもマヤ文明の辺りでそんなものを造れるわけがないので「これ、宇宙人が造ったんじゃね?」みたいな話になっていたのだと記憶しています。+20
-2
-
1016. 匿名 2016/02/19(金) 17:33:40
>>1012
私は宇宙の話にも興味ありま~す(^∀^)+31
-0
-
1017. 匿名 2016/02/19(金) 17:42:51
>>1007さんのエスキモー行方不明事件ですが、>>985さんも書かれている映画「フォースカインド」を見た私としては、レプタリアン系宇宙人にさらわれた可能性があると考えます。
「フォースカインド」はアラスカで起こった事件ですが、エスキモー事件も場所的に近いですよね。
彼らはよく人が少ない場所に現れるそうですから、エスキモー村なんてすごく都合が良いのかも。+23
-2
-
1018. 匿名 2016/02/19(金) 18:09:01
>>1017
え~…(トーンダウン)。酷過ぎる… 確かに人が少ない所だったら、誰にも知られずに連れ去られるし、悲鳴上げても聞こえないですよね… 山奥とか危険というし。本当にやめて欲しいと思う…+22
-1
-
1019. 匿名 2016/02/19(金) 18:23:51
映画「フォースカインド」見てないので、今予告覗いてみたらめっちゃ怖かった…
宇宙人と言ってもいい方でないのは、一目瞭然です…
+18
-1
-
1020. 匿名 2016/02/19(金) 18:38:59
>>1009
氷河期の海面は現在より100メートル低かったから、考古学者はダイビング免許を取らなきゃね+7
-0
-
1021. 匿名 2016/02/19(金) 18:49:56
古代核戦争説(モヘンジョダロ遺跡)
インダス文明の古代都市モヘンジョダロの遺跡は周囲5平方キロの広大な遺跡ですが、現在発掘が進んでいるのは全体の4分の1ほどの地域です。
遺跡で見つかった白骨遺体46体は突如、死がやってきたような状態でした。
そのうちの9体には高温で加熱された跡が残っていました。
また、『ラーマーヤナ』の記述に基づき戦闘の日時と場所を特定した研究者によると、炭素14の分析もして戦いの期間を紀元前2030年から紀元前1930年の間と特定したものの、モヘンジョダロにおいては400年程度の食い違いが見られるといいます。
ずれの可能性としては放射能の影響が考えられるがはっきりしなせん。
(中略)
このような広範な範囲の砂が溶けてガラス化するという現象はこれまで自然界では見つかっておらず、同様の風景は今のところ地表で核実験が行われた場所(砂漠)でしか見つかっていません。
因みにこの遺跡の名前の意味はモヘンジョ・ダロ(死の丘)と言う意味です。+19
-0
-
1022. 匿名 2016/02/19(金) 19:06:32
三星堆遺跡
星堆遺跡(さんせいたいいせき)は、長江文明に属する古代中国の遺跡の一つです。
1986年に中華人民共和国四川省広漢市の三星堆で発見されました。
紀元前2000年頃もしくはそれ以前と考えられる極めて古い時代に属する三星堆遺跡とその文化は、約5000年前から約3000年前頃に栄えた古蜀文化のものです。
三星堆の縦目仮面
瞳だけ飛び出すってどんな人間なんだろ 宇宙人かな?
+23
-0
-
1023. 匿名 2016/02/19(金) 19:29:34
>>1019
もし一人暮らしをされてるなら、観ない方がいいと思いますよ(笑)。
私はレンタルDVDが出たとき、すぐ借りて見たのですが、その頃転勤で非常に人が少ない地域の一軒家に住んでおり、夜、怖くて怖くて一時的にやや不眠になりましたから。
映画を観た方にしかわかりませんが、午前3:33に起きようもんなら「ギョエーッ!」みたいな。+18
-0
-
1024. 匿名 2016/02/19(金) 19:34:35
古代に核戦争があったと証明されるのは、モヘンジョダロはそうらしいですよね。
地球で核を使ったのは、広島、長崎が初めてはなかったようです。古代にも地球上で核を使った戦争が行われていた。
後、死海は長い間生命体がいないと知られているが、核爆発を古代に起こした事があって、その時に魚は絶滅したとされています。まさに死海という名そのものと思います。+29
-1
-
1025. 匿名 2016/02/19(金) 20:47:20
加藤段蔵
通称Γ飛び加藤」と呼ばれる戦国時代の伊賀出身の忍者
目眩ましという幻術を得意とする。
ある時、上杉謙信の居城春日山城の城下で大木に黒い大きな牛を繋いで群衆を集めていた。
群衆の見守る中、段蔵は大きな黒牛を頭から飲み込み、最後は自分自身も消えて見せた。
群衆はあっけにとられ見ていたが、その内の木に登って見ていた一人が
Γ牛を飲み込むなど嘘じゃ!術者はただ牛の背に乗っただけだぞ!」と見破ってしまう。
段蔵はムッとすると懐から夕顔の苗を取り出し扇であおぎ始めると苗はみるみる蔦を伸ばし見事大輪の花を咲かせる。
群衆はその見事な手際に拍手喝采!
すると段蔵はおもむろに短剣を取り出して夕顔の花を切り落とす。
それと同時にさっき木の上で見ていた男の首が切断され、鮮血を吹き上げる胴体と一緒に地面にドサッと落ちてきた。
見ていた群衆は急激に恐怖を感じ、みな一目散にその場から逃げ去ったという。
ちなみこの加藤さんの術、Γ呑牛の術」Γ生花の術」というものだそうです。しっかり種もしかけもあるそうですが
知らない人から見たら恐怖でありミステリーでしかありませんね。
+14
-0
-
1026. 匿名 2016/02/19(金) 21:36:01
クラークスドープの金属球(Klerksdorp sphere)/南アフリカの金属球
南アフリカの西、トランスヴァール州にある葉蝋石の鉱脈で見つかった金属球。
直径4cmほどで用途不明。
これまでに鉱脈の各地で複数個発見されています。
内部が空洞のものと、繊維状のガラスのような物質が詰まったものの2種類があり、外側には球体の中心に平行に走る3本の溝があります。
同国の地質調査によると、この鉱脈が形成されたのは約28億年前という結果が出ており、
そのため「28億年前の金属球」と呼ばれることもあります。
しかし、そのまま鉱脈にあったのか、ある時代に紛れこんだのかは不明。
また、この球体は「年に1~2回自転している」事でも知られています。
金属球を展示している博物館の館長によれば、ガラスケースの中にある金属球が近くにある鉱山からの振動によって少しずつ傾くせいだといわれています。
+14
-0
-
1027. 匿名 2016/02/19(金) 21:43:50
バグダッド電池(Baghdad Battery)
イラク・バグダード近郊で1932年頃に発掘された土器の壺。
出土したのは民家遺構の中で、呪文が書かれた3つの鉢と共に置かれていました。
高さ約10cm、直径約3cm程度で、粘土を焼いて作った素焼きの土器の中に固定された銅の筒が入っており、さらにアスファルトで塞がれたシリンダーの中に鉄製の棒が差し込まれています。
また、底には何らかの液体が入っていた痕跡があります。
1938年に「電池の一種ではないか」とする論文が発表され、その後1978年に「電池と推定される器具」と展示されたことで世界中に紹介されました。
電解液として酢や葡萄酒を用いた結果、電圧0.9~2ボルト程度で発電される事が分かりましたが、
発見時と同じくアスファルトで口を閉鎖した場合はすぐに電流が止まってしまう事も確認されています。
また、壷の様式はサーサーン朝様式で、同様の構造の壷が他にも多数発見されている事、それらからパピルスの繊維が確認されている事から、
この壷は宗教的な祈祷文を入れて埋める壷であり、金属棒は巻物の芯棒だったという説もあります。
+16
-0
-
1028. 匿名 2016/02/19(金) 21:47:19
秦のクロムメッキ剣(Chrome-plated swords of Qin)
中国・陝西省にある「秦の始皇帝陵墓」周辺に埋納された遺跡「兵馬俑坑」から出土した剣。
兵馬俑坑は考古学史における20世紀最大の発見の1つとされ、8000体の武士俑などが出土しています。
兵たちの特徴は、「どれ一つとして同じ顔をしたものはなく」「様々な民族で混成されており」、そしてオーパーツと呼ばれる剣を腰に差していました。
長さ90cmの青銅の長剣はクロムメッキ加工が施され、製作から2200年以上が経過した現在でも光沢があり、重ねた新聞紙を切るだけの切れ味を持つそうです。
西欧におけるクロムメッキ技術は1937年にドイツで発明された近代のメッキ技術で、
鉄とクロム化合物を密閉容器に閉じ込め、水素ガス/アルゴンガスを吹き込み、1000度に熱してメッキを施すというものでした。
秦の時代にこの技術が存在したという記録はなく、150年後の漢の時代に作られた銅剣は、どれも原形をとどめないほど腐食しています。
なぜテクノロジーが継承されなかったのか、どのような技術が使われたのかは現在も不明とされています。
+17
-0
-
1029. 匿名 2016/02/19(金) 21:53:10
ピラミッド・アイ・タブレット(Pyramid with the eye in Ecuador)
エクアドルのラ・マナで発見されたといわれる石造のピラミッド型工芸品。
1980年代に金の採掘主任ギレルモ・ソトマヨーアによって、深さ10mの廃坑から300余りの遺物が発見されました。
その後、これらの遺物はソトマヨーアの知人にまとめて譲渡され、保管されていました。
1999年、遺物の中に「プロビデンスの目」に似た模様があるピラミッド・アイ・タブレットが眠っていたのが発見され、
その後ウィーンで開かれた「未解明の謎展」で大きく取り上げられました。
高さは27cmで、表面は三角形状になっており、頂点部分に一つの目が象嵌されています。
目の下部には13の水平な段が刻まれていて、底面には黄金の埋め込み細工で、オリオン座の配置が描かれています。
その下には絵文字が刻まれており、クルト・シルトマン教授の解読によると、先サンスクリット文字で「創造主の息子がやってくる」と書かれているそうです。
2005年時点で、この遺物について学術的な調査は行われていません。
+15
-1
-
1030. 匿名 2016/02/19(金) 21:56:19
古代トルコのロケット(The rocket of Ancient Tukey)
トルコの東方にあたる古代ウラルトゥ王国から出土した奇妙な彫像。
(トルコ・イスタンブールのトゥスパ遺跡から発掘という記述もあり)
遺跡の年代から約3000年前のものと推定されており、長さは23cm程度。
円錐形の機体の左右に短い水平翼があり、中央にあるコップピットのような場所には、
首の欠けてしまったパイロットが宇宙服のような服を着て、ひざを抱えるようにして座っています。
また、後方にはジェット噴射ノズルのようなものが3本付いています。
紀元前に空を飛ぶ乗り物の存在は確認されていませんが、トルコ近辺、メソポタミアには非常に発展した文明がありました。
そのため、一部では「宇宙人がシュメール人を作った」
「(王位が1万年という謎の記録がある事から)シュメール人は地球人ではなかった」などという噂が囁かれています。
+20
-1
-
1031. 匿名 2016/02/19(金) 22:00:49
カンブリア紀の金属ボルト(The metal bolt of Cambrian)
1997年にロシア・ブリャンスクで発見された、石の中に埋まっていたボルトのようなもの。
モスクワ地質研究所が石の年代を調べたところ、およそ15億年前という結果が出ました。
石の大きさは20cm程度で、後のX線検査で石の中には同様のボルトが10個ほどあるのが確認されました。
当時、15億年前はカンブリア紀と知られていた事からこの名称が付いたと思われますが、
現在の地球年表を見てみるとカンブリア爆発が起きたのは5億7000万年前で、15億年前には大陸移動による超大陸の誕生が起きており、
多細胞生物の出現は10億年~6億年前とされています。
また、ヒトの歴史は約200万年~300万年、猿人の誕生を含めても600万年~700万年なので、当然このボルトができた時代にはカケラも存在していません。
モスクワ航空大学のチェルノブロフ教授は「15億年前に地球にやってきた宇宙船が何らかの原因で故障・爆発し、飛び散った部品の一部」と主張しています。
+14
-1
-
1032. 匿名 2016/02/19(金) 22:09:36
ドロパ族の石円盤(Dropa Stones)
1938年に中国とチベットの境界に住む「ドロパ族」の地、青海省にあるインハル山脈(バインバル山麓という記述もあり)の洞窟から発見された石円盤。
ディスクは全部で716枚あり、花崗岩で作られ、内部に電気回路のようなものがあったとされています。
ロシアの検査によると、コバルトを含む金属物質が確認されたといいます。
製造年代は約1万2000年前~2万年前とされています。
また、ディスクの横からは正体不明の遺骨が数体発見された。
遺骨は幼児と思われ、身長が低く、頭が異常に大きいのが特徴だそうです。
(もっと大きく120cm程度で、洞窟には宇宙の星々が描かれていたという記述あり)
写真を見ると眼窩が大きく、奇形の水頭症などとは違うようにも見えます。
学者による調査の結果「適切な変換機があれば、ディスクに収められている電気信号を再生する事は可能だろう」ということでしたが、再生機器はいつしか失われたといいます。
遺骨
+13
-0
-
1033. 匿名 2016/02/19(金) 22:59:21
こりゃ絶対いるね、宇宙人
むしろ宇宙人の存在を無視して考える方が不自然な気がする
古代の文明が今より劣るという先入観もおかしい+40
-0
-
1034. 匿名 2016/02/19(金) 23:37:18
ここで出てる話は真面目に考古学やってる人にはトンデモすぎるんだろうけど、
こう考えた方が人生楽しいw+24
-1
-
1035. 匿名 2016/02/19(金) 23:56:11
まーたがだか数千年の歴史しかない現人類の文明が
45億年の地球の全てがわかること自体無理あるしねえw
宇宙のこともそうだけどアレコレ決めつけないで色んな想像(妄想)して楽しむのが一番かな~♪+31
-1
-
1036. 匿名 2016/02/20(土) 00:12:49
なんかの番組でやってたシミュレーションだと
文明が一旦滅びると10万年ほどで文明の痕跡がきれいさっぱり消え去るそうな
もし今の文明が滅びてまた次なる文明が興った時には
私たちってΓかつて月にまで到達した文明」とか呼ばれるのかな?
なんかカッコいい(笑)
+31
-1
-
1037. 匿名 2016/02/20(土) 01:53:15
>>1002
大丈夫と思いますよ。地球は今宇宙の生命体により監視されてますから。
ロシアでも隕石による落下がありましたが、あれも被害が少ないように、宇宙の生命体によって地球上に落ちる時には粉々にしたらしいです。その時に人間が命を落としたという事例もないし、ケガ人も出なかったと思います。そういうのも、既に計算済みです。+15
-5
-
1038. 匿名 2016/02/20(土) 05:38:34
過去にそんな優れた文明があったのなら
後世に伝える方法も編み出したはず
+8
-4
-
1039. 匿名 2016/02/20(土) 06:54:06
>>1038
はっきりと私達が理解できる物が見つかったらいいですよね
何せ言語が違うし、そもそも言語を伝達手段としていたかもわからないし
これまでのコメで出てきたオーパーツが後世に伝えたものの一部なんだろう
私達が理解できないだけかも+15
-0
-
1040. 匿名 2016/02/20(土) 07:22:14
>>20
自分たちにない歴史感のある日本を妬み、日本の歴史を覆そうとしている反日の日教組のもくろみ。
+10
-2
-
1041. 匿名 2016/02/20(土) 07:32:14
閲覧注意!!>>958の謎の文字
音声圧縮方式でも解読できないのかな?
考古学者が単独で研究するのは限界がある
多くの分野の専門家が協力すべきでない?+9
-1
-
1042. 匿名 2016/02/20(土) 09:43:26
月の宇宙船とモナリザの話って、ルワンダのユーチューバーが上げた動画のみがソースで、NASAもキレイに無視してるただのフェイクというのが専らの見方なんだよね。
だから女性のミイラも謎の文字も作り物。ちなみに月面の巨大宇宙船と呼ばれるものは日本の衛星かぐやも同じとこ撮影していて、その映像見るとどう見てもただの大きな岩なんだよ。つまり宇宙船っぽく画像を作り直していただけ。
ごめんね、夢を壊すようなこと言って。+15
-3
-
1043. 匿名 2016/02/20(土) 09:54:23
宇宙人はいると思います。
地球内外で活動してるだろうし人間との接触も果たしてると思います。
ただそれと同時に根拠のない仮説をもっともらしく仕立てて世間の反応を楽しむ釣り師みたいな存在や、人を騙すのも何とも思わない山師のような人々も多く存在すると思います。
でも、でも…
夢のある嘘なら許せちゃう気がする。こういう話って面白いんだものf(^_^;+19
-0
-
1044. 匿名 2016/02/20(土) 09:58:56
>>1042
(゚◇゚)ガーン ガラガラガッシャーン
ルワンダってアフリカですよね
映像の宇宙人をネグロイドにせずモンゴロイドにしたのはなぜだろうね+18
-1
-
1045. 匿名 2016/02/20(土) 10:01:16
全部が全部本物とは思わないけど、全部が偽物とも思わない。
例えば数年前に中国の空港上空に葉巻型UFOが出現し、現に飛行機が数時間止まったことがある。
あの共産国で多くの人々が目撃し、飛行機が止まるほどっていうのは作り話とは思えない。+25
-1
-
1046. 匿名 2016/02/20(土) 10:14:10
うーん、宇宙人の存在って私にとっては「夢」じゃないんだよね。
ほとんど「現実」。
だから夢が壊れるようなことは無いので大丈夫です。+9
-4
-
1047. 匿名 2016/02/20(土) 10:17:11
モナリザ動画、ルワンダ以外の国の人がわざわざルワンダに来てYouTubeに上げたんじゃないかと勝手に想像。
もしアメリカなんかで上げたら騒動を起こした罪で検挙されたりしかねないからね。その点ルワンダだったらなにしても規制が緩そうw内戦でそんなの構ってられないだろうしね。
これだけ凝ったことするのなら、せっかくの作品を台無しにされたくないだろうから、それだけのことはやりそう。
+11
-0
-
1048. 匿名 2016/02/20(土) 10:42:32
ロシア隕石落下事件のとき、隕石落下直前に何かの飛行物体が隕石を割ってる映像、テレビで見ませんでしたか?
スーパースロー映像でしかわからないんだけど、隕石より速いスピードで近づいて来て、一瞬で隕石を割ってどこかへ飛んで行った。
あれ、まさかロシア空軍の神パイロットがやったってわけじゃありませんよね・笑。
(だとしたら、とっくにプーチン大統領が「ロシアすごいだろ!」と発表してると思う)。
今後すべての隕石から地球を守ってくれるってわけじゃないと思うけど、あれはUFOだったと思うよ。+16
-2
-
1049. 匿名 2016/02/20(土) 10:42:58
古代人の足跡
これは解剖学的に明らかに現生人類の足跡ですが、およそ2億9000万年前の石につけられた足跡の化石です。
1987年、ニューメキシコで古生物学者によって発見されたものですがが、鳥やその他の動物につけられた足跡の化石も残っています。
しかし、この時期はペルム紀(2億9000年から2億4800年前)で、人類が地球に登場する遥か以前の時代であり、現在の科学の解釈では、鳥や恐竜でさえ存在していないのです。
謎ですね・・・。+12
-0
-
1050. 匿名 2016/02/20(土) 10:45:37
石器時代の長大トンネル
1万2000年前の石器時代に作られた巨大な網状の地下トンネルは、東はトルコから西はスコットランドまでヨーロッパ各地に見られます。
この地下遺跡がどんな方法で作られたのか分かっておらず、また、その目的も分かっていません。
+20
-0
-
1051. 匿名 2016/02/20(土) 11:13:51
ポロックの双子
1957年、イギリス、ノーサンバーランド州で、11歳のジョアンナ・ポロックと、6歳のジャクリーン・ポロックの姉妹が、悲劇的な車の事故で死にましたi。
一年後、姉妹の妹として双子のジリアンとジェニファーが生まれます。
妹のジェニファーの体には、ジャクリーンとまったく同じ場所に痣がありました。
双子は誰もおしえないのに、死んだ姉たちが遊んでいたおもちゃを欲しがるようになり、行ったこともない公園に連れていってくれるようせがむようになったのです。
当時の著名な心理学者のイアン・スティーブンソン博士は、この事例を詳しく調べ、双子は亡くなった姉たちの生まれ変わりではないかと結論づけました。
+18
-0
-
1052. 匿名 2016/02/20(土) 11:18:08
騙す人がいるのかと(゚◇゚)ガーンとはしましたが、私も宇宙人はいると思っています
リンクの動画は面白いし共感できるので興味があれば見てみてください
アポロ11号アームストロング船長の怪しい発言を月の3Dで検証されています
![宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon - YouTube]() 宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon - YouTubeyoutu.be
宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon - YouTubeyoutu.be宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon 1969年7月16日アポロ11号のアームストロング船長が 月面に着陸後、地球と交信した際に放った奇妙な言葉 「な、なんだ!?あれは!?」 「ここのベイビーはすべて巨大だ!...
+12
-0
-
1053. 匿名 2016/02/20(土) 11:27:00
アポロ11号の消えたテープ
1969年7月21日、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面を歩いた映像が、世界中に放映されましたが、当時の技術の限界で、映像はかなり不鮮明だった。限られた帯域でしか、映像のシグナルを伝送できず、地球に送るには多重送信しなくてはならなかったそうです。
さらにモニターやカメラの光学的技術の限界のせいで、コントラストや明るさの精度が低く、オリジナルのSSTVの映像の解像度も悪かったそうです。
2006年に、NASAがこのオリジナル版を含む磁気テープのデータを700箱分も紛失した大失態がが明るみになりました。
重要な証拠を失くすというこの失敗のせいで、月面歩行は捏造だったという陰謀説に油を注ぐことになったのです。
700箱も紛失ってあるのかな??
なにか公開出来ない何かが写ってたとしか思えない・・・。+19
-0
-
1054. 匿名 2016/02/20(土) 11:30:03
バブーシュカ・レディ
1963年のJ・F・ケネディ大統領の暗殺時に撮影されたフィルムに、謎めいた女性が写っています。
彼女は茶色のコートを着て、ロシアの年輩女性が被るスカーフ、バブーシュカを頭に巻き、顔の前でカメラのようなものをかまえています。
この“バブーシュカ・レディ”は、映像の中に何度も登場し、ほとんどの人々が立ち去った後もまだ現場に留まっていて、しばらくすると、エルム通りを東へと立ち去っていきました。
FBIはこの謎の女性に対して、名乗り出て、撮っていた映像を提供するよう呼びかけたが、ついに彼女が現れることはなかった。
名乗り出た者もいたがその話は矛盾点が多く、本当にバブーシュカ・レディであったのか確かな証拠がありません。
現在に至るまで、バブーシュカ・レディが誰なのかわかっておらず、なぜ、狙撃の現場にいたのか、どうしてカメラのフィルムを提出するのを拒むのか、一切謎です。
+23
-0
-
1055. 匿名 2016/02/20(土) 11:33:22
キャロライン・ウォルターの墓の謎の花束
1867年、ドイツのフライベルクという都市である悲劇が起きました。
キャロライン・ウォルターという16歳の若き女性が亡くなったのです。
彼女の姉はこの事にひどく心を痛め、彫刻家にお願いをして、彼女がベッドに横たわる姿そっくりに象った墓を作ってもらったそうです。
ここからが少しぞっとする話なのですが、それから148年間、彼女の姿をかたどった彫刻の腕の中には定期的に同じ花束が添えられているといいます。
数年でもなく数十年でもない、148年です。
+25
-0
-
1056. 匿名 2016/02/20(土) 12:59:39
>>1048さんのが気になる!!!すごい!
その映像見てみたいなー+4
-0
-
1057. 匿名 2016/02/20(土) 13:09:58
>>1056
![Make In India - YouTube]() Make In India - YouTubeyoutu.be
Make In India - YouTubeyoutu.beFrom Automobiles to Agro-products. From Hardware to Software. From Satellites to Submarines. From Televisions to Telecom. From Pharma to Biotech. From Paper ...
これですね。
+1
-6
-
1058. 匿名 2016/02/20(土) 13:16:19
「UFOの実在を示す発言」
1996年3月21日 ワシントンでの記者会見場
ジョンソン宇宙センター勤務 ケネディ・ジョンストン
「宇宙飛行士たちは月面に存在する遺跡、つまり透明なピラミッドやクリスタル質のドームなどをその目で見ている。」
アポロ14号宇宙飛行士 エドガー・ミッチェル
「月では、絶えず頭の向きを変えなければならなかったので、まだ首が痛みます。月にいるのは、私たちだけではなかったからです。NASAの専門家たちは、古代都市によく似た一部破壊された建造物に、とくに興味を抱いている。それらの写真では、構造物は驚くほど規則的な正方形と長方形による幾何学模様を形成しており、上空5~8キロから見下ろしたときの、われわれ人間の都市に似ている。私たちは、NASAの金庫の奥深くに隠されている、月面都市の廃墟や透明なピラミッド、ドームなどの写真を見たとき、見捨てられた小島の砂の上で、裸足の足跡を見つけたロビンソン・クルーソーのように感じました」
■1968年12月、アポロ8号。
乗組員「サンタクロースが付きまとっている(暗号)。」
乗組員「月の裏側だけでなく表側にも駆逐艦位大きな掘削機が幾つも地表を掘削している」
■1969年7月 アポロ11号
アームストロング船長
「クレータの反対側に別の宇宙船がいる。俺達を見張っているぞ。」
1970年4月、アポロ13号。
月への中間地点
アポロ13号乗組員「今回のサンタはやたらとしつこいぞ。 サンタがソリから2機降りてきた。底部の3ヵ所が白色。」
ヒューストン管制センター「やつらは攻撃しないから安心しろ。」
■1971年8月、アポロ15号。
乗組員「矢尻(暗号)が走っている。トラック(暗号)がある。一定の幅でハドレー山まで敷かれているみごとな構造物がある。」
■1972年4月、アポロ16号
乗組員「ストーン山の山頂にドーム群がある。ドーム群の向こう側に構築物が峡谷に向かって伸び、頂上まで伸びているものもある。フラッシュライトみたいな光景が見える。」
■1972年12月、アポロ17号。
乗組員「月の裏側のエイトケンの中に立体交差路を見た。ドームもあった。複数のトラックがクレータの端まで続いている。」
管制「ブラボーへ行け、ウイスキー、ロメオ(暗号)」
+19
-1
-
1059. 匿名 2016/02/20(土) 14:25:05
どれもおもしろいね
月の古代遺跡とかクリスタルタワーとか
まるでセーラームーン!?なんて思っちゃったよ〜w+23
-0
-
1060. 匿名 2016/02/20(土) 15:10:29
ロシアの隕石落下…
2013年のチェリャビンスク州の隕石落下事件のことかな?あれは確かに衝撃的な映像で、当時世界中で話題になってましたね
UFOらしきものは映像で強力な発光に伴うゴースト現象だろう、いやいや複数の撮影でどれにも写ってるし、マッハ2の速度を追い越せるのはUFOしかない、など言われていましたよね
でも実際は隕石が大気を通過する圧力に耐えきれなくなって分裂をしたというのが真相であり、強く光を放ったのも、分裂時にΓ爆発的なエネルギーの放出時に伴う発光」という当然の現象だったわけです。
ちなみにUFOに見えるものですが、この隕石から分離し爆発力を増した小さな隕石がメインの大きな隕石を追い越していったという普通の現象のようです
例えて言うなら、高速道路をFFの車で走行時に後ろのタイヤが外れたとします。すると軽くなって抵抗の少なくなったタイヤが自分の車本体を追い越して転げていった。そんな現象と一緒ですね
ただ、だからといって宇宙人やUFOを否定はしませんよ?今回のケースがそうだと思っただけで、もし私が地球を守る立ち場のUFOだったら、大気圏に突入する前の抵抗の少ない宇宙空間で隕石を処理するだろうなあって思っただけですw
良くも悪しくも宇宙人って人類になんらかの関わりをもってるとは思いますね
+6
-4
-
1061. 匿名 2016/02/20(土) 15:52:17
>>1047
モナリザを捏造とするソースが見つかりません
よければ教えて欲しいです+6
-1
-
1062. 匿名 2016/02/20(土) 16:25:51
モナリザの発見された宇宙船と設定されていた岩の比較写真
![apollo20-pseudospaceship22 - tasfastas]() apollo20-pseudospaceship22 - tasfastassites.google.com
apollo20-pseudospaceship22 - tasfastassites.google.comapollo20-pseudospaceship22 - tasfastasapollo20-pseudospaceship22Apollo 20 - Pseudo Spaceship - Photo Analysis - Brief ITopic The Begining of the Speculation - the photographical source as hypothetical correlation to the controversial videos.photog...
+4
-0
-
1063. 匿名 2016/02/20(土) 16:36:51
>>1056
こっちかな?
突き抜けるって…よほど比重が大きいものなのかな
慣性の法則を無視した動き方ですよね
UFOだと考えた方が自然なような…
あるいはロシア政府の捏造とも考えられなくもない+7
-3
-
1064. 匿名 2016/02/20(土) 16:40:19
アマゾン文明
古代アマゾン文明は、紀元前200~300年頃から1200年代後半までのキリスト教伝来以前に栄えた、アマゾン川流域の古代文明の総称です。
ボリビア モホス大平原に巨人族の墓があります。
総延長5000kmの道が衛星写真により発見。
1辺数キロの四角い湖、2万個以上の丘(ロマ)。
丘の一つから身長2mを超える巨人の人骨が発掘されました。
DNA分析の結果、遺伝子は中国東北部山東省のものと一致。
山東省出身の孔子の別名は長人。9尺6寸、2m以上。
ロマ
雨期には氾濫し広大な氾濫原を出現させます。このため古代人はロマとよばれるマウンド(盛土の人工島)をつくり、そこに居を構えコミュニティを作りました。そのロマの数は大小2万個も確認されています。
テラプレン
ロマ同士を結ぶ直線の交通路テラプレンをめぐらせて、行き来をしたと考えられます。このテラプレンは総延長は5000km以上になると想定されています。
人造湖
人造湖は、どれも一辺が数キロもある巨大な正方形をしています。
この湖が、自然の産物ではないことの証拠に、余分な水を取り除く排水溝らしき水路が設けられていることと、湖の周囲が一際高く土が盛られてことなどを見ても、これが人間の手によってつくられた人工の湖であることがわかります。
+18
-0
-
1065. 匿名 2016/02/20(土) 16:41:37
>>1060 さんのような考察わくわくする。こういう不思議現象の解明とかの話のほうが個人的に好きだし面白い。
最近のなんでもかんでも宇宙人とかUFOに絡める感じ、だんだんシラけてきたなー。+8
-6
-
1066. 匿名 2016/02/20(土) 16:56:28
>>1062さん ありがとうございます
英語で理解できるって羨ましい
上下の画像が違うって事ですか?
下の方が少し鮮明なだけで同じに見えますが…
σ(^_^;
+4
-0
-
1067. 匿名 2016/02/20(土) 16:57:21
色々と投稿してる者ですが、色々と解釈して頂いてうれしいです。
怪しいものもありますが、それをまた個々で調べてみたりなどして詳しく知って頂けたら幸いです。
+21
-0
-
1068. 匿名 2016/02/20(土) 17:02:12
幻のアポロ20号
20号は1976年8月16日、3名の宇宙飛行士を乗せて無事打ち上げに成功、月に行った。宛先は、Iszak D、elporte Craterの南西、月の縁だ。乗組員はウィリアム・ルートレッジCDR(ベル研究所)、レオナ・シュナイダーCSP(ベル研究所)、アレクセイ・レオノフ(ソビエトの宇宙飛行士、1年前のアポロ・ソユーズ計画。)
月の裏側に横たわる宇宙船らしき物体の調査が主な目的だった。このアポロ20号は、月面に人工物を発見し、それをコードネーム「ノアの方舟」と呼称している。月面とおぼしき地形に葉巻状の構造物が見てとれる。発見された宇宙船や廃墟、その他のオーパーツについてはNASAは一切のコメントを出していない。
![GEHEIMER APOLLO 20 FILM // SECRET APOLLO 20 FILM - YouTube]() GEHEIMER APOLLO 20 FILM // SECRET APOLLO 20 FILM - YouTubeyoutu.be
GEHEIMER APOLLO 20 FILM // SECRET APOLLO 20 FILM - YouTubeyoutu.beDies soll ein Apllo-20 Flug über den Mond von 1976 sein, mit Aufnahmen eines UFOs, welches angeblich schon 1971 entdeckt wurde. This should be a Apllo-20 fly...
+7
-2
-
1069. 匿名 2016/02/20(土) 17:13:46
>>1063さん。
>>1048です。
いろいろ探していただいて、ありがとうございます。
私が見たテレビは最近よくある2時間特番の「不思議映像大集合」みたいなものだったと思います。
テレビではもう少し映像が鮮明でわかりやすかったのですが、どう見ても偶然には見えず、意図して隕石に近づいて割ったような印象を受けました。+12
-1
-
1070. 匿名 2016/02/20(土) 17:44:14
>>1069
UFOですよね
そうでなければロシア政府の捏造かも?としましたが、それは第二次世界大戦後から米ソはテクノロジー競争が激化しているからです
米は特に捏造が疑わしく、ソは負けじと頑張りすぎて原子力事故多発…
この映像はUFOであろうがなかろうが結果的に隕石(?)を撃墜するだけの防衛機能があるからロシアを敵にまわすなという間接的なアピールになっています
仮に捏造として、それで世界が救われるのなら私はそれも有りかと思います+8
-5
-
1071. 匿名 2016/02/20(土) 18:00:35
1062です
海外のサイトで解りづらくてごめんなさい(汗
モナリザの宇宙船として引用されていた月面の写真のもととなっている、
NASAが公開している原本の写真。
これの宇宙船とされている葉巻型の部分を拡大し、解像度と輝度をあげる。
つまり影となっている部分を明るくすることにより
それの実体を明らかにしている試みです。
これを見ますと、本物の宇宙船もしくは人工物であれば
いくら解像度を上げようが宇宙船は宇宙船のまま。
しかし実際に解像度を上げた結果、影となっていた部分は岩であることが
見てとれますね。
この解像度をどんどん上げていく比較方法で、この葉巻型のものが
宇宙船ではなく岩であることが分かるのです。
YouTubeで宇宙船ぽく描かれていた映像は
NASAが公開した写真の影の部分を濃くして浮き上がらせたり、
それらしい模様を書き足した加工画像なのではないでしょうか。
NASAが所持している月面写真のうち、ほんの数%しか公開されていないと言われています。
その少数の写真の中に本物の宇宙船を写した写真を紛れ込ませるような真似を
NASAという組織が行うとは私にはとても思えないのです。
+5
-2
-
1072. 匿名 2016/02/20(土) 18:10:54
>>1042
>>NASAもキレイに無視してる
ここの部分読んで逆に本物だったんじゃないの?と逆に思った♪
>>1044
>>映像の宇宙人をネグロイドにせずモンゴロイドにしたのはなぜだろうね
ほんとですよね。モンゴロイドというのがリアルだし、偽物にわざわざ第三の目なんて入れるだろうか?
第三の目って、実際宇宙人にある生命体がいるそうですよ。額にあって、テレパシーで会話する時に、パッパッと光るそうです。+5
-5
-
1073. 匿名 2016/02/20(土) 18:20:35
>>1071さん ありがとうございます
私は宇宙船の画像が岩かどうかはもっとアップの写真を見てから判断しようと思います(疑い深くてごめんなさい)
しかし数%しか画像を公開していないなんて…NASA情報共有しようよ~!+6
-0
-
1074. 匿名 2016/02/20(土) 18:35:26
>>1063
UFOが隕石を突き抜けていく映像ですよね。こんな芸当、三次元の技術ではできません。
内部地球の方が危険を察し、隕石の中に飛び込んで粉々にしたらしいです。
チャネラーの方がそう聞いたそうです。+6
-4
-
1075. 匿名 2016/02/20(土) 19:13:09
聖ヤヌアリウスの血
305年にローマ帝国によって斬首された、ナポリの守護聖人、聖ヤヌアリウスの乾いた血を、聖人の保存された首のそばに置くと、液状化し、泡立つという。これが年に18回も起こるらしいです。
この血はナポリの安泰と関係があり、血が液体になると、町は火山の噴火や地震、疫病から守られ、液化しないと、差し迫る災害の予兆だと言われています。
1980年は液化せず、イタリア南部で起きた地震のため、3000人近くが亡くなりました。
+18
-0
-
1076. 匿名 2016/02/20(土) 19:15:33
パドヴァの聖アントニウスの腐らない舌
1231年、パドヴァの聖アントニウスは、麦角中毒になり、ろくな手当も受けられないまま35歳で亡くなりました。
死後30年たってから、その遺体を掘り返すと、舌だけが柔らかなまま、まるで生きているような状態で完璧に残っていたといいます。
聖アントニウスは生前、弁のたつたぐいまれな伝道師で、聖書の知識も豊富だったため、舌が腐敗せずに神聖なまま残っていたのも納得がいきます。
この舌はすぐに尊い聖遺物となり、2013年には巡礼者たちがこれをひと目見ようとウェストミンスター大聖堂に押し寄せました。
この年は、舌が発見されて750年目の記念すべき年でもありました。
+9
-1
-
1077. 匿名 2016/02/20(土) 19:25:22
白亜紀の指
出土したのはアメリカのテキサス州グレンローズから数キロはなれたチョークマウンテンの泥炭土層からこの土地に住む住民がたまたま発見したものです。
この地層からは絶滅した鱗木類の化石も見つかっており指の化石と鱗木の化石は、ほぼ同時代の白亜紀のものとされています。
外観を見た感じでは爪も残った指の化石にしか見えません。
この指の化石は成人女性の指ではないかという声もありますが、単なる指に似ているだけではないかと思われたため切断して調べてみました。
すると切断面で皮膚の組織や骨髄などあり明らかに人間の指であることは間違いないと鑑定されました。
また、このように肉質そのまま化石化することは非常に珍しいことで、高圧で瞬時に固まれば可能とされていますが白亜紀にそのような高圧を出すことは可能だったのか疑問です。+16
-0
-
1078. 匿名 2016/02/20(土) 20:31:03
アポロ12号月面着陸時
半透明のピラミッド型UFOを目撃、それらに監視されていました。そのUFOは月面上の数メートルにホバリングしており、暗黒の空へ虹色の光を放っていました。1969年、嵐の海に着陸したアポロ宇宙飛行士も同じUFOを目撃し、それは後に“縞模様の眼鏡”と呼ばれるようになりました。
英国のストーンサークルを彷彿とさせる構造岩。
月面上の浮遊物
+11
-0
-
1079. 匿名 2016/02/20(土) 20:44:18
この指を撮影したのはエジプトへの古代遺跡発掘に情熱を注ぐスイスのグレゴリー・シュペリ(56歳)。
過去に何度もエジプトを訪れ発掘調査を行っていたが、1988年、エジプトの盗掘者グループから連絡を受けました。
彼らは「300ドル払えば、“お宝”を見せてやる」と持ちかけたそうです。
その話に乗り、首都カイロから100キロ北東にある農場に向かいました。
お金を支払うと、彼らはぼろ布に包まれた巨大なミイラ化した指を見せてくれました。
楕円形の箱に入っていたその指は、曲がった状態で驚くほど軽かったといいます。
シュペリは売ってほしいと交渉を持ちかけましたが、アラーの御名の下、指を売ることはできないと拒否されたそうです。
結局写真だけを撮影しこの場を後にしました。
その後、指のことが頭を離れないシュペリは2009年、再びエジプトへと向かいましや。
あの時の盗掘者グループを血眼になって探し回りましたが結局見つからなかったと言います。
今どこにあるのでしょうね・・・。
+10
-0
-
1080. 匿名 2016/02/20(土) 20:58:35
アタカマ・ヒューマノイド
アタカマ・ヒューマノイドは2003年10月19日、オスカー・ムニョスという男性が、アタカマ砂漠のゴーストタウンラノリアで発見したもので、ムニョス氏は発見当初、このミイラに関し、「人間とは異なる9本の肋骨があり、頭の形が極端に長く膨らんでいて、皮膚はウロコで覆われているようだった」と語っています。
結局このミイラは人間の胎児だったそうだ。胎児というか胎児サイズで出産後6~8年生き延びた男性だということなのだそうです。
その証拠に呼吸し、食べ物を代謝した後が見られたといいます。
これは突然変異ではないかとみられています。
これは、米カリフォルニア州スタンフォード大学の幹細胞生物学研究スタッフが行ったエックス線テストやDNA鑑定で明らかになったもので、エイリアンなどではなく、猿でもなく、人間の遺伝子を持っていたといいます。
そう言われても人には見えません・・・。
+20
-0
-
1081. 匿名 2016/02/20(土) 22:27:58
この人たちはシュメール人ではないかもしれません
コーカソイドの特徴をよく表現してはいますが、実際こんな人間はいませんよね
人がモンスターに見える映像をご存知ですか?
![人がモンスターに見える?!話題の動画【やりすぎ都市伝説】 - YouTube]() 人がモンスターに見える?!話題の動画【やりすぎ都市伝説】 - YouTubeyoutu.be
人がモンスターに見える?!話題の動画【やりすぎ都市伝説】 - YouTubeyoutu.be【やりすぎ都市伝説】2週連続2時間SP 主題:人がモンスターに見える?!話題の動画 語り:有村昆 内容: ・全米でも話題になった目の錯覚を利用した動画 ・ある一点を見つめながら動画を見ていくと... やりすぎコージープレゼンツ動画
ふだん見てる顔でないと違うパーツが強調されて見えてしまうのです
このことから目が異常に大きく表現されているコーカソイドはシュメール人ではないと考えられませんか+10
-1
-
1082. 匿名 2016/02/20(土) 22:58:30
>>1070です
このトピにしてはマイナスがついちゃいましたので、ついでに最近のモヤモヤをぶちまけてスッキリしようと思います
m(_ _)mごめんなさい
アメリカが人類初「重力波」を捉えました
日本の『かぐら』が建設中の今…
タイミング的にモヤモヤするわー
あー私って結構ブラックだわ+4
-4
-
1083. 匿名 2016/02/20(土) 23:54:27
>>1074ですが、どうやったのか抜粋しました。
「隕石を破壊したのは、私の宇宙船で、小惑星の後方から衝突した。私は、小惑星の尻尾から入り、前方から抜け出た。宇宙船を次元的に変態させて小惑星の中心に入り込んだ。そして、力の場を拡張させ、それによって小惑星を破壊した。」だそうです。
+5
-3
-
1084. 匿名 2016/02/21(日) 06:55:43
>>1067
ありがとうございます!
トピが閉じてしまっても楽しませていただきます
(≧∀≦)
+9
-1
-
1085. 匿名 2016/02/21(日) 10:40:53
シュメール神話によると、ニビル星のアヌンナキは労働用に人間を量産した。人間はアヌンナキと猿のハイブリッド。
シュメール人自身は自らを「ウンサンギガ」(「混ぜ合わされた者」と呼んでいた。様々な人種がいたらしい。
人類はアヌンナキが作った奴隷だったのね…+14
-3
-
1086. 匿名 2016/02/21(日) 11:20:04
ちょっと怖いのも・・・。
サギー(thugee 旅人殺戮教徒)
活動地域】インド
【設立年】12世紀ごろ
【目的】金品強奪/インド神話崇拝
12世紀ごろからインドに存在した暗殺集団。「タギー」「パンシガル」とも呼ばれる。
ヒンドゥー教の死の女神「カーリー」への供物として殺害を行った。
教義では、血はカーリーに捧げるものとされ流血を禁じていたため、殺害の方法は絞殺に限った。
裕福な旅人や旅の商人をターゲットとし、仲間が気を逸らせている間に音もなく血も流さず殺し、荷物を奪った。
凶器がスカーフによる絞殺ということで、持ち物の中に発見されても罪に問えない利点もあった。
サギーが歴史上の記録に現れ、壊滅する1853年までの約300年間に、少なくとも200万人が殺害されたと推測されている。
19世紀半ば、イギリス植民地政府の役人が、インド人の迷信として存在が信じられなかったタギーの実態を、
幾度にも渡る暗殺の危機にさらされながら暴き、2年間に渡る掃討戦でサギーは壊滅した。
メンバーの中にはベーラムという男がおり、50年間に渡る犯行で931人を殺害したと供述している。
+13
-0
-
1087. 匿名 2016/02/21(日) 11:37:06
バートリ・エルジェーベト
16世紀のハンガリーの貴族。
史上名高い連続殺人鬼とされ、吸血鬼伝説のモデルともなりました。
夫と死別後に残虐趣味はエスカレートしたようです。当初は領内の農奴の娘を誘拐したりして惨殺していたようですが、やがて下級貴族の娘を「礼儀作法を習わせる」と誘い出し、残虐行為は貴族の娘にも及ぶようになりました。残虐行為は惨く、歳若い娘を「鉄の処女(拷問器具)」で殺し、その血を浴びたり、拷問器具で指を切断し苦痛な表情を見て笑ったり、使用人に命じ娘の皮膚を切り裂いたり、性器や膣を取り出し、それを見て興奮しだすなど、性癖異常者だったといいます。
被害者の数は、エルジェーベト本人の記録では650人だといいます。+17
-1
-
1088. 匿名 2016/02/21(日) 11:42:56
メアリー1世 (イングランド女王)
メアリー1世は、イングランドとアイルランドの女王(在位:1553年7月19日 - 1558年11月17日)。ヘンリー8世と最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴン(カスティーリャ女王イサベル1世とアラゴン王フェルナンド2世の娘)との娘として、グリニッジ宮殿で生まれました。イングランド国教会に連なるプロテスタントに対する過酷な迫害から、ブラッディ・メアリー(血まみれのメアリー)と呼ばれました。
血を思わせるトマトジュースとウォッカを混ぜたカクテルの「ブラッディ・マリー」の名はこのメアリー1世の異名に由来するそうです。
+12
-1
-
1089. 匿名 2016/02/21(日) 12:04:43
血天井【伏見城】
慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いの直前、徳川家康は会津の上杉景勝討伐に向かうため、留守居として鳥居元忠(1539~1600)以下1800名に伏見城を守らせていました。
すると家康が京を離れた隙を狙っていた石田三成の軍勢9万が伏見城を攻撃!鳥居元忠とその部下は三成軍を少しでも長く京に留まらせ、会津まで援軍に行かせないようにと奮戦しましたが8月1日遂に力尽き、落城の際に鳥居元忠ら380名以上が自刃(元忠は討ち死にとの説も有)。
鳥居元忠達の遺骸は関ヶ原の戦いが終わるまで約2ヶ月もの間、伏見城に放置され、その血痕や顔や鎧のあとが縁側の板に染み付き、いくら拭いても洗っても落ちなかったそうです。
そこで供養のため寺に移した際に、足で踏む床板にしては供養にならないからと、天井にして手厚く供養しているものがいわゆる「血天井」として京都各地に今も残っているのです。
養源院、源光庵、正伝寺、宝泉院、興聖寺に移築されています。+15
-0
-
1090. 匿名 2016/02/21(日) 12:11:41
お菊井戸【姫路城】
永正年間のこと、城主小寺則職の執権青山鉄山が城の乗っ取りを計画。これに気づいた忠臣の衣笠元信は、愛妾のお菊を青山家に女中として送り込み内情をスパイさせますが青山一家のクーデターは成功。
それでもお菊は青山家に残り、龍野に逃れた元信に情報を送っていましたが、ついに町坪弾四郎に気づかれてしまい、それを盾に結婚を迫られます。
しかし、お菊はどうしても首を縦に振りません。
腹を立てた弾四郎は家宝の皿10枚のうち1枚を隠し、お菊の不始末として責め殺して井戸に投げ込みました。
それからというもの毎夜、「1枚、2枚…」と皿を数えるお菊の悲しげな声が井戸から聞こえるようになったといいます。
その後、元信ら忠臣によって鉄山一味は滅ぼされ、お菊は「於菊大明神」として十二所神社の境内にあるお菊神社に祭られています。+16
-0
-
1091. 匿名 2016/02/21(日) 12:13:46
築城時に殺された者の呪い【熊本城】
加藤清正が熊本城を築城中にある工事現場に2、3人分の働きをする評判の力持ちの者がおりました。
しかし、その正体は、過去に清正に打ち取られた者の息子であるという噂が流れ、それを信じた清正によって騙され、自ら掘った井戸に生き埋めにされてしまいます。
その後、基礎工事ができ、無事の完成を願う祈祷をした修験者が「この地には騙されて生き埋めにされた男の呪いと、その父の呪いがある!」と見抜いたために殺されてしまいます。
死のまぎわに修験者は
「私を人柱にしても呪いは無くなりません・・・きっと殿様の家は滅びるでしょう」
と言い残し、命果てたそうです。
加藤清正はこの10年後に突然亡くなり、その嫡男である加藤忠広も、配流となり2代で加藤家は滅亡します。+17
-0
-
1092. 匿名 2016/02/21(日) 12:20:22
片目の女の怨霊【丸岡城】
丸岡城を築城する際に、天守台の石垣が何度も崩れて工事が進行しなかったため、人柱を立てることとなりました。
城下に住む貧しい片目の未亡人「お静」は、息子を武士に取り立てる事を条件に人柱となる事を申し出ました。
その願いは受け入れられ、お静は人柱となって土中に埋められ、天守の工事は無事完了しました。
しかし、柴田勝豊はほどなく移封となり、その約束は果たされなくなったそうです。
それを怨んだお静の怨霊は大蛇となって暴れたといいます。
毎年4月に堀の藻を刈る頃に丸岡城は大雨に見舞われ、人々はそれをお静の涙雨と呼びました。
城内にはお静の慰霊碑が残っています。
柴田勝豊は移封された一年後に28歳という若さで死んでしまいます。
これもお静の祟りなのでしょうか。+16
-0
-
1093. 匿名 2016/02/21(日) 12:25:58
事情もわからず埋め殺された娘の祟り【松江城】
築城時に天守台の石垣を築くことができず、何度も崩れ落ちました。
人柱がなければ工事は完成しないと、工夫らの間から出たそうです。
そこで、盆踊りを開催し、その中で最も美しく、もっとも踊りの上手な少女が生け贄にされました。
娘は踊りの最中にさらわれ、事情もわからず埋め殺されたといいます。
石垣は見事にでき上がり城も無事落成したが、城主の父子が急死し改易となりました。
人々は娘の無念のたたりであると恐れたため、天守は荒れて放置されました。
その後、松平氏の入城まで天守からはすすり泣きが聞こえたという城の伝説が残ります。
また、城が揺れるとの言い伝えで城下では盆踊りをしなかったといいます。
+13
-0
-
1094. 匿名 2016/02/21(日) 20:40:13
ヘレフォードの地図(Hereford Mappa Mundi)
1300年頃に作成された、中世ヨーロッパの思想を反映した世界地図。
「マッパ・ムンディ」と呼ばれる中世ヨーロッパで製作された地図で、その中でも現存する最大のものです。
製作年代は14世紀前半で、「ホルディンガムとラフォードのリチャード」という人物の作とされています。
大きさは縦1m60cm×横1m30cm、上質な皮の紙にインクを用いて描かれています。
この地図は3つある祭壇画の中央部分で、左のパネルには大天使ガブリエル、右のパネルには受胎告知があったとされるが現存しはしていなません。
地図は東が上になっており、ヨーロッパとアフリカの表示は何故かひっくり返っています。
また、頂点付近の日本にあたるところには「HEAVEN」(天国)と記されているそうです。
そして、東の果てでは楽園エデンからの追放、最後の審判が描かれています。
+6
-0
-
1095. 匿名 2016/02/21(日) 20:42:41
石の世界地図(Ecuador stone map)
南米・エクアドルのラマナで1984年に発見された地図が石に描かれた遺物。
大きさは縦60cm、横40cm、奥行き30cm程度で、どの文明のものかは不明です。
この石には南北の回帰線を境とする世界地図が描かれており、
南北アメリカの大陸、ヨーロッパの大陸、アジアの大陸の一部のほかに、3つの未知の陸地の輪郭が刻まれています。
地図が描かれた年代は数千年前~1万年前と見られており、地球を上空から見て描いたような地図になっています。
また、石には目に似た印が2つ嵌め込まれており、
1つは中東・バビロンの辺りに、もう1つは石のあるエクアドルに埋め込まれ、白線で結ばれています。
そのため、古代メソポタミア(中東)とエクアドル(南米)の間に文化的接触があったという推測が存在します。
メソポタミアと石の目が一致するらしいです
+9
-0
-
1096. 匿名 2016/02/21(日) 20:44:55
バシキールの立体地図(Bashkir's Dashkin kamen)
ロシアのバシキール共和国にあるチャンダール村で1999年に発見された石版。
地表から約1m地下にあり、高さ1m50cm、幅1m、重さは約1tでした。
石版は3層の特殊なセメントから生み出されており、3番目の層は白色の磁器だったといいます。
製造年代は1億2000万年前といわれている(調査方法は不明)。
また、科学的な調査の結果、石版はバシキール地域の立体地図(3D MAP)であることがわかり、
そこには現存しない1万2000mにもおよぶダムのようなものが描かれていました。
バシキール国立大学の教授は、石版の上にあるレリーフが、手作業ではなく機械的に削られたという事も指摘しています。
しかし、1億年前となれば機械的作業はおろか、人類の誕生(ヒトの歴史は約200万年)すら迎えておらず、地球外生命体によるものという説も挙げられています。
+11
-0
-
1097. 匿名 2016/02/21(日) 20:46:25
中国の衛星撮影地図
正式には「長沙国南部図」と呼ばれているもので、
中国・湖南省の博物館に収蔵されている縮尺約18万分の1の地図。
2100年前の「馬王堆漢墓」(利蒼と妻子を葬ったといわれる墓)から発見されたといわれます。
馬王堆漢墓は1972年から発掘が開始されたので、発見されたのはその頃と思われます。
地図は長沙国南部を描いたものとされ、幅50cmの帛を2枚つなぎ合わせた約1mの正方形で、縮尺は17~19万分の1。
描写の中心となる部分は非常に精度が高く(河川の屈曲がほぼ現在のものと一致するなど)、
現在の測量技術はもとより、衛星写真で撮影された地図と寸部違わぬ精度で描かれています。
同地図を保管している王世平教授は、この地図の現本は数千年前にあった人口衛星から撮影した写真を元に作成されたと主張しています。
+9
-0
-
1098. 匿名 2016/02/21(日) 20:49:28
トゥーラの戦士像(Tula warrior statues)
メキシコ・イダルゴ州にある遺跡「トゥーラ=シココティトラン」の戦士像。
この遺跡にある「ピラミッドB」と呼ばれる建物は、構造などがチェチェン・イツァの建物と酷似しており、
どちらが先の技術なのか論争が繰り返された過去があります。
そのピラミッドBの上に立つ戦士像は、腰にホルスターに入った銃のようなものを携えているという話があります。
写真を見たところそのようにも見えなくもないが、何かの工具のようにも見えます。
セント・クラウド州立大学のアイヴァン・ ワトキンズ教授は、
トゥーラ以外の遺跡でも多くの切り石が未知の技術によって切断・加工されており、太陽光を利用した熱放射装置のような技術があったのではないかと主張しています。
下の写真は、装置で火を扱う戦士が彫られているという説があります
+10
-1
-
1099. 匿名 2016/02/21(日) 20:52:38
コッテンフォルストの鉄柱(Iron pillar of Kottenforst-Ville)
ドイツのコッテンフォルストにも錆びない鉄柱といわれるものが存在します。
地元では「Eiserner Mann」(英語訳でIron Man=鉄の男)と呼ばれています。
しかし、デリーの鉄柱の方が圧倒的に有名になってしまったため、写真や記述は少ない。
地上に1.4m、地中に2.7mの深さまで埋められた鉄柱で、600年以上の間錆びていない部分があるそうです。
鉄は酸素を取り込み、鉄鉱石などは酸化鉄の状態で安定し、精錬した鉄も同様に酸化するため、過程で生じる酸化鉄は錆となります。
デリーの鉄柱はインド特有のリンという不純物や観光客が触れた事などが原因として挙げられていますが、
ドイツの鉄柱はsandbed pouring techniqueという技術が使われたと考えられています。
+12
-0
-
1100. 匿名 2016/02/21(日) 21:07:29
褐炭の頭蓋骨/フライベルグ・スカル(Freiberg lignite skull)
19世紀初頭、鉱山で栄えたドイツのフライベルグで発見された頭蓋骨型の遺物。
1500万年前に形成された中央ヨーロッパの褐鉄鉱石の地層から見つかりました。
大きさは不明。褐炭、褐鉄鉱石、磁鉄鉱石で構成されています。
当初の研究では、炭素素材量が人間の頭骨の内部に蓄積し出来たものであると判断されています。
その後何度も分析が行われ、無名の一般人が作った贋作という見解が一般的でしたが、
1998年にCTスキャンで調査したところ、頭蓋骨内部が樹木の年輪のような層をなしていることが判明したといいます。
贋作だとすれば、高熱の素材(褐炭の融点が110度~360度であるため)の薄膜を1枚ずつ重ねて作り上げたことになり、
また、当時そのような手法で制作された工芸品は存在しないことから、模造品の可能性は低いとする主張があります。
+8
-0
-
1101. 匿名 2016/02/21(日) 21:10:36
トリノの聖骸布(Shroud of Turin)
聖骸布(Holy Shroud)は、キリスト教でいう「聖遺物の」1つで、
イエス・キリストが磔にされて死んだ後、その遺体を包んだとされる布。
イエスの風貌を写したという布には、「聖ヴェロニカの聖骸布」「自印聖像」など複数が主張されていますが、現存するのはイタリア・トリノの聖ヨハネ大聖堂に保管されている「トリノの聖骸布」のみとなっています。
この聖骸布は1353年、伝存の経緯は不明ですが、フランス・リレのシャルニー家が所有しているところを発見されました。
本体は縦4m、横1.1mの亜麻布(リンネル)で、布の上に痩せた男性の全身像がネガ状に転写されているように見えます。
裏には当て布があてられ、はがすと血の染みが見られます。
布上に残された全身像の痕跡から、頭を中心に縦に二つ折りにして遺骸を包んだと見られ、頭部、手首、足、脇腹部分には血痕が残っています。
信憑性については、本物か捏造かでかなり支持派・懐疑派が分かれています。
2010年には修復後初めて一般公開され、2015年にも一般公開されました。
+18
-0
-
1102. 匿名 2016/02/21(日) 21:15:36
サクサイワマンの逆さ岩(Upside down stairs of Saksaywaman)
サクサイワマンは南米・ペルー、インカ帝国の遺跡で、ナンコ・カパック二世がスペイン軍と戦った要塞とされる(現在は諸説あり)。
「逆さ岩」は、砦から100mほど離れた場所にある、4階建てのビルに相当するほどの巨大な岩石。重さは推定20,000t。
中が削られたり、くり抜かれたりしており、人の手によって加工された様相を呈します。
岩の内部には階段や廊下、らせん状の模様やソファのようなものが作られていますが、
それらの家具は奇妙なことに天地が逆さまの状態になっています。
岩をくり抜いて家のように使っていたとも考えられますが、
家具全てが天井につけられているというのは不自然であり、違う目的で作られたという説もあります。
また、この大岩を逆さまに返すほどの自然現象が起こったならその痕跡が辺りで見つかる筈ですが、その様子もないそうです。
正確な加工時期は分かっておらず、推定5000年前程度のものとされています。
+17
-0
-
1103. 匿名 2016/02/21(日) 21:17:45
オリャンタイタンボの屏風岩(The walls of Ollantaytambo)
「逆さ岩」と同じく南米ペルー、インカ帝国の遺跡にある構造物。
南米大陸周辺に興ったプレ・インカ文明の1つであるクスコ王国を1200年頃にケチュア族が建国し、
その文化を受け継ぎ興ったのがインカ帝国とされています。
この遺跡には6枚岩が連なる屏風岩があり、1枚平均の高さは4m、重さは50t~80t。
屏風岩が建てられているのは高さ150mほどの丘の上ですが、材料を切り出したと思われる場所は、
丘の下を流れるウルバンバ川の向こう岸の山の中、高さ330mの地点にあります。
インカ帝国には巨石を使った遺跡が数多く残されており、加工技術も謎のままで、表面が非常になめらかに加工されているものが多い。
また、合計300tの石を人力で切り出し、運び、並べて建てるのは不可能に近いため、その面でもオーパーツに挙げられています。
(重さ自体は人力で運搬可能と思われるが、山の斜面では木のコロが使えないと言われる)
+15
-0
-
1104. 匿名 2016/02/21(日) 21:20:39
ストーンヘンジ(Stonehenge)
イギリス・ロンドンから西に約200kmのソールズベリー周辺に位置する環状列石(ストーンサークル)。
アングロ・サクソン人がブリテン島に移住した時には既に存在していたといわれます。
ストーンヘンジは、円陣状に並んで直立した巨石と、それを囲む土塁からなります。
考古学者はこの巨石が紀元前2500年~紀元前2000年の間に立てられたと考えていますが、それを囲む土塁と堀は紀元前3100年頃まで遡るといいます。
遺跡の目的は、「太陽崇拝の祭祀場」「古代の天文台」「ケルト民族のドルイド教徒の礼拝堂」など様々な説が唱えられていますが、未だ結論はでていません。
また、建設技術についても謎が多く、
「巨石の運び方」(丸太と縄で運ぶ/水に浮かべて運ぶなど)、
「石の組み方」(巨石を立てる技術はあったと思われるが、石の上に石を寝かせる技術)、
「労働力」(何百日~何十年かかる年数、労働者、組織力などの謎)など、完全に判明していない部分も多くあります。
この地では巨石のモニュメント以前にも数々の古代建造物が造られており、
それらから当時の生活、文化、思想を紐解くことが重要な鍵とされています。
復元イメージ
+19
-0
-
1105. 匿名 2016/02/21(日) 21:22:47
大湯環状列石
大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)は、秋田県鹿角市十和田大湯にある縄文時代後期の配石遺跡。
「日本のストーンヘンジ」とも呼ばれています。
昭和6年(1931年)に発見され、約130mの距離をおいて東西に対峙する野中堂と万座の環状列石で構成されています。
山岳丘陵の末端にのびる台地の先端部に造られており、河原石を菱形や円形に並べた組石が二重の環になって配置されています。
外輪と内輪の中間帯には一本の立石を中心に細長い石が放射状に並び、
その形から「日時計」といわれており、万座・野中両方の遺跡にあります。
大湯環状列石が作られた目的に関しては諸説ありますが、近くに構造が似ている遺跡があり、
これは墓であることが明らかになっているため、大規模な共同墓地ではないかという説が有力視されています。
+13
-0
-
1106. 匿名 2016/02/21(日) 21:25:02
王位石
王位石(おえいし)は、長崎県野崎島の沖ノ神島神社にある巨石。
野崎島は長崎県五島列島の北東部に位置する島で、住民表が1人分だけ置かれているほぼ無人の島。
旧石器時代から戦国時代にかけての遺跡や遺物が多数出土している事から、太古より人が住んでいたとされます。
沖の神島神社は飛鳥時代にあたる704年に建てられた社で、五島で最も古い神社といわれています。
王位石は頂上までの高さ24m、両柱の幅12m、頂上の巨石は5m×3mという大きな石の構造物で、
この奇妙な石の配置は自然の産物か、人の手によるものかは不明とされています。
+15
-0
-
1107. 匿名 2016/02/21(日) 21:30:32
スフィンクスと侍の写った写真
1998年に河田家で発見された写真。
幕末期、交渉のためヨーロッパを訪問した外交奉行・池田筑後守長発たちの一行が、
途中エジプトを経由し、その際ギザのピラミッドを訪れています。
この時、スフィンクスを背景に記念写真が撮影されました。
写真には24人ほどの和服姿の日本人が写っています。
また、スフィンクスに登ろうとした侍もいたとみられます。
幕末とほど近い1838年に描かれた絵。写真と同様に、胴体のほとんどが埋没している事が分かります。
+19
-0
-
1108. 匿名 2016/02/21(日) 21:33:34
ボスニアのピラミッド(Bosnian Pyramid)
世界最古のピラミッドは、
紀元前2700年に建てられた古代エジプト第3王朝時代の「ジェセル王のピラミッド」(サッカラのピラミッド)とされています。
しかし、東欧のボスニア・ヘルツェゴビナから、紀元前1万年前に建てられたピラミッドが見つかったといいます。
2006年にNational Geographicがこのニュースを取り上げた事で有名になりました。
地元のアマチュア考古学者であるSemir Osmanagic氏が同国の町、ヴィスコにある小さな丘をピラミッドであると主張しており、
それは全部で5基が確認されているといいます。
外観はただの山のようですが、地下には計10マイル以上の複雑なトンネルが存在しており、これが根拠の1つとなっているそうです。
また、建設時期は1万2000年前と推定されており、これが証明されれば世界最古の記録を大幅に更新することになります。
+14
-0
-
1109. 匿名 2016/02/21(日) 21:54:59
ギガス写本(Codex Gigas)/悪魔の聖書(Devil's Bible)
「ギガス写本」は13世紀初めにボヘミア(現:チェコ)で作られたコデックスで、中世期の現存する最大の写本。
正確な製作者は不明。完成までに20年以上を要したと見られています。
高さ92cm、幅50cm、厚さ22cm、重さ75kgで、その巨大さからギガスの名が付きました。
ヴルガータ版聖書を含み、他にも様々な歴史的文書が含まれ、全てラテン語で書かれています。
最大の特徴は、聖書の文献の後に掲載されている巨大な「悪魔の挿絵」であり、
悪魔に魂を売った僧侶がこの写本を作ったという伝説から「悪魔の聖書」とも呼ばれています。
そのほか、「命日入りのカレンダー」「魔法の作法」なども書かれています。
+11
-0
-
1110. 匿名 2016/02/21(日) 22:45:28
イタリアのパレルモにあるカプチン・フランシスコ修道会地下納骨堂内のロザリア礼拝堂に安置されている伝説の美少女ミイラ、ロザリア・ロンバルド。
この少女は1920年、肺炎によりわずか二歳で亡くなった。その後の保存状態が良かったため、眠っているようにしか見えず、「ガラスの棺に眠る美少女」とも言われている。
彼女の父親であり将軍だったマリオ・ロンバルドは、ロザリアちゃんが亡くなった事に深い悲しみを覚え、その当時、死体防腐処理や剥製師として一流と名が知れ渡っていたアルフレッド・サラフィアに「少女を永遠に残してほしい」と依頼した。
彼女は8000人のミイラを安置しているパレルモのカプチン・フランシスコ修道会で最後に保存されたミイラの一つになった。
サラフィアの施した技術は素晴らしく、現在も彼女は生きているかのような姿で安置されており、毎年数多くの観光客が彼女の姿を見に来るのだ。
カプチン・フランシスコ修道地下納骨堂はグッビオ出身の16世紀の修道士「シルベルストロ」の死後建てられた。ライムストーンで建てられたこの建物は8000人のミイラを保管しており今でも美しい状態を保っている。
学術誌「Peruvian Journal El Comercio」によると、学者らはロザリアちゃんに施された死体防腐処理法の謎を解き明かす為にロザリアの棺にカメラを設置したそうだ。カメラは1分毎に写真を撮るものだったが、そのデータを見て学者等は驚愕した。
数日間観察を続けたが、数回にわたりロザリアの瞼が開いたり閉じたりを繰り返しているたのだ。また、その数年後に再度研究を行ったイタリアの研究者等が同じ現象を撮影する事に成功したのだという。
死んだ者が瞼を開くことは可能なのだろうか?
科学者らは、棺内の湿度変化によって引き起こされる自然現象なのでは?と推測した。カプチン・フランシスコ修道会の館長ダリオ・ピオンビーノ・マスカリ氏はこう推測する。「日中に窓から差し込む日の光がもたらす錯覚現象でしょう。彼女の瞼は今も、これからも、永遠に閉じたままなのでしょう。
+18
-0
-
1111. 匿名 2016/02/21(日) 23:08:40
>>1102
サクサイワマン=逆さ岩
…ってかなーり日本語とリンクしてる+21
-0
-
1112. 匿名 2016/02/21(日) 23:16:51
>>1111
気づかなかった!笑 これはすごーい!+12
-0
-
1113. 匿名 2016/02/21(日) 23:23:11
>>1111
投稿した者ですが気が付きませんでした笑
流石です!!+14
-0
-
1114. 匿名 2016/02/21(日) 23:44:37
まだ見ている人居るかな?
1995年に、トルコのアシクリ・ホユク遺跡から出土したとんでもないブレスレット!!
このブレスレットも同じ紀元前7500年頃のものと言われており、直径が10センチで、とんでもなく緻密な模様が彫られており、黒曜石で作られたことがわかっています。
しかも、表面の研磨が現在の望遠鏡のレンズに劣らないほどの技術が使われているとか。
まさに、オーパーツとしか考えられないのです。
まだこの時代、やっと農耕が一部で行われだした頃で、どちらかというと石器時代後期の時代です。
日本でいうと、縄文時代まっただ中。
世界的に言うと、世界最古の文明と言われるメソポタミア文明を起こしたシュメール人でさえもまだこの時代はやっと農耕を始めたころで、シュメール人が都市文明を築いたのはそれからもっと先の紀元前3500年頃のウルク期で4000年も開きがあるのです。
シュメール人よりさらに古い古代文明ってドキドキします。
+34
-0
-
1115. 匿名 2016/02/21(日) 23:50:41
ピラミッドキャップストーン
エジプトのカイロにある考古学博物館にピラミッドの頂点に置かれていた!と言われている彫刻を施された石が展示されています。
以外に知られていないピラミッドキャップストーンですが、これがピラミッドの頂点に置かれていたのではないか?と言われています。
細かい彫刻や、古代エジプトの文字であるヒエログリフが彫り込まれています。
写真のキャップストーンは、古代エジプト王であるアメンエムハト3世のもの。
他のピラミッドにもあったのかは不明ですが、あった可能性が高いらしいです。
ピラミッドは、何かの装置だったのではないか?と言われています。
その中で、宇宙へ向けた何だかの電波装置だったのではないか?という説があります。
そうすると、このキャップストーンから電波の送受信を行っていたのでしょうか?
なんて想像しちゃいます。
+23
-0
-
1116. 匿名 2016/02/22(月) 00:25:22
>>1112
>>1113
ありがとう(^^)
頭の中で言葉が映像と音で再現されるのです+8
-0
-
1117. 匿名 2016/02/22(月) 00:39:17
では、本日最後に・・・。
ピラミッドの謎
地球と金星の関係
ふたつのピラミッドの値に4/3πを掛けてみると・・・
地球を赤道半径だけの完全な球体として体積を求めてみると
偶然なのでしょうか・・・。
それとも・・・・。+18
-1
-
1118. 匿名 2016/02/22(月) 01:02:31
>>1117
ピラミッドは地球の縮図ですね すごい
お疲れさまです
(・ω・)ノシ (-_-)zzz+21
-1
-
1119. 匿名 2016/02/22(月) 11:28:35
謎の古代都市ウバール
イスラム教の「コーラン」やアラビアンナイトにも登場する数千年前に栄え、そして滅びた謎の古代都市ウバール。
多くの研究者がウバールを探し求め続けたが見つけれずいたところに、1990年代、NASAの衛星がレーダーの追跡調査で謎だったウバール発見へと至り、その遺跡と謎を更に深めることになった大きな巨大洞窟が発見されたのです。
発掘調査で明らかになった事、それは、発見された要塞の下に巨大な石灰石洞窟「マジリス・アル・ジン(Majlis al Jinn)」が発見されたことです。
つまり、ウバールこの地下の洞窟空間へと崩れ落ちて消失してしまい、歴史から忽然と「消失」していたのです。
神の怒りですかね。
+18
-0
-
1120. 匿名 2016/02/22(月) 11:49:02
ガリバー旅行記の謎
実は、この 「ガリバー旅行記」には、当時書かれるはずのない事が書かれていました。
それは、ガリバー旅行記が出版された1726年にはまだ発見されていなかった火星の衛星フォボスとダイモスについての記述です。
火星の衛星フォボスとダイモスは発見されたのは、1877年。
つまり、151年も前に火星に2つの衛星があるという事実を作者であるスウィフトが知っていたという事になります。
どういった記述だったかと言うと、
•火星の周囲を回る2つの小さな星がある
•内側にある星(フォボス)は火星の中心からその直径の3倍の距離である
•外側にある星(ダイモス)は5倍の距離である
•内側にある星(フォボス)は10時間の公転周期で回っている
•外側にある星(ダイモス)は21時間半の公転周期で回っている
これは、ガリバーがガリバーが天空に浮かぶ「ラピュータ」という空飛ぶ島を訪れた時に、ラピュータの人が持つ天文知識を説明したものなのですが、上記にも書きましたが火星に2つの衛星があることをこの時代の人は知りえません。
実際の公転周期を比べると
フォボスの公転周期→約8時間
ダイモスの公転周期→約30時間
と、少し開きがありますが、なくはない数字。
ガリバー旅行記で書かれた「ラピュータ」でその住人が得ていた天文知識の話として書かれているが、実話だったのではないでしょうか?
しかも出版前にいろいろ修正されてるらしいから本来の内容は少し違うらしい ですし・・・。
+21
-0
-
1121. 匿名 2016/02/22(月) 18:25:13
ロシアでピラミッド発見!
ロシア北方にあるコラ半島で、人間の手によって作られたピラミッド型の遺跡が発見された。これは約9000年前のもので、エジプトのピラミッドよりも2倍も古いこととなります。
ピラミッドは単体ではなく、多くのピラミッドがあるらしです。
コラ半島は北極圏の極寒地域で、150km四方ほどの広大な無人地域の中にあるらしく、詳細な調査が困難らしいです。
実は、エジプトのピラミッドについてエジプトのエドフ神殿に気になる記述があるのです。
それは、
洪水のおきた北国ドゥアトゥンバから啓蒙された人々がやってきてピラミッドを建てた。
このドゥアトゥンバこそ、今のコラ半島であり、啓蒙された人々が“ヒュペルボレイオス” の人々の可能性があるのです。
何故かと言うと、このドゥアトゥンバについて伝えられているのが、
隠された世界の太陽がわが世界の太陽と出会う場所。
という事。
実は、日の出前に赤い光線のようなものがロシアの北方では見ることができるのです。
北緯65度ならではの見ることができる自然現象。
ドゥアトゥンバの“ドゥアト”とは、赤い光線という意味。
そして今回のピラミッドの発見。
つまり、エジプトのピラミッドの起源は現在のロシアにあったとされる理想郷“ヒュペルボレイオス” の人々がいたこのコラ半島なのかもしれないのです!!+23
-0
-
1122. 匿名 2016/02/22(月) 18:31:23
エジプトのピラミッドが太陽系を模した配置だということはよく知られています。
しかし、我が日本にも宇宙の天体を模した配置をしている場所があったのです!!
古来から日本人は自然崇拝という信仰を持っています。
その中で、岩にも神様が宿っているという“岩”に対する信仰である磐座(いわくら)。
今も多くの場所で岩をご神体として祀られている場所が多くあります。
磐座(奈良県桜井市・與喜天満神社)
その中で、大和高原のほぼ中央に聳える神野山(こうのさん/こうのやま)という山がありその山腹にある鍋倉渓。
ここには、天狗伝説があります。
鍋倉渓は、神野山の天狗と青葉山の天狗がけんかをした際、投げつけられた岩が積み重なって出来た
この伝説がなぜ今も伝わるかは不明だそうですが、この“投げつけられた岩”からできる鍋倉渓と、周りにある王塚、八畳岩、天狗岩、竜王岩の“磐座(いわくら)”の配置が宇宙のある天体達を示していたのです。
夏の大三角(画像元:wiki)で知られるアルタイル・デネブ・ベガがそれぞれ天狗岩、王塚、八畳岩の配置とピッタリと一致するらしいのです。
更に、この夏の大三角は天の川の中にあるのですが、同じ配置間隔で竜王岩がさそり座のアンタレスの配置と一致。
神野山一体の“磐座(いわくら)”の対象であるそれぞれが奇跡的に天の川を現していたのです!!!
天狗自体“神”とも言われている伝説の対象です。
古代の日本から伝わるこの伝説の対象である天狗とは宇宙の天体の配置を知っていた宇宙人=神々だったのではないでしょうか???
エジプトのピラミッドもそうですが、古代日本にも当時の天体知識を一体どうやって得ていたのか謎が多く残ります。
そして、多くの謎の中で出てくるのが空(宇宙)からやってくる神々(宇宙人)にまつわる神話や言い伝え。
やはり、古代の地球は宇宙人によって干渉されていたかもしれません。+14
-1
-
1123. 匿名 2016/02/22(月) 18:36:56
勾玉
日本古来の装飾具のひとつ“勾玉”は縄文時代には既にあったもので、まだ狩猟をメインに生活していた頃の産物です。
この勾玉には、紐を通したと思われる丸い穴が基本的にひとつあいているのが特徴。
実は、その丸い穴に謎があったのです。
物質の硬さを表す“モース硬度”という言葉を聞いたことがある方も多いはず。
勾玉は主に翡翠で作られることが多いのですが、翡翠のモース硬度は「7」。
どのくらい硬いのかと言うと、
ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる。
現在、加工で多く使用されているダイヤモンドカッターで加工するにもなかなか苦労するレベルの硬さ、それがモース硬度「7」なのです。
そんな固い物質である翡翠を一体どうやって加工し、勾玉に穴を開けたのでしょうか??
しかも、きれいな丸い穴です。
割れることなく貫通した穴です。
今のところ、どうやって加工され穴を開けることができたのかは不明。
日本各地の遺跡や古墳から数多く発見されていますが、同時の日本人には現代の技術レベルの加工技術が既に各地で確立されていた!ということになります。
一体“誰”がこの技術を作り上げたのでしょうか????+19
-2
-
1124. 匿名 2016/02/22(月) 18:43:36
ピラミッドの謎2
実は、三大ピラミッド以外のピラミッドにも同じように太陽系の惑星との不思議な謎が隠されているのです。
エジプトのカイロの南に数十キロのところにあるダシュハールにある2つのピラミッドがあります。
このピラミッドは、三大ピラミッドを建てたと言われているクフ王のお父さんであるスネフェル王が建てたと言われているピラミッドで、「赤いピラミッド」と「屈折ピラミッド」と呼ばれている大きな2つのピラミッドです。
この2つのピラミッドにも、三大ピラミッドと同じように太陽系の惑星との関係が数字に現れています。
屈折ピラミッド
屈折ピラミッドの質量:土星の比重=0.71:0.70
屈折ピラミッドの体積:土星の体積=8.091×106m3: 8.071×1014Km3
赤いピラミッド
赤いピラミッドの質量:木星の比重=1.31:1.33
赤いピラミッドの体積:木星の体積=1.425×107m3: 1.425×1015Km3
前回の三大ピラミッドもそうですが、エジプトのピラミッドには、太陽系の惑星が示されているのです。
なぜそんな大昔にこんな高度な天文知識があり、更にこんなにも大きな構造物を建設できたのでしょうか?
赤いピラミッドに至ってはエジプトのピラミッドの中でも高さが3番目に高い巨大なものです。
なぜ惑星を模す事ができたのか?
ピラミッドの本当の意味がいつかわかるといいですね。
+10
-0
-
1125. 匿名 2016/02/22(月) 18:53:29
スフィンクスの謎
旧約聖書に書かれている神から授かったとされる秘宝「ゾハル」がスフィンクスの下には眠っているという説があります。
ギザのピラミッドの地下については約数十年前までに調査が終わっており、地下には何もないとわかっていますが、スフィンクスには、何と「地下室」があるらしいのです!!!
実はスフィンクス、今は1体しか現存していませんが、大昔には2体あったと言われています。
もう1体があったとされる場所には、その残骸がみつかっているらしいのです。
日本の神社にある“狛犬”のように対になって2体並んでいたようで、現存するスフィンクスの足元と、その昔あったとされるもう1体のスフィンクスの足元にも両方に大きな“地下室”があることがわかっているのです。
ですが、何故かエジプト政府がスフィンクスの足元の地下室の発掘調査を拒否。
もし発掘調査の許可が出ればもしかするとすごいものが見つかるかもしれません。
スフィンクスが建造されていたとされる時代のエジプトの宗教の言い伝えでは、
スフィンクスの足元には、ウリムとトンミムという神から授かった「光る石」が眠っている
と言われているらしく、その「光る石」こそ、旧約聖書で神が授けたと言われる秘宝「ゾハル」ではないか?と言われているのです。
実はこの「ゾハル」ですが、これが見つかった時、世界が終わる!と言われています。
エジプト政府が発掘を許可しないのもこれが原因なのかもしれません。+17
-0
-
1126. 匿名 2016/02/22(月) 18:57:52
スフィンクスの謎2
エジプトのギザのスフィンクスが実はピラミッドよりも古い時代に作られていた!という説があります。
ギザの三大ピラミッドが約4500年前に作られたと言われており、この説ではなんとこれよりも数千年も古い今から約一万年前に作られたと言われているのです!
なぜフィンクスがピラミッドよりも前に作られていた!という説があるかというと、スフィンクスにある“痕跡”があるからです。
それは・・・
スフィンクスの体に縦溝があるから!
なぜ縦溝があることがピラミッドよりも古い理由になるのでしょうか?
エジプトのイメージと言えば暑くて乾燥した「砂漠」だと思います。
エジプトは雨がほとんど降らない乾燥地帯です。
ですが、大昔約9000年以上前は、なんとエジプトもかなり雨が降る地域だったらしいのです。
地質学者や気象学者によると、“縦溝”は雨がかなり降っていないと作られないものらしく、“縦溝”ができる原因は「水による侵食」。
大量に降る雨が長い期間をかけ、スフィンクスの体を伝って流れ落ちることによって“縦溝”はできたらしいのです。
つまり、スフィンクスはピラミッドよりももっと古い時代に作られていたのです!!!
約1万年前というと、一般的には最後の氷河期が終わり、まだ人類は洞窟に住んでいた時代で、文明はまだ誕生していなかったと言われている時期なのです。
もし本当にスフィンクスが約1万年も前に作られていたとすれば一体誰が作ったのか??
+17
-0
-
1127. 匿名 2016/02/22(月) 19:02:38
世界最古のカレンダー
スコットランド北東部のアバディーンシャーで、世界最古のカレンダーが見つかったそうです。
現在までに見つかっていた最古のカレンダーと言われていたものは、メソポタミアの遺跡にあるカレンダーで、今回みつかった物は、それよりも数千年前の物で約1万年前のものらしいのです。
バーミンガム大学のビンセント・ガフニー(Vincent Gaffney)博士ら、イギリスの考古学チームが発見したコンカレンダーは、
12個並んだ穴
どうやら「太陰暦」に基づいたものらしく、それぞれの穴は、太陽の満ち欠けを表したものらしいのです。
しかもすごいのが、約1万年前の「冬至の日」に太陽がちょうどこの穴の上を動くように掘られている。
このカレンダー相当長きにわたって使われていたようで、約4千年前まで繰り返し修復しながら使われていたそうです。
2004年にこの穴は見つかってはいたのですが、まさかこれがカレンダーだったとは多くの人を驚かせる結果になりました。
凄い知識ですよね。
+14
-0
-
1128. 匿名 2016/02/22(月) 21:00:06
月の謎
月は以前から実は内部が空洞ではないのか?という説があります。
アポロ12号が月面へ入った際、月の上空65kmから機器を捨て、その衝撃による振動が、中が空洞でなければならないような測定値だったらしいのです。
それに、月は地球の60%ほどの密度しかないらしく、中身の40%は空洞ではないかと言われています。
2009年には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のかぐやがすごい写真を撮影しました。
月表面に、直径60~70メートルもの大きな縦穴が見つかりました。
中にどんな世界が広がっているのか知りたいですね。+14
-0
-
1129. 匿名 2016/02/22(月) 21:06:14
月の謎2
地球の衛星である“月”ですが、月には偶然では説明できないような不思議な事がいろいろあります。
まずは、
月は、地球に対して常に同じ面を向けている
月の自転と地球の公転周期が一緒なのが一応原因ではありますが、偶然にしてできすぎています。
自然にこうまでぴったりと合うものなのでしょうか?
地球から見ると、月と太陽が同じ大きさに見える
これも不思議な現象です。
これは、太陽と地球との距離は、月と地球との距離の395倍で、太陽の直径は、ちょうど月の直径の395倍である、という偶然の産物です。
地球サイズの衛星としては月は大きすぎる
月の直径は、地球の直径の約27%ほど。
他の惑星と衛星の関係からみてもありえないくらい衛星との比率が月だと大きすぎます。
しかも、地球と月はぶつかることなく、離れることなく安定して動いている。
これもどう考えてもありえないくらいの偶然です。
月は地球よりも古い
宇宙飛行士が持ち帰った“月の石”の年齢。
地球の年齢は約45億年と言われていますが、その“月の石”は53億年や、200億年というとんでもなく古いものであるという発表がありました。
地球どころか、太陽系もない時代の産物であると。
いつも見慣れていますが不思議な星ですよね・・・+22
-0
-
1130. 匿名 2016/02/22(月) 22:43:10
なにか知りたい事とかリクエストが有れば是非。
+14
-0
-
1131. 匿名 2016/02/23(火) 08:19:02
>>1115
「UFOに乗ったことがある」という外国の方が書かれた本で、ピラミッドの上でUFOが停止し、何らかのエネルギーを充電してたと読んだ記憶があります。やはりピラミッドの頂点から何かのパワーが出てるのかな。+15
-1
-
1132. 匿名 2016/02/23(火) 08:27:17
>>1129
「地球から見ると、月と太陽が同じ大きさに見える 」
この事実を子供の頃に初めて知り、あまりにも不思議で、それだけで天文学者になったという方のインタビューをテレビで見たことがあります。
本当に不思議なことですよね。
これがあるから、金環日食も指輪のように見えるのだから。
宇宙の芸術ですなぁー。+23
-1
-
1133. 匿名 2016/02/23(火) 10:10:22
宇宙を舞う「光の天使」
「宇宙の天使」を見たのは、ソビエト連邦時代に打ち上げられた宇宙ステーション「サリュート7号」に搭乗していた6人の宇宙飛行士 たちで、それは1984年の事です。
司令官アルコフと他の搭乗員たちが宇宙ステーション内で日常の業務をおこなっていた時、ふいに宇宙ステーション内が「オレンジ色の光に包まれる」という事態に陥ります。それはまるで、船内が「光の洪水」で満たされるかのような状態だったそうです。
すぐに地上の管制官にこのことを報告しましたが、不思議なことに、そのオレンジ色の光は宇宙空間の外から来ているのに、「窓以外」の不透明の壁を突き抜けて宇宙ステーションの内部にオレンジの光をもたらしていました。
オレンジ色の光が宇宙ステーション内を満たしていたのはかなり短い時間で、宇宙飛行士たちは何が起きたのかよくわからなかったのですが、宇宙ステーションから外を見た飛行士たちはさらに驚きます。全員、窓から外を見ると、その宇宙空間に、7つのシルエットがあるのがわかったそうです。
そのシルエットは人間の形をしていることもすぐにわかりました。しかし、形は確かに人間なのですが、身長が大きい。彼らには全員、背中に大きな翼があり、そして、頭の後ろから強い光が輝いていたそうです。乗務員たちはその姿を見て「ああ、これは天使みたいだ」と思ったそうです。その「天使」 たちの姿は10分間ほどで消えました。
彼等が見て撮影したのは本物の天使だったのでしょうか?+15
-1
-
1134. 匿名 2016/02/23(火) 11:34:43
>>1133
このようなファンタスティックな話、私はすごく好き。
たまたま外を見たら天使のようなシルエットがあったというのではなく、その前にオレンジ色の光が差し込んだってところが、「よかったら、外見てね~」という事前告知のようで、偶然じゃないと感じる。+18
-1
-
1135. 匿名 2016/02/23(火) 11:37:56
地震に消えた帰雲城
帰雲城は当地の有力武将である内ヶ島氏の居城でした。寛正年間の1462年ころに内ヶ島為氏により築城されました。
天正13(1585)年11月29日(新暦1月18日)の午後11時ころ、東海・北陸・近畿の広い地域を襲った巨大地震によって庄川右岸の現帰雲山が大崩落を起こします。これによって、帰雲城をはじめ、時の城主内ヶ島兵庫頭氏理(うちがしまひょうごのかみうじよし)以下一族家臣と、城下300余件、推定500人余り、牛馬にいたるまでことごとくが埋没してしまったとされています。
帰雲山の大崩落箇所。いかにスゴい大崩落だったのかがよくわかります。
この時の巨大地震はM8.0~M8.1とも言われ、帰雲城は、内ヶ島一族、在家三百余軒、男女数百人とともに、埋没してしまったそうです。450年近く経った今日でも、帰雲山の大崩落ははっきりと見て取れます。阪神・淡路大震災の時はM7.3、関東大震災の時はM7.9ですので、それ以上の、わが国の内陸直下地震としては最大規模の大地震だったみたいです。
生き残ったのはたまたまこの場所を離れた4人だけだったとか・・・。
地震は本当に怖いですね。+12
-0
-
1136. 匿名 2016/02/23(火) 11:53:43
>>1129
月って一年に数センチずつ地球から遠ざかっていると聞いたことがあります
なので古代の月ははもっと大きく見えていたと…
だとしたら現代は太陽と月が同じ大きさになる貴重な時代ですね+18
-0
-
1137. 匿名 2016/02/23(火) 12:08:38
戦国大名の手紙を今風にすると・・・
・武田信玄 恋人へ送った誓文
一.ワシが言い寄ると、弥七郎はいつも腹が痛いと言って逃げた。
一.だからワシは弥七郎とは寝てない。本当だ。
一.言い訳をするとかえって怪しく感じるだろうが、神に誓って嘘はついてない。信じてくれ。
7月5日 晴信(信玄)より 春日源助さま(おそらく高坂昌信)へ
・北条氏康 息子に送る三ヶ条
・酒は朝飯の時に飲むもので、三杯までがベスト
・お前の断りなく外出する家臣はクビにしろ
・家臣が酔っぱらって他人に迷惑を掛けないよう、厳しく躾けろ
もし、お前がこれを守ってないという話を俺が聞いた時は
絶交するぞ。
8月10日 三郎(後の上杉景虎)へ
・武田勝頼 後方の城へ送った手紙
長篠の心配をしてくれてありがとう。こっちは順調だ。
織田と徳川が後詰めにきたが、びびって何もできずにいる。
これから一気に攻撃して蹴散らしてやるよ。
それより、そっちは重要な城なんだから、十分に注意してね。
あとお土産ありがとう。
5月20日 勝頼より 三浦左馬助さまへ
・織田信長 ねねに送った手紙
安土城へようこそ。お土産ありがとう。いつかお返しするね。
しかし、しばらく合わない内にすごい美人になったね。
それなのに藤吉郎(秀吉)は何か文句を言っているようだが、言語道断だ。
お前ほどの女は、禿げ鼠には二度と見つけられんだろう。
そういう訳だから、お前さんは堂々としていなさい。
ただし、女房というものは夫を立ててやるもんだから忘れないように。
あとこの手紙は羽柴(秀吉)に見せてやりなさい。
のぶより 藤吉郎の女共へ
なんだか素の武将っていいですよね笑+19
-0
-
1138. 匿名 2016/02/23(火) 12:19:21
降臨した天使に救われた少女
2008年12月23日、アメリカのノースカロライナ州チャールストンの病院で
先天性の疾患により、死を宣告された15歳の少女チェルシーが、
明るく輝く光と遭遇した後、死の淵から生還するという奇跡的な出来事がありました。
チェルシーは、極度の早産のために内臓が未発達の状態で誕生し、入院生活を送っていました。
しかし、誕生日を間近に控えた23日、彼女の母親は担当医から人工呼吸器を
外し、最後の別れをするように勧められます。
母親が病室の前で思案している時、白く輝く謎の光がチェルシーの病室の前の廊下に突如姿を現しました。
この謎の光がチェルシーに触れた瞬間、瀕死の状態にあったチェルシーの容態は
奇跡的に回復、担当医も唖然とした状態だったと言います。
この輝く光は病院の監視カメラに撮影されており、病院スタッフやチェルシーの母親、チェルシー自身も目撃しています。
+15
-0
-
1139. 匿名 2016/02/23(火) 12:28:15
太陽探索機「SOHO」の不思議な画像
2012年10月15日と2013年2月20日に、太陽探索機「SOHO」が不思議な画像を撮影しています。
掲載した画像は、SOHOが撮影し「NASA」が一般公開しているものですが、太陽の下に不思議な光があるのがわかると思います。
羽を広げたような光は、まさに天使といった感じですが、10月と2月を比べると太陽にどんどんと近づいていっているのがわかると思います。
ちなみに、この天使らしき物体は、写真だと豆粒のようですが、あくまでも宇宙のスケールですので、実際には「超巨大」です。
どのくらい巨大かというと羽根の長さは「128,400km」、「地球が10個すっぽりと入る」ほどのサイズなのです。
太陽に向かっていくことから考えると、もしかしたら太陽系を守護するような存在なのかもしれません。
+17
-0
-
1140. 匿名 2016/02/23(火) 13:32:27
>>1139
この動画、テレビでみましたよ!
この天使型の物体が、このあと太陽に突入、その後太陽内で爆発のようなものが起こり、その後この物体が太陽から突き抜けて出て来たと記憶してます。
この天使型以外にも、葉巻型の物体が太陽の端で充電みたいなことをしていて、その後スルメイカのようにスルリと太陽から抜け出た映像の紹介もありました。
不思議!!+14
-0
-
1141. 匿名 2016/02/23(火) 15:09:42
ちょっとグロ注意
首なし鶏マイク
コロラド州Fruita(フルータ、フルイタ)の農家ロイド・オルセンの家で、1945年9月10日に夕食用として1羽の鶏が首をはねられました。通常ならそのまま絶命するはずですがが、その鶏は首の無いままふらふらと歩き回り、それまでと変わらない羽づくろいや餌をついばむようなしぐさをし始めました。翌日になってもこの鶏は生存し続け、その有様に家族は食べることをあきらめ、切断した首の穴からスポイトで水と餌を与えました。
翌週になって、ロイドはソルトレイクシティのユタ大学に、マイクと名づけた鶏を持ち込みました。科学者は驚きの色を隠せなませんが、それでも調査が行なわれ、マイクの頚動脈が凝固した血液でふさがれ、失血が抑えられたのではないかと推測されました。また脳幹と片方の耳の大半が残っているので、マイクが首を失っても歩くことができるのだという推論に達しました。
結果、マイクはこの農家で飼われることになりましたが、首の無いまま生き続ける奇跡の鶏はたちまち評判となり、マイクはマネージャーとロイドとともにニューヨークやロサンゼルスなどで見世物として公開されました。話題はますます広がるとともに、マイクも順調に生き続け、体重も当初の2ポンド半から8ポンドに増えました。雑誌・新聞などのメディアにも取り上げられ、『ライフ』、『タイム』などの大手に紹介されることとなったのです。
1947年3月、そうした興行中のアリゾナ州で、マイクは餌を喉につまらせ、ロイドが興行先に給餌用のスポイトを忘れたため手の施しようもなく、窒息して死亡しました。
マイクの死後、ギネス記録に首がないまま最も長生きした鶏として記録されたそうです。
生命力って凄いですね。
+9
-0
-
1142. 匿名 2016/02/23(火) 15:20:53
フーファイター
1942年ロサンゼルス上空に出現した謎の発光編隊。米軍が迎撃するが撃墜の戦果は無し。
1942年2月25日(日本軍の真珠湾攻撃の80日後のことです)、ロサンゼルスの西、約193kmの地点を、20~25個もの点滅する「銀色の光」:未確認飛行物体の編隊が、 太平洋岸の米軍事施設および海軍基地に向かっているとの情報が海軍情報部から、極東戦略作戦本部へ発信されました。
午前2時15分、問題の物体は日本軍の航空機の疑いがあるとして、第37沿岸砲兵旅団の対空砲兵中隊が警戒体制に入ったそうです。
この銀色の20~25個の飛行編隊は湾岸近くで高度約4000mから約2600mまで降下して、戦術的飛行編隊に戦力を分散しており(各3~6機の編隊)、
軍のレーダー、探査用光学機器、ロス市警、市民などによりその存在が確認されました。
西部防衛司令部は、未確認飛行物体は防空当局に登録されておらず、これらは「合衆国の航空機ではない」と主張しました。
「ロサンゼルス・タイムス」の公式写真から見て、当時件の円盤型機械はいかなる「地球起源の航空機」とも異なり、無音で低高度を低速で (時速150m~200m)で飛行し高性能の対空放火をまったく無視するように回避しています。これだけの対空砲弾の中、1機も撃墜されなかった言うのはありえないことですよね。+9
-0
-
1143. 匿名 2016/02/23(火) 15:22:51
肉付きの面
越前の吉崎観音の霊験物語。邪悪な姑が鬼女の面をかぶって嫁を脅すと、その面が顔に食いついて外れなくなったお話。
お経を唱えると面は取れましが、内側には顔の皮膚や前頭部の毛根がついたままだったと云います。
+8
-0
-
1144. 匿名 2016/02/23(火) 15:25:56
ヴォイニッチ手稿
暗号とおぼしき未知の文字で記され、多数の彩色挿し絵が付いた230ページほどの古文書。暗号が解読できないので、
何語で書かれているのか、内容が何なのか不明です。また、多数の挿し絵も本文とは無関係であるとの説もあります。
作成時期は14世紀から16世紀頃と考えられています。アリゾナ大学で行われた放射性炭素年代測定により、 使用されている羊皮紙は1404年から1438年に作られたと判明しました。しかし執筆時期はさらに後年の可能性があります。
手稿の名称は発見者であるポーランド系アメリカ人の古書商、ウィルフリッド・ヴォイニッチ(en)にちなむ。彼は1912年に、イタリア・ローマ近郊のモンドラゴーネ寺院で同書を発見しました。現在はイェール大学付属バイネキー稀書手稿ライブラリが所蔵しています。
+9
-1
-
1145. 匿名 2016/02/23(火) 16:52:19
八幡の藪知らず
タタリの藪知らずとも呼ばれる八幡の藪知らずは、国道14号沿いの市川市役所の向かいに位置する。この藪には、一度藪にはいったら二度と出てこられなくなるという伝承があります。古くから伝わる伝承の他にも、藪の竹を切ろうとした者が大怪我をしたり、変死してしまったという噂もあるそうです。藪自体はけっして大きいわけではありません。奥行き幅とも18mに過ぎないのです。文献によると少なくとも江戸時代にはこの大きさになっていたそうです。
なぜこの地が禁足地になったかの理由についても、唯一の明確な根拠があるわけではありません。しかし諸説いずれにせよ、近隣の人たちはこの地に対して畏敬の念を抱いており、現在も立ち入る事はタブーです。
伝承の由来に関する有名な説として。
・日本武尊の陣屋説
・平良将の墓所説
・平将門の墓所説
・その他、昔の豪族・貴人の墓所とする説
・水戸黄門が迷って出てこられなかった説
・藪の中央部の窪地から毒ガスが出でいるという説
・藪に底なし沼があるという説
・葛飾八幡宮の跡地説
・近隣の行徳村の飛び地(入会地)説
あまりはっきりしていないみたいですね・・。
+8
-0
-
1146. 匿名 2016/02/23(火) 19:21:10
パタゴン”と呼ばれる“巨人
16世紀から18世紀にかけて探検家や船乗りの中である噂がささやかれていました。
まず、この伝説の巨人族“パタゴン”についてまとめてみます。
•南アフリカの南端にいたとされ、16世紀~18世紀の長きに渡り目撃されていた
•身長は約3.7メートル~4.6メートル
•毛皮の履物を履いていた
•裸であったり、毛皮を着ていたという記述が残っている
•巨人は顔を赤く塗り、目の回りは黄色、そして頬にハート型の模様を描いていた
•はじめて鏡を見たパタゴンはかなりびっくりしたらしい
•毛皮と木の棒で作ったテントで暮らしている
•生肉を食べる
•歌や踊りが好き
•弓矢を使う
•一箇所に定住せず移動しながら暮らしていた
•彼ら独自の言葉がある
•文字を持っていない
原始的な狩猟生活をしていたようで、ヨーロッパ各地からやってきた人々との文化の違いにパタゴンも驚いたと思われますが、かなり友好的な種族のようです。
1840年代にフランスのデュモンデュルビルの船隊が描いたパタゴン
1840年代に描かれた戦闘服をまとったパタゴンの族長とパタゴン族
1766年ジョン・バイロンの船がパタゴニアを訪れた際に船員(左)が子供の為のパンをパタゴニア人女性に与えているとされているイラスト
そして、このパタゴンに遭遇した探検家達についてもまとめます。
•最初にパタゴンについて提言したのは1519年に人類初の世界一周の航海に出発し、その途中で南アメリカの海岸を訪れたマゼランとその艦隊の乗組員達
•1579年、フランシス・ドレークの艦隊の船長、フランシス・フレッチャー(Francis Fletcher)はとても背の高いパタゴニア人に遭ったことを書いている。
•1590年代にはアンソニー・ニベット(Anthonie Knivet)はパタゴニアで12フィート(3.7メートル)の長さの死体を見たと主張している。
•1590年代にはオランダ船に乗っていたイギリス人ウィリアム・アダムス(三浦按針)はパタゴニア南部の島ティエラ・デル・フエゴを回っているときに船員と不自然に背の高い原住民との間に暴力的な出会いがあったと報告している。
•1766年にはジョン・バイロン(John byron)が指揮するHMSドルフィン号が世界一周の航海からイギリスに帰ってきたとき、その船員によってパタゴニアで9フィート(2.7メートル)の背丈の現地部族を見たとのうわさが流れた。
多くの探検家がパタゴンに遭遇しているのです。
因みにパタゴニアの国名の由来は1520年、フェルディナンド・マゼランが、この付近に住んでいた先住民を見て、「パタゴン」(patagon)族と命名した。「パタ」(Pata)はスペイン・ポルトガル語の「足」でありますが、「ゴン」の意味は不明だそうです。大足パタゴン族の住む土地ということからパタゴニアという名がついたと言われています。
+11
-0
-
1147. 匿名 2016/02/23(火) 19:31:14
ギルガメッシュ叙事詩
ギルガメッシュ叙事詩とは、古代メソポタミアの伝説的な王であるギルガメッシュについての物語が書かれています。
楔形文字でかかれた粘土板で、ギルガメッシュは、紀元前2600年頃に実在していたと言われている王です。
その粘土板の1つ目に、ギルガメッシュに自身の紹介文が書かれているのですがこれが謎を呼んでいるのです。
ギルガメッシュは、2/3が神、1/3が人間であった。
ここで注目されるのは、2/3や1/3という割合。
遺伝子研究が進んできた現代の医学知識と照らし合わせるととんでもないことがわかったのです。
結論から言うと
子供は、母親のDNAを2で父親のDNAを1の割合で持っている
↓
2/3が母親のDNA 、1/3が父親のDNA
これは一体どういうことなのか?
他のDNAは違いますが、ミトコンドリアDNAは母親からしか受け継がれません。
そうすると、母親、父親から受け継がれるDNA全体の割合は上記の割合と等しくなるのです。
古代のシュメール人には遺伝子の情報を知っていたのかもしれないのです。
ちなみにギルガメッシュ王は母がアヌンナキの女神リマト・ニンスンで父がウルク王のルガルバンダです。
やはりシュメール人は神(宇宙人?)と人間のハーフなのでしょうか?
+9
-0
-
1148. 匿名 2016/02/23(火) 22:00:24
メソポタミア文明の起源の復習をもう一度。
紀元前5千年頃、後にメソポタミアと呼ばれるユーフラテス河の沿岸地帯に、ある農耕民族が住み着きました。彼らの住み着いた土地は、耕作や放牧に適しており、近くの湿地帯では、魚と鳥が常に豊富に得られるという生活するには理想的な環境でした。
その農耕民族は、ウバイド人と呼ばれ、その後、千年以上もそこに住み着き、泥でレンガをつくって街や神殿をつくり、その後のメソポタミア文明の基礎をつくることになった民族です。彼らの有能で進取性に富んだ気性は、まもなく、この地を中近東で最も繁栄した地帯に押し上げていきました。ただ、彼らは、文字を持たなかったので、詳しい記録を残すことはなかったのです。
ところが、紀元前3800年頃、どこからかシュメール人と呼ばれる民族がやって来ると、信じられない大変化が起こります。文明の一大ブレークとも言うべき現象が起きたのです。メソポタミアの地は、わずかの間に、前例のない大繁栄を記録しました。そして、空前とも言える政治権力が打ち立てられたのです。それは、美術、建築、宗教は言うに及ばず、社会機構、日常の細かな慣習から楔形文字の発明に至るまで、それらは、すべて、彼らシュメール人の成せる画期的偉業でした。世界最初と言われる船や車輪つき戦車なども、この頃、シュメール人によってつくられたのです。
この後も、彼らは、エリドゥ、ウル、ウルク、ラガシュと言った高度な都市国家を次々とつくり上げていきました。
それらは、都市としては世界最古のもので、今日、我々は、この文明をメソポタミア文明と呼んでいます。
くさび形文字のほか、太陰暦、七曜制、60進法も生み、暦とともに占星術も発達、金属の鍛錬も知っていたといわれています。
エジプト文明、インダス文明の誕生にも影響を与え、両文明との交易もしていたと考えられています。
彼らは自らを「混ざり合わされた者」と呼び、自分たちは「アヌンナキ」という神々の集団によって作られたと信じていたそうです。また、「アヌンナキは金を採掘するために他の星から地球へとやってきた」と信じていたともいわれており、シュメール人の古代神話を「アヌンナキは金を採掘する労働者を求めていたので、遺伝子操作によってシュメール人を作り出した」と解釈する「古代宇宙飛行士説」支持者もいるとのこと。
何よりも不可解なのは、シュメール人が、使っていた暦です。
それは、月の満ち欠けで、年月をはかる太陰暦と呼べるもので、世界最古の暦(こよみ)と言えるものでした。
彼らの用いた暦は、驚異的とも言えるほど恐ろしく正確な暦で、日食、月食のタイミングを始め、様々な惑星の事細かな動きまで詳細に予想出来たのです。
さらに、信じられないことには、2万5920年かかって地球の地軸が円を描くという歳差運動(さいさうんどう)の周期すら知っていたのです。
記録によれば、シュメール人は、当時、すでに何百もの天文用語を使っていたことも判明しています。
彼らがどのようにして、そのような高度な天文学を持つに至ったのかはわからりません。
彼らは、世界最古とも言える60進法を基本とする数学を確立し、それに基づいて高度な暦をつくり上げたのです。
この様な高度な天文知識に加えて、恐ろしく高度な彼らシュメール人の文明が、何を手本にし、また何に影響を受けたのかは不明なのです。
ただ言えることは、シュメール文明は、紀元前3800千年ほど前に、奇跡と思える暦、高度な数学、複雑な社会機構や合金技術を持った状態で いきなり歴史に登場して来たということです。
しかもこれだけの文明を持っていたシュメール人が消滅してしまうのが一番の謎ですね。
一体彼らは何者だったのでしょうか??+9
-0
-
1149. 匿名 2016/02/23(火) 22:09:20
>>1137
信玄さん「弥七郎とは体の関係は無い!」
などと一生懸命に恋人(男…)へ訴えているけど、他の男に言い寄った時点でアウトですよね
( ̄。 ̄;)+11
-0
-
1150. 匿名 2016/02/23(火) 22:48:21
+9
-0
-
1151. 匿名 2016/02/24(水) 15:30:06
メキシコ女王伝説
島野浦で語り継がれる伝説・・・といっても、それはつい100年ちょっと前の出来事。
実際、政府も調査にのりだす程、広く信じられている伝説なのです。
江戸時代の終わり頃、ある夏の日の出来事でした。
一隻のカツオ漁船が漁を終え、島への帰港中、
ふと波間に漂う大きな木箱のようなものを見つけました。
船中の12名は老船頭の命令で、その木箱を引き上げ、
手斧で開けてみることにしました。
すると中からは、白骨化した人間の顔がのぞいたのです。
髪はフサフサの金髪、そしてその周りにはキラキラ光る石や黄金の冠などが入っていたそうです。
これを発見した漁師達は祟りをおそれ、どこかに埋める事にしました。
そして「他言は無用」と漁師達はこの事を「秘密」にしたのです。
しかし・・・月日が経つうちにこの秘密は噂となって流れ出し、島の外からも木箱(宝)探しに来る人達が出るようになったのです。戦時中、警察や軍隊も島に探しに来た程です。この間、いつしか木箱の中の亡骸は「メキシコ女王」であると言われる様になったといいます(正確な根拠不明)。しかし木箱の行方は知れず、未だどこに埋められているのか、流されてしまったのか、証拠が一切残っていない事から、真相は謎のままです+13
-0
-
1152. 匿名 2016/02/24(水) 15:58:26
アーモンドは、バラ科サクラ属の落葉高木。和名はヘントウ(扁桃)、あるいはあめんどう。ハタンキョウ(巴旦杏)とも呼ばれる(スモモとは別種)。
アーモンドはヘブライ語で「シェケディーム」といい、「見張る」「目覚める」という意味の「サクダ」や「シャカッ」と共通の起源を持つ言葉である( 現代ヘブライ語では「シャケド」(שקד)という)。
モーセの兄アロンの杖はあめんどう(アーモンド)の木で作られており、その杖が芽を出し花が咲いて実を結んだことからイスラエルの祭司族の祖となる『レビ』が選ばれた。そしてそのあめんどうの杖は、契約の箱の前に保存するようにと、旧約聖書民数記17章3節から10節に記述されている。
SF作家であるH・G・ウェルズは未来の出来事を記録した年代記『THE SHAPE OF THINGS TO COME』(邦題・世界はこうなる)を残しているが、その中に日本に関する謎めいた四行詩を残している。
Almond blossom in the spring sunshine.
Fuji-Yama gracious lady.
Island treasure home of lovely things.
Shall I never see you again?
アーモンドの花が咲き誇る 春の太陽の光の中に
富士山 優雅で美しく凛とした女性
寶の島 かわいい者達に滿ちた家庭
僕は其れ等を もう決して見る事は出來ないのだらうか?
↑「アーモンドの花が咲き誇る」という言葉で想像するに、日本に住むレビ支族が再び祭司として認識される事を予言しているのかな…と。「サクダ」って…ここでもヘブライ語と日本語は似ていますね!
「寶の島」ってのは、広島県江田島市の「寶持寺」と関係があるのかな?江田島は”音戸大橋”で本土とつながれている島で、この地域は平清盛が沈む夕日を扇で招いて1日で開削したとの伝承「日招き伝説」が残る、古くからの交通の要所です
↓そして、この詩に関して忠告した人がいるみたいなんです
「おお、あの詩に手を出しては成らん。特に日本人は手を出すな。
世の中には日本人が知らん方が良い事もあるぞ。日本の事を思ふなら
あの詩をあのまま日本語に譯すのは止めろ。君の爲だぞ。」
「ミスター・ヨシオカ、彼方のウエルズ作品の翻譯の成功を祈ります・・・・・。
唯、あのアーモンドの詩を、あのままの形で譯して廣めるのだけは、止めてゐただけないでせうか。
決して惡い意圖で言ふのでは無い。あの詩があのままの形で譯されて
日本に廣まると、間違つてとられるリスクがある。だから日本の未來の爲
世界の未來の爲に、吾の詩の譯にはアーモンドと云ふ言葉を入れずに譯して欲しい。
また、なるべく無意味な、詰まらない詩として扱つて欲しい。
其れさえ受け入れてくれれば、後は全部、彼方の好い様に譯して構わない。
其れについて、我々も今後一切、何も申しません。アーモンドの入らない
詰まらない詩に爲て下されば・・・・・。」
「其の場合、彼方は其の譯本を出せなくなります。我々には其れを出せないやうにする
力があります。然し此れは強制では無くお願ひです。吾の詩の譯に
アーモンドと云ふ言葉を出さない。吾の詩全體を目立たなくする。其の二つだけを
我々はお願ひするのです。」
「理由は知らない方が宜しいと思ひます。何しろ吾れはナンバーズの祕儀ですから。」
↑なんのこっちゃわかりませんが…ただならぬ予感がします。ご存知だったら教えてください
アーモンドの花+9
-0
-
1153. 匿名 2016/02/24(水) 17:01:06
>>1152
ではお話ししますね。
翻訳者はこのAlmond blossomを「桃の花」と誤訳せざるを得なかったのだといいます。それ程までに「アーモンドの花」は日本人には知られてはならない内容であり、それはナンバーズ(民数記)の秘儀に関わる内容だともいわれています。
そもそもH・G・ウェルズは100年前に作品内で「ミサイル」「アトミックボム」等の当時発明されていない科学用語を色々使っていることはよく知られていて、このことから実はフリーメーソンだと言われてもいます。
そして「生命の木」は桃の木だと考えれています(桃源郷や桃太郎伝説等)。ここで大事なのは実は、桃とアーモンドは近縁種。ただしアーモンドの果肉は薄くて食用にならず、食用に供しているのは仁の部分のみ。カバラの「生命の木」は花咲くアーモンドの木であらわされることが多いと言われてています。
民数記に登場するアーモンドとは・・・
主はモーセにイスラエルの人々が神のための祈る聖なる場所を造る様に命じ、六本の支柱にアーモンドの花の形をした萼と節と花弁を付けた燭台を純金でつくらせました。古代イスラエルの時代より礼拝所である幕屋の聖所にある純金の燭台にはアーモンドの花を装飾に使う事が決まり事となっており、この燭台はメノラーと呼ばれているのです。このアーモンドの七枝で作られる燭台の七は、イスラエルの民にとって完全数を表しでおり、燭台に灯される光は完全な光、即ち神そのものであることを意味します。そしてその燭台に装飾されたアーモンドの花は「復活の表象」。
アーモンドの花は大和民族がヤ・ウマトゥ(神の民)として目覚めることの暗喩にもなっているかのようです。フリーメイソンから見れば、これは日本人に知られたらマズイ内容ですね。道教で不老長寿の妙薬とされ卑弥呼の邪馬台国で大量に食されていた桃。エドガー・ケイシー療法でガン消滅に効果あると云われる生アーモンド・・・。やはり桃とアーモンドは生命の木の実なのです。
民数記にはさらにアーモンドは登場しています。
出エジプトしたヘブライの人々は、モーセとその兄アロンの指導で荒野へ出ましたが、その旅は苦難の連続。12部族の間で祭司アロンに対する不平不満が巻き起こり、モーセは12部族の族長が持つ杖を幕屋前に置き、神の判断を仰ぎました。翌日レビ族の「アロンの杖」だけが芽を吹き、アーモンドの花を咲かせた事から 神がアロンの杖を選び祝福したとして、そのままアロンに従うことになったという逸話があります。
この人々がどこに辿り着いたのか・・。
翻訳の制止を掛けたのは欧米支配者層だと思われますが、何を日本人に知られるのはマズイことなのでしょうか?
ここでのキーワードはH・G・ウェルズの四行詩には、見れなくなった対象として「富士山」「優雅で美しく凛とした女性」「宝の島」「かわいい者達に滿ちた家庭」の4つを挙げています。「僕は其れ等を もう決して見る事は出來ないのだらうか? 」という絶望的な内容が続きます。これはもうそのようなものは地上には存在しないという風にも取れますが・・・。また「宝の島」とは世界の至宝であるユダヤ3種の神器が隠されていた日本列島のことを言っているらしいのです。
多分、ウェールズ始め欧米のメーソンが日本にユダヤ神器が存在することを熟知していることを秘密にしたかったという事ではないのでしょうか?+7
-0
-
1154. 匿名 2016/02/24(水) 17:19:32
ファティマの預言
1917年、ポルトガルの一寒村、ファチマに住む3人の幼女の前に聖母マリアが6回にわたって出現し、最後の日には10万人の大観衆の前で大奇跡を現出させ、当時のヨーロッパ全土に一大センセーションを巻き起こしました。しかもその際に「人類の未来にかかわる3つのメッセージ」が託されました。これが有名な「ファティマ予言」です。
1917年5月31日、ポルトガルの小さな町ファティマで、最初の奇跡が起こりました。聖母マリアと名乗る光り輝く美しい女性が、3人の羊飼いの子どもたち(ルチア、フランシスコ、ヤシンタ)の前に現れたのです。
彼女は、自分が天国から舞い降りたことと「世界が平和であるように毎日祈りなさい」と言い、毎月13日の同じ時刻、同じ場所に来るように告げました。そして、彼女は今回を含め6回続けて出現することを約束し、消えていきました。
その後、聖母マリアの出現のうわさが広まり、その奇跡を見ようと見物人がやってきました。最後の6回目に当たる10月13日には、10万人を超える人々がファティマに集まったのでした。しかし、聖母マリアの姿を見ることができたのは羊飼いの子どもたちだけ。多くの人たちは、銀白色に輝くタマゴ型の物体が浮遊するのを見たり、光輝く太陽が現れたりと、不思議な現象を目撃したのです。
<ファティマの予言>
1 第一次大戦は終わりに近づいたが、このままでは次の法王(ピオ11世)のときに大きな不幸が起こる。
2 次の大きな不幸の前に、夜間に不思議な光が見える。これは神の警告のしるしである。
3 ロシアは誤りを世界にまき散らし、戦争をあおりたて、多くの国が滅びる(この後に重要な「第三の予言」が続くのだが、徹底した秘密となっている)
【第三の予言】が秘密となっている理由
バチカン法王庁が公認する聖母マリア再臨の地の「ファティマの予言」
第1と第2の予言に続き、人々は「第3の予言」の公表を待ちましたが、解禁となる1960年を過ぎても、「第3の予言」の内容は発表されませんでした。その理由は、当時のローマ法王が恐怖のあまり失神するほどの予言内容だったため、と言われています。
1981年5月2日には、アイルランド航空164便がハイジャックされたが、犯人はカトリック修道士で、要求は「ファティマ第三の秘密を公開せよ」でした。
60年代になってこの記録を閲覧したローマ教皇ヨハネ23世はその内容に絶句し、再度封印してしまい、続いて次代の教皇パウロ6世も再度封印を解きましたが、そのあまりの内容に、数日の間、人事不省になったといいます。
教皇ヨハネ・パウロ2世は、2005年2月23日に著作『記憶とアイデンティティー』においてファティマのメッセージの全容に関する解釈を開示し、その内容を1981年5月13日の教皇暗殺未遂事件であったと規定し、背後に20世紀に生まれた暴力的なイデオロギーに属するしっかりした組織があったと述べ、更に2005年4月に発表された遺言において核戦争なしに冷戦が終結したことを神の摂理として感謝しています。
しかし2000年に発表された文章は前の二つの預言と比べると矮小が過ぎること、前述したように40年に渡って隠匿され、60年代には当時の教皇が絶句したり発表を見送ったりする内容とはとても思えないこと、公開された「第三の秘密」は一群の兵士達によって、白衣の司教ら大勢の高位聖職者達が射殺される、とあり、1981年の事件とはあまりに食い違うことから、疑問を投げる向きがあります。
本当の第三の秘密はなんなのでしょか?
+9
-0
-
1155. 匿名 2016/02/24(水) 17:53:43
>>1153
おお~ありがとうございます!
ナンバーズとは『民数記』なのですね、このあたりから解らなかったので詳しく教えていただけて感謝感激です!
「僕は其れ等を もう決して見る事は出來ないのだらうか? 」ってやはり絶望的な内容ですよね…
>翻訳の制止を掛けたのは欧米支配者層だと思われますが、何を日本人に知られるのはマズイことなのでしょうか?
↑ほんと…日本人としてはむしろ知っていた方が対処できそうですけど(相手が神なら絶望…)
ところで…あらゆるミステリーに精通されてるだけでなく、文才もおありですね
☆(^^)☆尊敬します!
+8
-1
-
1156. 匿名 2016/02/24(水) 17:58:52
アダムとイブは禁断の果実を食べ、楽園を追放された
と聖書にありますが、日本人の場合、禁断の果実を口にしておらず、まだエデンにいる状態なのではないでしょうか?
海外から、なぜ厳格な宗教観や戒律がないのに、日本では秩序が保たれるのか…という疑問をもたれるらしいですが、
そもそもエデンで暮らす人間に戒律は不要。
そう考えると、しっくりきませんか?
江戸時代、日本人が普通に混浴を利用するのを見た西洋人は、驚き飽きれたそうです。
でも決して、日本人が卑猥だった訳ではないと思います。
むしろその逆で、彼らはただ純粋で無邪気だった…まさに楽園を追放される前のアダムとイブのように!
正直さや信頼関係を築く能力は、学力や経済力だけでは説明がつかないと思います。
私は「悪いことをすると、この世界から追い出されてしまう」という恐怖を漠然と持っています。
皆さんもそうじゃないですか?
おそらく悪事=禁断の果実なのです。
しかし悲しいことに、この楽園も永遠に続く保証はない。
もしかしたら、すでに私たちも、禁断の果実を口にし、楽園を追われつつあるのかもしれません。
妙な宗教の勧誘みたいなコメントでm(_ _)m
+15
-1
-
1157. 匿名 2016/02/24(水) 18:34:50
>>1156
確かにそうかもしれませんね。
でも別の角度から見てみるのも宜しいかと。
仏教では弥勒菩薩は現在仏であるゴータマ・ブッダ(釈迦牟尼仏)の次にブッダとなることが約束された菩薩(修行者)で、ゴータマの入滅後56億7千万年後の未来にこの世界に現われ悟りを開き、多くの人々を救済するとされています。
それまでは兜率天で修行(あるいは説法)しているといわれています。
弥勒の下生は56億7千万年後とされているが、この気の遠くなる年数は、弥勒の兜卒天での寿命が4000年であり、兜卒天の1日は地上の400年に匹敵するという説から、下生までに4000×400×12×30=5億7600万年かかるという計算に由来します。そして、後代になって5億7600万年が56億7000万年に入れ替わったと考えられています。
他の古い経典では3000年後とするものもあり、その未来仏の出現する時代は厳密には定かではなく「遠い未来」の比喩ではないかとの説もあります。
楽園を追われてもこの世に弥勒菩薩様が現れて救済して頂けるかも・・・。+10
-1
-
1158. 匿名 2016/02/24(水) 19:29:27
…φ(・ω・ )メモメモ+8
-1
-
1159. 匿名 2016/02/24(水) 19:35:23
>>930さん
シリアスな文体で書いてくれてるのに
内容がパタリロのことだからギャップに笑ってしまいました(*^^*)
教えてくれてありがとう!
偶然の一致ってありますけど、名前がすごく似てるし長髪っていうところも
リンクし過ぎててビックリしました♪
+9
-0
-
1160. 匿名 2016/02/24(水) 20:56:28
聖徳太子の謎
聖徳太子の母・間人皇女は、救世観音が胎内に入る夢を見て太子を身籠もりましたが、これは聖母マリアの夢に、天使ガブリエルが現れてイエスを受胎したことに似ています。
救世観音は「イエス・キリスト」の象徴であり、イエスと同じ星の下に生まれた太子は、キリスト精神(ヤハウェ)の受肉だということではないでしょうか。
国宝第一号に指定された広隆寺の仏像「弥勒菩薩半跏思惟像」は、再臨するイエス・キリストの象徴で、右手の親指と中指で三角形を作り、キリスト教の三位一体を表しているとも言われています。
中国で発見された景教(キリスト教)の牧師の壁画にも、太子の頭の冠に十字架が描かれ、指は弥勒菩薩像と同じように親指と中指で三角形を作っています。
「冠位十二階」はイエスの12使徒、「十七条憲法」はモーゼの十戒を彷彿させます。
原始キリスト教は、イエスの使徒によって日本に持ち込まれ、卑弥呼の鬼道(神道)を併合して神社神道の基が形成されたのではないでしょうか。
「太子は仏教を導入したが、実は隠れキリシタンだった」という説がありますが、神道自体が「隠れキリスト教」だと言えます。
もっとも、キリスト教という表現は適切ではなく、「原始キリスト教」でありますが……。
やはり太子は、何らかの理由で仏教を取り入れたものと思われます。
では、なぜ仏教を広めたのか・・・。
やがて押し寄せてくる「西洋キリスト教文明」に対抗する為だったと考えられます。
現在のキリスト教は、白人社会によって築き上げられたものであり、「原始キリスト教」とは別物です。
また、ここでいう「キリスト教文明」とは、それを背後から動かす「ユダヤ勢力」を指すのです。
これはあくまで説ですが中々考えさせられますね。
+9
-0
-
1161. 匿名 2016/02/24(水) 22:50:50
>>1130
自分は天皇家の起源に興味あるので教えてもらえたら嬉しいです
なんか友達の話では天皇はUFOに乗って地球にやってきたwwwとか言ってるし
ここ読んでたらどうやら外国から日本に渡って来た人みたいな感じなので
もともとどんな風に天皇家が誕生したのかなって…
あと「天照オオミカミ」って、神様ですか、それとも人間ですか
天皇家と何か関係あるんですかね
自分無知でホント済みません(つД`)
+8
-2
-
1162. 匿名 2016/02/24(水) 23:38:53
>>1161
良いですよ。
あくまで説ですけど・・・。
まず、天皇=神についてはここで良く出てくるシュメール人が関わってきます。
シュメールや古代バビロニアには、日像鏡、月像の首かざり、武神のシンボルである剣という三種の神器がありましたが、日本の三種の神器と同じです。 日本の天皇家に伝わる三種の神器は、鏡、勾玉(三日月?)、剣であります。
さらに一致を見るのは、日本神話では8つの首を持つヤマタノオロチを退治したときに得た草薙の剣であるのに対し、シュメールでも7つの首を持つ竜を退治したときに、三種の神器の剣を得ています。
また
日本語の大きな特徴に、語の格を示す為の語尾変化ではなく、~は、~に、~を、~に、~で、とか助詞を付加する事から、膠着語に分類されていますが、シュメール語も膠着語であり、シュメール文字は子音だけでなく母音も記す事や、日本の漢字かな混じりのような同じ構造を持つことが分かってきています。 また、日本語のルーツが良く分からない原因の一つに、文法のルーツらしきところと、単語のルーツらしきところが違うので余計にルーツを辿るのが困難化しています。
さらに
「スメ(皇)、スメラ(天皇)とは古代バビロニア語のスメル(Sumer)と同語で、ル、ラは助辞の変化、シュメールとも発音されました。このスメとは神の意で、ラテン語のスメ(Summae)も至上至高の意で同系語です。スメ(皇)をすべ(統)の意に解して“統制”の意にするのは、はなはだしい間違いで、天皇=神であり、スメル国は皇(スメ)国と一致して神国ということなのです。また、スメラギとはスメル、アグ(AK)の複称であり、ミコト(尊、命)、ミカド(天皇)の言語はミグト(Migut)の転訛で“天降る開拓者”すなわち神ということ。明津神とは、シュメール語の日神ウツ(Ut)の御子たる火神アグの権化として、この国土に降りたまわったのです。」
すなわち、
天皇の古語はすべてシュメール語で解釈できるのです。いずれも“天から降られた神”を意味しています。とすれば、古代の日本に天皇をいただいて天降った(=渡来した)民族は、シュメールの王族とその民だったのでは?と言われているのです。また肝心のシュメール人が自分達を宇宙から来た神と人間の間に出来た民族と言って居る為、宇宙人説が出てくるんですね。
また初代・神武天皇から十数代の初期天皇の実在性については、諸説あります。現代の考古学及び歴史学においては、初期天皇は典拠が神話等なので、その実在性が疑問視されています。
第10代・崇神天皇から第14代・仲哀天皇までは、実在説と非実在説がありましたが、現代では崇神天皇が実在可能性がある最初の天皇とされています。
最後に天照大神についてですが
日本神話に登場する神。皇室の祖神で、日本国民の総氏神とされています。『延喜式』では自然神として神社などに祀られた場合の「天照」は「あまてる」と称されています。
天岩戸の神隠れで有名であり、記紀によれば太陽を神格化した神であり、皇室の祖神(皇祖神)の一柱とされています。信仰の対象、土地の祭神とされる場所は伊勢神宮が特に有名ですね。
神道の神々についてはキリスト教とは違い、親兄弟が居ます。
天照大神の系譜
父 イザナギ
母 イザナミ
弟 ツクヨミ
弟 スサノオ
夫 いない(ただしスサノオとの誓約が両神の結婚を表しているという解釈もあります)
五男三女神(アマテラスとスサノオの誓約の際に生じた神:男神がスサノオが口から生んだ子、女神がアマテラスが口から生んだ子とされています)
男神 正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命
男神 天之菩卑能命
男神 天津日子根命
男神 活津日子根命
男神 熊野久須毘命
女神 多紀理毘売命 - 別名:奥津島比売命(おきつしまひめ)
女神 市寸島比売命 - 別名:狭依毘売命(さよりびめ)
女神 多岐都比売命
長くなってすみません・・・。+6
-0
-
1163. 匿名 2016/02/25(木) 03:11:46
趣向を変えて少し面白いお話を・・
徳川家康
三方ケ愿の合戦に敗戦した家康軍は、逃げる途中、空腹に耐えかね、一軒の茶屋に立寄り、そこで小豆の餅をほうばりました。
そこへ追ってきたのは武田軍、家康はあわてふためき代金を払わずに茶屋を飛び出しました。驚いた茶屋の老婆は数キロ先まで追いかけて、家康を捕まえ、殿様が食い逃げするとは何事かね、銭を払えとえらい剣幕、家康は慌てながらも、さすがは三河の婆さんと金子を手渡し、城に逃げ込んだそうです。
老婆の茶屋があった場所を「小豆餅」、老婆が餅の代金を受け取った場所を「銭取」と呼ばれるようになったとか。
そうして、やっとの思いで浜松城に逃げ帰ると何と家康は「脱糞」してました・・・。
家康は城へ入るとすぐに絵師を呼び自らを「戒める」ため、自分の絵を描かせます。家康はこの敗戦と脱糞の悔しさをバネに天下人となったのかもしれません。家康アッパレ♪
+11
-0
-
1164. 匿名 2016/02/25(木) 03:15:37
アンデルセン
極度の心配性だったらしく、外出時は非常時に建物の窓からすぐに逃げ出せるように必ずロープを持ち歩いていたそうです。さらに、眠っている間に死んだと勘違いされて、埋葬されてしまった男の噂話を聞いて以来、眠るときは枕元に「死んでません」という書置きを残していました。
世界中で愛読されていたにもかかわらず、自身は常に失恋の連続だったそうです。要因として、容姿の醜さ、若い頃より孤独な人生を送ったため人付き合いが下手だったこと、他にもラブレター代わりに自分の生い立ちから、童話作家としてデビューした事、初恋に敗れた悲しさなどを綿々と綴られた自伝を送るという変な癖があったことを指摘する人もいます。
今でいうコミュ障だったんですね笑
+13
-0
-
1165. 匿名 2016/02/25(木) 03:20:18
野口英世
まず故郷のお金持ちの娘と婚約し、帰国したら娘と結婚するという約束で結納金として300円をいただきます。さらに渡米の費用として恩師から200円をもらっちゃう。
そこでおとなしく渡米すりゃいいものを、送別の大宴会を開いた。あまりにもど派手な宴会にしちゃったので30円しか残らなかったそうです。
婚約した娘さんはどうなったのかって? けっきょく結婚しなかったのだそうです。
この娘さんの家からは結納金以外にもいろいろと金をむしりとっていたらしいから、まあ、世間でいうところの結婚詐欺ですね。+20
-0
-
1166. 匿名 2016/02/25(木) 03:48:03
明智光秀は、本能寺の後 豊臣秀吉に殺されてはいない。
殺された事にして、天海和尚という名前でその後を生きた。
+8
-0
-
1167. 匿名 2016/02/25(木) 03:49:38
ブタ戦争
ブタ戦争は、サンフアン諸島におけるアメリカ合衆国とイギリス領北アメリカ(後のカナダ)との国境をめぐる紛争の中で、1859年にアメリカとイギリス帝国が衝突した事件。サンフアン諸島はバンクーバー島と北アメリカ大陸との間にあります。
ブタを射殺したことがきっかけで発生したため「ブタ戦争」と呼ばれるようになりましたが、
他に「ブタエピソード(Pig Episode)」とも呼ばれています。
そのブタは、衝突により血が流れることのなかったこの戦争における唯一の犠牲者でした。
豚にとっては迷惑な話ですね。
+5
-0
-
1168. 匿名 2016/02/25(木) 03:57:48
クサンティッペ
ソクラテスと言えば、智人賢人を論破して回って古代ギリシャにその名を轟かしていました。
でもニート。超ニート。
嫁のクサンチッペに「そんなことしてないで仕事しろ!」といわれると反論できないのでした。
ある時クサンティッペはソクラテスに対して激しくまくしたて、彼が動じないので水を頭から浴びせました。ソクラテスは平然と「雷の後は雨はつきものだ」と語ったそうです。
ソクラテスが語ったとされる言葉にこのようなものがあります。「セミは幸せだ。なぜなら物を言わない妻がいるから」
またソクラテスが語ったとされる言葉にこのようなものもあります。「ぜひ結婚しなさい。よい妻を持てば幸せになれる。悪い妻を持てば私のように哲学者になれる」
ある日、「そんなにひどい妻なら別れたらいいじゃないか」と言った人に対し、ソクラテスが言ったそうです。「この人とうまくやっていけるようなら、他の誰とでもうまくやっていけるだろうからね」
なんだかお似合いの夫婦の気がします笑
+8
-0
-
1169. 匿名 2016/02/25(木) 04:08:51
小野篁
平安時代前期の公卿・文人。 参議・小野岑守の長男。官位は従三位・参議。異名は野相公、野宰相、その反骨精神から野狂とも称されました。小倉百人一首では参議篁(さんぎたかむら)。
嵯峨天皇のころ、「無悪善」という落書きを「悪(さが(嵯峨のこと))無くば、善けん」(「悪なからば善か らん」とも読めますが。いずれにせよ、「嵯峨天皇がいなければ良いのに」の意。)と読んでしまいます。これが読めたのは篁自身が書いたからに違いないと立腹した嵯峨天皇は激怒。
「子子子子子子子子子子子子」(子の字12個) ←コレを読めと無理難題を言われます。
そこで小野は「ねこのここねこ、ししのここじし(猫の子子猫、獅子の子子獅子)」と読み許してもらったそうです。
まるで一休さんのトンチですね。
+8
-0
-
1170. 匿名 2016/02/25(木) 09:28:17
>>1162
1161です、ありがとうございます
昔フォースカインド見たときにシュメールがどうたらって出てきたんですが
天皇の話にもシュメール人とやらが出てきてびっくりです(°A°`)
しっかりメモっときます!
+6
-0
-
1171. 匿名 2016/02/25(木) 09:50:18
>>1162さん、私は質問された方ではありませんが、
血縁がいる神…エジプト・インド・ギリシャ・日本も多神教(メソポタミア神話やウガリット神話も)
これら多神教の神話は似通っていたり、一つの出来事を他方から見た話であったりします
神話は実際にあった話ではないかと思い、もっと知りたくなりました+6
-0
-
1172. 匿名 2016/02/25(木) 10:30:47
シュメール人、天皇の話おもしろい!!!
そして日本にユダヤの三種の神器が!?!?
わくわくドキドキしながら全部見てます
書き込んでくれる方ありがとう!+11
-0
-
1173. 匿名 2016/02/25(木) 11:26:49
皆さんに楽しんで頂いて嬉しいです。
では、今日はユダヤと日本との関係説を書かせていただきます。
イスラエルにも三種の神器があることはご存知だと思います。
「出エジプト記」には、イスラエル人(ユダヤ人)がエジプトから脱出する時の話が書かれています。
神との約束の地「カナン」に辿りつくまで、イスラエル人たちはシナイ半島を40年間さまようわけですが、イスラエルの三種の神器は、その間にモーセが作らせたものです。
まず、モーセの兄にアロンという人物がいましたが、このアロンが持っていた「杖」が三種の神器の一つです。
「出エジプト記」には、「アロンの杖」がエジプトで、いくつもの災いを起こす様子が描かれています。
「出エジプト記」で最も有名なのが、ユダヤ人がエジプトを脱出する時に、モーセが「アロンの杖」を持って、神に祈ると、海が真っ二つに割れ、道ができ、そこをユダヤ人たちが渡って脱出するという話です。
その過程でアロンの杖にはアーモンドのツルが巻きつきますが、日本の三種の神器の一つ「草薙の剣」にも草のツルが巻きつきます。
「杖」と「剣」の違いはあるものの、ツルが巻きつくという意味では両者は非常によく似ています。
日本の三種の神器、二つ目に「勾玉」がありますが、実はこれは外宮に祀られているわけではありません。
もともと、天橋立にある籠神社にあった、あるモノが外宮に祀られているのです。
それは「勾玉」ではなく黄金でできた「壺」です。
そして、この黄金の壺を祀っていた所が、天橋立の籠神社の奥宮にある「真名井神社」です。
そこに祭られている神様の御神体は「真名の壺」なのです。
これが、伊勢神宮の外宮に持っていかれた…というわけです。
モーセは「マナ」というウエハースに似た食べ物を記念に残そうと、黄金の壺を作らせましたが、その壺の名前も「マナの壺」です。そう、イスラエルの三種の神器の二つ目は「マナの壺」です。
日本の「真名の壺」と、イスラエルの「マナの壺」…両者は黄金製で、しかも名前までが同じです。
そう、両者は同一なのです。
しかも、このマナの壺が天皇陵である「前方後円墳」の形の元になっているという事をご存知でしょうか?
マナの壺のシルエットを逆さにすれば、それがわかります。
最後に、日本の三種の神器の三つ目は何でしょうか?
天照大神の御神体が「鏡」だということは有名ですよね。
実はこの鏡は、陰と陽で2つあるのです。
今の女性は鏡は一つしか使いませんが、昔の女性は必ず2枚鏡を使っていました。
その理由は、2枚で合せ鏡にしないと着物の帯が締められなかったからです。
なので2枚1組の鏡を用いてたわけです。
では、イスラエルの三種の神器の三つ目は何でしょう?
それは、神がモーセに与えた10項目の戒律が焼き付けらた「石板」です。
この石板も2枚で1組です。
鏡も2枚1組、石板も2枚1組、両者は一致しています。
石板の10の戒めを自分の精神的・霊的な姿と合わせ見たのです。
要するに十戒の石板は、人の内面を確認する鏡とも言えるでしょう。
田舎の古い祠(ほこら)に行くと、石が2枚1組で祀ってありますが、これは、十戒の石板がルーツとなっていると考えられます。
つまり、日本の三種の神器は、「鏡」「勾玉」「剣」となってますが、これは、あくまでもカムフラージュです。
実際は、イスラエルの三種の神器、「十戒石板」「マナの壺」「アロンの杖」が本物の三種の神器です。
これらが日本には全て揃っていることになります。+11
-0
-
1174. 匿名 2016/02/25(木) 12:06:16
伊勢神宮の秘密
最近、天皇家と最も関係が深いとされる伊勢神宮があることを行いました。
それは、石灯籠の撤去です。
伊勢の外宮と内宮の参道にある石灯籠には六芒星が刻まれていて、日ユ同祖論の証拠としても、よく取り上げられます。
これがその石灯籠の画像。
伊勢神宮は、この石灯篭を急に全て撤去したのです。
ところが、石灯籠はある団体が昭和30年に寄進として建てたもので、 伊勢神宮の管理物ではないと主張する者も存在します。
しかし、もうそこからがカムフラージュされているのです。
なので勿論、石灯籠は伊勢神宮の管理物です。
もっと言いましょう。
全くと言っていいほど知られてませんが、実は伊勢神宮そのものが天皇家の所有物なのです。
当然、内宮も外宮もです。
ということは、石灯籠も伊勢神宮も天皇家の管理物なのです。
それくらいの小細工やカムフラージュなんていたって簡単です。
さて、伊勢神宮はこの石灯籠の撤去の理由を「危険だったから」と言っています。
そして、建てたのも石工が勝手にやったことだと…
危険だからと、急に撤去するのもおかしな話で、
ましてや、石工って「フリーメイソン」じゃん?って感じですよね(笑)
※フリーメイソンリーのシンボルマークの定規とコンパスは石工職人のギルドだったことの名残。
前に書いた籠神社もカムフラージュを行っています。
それは、籠神社には奥の宮があり、それを「真名井神社」と言います。
その途中には石碑があり、はじめはその石碑には堂々と六芒星が刻まれていました。
ところが、その六芒星は削り取られ三つ巴…すなわち666のマークに変更されたのです。
それがこの画像。
どう見ても、同じ石碑ですよね。
そう、裏社紋(本当の社紋)である六芒星が削り取られ、三つ巴(666のマーク)を彫り直したのです。
籠神社の絵馬にも六芒星と三つ巴が描かれいています。
ちなみに、真名井神社の「真名(マナ)」とは「出エジプト記」に登場する聖なる食べ物「マナ」を指しています。
この聖なる食べ物「マナ」を入れる壺がイスラエルの三種の神器「マナの壺」です。
前にも紹介しましたが、マナの壺を象った墓が「前方後円墳」で、マナを調理する時に使われた板が「マナ板」というわけです。
マナの壺は王権のシンボルとされていたものです。
籠神社にもあったとされる「真名乃壺」とイスラエルの「マナの壺」は同じ名前で、しかも陶器ではなく両者とも黄金製です。
これらでも分かるようにイスラエルと日本はともて深い関係にあるのです。+14
-1
-
1175. 匿名 2016/02/25(木) 13:52:15
天照大神男性説
天照大神が女神だと皆さん思っていると思いますが異説が有るのをご存知ですか?
実は天照大神を祀った伊勢神宮の昔の内宮に荒木田家というのがあって、
そこの神主の一族の伝承があります。
それによると、天照大神は「蛇」で、斎宮は「妃(きさき)」だそうです。
これを伊勢神宮の神官の一族が伝えているのです。
もっというと、その蛇が斎宮のところへ夜な夜な通ってたそうで、
ことを済ませた後、すぐに帰っていくと…
しかも、通った道には鱗(うろこ)が落ちていたと…
この話が様々な形に変えられ、日本の昔話として色んな地域に残っています。
また、天照大神が天岩戸にお隠れになっている時、
「アメノウズメ」という女神が外で裸踊りをしているからと、
気になって、丸い石蓋を少し開けて裸踊りを覗きます。
もし、天照大神が女神ならば、外で裸踊りしているアメノウズメに対して、 特に気にはならないはずですよね。
男神だからこそ気になって覗いたのではないでしょうか?
次はアメノウズメの裸踊りの画像です。
裸踊りを覗いたということは、女の神様では無いのではないか?
男の神様だったから覗いたのではないか?…というヒントが隠されています。
外の騒がしい様子が気になった天照大神が、
「何の騒ぎじゃ?」と、丸い蓋を僅かに開け、右目で外を覗きますが、
この時、榊に掛かった鏡を見た天照大神は、もう一人の太陽神が現れたと勘違いします。
ここで鏡というのが重要となります。
例えば、自分が右手に何か持っているとしたら、鏡に映った自分は左手に何か持っている形になります。
鏡は自分の姿をそのまま映しているように見えますが、それは逆転していいる姿ですから本当の自分の姿ではないのです。
ところで、神社というのは北向きに建っていることはご存知でしょうか?
神社には、拝殿、社殿がありますが拝む方向は全て北向きです。
そこにはなぜか鏡が置いてあり、拝む人の方向を向いています。
そこに映し出される自分の姿は左右反転しています。
北向きで左右逆転ということは東西逆転です。
普通なら、北に向かって東は右、西は左ですが、これが逆転するということは、大変深い意味があります。
東は太陽が昇るから陽で男です。
西は太陽が沈むから陰で女です。
これを鏡で逆転しなさいという意味が示唆されているわけです。
あなたの拝んでいる神様は、建て前としては女神になっているけど、
本当は男神なんだよ、という意味です。
そうした示唆が与えてあるわけです。+14
-1
-
1176. 匿名 2016/02/25(木) 14:56:22
>>1175
すみません!間違えてマイナスを押してしまいました(>_<)
とても興味深く読ませていただきました。
ここを読むのが毎日の日課です。皆さんの沢山のお話で勉強させていただいてます‼︎+12
-1
-
1177. 匿名 2016/02/25(木) 16:20:39
>>1176
どうしてそんな嘘つくの?
>>1175にマイナス押したのは私です。
記事上げてる人だって、いちいちマイナス1ついたぐらいでヘコまないと思うけど。
そんな嘘をつくあなたに驚く。+5
-9
-
1178. 匿名 2016/02/25(木) 17:36:01
>>1176さん
>>1177さん
私は携帯で+を押した後で、パソコンでここを開くとなぜか+が反映されていない事があります
どうしてでしょうかね~+14
-1
-
1179. 匿名 2016/02/25(木) 18:10:01
>>1174
石灯籠の撤去するなんて…(ー∀ー;)
そして、アーモンドってサクラにそっくりですよね。ソメイヨシノとか結実しているの見たこと無いです。じつはアーモンドだったりして…
こうなったら神社にサクラがあるのさえ…いや国を象徴する花がサクラである事も…その他いたる所にシュメールやユダヤの証拠があるのにどうするんだろう?
↓コピペです
空海は実は、ユダヤの「レビ族」の血を引いている、つまりイスラエルの末裔だそうです。
彼は四国の香川県の生まれなのですが、母方の「阿刀家」というのが、ユダヤ人で名前から判断すると、レビ族です。
祭りごと(神様の行事)一切は、レビ族しかできないのだそうです。
日本全国の祭りの象徴である「御輿」は、「契約の箱」(アーク)をもとにデザインしたと言われているのですが、そのアークが、四国の剣山に埋蔵されています。
ですから、その聖地・剣山を取り囲むように、空海の巡った四国88ヶ所があるというのも、どうやら空海が結界を張ったのではないか、と思えるわけなのです。
空海は中国(唐)に渡り、長安で密教を学ぶのですが、当時の長安には、密教・道教・景教(原始キリスト教)・イスラム教・ゾロアスター教などの人々が、世界中から学びに来ていて、そこで空海はヘブライ語を習い、景教の影響を受けたようです。
そして803年、空海(弘法大師)は最澄と共に、潅頂(頭に潅ぐの意=キリスト教の洗礼)を受け、「遍照金剛」という洗礼名を受けました。
それは、「あなたがたの光を人々の前で輝かせ」という、マタイ5:16の漢語聖書からとったものでした。
空海は新約聖書を持ちかえり、最澄は旧約聖書を持ち帰ったということです。
帰国後、最澄は天台宗を創建し、空海は真言宗を作るわけですが、 彼の仏教は釈迦が説いた原始仏教とは似ても似つかぬ教えで、「景教と混合した仏教」でした。
皇室が菊紋を用いるきっかけとなった菊の花は最澄が桓武天皇に献上したという伝説がありますが、天台宗や真言宗はかなり秘密を知っているかもしれません
アーモンドはヘブライ語で「シェケディーム」といい、「見張る」「目覚める」という意味の「サクダ」や「シャカッ」と共通の起源を持つ言葉である( 現代ヘブライ語では「シャケド」(שקד)という)。
↑「シャカッ」お釈迦さまもレビ族なんでしょうか?+12
-2
-
1180. 匿名 2016/02/25(木) 18:35:09
>>1179
かなり良い所をついてらっしゃいますね。
では、ここで出てきたレビ族について書かせて頂きますね。
レビ族とは、ヤコブの子であるレビを祖とするイスラエルの氏族の一つです。
祖であるレビはヤコブの12人の子供の1人で、祭司の一族として特別な役割を与えられ、 継承する土地を持てませんでした。
そのため、レビ族はイスラエルの12支族には数えません。
これがユダヤの祭司レビ族の服装です。
胸当ての飾りは、イスラエルの12支族を意味するものです。
実はレビ族の末裔でなければ、本神輿は担げません。
本神輿は、すなわち「アーク(聖櫃)」のことです。
本神輿(アーク)と祭りで担ぐ御神輿は同じ構造です。
「本神輿(アーク)」と「御神輿」がこちら。
※勿論、写真のアークはレプリカ。
※本神輿をアーク、聖櫃、契約の箱とも呼びます。
こうした三種の神器やアークが日本にあるからこそ、
天皇家はそれを徹底的にカムフラージュしてるわけですね。
『レイダース/失われたアーク』にも描かれていましたが、争いの元になるからです。
このことからも、天皇家とイスラエルが深く関係していることが分かって頂けると思います。
前にも書きましたが、イスラエルの聖地にある「ヘロデ門」にだって天皇家の紋章「菊の御紋」が刻まれています。
もしかすると、色々な文明が日本に集まっているのかもしれません。
他の説にはシュメール文明を滅ぼした鉄の文明と呼ばれたヒッタイトこそ日本人の祖だというものもありますよ。
+12
-0
-
1181. 匿名 2016/02/25(木) 21:31:44
「第四帝国」にまつわる不思議な話
ヒトラーの命令で、ナチス・ドイツが南極探検を実施していたことを知っている人はどれくらいいるのでしょうか?
1938年、南極にナチス・ドイツの旗を立てる遠征隊の科学者たち
ナチスの南極遠征隊に与えられたバッジのデザイン
なぜヒトラーは本気で南極進出を考えていたのでしょうか、単に基地を建設するどころか、ベルリンなみの都市まで建設するつもりであった、ともいわれています。いわゆる「ナチス第四帝国」というものです。
戦後、ドイツ国外に逃亡した元ナチスの高官は、次のような証言をしています。
「かつてアルゼンチンへ来る船の中で、ゲシュタポ長官ミュラーが不思議なことを私に言ったことがありました。これで第三帝国はおしまいだろうかという私の問いに対して、ミュラーはこう答えました。
『第三帝国は12年で終わったが、まだ第四帝国がある。総統(ヒトラー)はその準備をなされておる。
時機到来までは時間がかかるだろう。一世代や二世代、もしかしたら三世代かかるかも知れぬ。我々の生きている間に実現するかも疑わしい。しかし、それでも良いのだ。我々は偉大な第三帝国のメンバーとしてその任務を全うしたのだから』と。さらにこんな事がありました。
「ドイツには日本と同じように住民登録制度があります。この住民登録には職業、性別、年齢、家族構成などが克明に書き込まれます。戦後、ドイツに進駐した連合国側がこの住民登録でドイツ国民を調べたそうです。そこで信じられないような事実が判明しました。
住民登録と実情を照会した結果、25万人のドイツ人男女が消えてしまったという事実が浮かび上がったのです。爆撃や病気で死んだ者、捕虜となって収容所に入れられている者などをすべて除いての数字です。せまいドイツにこれだけの人間を隠せる場所などあろうはずもありません。連合国側はこの事実に直面していろいろと調べてみましたが、ハッキリとした結論は出せなかったそうです。」
またジャーナリストであるケン・スネルは1968年頃に、「ナチス第四帝国」に関する不思議な情報を入手しました。
カール・グローガーというSS(ナチス親衛隊)の大佐がおり、彼はマルチン・ボルマンの直属の部下だったというのです。しかも彼は、ドイツの敗戦に備えてヒトラーやボルマン、そして科学者ら政府の要人たちを逃亡させるルートを確保するという極秘任務についていたといいます。逃亡用の中継地点として、アジア各地の寺院も候補地として挙げられていたらしいのです。
ドイツ敗戦後、カール・グローガーは僧侶ヒップ・シーリンの寺院に身を潜めていました。そして彼は「世界で最も権力のある2人の人物に会いに行きます」と言い残して、寺院をあとにしたといいます。その後、チベットの奥地から寺院を訪れたラマ僧によれば、チベット東部の寺院に「謎の2人連れ」が滞在しており、その2人を見慣れない武器を持った兵士が護衛しているとのことでした。
1948年、カール・グローガーは再び寺院に泊まりました、そのときは3人の科学者が同行しており、僧侶は、そのうちのひとりが「宇宙旅行の鍵を握る人物だ」と紹介されたといいます。また彼らはカール・グローガーの案内で、ある場所に行ってきたと話したというのです。「そこはどこなんです?」
僧侶が何気なく聞くと、「世界の果てさ」と、カール・グローガーは笑いながら答えたといいます。
カール・グローガーが次に寺院に戻ってきたのは1951年で、このときカール・グローガーはナチスの秘密を部分的に明かしたといいます。彼は僧侶に対して次のように語ったそうです。
「私の祖国は地球上でもっとも進歩している。しかもある“別の存在”から援助を受けているんだ。“第四帝国”にとって過去は何の意味もない。たとえば、われわれが生みだしているものはすべてが驚異的なものだ。“別の世界”まで飛んでいける飛行装置や地球の中心まで侵入可能な飛行潜水艦。そう、巨大な都市も建設した。防衛システムがまた独特なんだ。」
そこまでいうと、カール・グローガーはしゃべりすぎたという表情を見せたといいます。
しかし僧侶が「そこはどこにあるのですか?」とたずねると、「空路じゃ無理だが、陸路なら行くことができる。月は見えないが、“地球の太陽”が見える……そんなところさ」と教えてくれ、翌日、彼はいずこともなく去っていったといいます。
カール・グローガーは一体どこから来たのでしょうか?
消えた25万人の人々は一体+11
-0
-
1182. 匿名 2016/02/25(木) 21:41:27
リンカーンとケネディの奇妙な一致
米国には2人の大統領にまつわる奇妙な一致が存在します。
第16代大統領アブラハム・リンカーンと
第35代大統領ジョン・F・ケネディです。
この2人には偶然とは言い難い奇妙な一致が多く存在するのです。
<2人の多くの一致点>
リンカーンが初めて議員に当選した年は1846年で、ケネディが初めて議員に当選した年は1946年・・・つまり、議員の初当選が100年違い。
•エイブラハム・リンカーンが大統領に選ばれた年は1860年で、ジョン・F・ケネディが大統領に選ばれた年は1960年・・・つまり、二人はちょうど100年違いで大統領に就任している。
•リンカーンとケネディは名前を綴ると文字数がどちらもアルファベット7文字。
•二人とも黒人の『黒人人種差別問題』に深く関わりがあった。
•二人とも〝戦争〟に深く関わりがあった。
•二人の暗殺事件は、どちらも金曜日に起きている。
•二人が殺された武器は銃で、しかも、両者とも背後から頭を撃たれている。
•二人を暗殺したとされる犯人は、どちらも護送中に、コルト社製の銃で射殺されている。
•リンカーンには、ケネディという名前の秘書がいて、ケネディにはリンカーンという名前の秘書がいた。
•どちらの秘書も暗殺当日、大統領が、その場所へ出かけることに反対していた。
•リンカーンが撃たれた場所はフォード劇場で、ケネディが撃たれた時に乗っていた車はフォード社製のリンカーン。
•リンカーンは暗殺される1週間前にメリーランドのモンローにいて、ケネディは暗殺される1週間前にマリリン・モンローと一緒にいた。
•二人とも妻の目の前で暗殺された。
•二人の大統領の妻は、ホワイトハウスに在住中に子供を亡くしている。
•リンカーンの副大統領で、任期を引き継ぎ大統領になった人物の名はアンドリュー・ジョンソンで、ケネディの副大統領で、任期を引き継ぎ大統領になった人物の名はリンドン・ジョンソン。
•リンカーンの後を引き継いだアンドリュー・ジョンソンは1808年生まれで、ケネディの後を引き継いだリンドン・ジョンソンは1908年生まれ・・・つまり、生まれた年が100年違い。
•アンドリュー・ジョンソンはリンカーン暗殺の10年後に死亡し、リンドン・ジョンソンはケネディ暗殺の10年後に死亡。
•二人のジョンソンの名前は、どちらもファーストネームまで合わせてアルファベット13文字になる。
•どちらのジョンソンも南部出身者。
•リンカーンを暗殺したジョン・ウィルクス・ブースは1839年生まれで、ケネディを暗殺したリー・ハーヴェイ・オズワルドは1939年生まれ・・・つまり、生まれた年が100年違い。
•ブースとオズワルドは、正式な名前が〝ジョン・ウィルクス・ブース〟、〝リー・ハーヴェイ・オズワルド〟と、三つの名前で人々に知られ、その三つの名前はアルファベットで書くと15文字になる。
•大統領暗殺後、ブースは劇場から逃走して倉庫で逮捕され、オズワルドは倉庫から逃走して劇場で逮捕された。
•ブースとオズワルドは、どちらも裁判が行なわれる前に暗殺された
単なる偶然なのでしょうか?+13
-0
-
1183. 匿名 2016/02/25(木) 22:47:54
>>1180
日本は多民族国家ですよね
ミトコンドリアDNAの種類のうち約26%が日本に来てますから
ヒッタイト説は=皇室で正解ですか?
伝説では桓武天皇から菊紋を使用した…とは生母の高野新笠が菊紋をもたらしたということ。彼女のもとの氏姓は和史(やまとのふひと)で、大和民族→ヤ・ウマトゥ(神の民)になる。そうなると、天皇のルーツがわからないですよね
実はここが気になっていました!+15
-1
-
1184. 匿名 2016/02/25(木) 23:53:01
>>1183
ではお答えしますね。
大正10年、石川三四郎氏が『古事記神話の新研究』で、シュメールの故地メソポタミアと日本文明との関係を追求しています。
石川氏は明治時代に活躍したキリスト教社会主義者ですがが、社会運動への弾圧が厳しくなるなかで日本を脱出。ヨーロッパや北アフリカを流転して歩いました。この本の構想はその放浪生活の中で生まれたもので、したがって用いられた資料の多くは西洋のものでした。
石川氏もまた、日本とメソポタミアの文明が非常によく似ていることを、シュメール神話と日本神話の比較などから指摘します。が、彼の場合、直接的な日本人シュメール起源説をとらず、そのメソポタミア文明の媒介者としてヒッタイト民族を置くのです。
●“鉄を発明した民族”として知られるヒッタイト人は、紀元前2000年ごろ、いずこからともなく現れて、トルコ・アナトリア高原に一大王国を築きます。その勢力はシュメール文明を継承したバビロニア王国を滅ぼし、当時、世界最強を誇ったエジプトを破るほど強大でしたが、紀元前13世紀末に突如として消息を絶ってしまいます。
ヒッタイト人もまた、シュメール人と同様、どこから現れ、どうやってその“鉄の文明”を築き、どこへ行ってしまったのか、まったく解明されていない謎の民族です。が、石川氏はいいます。
「私はこのバビロンの神話を日本に伝えたのはおそらくヒッタイト民族であろう、ヒッタイト民族はすなわち我らが天孫民族であろう、と信じる者である。」
彼はその証拠として、
【1】天忍穂耳命が「正勝吾勝勝速目」の名を自ら冠り、「吾れカチカチ」と名乗ったこと。
【2】その「カチ、カチ」民族すなわちヒッタイトであること。
【3】ヒッタイトの岩屋生活は、天孫民族の天の岩屋戸に酷似すること。
【4】天孫民族の八咫烏(やたがらす)はヒッタイトの両頭鷲像に似ていること。
【5】古事記が諸神を『柱』の語で数えるのは、ヒッタイト人が『柱』形をもって国王を表徴するのと同じ意義を持っていること。
など9項目をあげ、それを詳しく論証しています。
強大な勢力によって、当時、世界最強の
エジプト軍さえ打ち破ったヒッタイト人
●更に注目すべきことは、石川氏が“ヒッタイト人の謎”に挑戦していることです。
彼は、紀元前2004年にメソポタミアから突然姿を消したシュメール人こそ、ヒッタイト民族の祖先ではなかったか、と考えます。なぜならば、シュメール人の消失とヒッタイト人の登場は、ほとんど時期を同じくしており、シュメール人の滅亡を歌ったメソポタミアの哀歌は“彼らは遠い山中に連れ去られた”ともいっているからです。
また、アナトリアの厳しい自然の中に、突然、高度な金属技術を持った新しい文明が誕生した謎も、彼らがシュメール人だったとしたら、たちどころに理解できます。そして何よりもヒッタイト人は文字を扱うことに優れていました。ヒッタイトの遺跡のひとつでは、古代世界最大の粘土板文書図書館が発掘され、そこには、当時メソポタミアで使われていた全ての言葉が記録されていたのです。つまり、石川説もまた、少し形をかえた「日本人シュメール起源説」なのです。
つまり、直接シュメール人が日本に来たのでは無くヒッタイト人となったシュメール人が日本に来たと言う事ですね。
ヒッタイト象形文字は<カナと漢字>と考えてみると解りやすいと思われます。
すでに一部分は解りはじめ、日本語と同じ形の子音プラス母音からなる音節文字(=カナ文字など)であることは、つきとめられています。
19世紀の始めから小アジアへ旅行した人たちが、次々に発見した奇妙な象形文字があります。
しかしそれをヒッタイト文字だと確認したのは、チェコのフロズエーで、第一次欧州大戦後のことでした。
彼は固有名詞を確認することから始めて、<魚>と<父>という表意文字を発見し、続いて食事を意味するシュメール語の「ニンダ」が含まれている一節を見つけました。
それは「ヌ ニンダ・アン エッツアテニ ワダル・マ エクテニ」
と読めましたたが、何を意味するのかは、まるで判かりませんでした。
しかしその後解読が進み意味が判ります。
それが
「ヌ ニンダ・アン エッツア テニ ワダル・マ エク テニ」 は、
「汝 飲んだ あの 餌=食物 手に 渡る 間 水を 手に」 で、
『君は 航海するあいだ あの 食べ物と 真水を手に持って 飲食をする
=航海中無事で飲食も充分だ!』という、『神託』を特記したものだったのである。
いかがですか?+11
-0
-
1185. 匿名 2016/02/26(金) 06:38:04
>>1184ありがとうございます(≧∀≦)
私のは勘とコピペなので、理路整然と教えて頂けるのは嬉しいです!
よく読んで考えてからまたコメントします
本当に有りが多や~
(。・ω・。)ノシ+10
-0
-
1186. 匿名 2016/02/26(金) 09:43:40
カチカチといえば「カチカチ山」を思い出すが、ストーリーをザッと見てみよう。
――お爺さんが悪さをする狸を捕まえて、狸汁を作るようにお婆さんに言い残して出掛け、夕方帰宅して狸汁を食べると、実はお婆さんは狸に殺されていて、お爺さんが食べたのはババア汁だった。
そして、お爺さんの話を聞いた裏山の白兎が、狸の隠れ家の前で鎌で芝刈りをしながら栗を食べ始めると、穴の中から狸が出てきて栗を分けてくれるよう頼み、兎は向こうの山まで芝を背負って行くという交換条件を出した。
兎は狸の後ろで火打ち石を出し、「カチカチ」と火を切り始めると、変に思った狸が「カチカチ鳴るのは何だろう」と質問した。
「この山はカチカチ山だからさ」と答えると狸は納得し、また歩き出した。
やがて、兎の着けた火が狸が背負った芝に移って燃もえ出すと、狸は 「ボウボウいうのは何だろう」と質問した。
「向こうの山はボウボウ山だからさ」と兎が答えると狸は納得したが、既に火は背中に燃え拡がり、狸は燃える芝を振り落として穴の中に逃げ込んだ。
兎はわざと大声で、「火事だ!火事だ!」と言いながら帰っていった。
翌日、兎は味噌の中に唐辛子を擦り込んで膏薬を作り、大火傷をした狸のお見舞いに行って塗って来た。
それから数日後、兎は狸を海に連れ出して、兎は木の舟を造り、狸は泥で舟を造って沖に出て、泥舟は溶けて狸は溺れ死んだ――
火打ち石で「カチカチ」と火を切るというのは、製鉄を象徴しているのではないだろうか。
「火事」は、音も字義も「鍛冶」に通じる。
更に、木の舟を造って航海技術を持っていた。
カチカチ山の白兎の正体は、古代日本列島に製鉄技術をもたらして山人となった「アマ族」ではないだろうか。
ここで注意すべきは、兎は「製鉄技術を持っていたアマ族」で、陸路ルートで渡来したヒッタイト人(牡牛族)だということである。
また、白兎といえば「稲葉の白兎」の神話もある。
淤岐島の白兎が渡海する為に、ワニを利用して毛皮を剥がされるのだが、白兎が牡牛族だとすると、ワニは舟を示唆し、龍蛇族系のアマ族であることを暗に示している。
また、白兎は大国主命の処方によって怪我を治癒させたことから、大国主命も牡牛族だった可能性がある。
この神話の舞台は鳥取県だが、やがて島根県(出雲地方)に移っていく。
出雲は「製鉄民=牡牛族=鬼」所縁の地だが、彼らは最終的に日本列島の鬼門(東北地方)に追いやられていった。
牡牛族は隠れたことから「隠(鬼)」となったが、大湯ストーンサークルのある秋田県ではナマハゲが有名である。
これはまさしく鬼であり、「生剥げ」の名称は、白兎が毛皮を剥がされて赤くなったことに因んでいるのかも知れない。
秋田県の上の青森県では、古来より大国主信仰が盛んだが、鉄を産出する山に「大国主命」が祀られている。
また、大国主命が信仰していた「磐座信仰」があるが、これは黒い鉄鉱石であることから、「大国主命=大黒天」と同一視されており、そのルーツはヒンドゥー教の破壊神「シヴァ」である。
いずれにしても、スサの王が率いるヒッタイト人が、朝鮮半島から渡来したことは間違いないと思われる。
ところが、紀元前3~2世紀に海路ルートで上陸したアマ族が「出雲族」だという説もある。
しかも、その出発地点はパミール高原である。
だとすれば、前述のシュメール系アマ族が「出雲族」ということになるが、出雲族が渡来する以前からアマ族は日本列島に渡来していた。
それに、出雲族は「牡牛族」で、それより遥か以前から渡来していたアマ族は「龍蛇族」だと言える。
以上の仮説を踏まえた上で、もう1度振り出しに戻って、よく考えて頂きたい。
ヒッタイト帝国が、王位を巡る内紛が原因で国家の崩壊を招いたのであれば、勢力の分裂があったはずである。
つまり、東南アナトリアに移動して新ヒッタイトを築いたグループの他に、もう1つのグループがあったと考えるのが自然である。
それが陸路ルートで日本列島に上陸したのだろうか。
大黒天のルーツがシヴァであるなら、インドと無関係ではない。
もしかすると、古代シュメール人が日本列島に入ってきた同じルートで、ヒッタイト人が渡来したのではないだろうか。
そうとう長いコピペで申し訳ないですが、『カチカチ』をはっきりさせたかったので(^^;)
朝ドラの『パチパチはん』みたいなものかと思い調べました
>>1184さん
天孫族も大和もシュメール系ということですよね+9
-0
-
1187. 匿名 2016/02/26(金) 10:25:55
>>1186
1184です。丁寧に有難うございます。
素晴らしいですね。
シュメール系というのは間違い無いと思いますよ。
調べれば調べるほど謎が深まって楽しくなりますよね。
ここで書かれていらしゃる事で気になった事を・・・。
出雲族は「牡牛族」で、それより遥か以前から渡来していたアマ族は「龍蛇族」だと言える。
の箇所ですが・・・。
上で書かせて頂きましたが天照大神が実は男性神ではないか。
またその姿は蛇として描かれている事。
もう一方の牡牛ですが、出雲大社に祭られているのは大国主命です。
この神様の父親はスサノオですが別名を牛頭天皇(インド祇園精舎の守護神<除疫の神>)といいます。
「牛冠をかぶった貴人」の意味です。
しかも大国主命は出雲大社を建てる事を条件に国を譲っています。
偶然にしては出来過ぎですよね。
+11
-0
-
1188. 匿名 2016/02/26(金) 12:49:46
>>1187
本当に謎が謎を呼びますね…
アマ族「龍蛇族」と出雲族「牡牛族」、気になります(>ω<)
どちらも弥生人なのでしょうか?
卑弥呼はアマ族なのでしょうか?
その族名は星座だと思われますが、なぜにそうなったのでしょうか?
他の星座族も存在するのでしょうか?
そんな疑問が出てきました+12
-1
-
1189. 匿名 2016/02/26(金) 12:53:37
前回ユダヤと日本との関わりを書きましたが、他にもあるので書かせて頂きます。
●日本の神社には狛犬がありますが、イスラエルのソロモン神殿にも同じように獅子の像がありました。日本の狛犬は名前こそ犬だが、どう見ても獅子です。
●山伏は頭に兜巾と呼ばれる黒い小箱をつけホラ貝を吹きますが、ユダヤ人は祈る時にフィラクテリーという黒い小箱を頭につけ、ショーファールという羊の角で作った笛を吹きます。<下の画像1>
●祭りで担がれる日本の神輿の上には鳳凰がいるが、ユダヤの契約の箱にはケルビムという天使が羽を広げています。<下の画像2>
●京都の祇園祭の最大イベントは7月17日に行われますが、これはノアの方舟がアララト山に漂着したまさにその日です。<下の画像3>
●平安京をヘブライ文字に翻訳するとエル・シャロームで、これは古代イスラエルの首都のエルサレムと同じです。
●京都(平安京)の近くには琵琶湖がありますが、エルサレムの近くには琵琶湖と似たガリラヤ湖があり、この湖は、古くはキネレテ湖と呼ばれていました。キネレテを訳すと『琵琶湖』になり、つまりエルサレムも琵琶湖があったことになります。<下の画像4>
●祇園(GION)の言語はユダヤのシオン(ZION)と同じ。
●旧約聖書の創世記32章には、ヘブライ人の族長であるヤコブが天使と力比べをしたと記されていますが、これが相撲の起源だと言われています。この時、勝利したヤコブはイスラエル(神の戦士)という名前を授けられました。<下の画像5>
●神社にある鳥居は日本のものでありながら日本人には説明がつかない代物です。しかし、ユダヤ人が見れば即座に理解できるそうです。なぜなら、鳥居の形は古代ヘブライの建物(玄関口)と似た構造をしていて、しかも赤い色は宗教的根拠があるからです。『トリイ』はヘブライ語アラム方言で『門』という意味。モーセは、玄関口の二本の柱と鴨居に羊の血を塗らせ、『殺戮の天使』が静かに通り過ぎるまで家の中で待つように指示しました。この有名なエジプト脱出事件が鳥居のルーツであり年越しのルーツであります。<下の画像6>
最後にユダヤ語の音、訳 ― 音と意味が近い日本語が沢山あるのです。その一部を紹介します。
ハーヤー=早く→日本語:早い
アンタ=あなた→日本語:貴方
バレル=明らかにする→日本語:ばれる
ダベル=話す→日本語:だべる
ミ・カドー=偉大な人→日本語:帝(みかど)=天皇
ミツ=蜜=果汁→日本語:蜜
ソトー=甘み→日本語:砂糖
シュラ=要塞→日本語:城
コオル=冷たい→日本語:氷
グンダ=軍団→日本語:軍団
ハラ=怒る→日本語:腹が立つ
シャムライ=守る者→日本語:侍
シュマショ=ユダヤ教会の事務所→日本語:社務所
アッパレ→日本語:栄誉を誇る
アラ・マー→どうした理由・何?
アノー→私に応答させてください
アリガトウ→幸運です
オハリ→終端
グル→団結する
グル→回る
サヨウナラ→悪魔は追い払われた
サラバ→平安あれ
スケベー→肉欲的に寝る
ダマレ→沈黙を守れ
ワル→凶悪者+7
-1
-
1190. 匿名 2016/02/26(金) 13:51:27
>>1188
もし星座が関わっているとすれば前にも書いたユダヤの12支族が関わってくるかもしれませんよ。
牡牛族がヒッタイト人ならば龍蛇族はユダヤの12支族なのかも・・・。
なぜそう思うかはイスラエル12支族の各シンボルマークを見て下さい。
いかがですか?
+10
-1
-
1191. 匿名 2016/02/26(金) 14:33:21
>>1190ありがとうございます…ほんと幸運です!
シンボルマークを初めて見て感動しました!88星座にないマークもあり、わかりませんでした
>>1189
チョイチョイ悪い言葉がありますよね(^^;)
「アノー」はそんな昔からあるのか?!とウケました(笑)+14
-1
-
1192. 匿名 2016/02/26(金) 17:57:39
遺物の呪い
イスラエル考古学庁は、約20年前に盗まれた古代遺物が窃盗犯自らの手によって返却されたことを明らかにしました。
返却された遺物には、不幸が続いたという窃盗犯から、誰も遺物には手を出すべきではないとのメッセージが添えられていたそうです。
IAAによると、ゴラン高原(Golan Heights)の古代都市ガムラ(Gamla)で盗まれた約2000年前の古代遺物は、イスラエル南部のベエルシェバ(Beersheba)にある博物館「Museum of Islamic and Near Eastern Cultures」の中庭に袋に入れられた状態で置かれていました。
関係当局が公開したヘブライ語のメモ書きには、1995年7月にガムラから古代ローマの投石器用の石2点を盗んだが、それ以来不幸が続いたと書かれていました。
また「古代遺物は盗まない方がいい」との忠告も記されていたといいます。
略奪された古代遺物が返却されたのは、今回が初めてではありません。当局によると、テルアビブ(Tel Aviv)でも、「おぞましい力」があるとして棺が返却されています。
この棺は窃盗犯の寝室で保管されていたとされています。
本当に呪いはあるのでしょうか?+8
-0
-
1193. 匿名 2016/02/26(金) 20:12:23
ちょっと調べたので、せっかくだからご紹介します
「7本立燭台(枝付き燭台)」の『枝付き燭台』がメノラー。台座に12支族のマークがあるようです
七支刀はメノラーに似ています(古代倭王家に仕えた豪族物部氏の武器庫であったとされる奈良県天理市の石上神宮に伝来した鉄剣)
皇室の副紋(五七の桐の紋)にメノラーが隠れているという説も…![歴史のミステリーを語ろう]()
+12
-0
-
1194. 匿名 2016/02/26(金) 21:27:54
>>1190
アマ族「龍蛇族」と出雲族「牡牛族」
星座と関連付けるのはちょっと違ったかもと思い、考えてみました
もしかしたら古代イスラエルに関係あるのかなと
●モーセが帰ってこないことで不安になった民がアロンに要求し、アロンは”金の子牛”の像をつくらせて神とモーセの怒りをかっている。
●モーセは石版の破片を入れた『契約の箱』を先頭に約束の国を目指す旅の途中で、不平を言う民を罰する民に神が炎の蛇を送り多くの死者が出たため、モーセが”青銅の蛇”を示して民を救った
結局、モーセ(蛇)とアロン(牛)はメリバの泉で神を怒らせたため約束の土地に入ることが許されなかった
神の民はモーセの従者ヌンの子ヨシュアが後継者となり導いた
アマ族「龍蛇族」=モーセの民
出雲族「牡牛族」=アロンの民
もしかしたら神の民=縄文人だったりして
↑単なる妄想ですが…そんな気がしてなりません+7
-1
-
1195. 匿名 2016/02/26(金) 22:20:57
>>1194
そうかもしれませんね。
なんだかそうやって考えるとワクワクしますよね。
では12支族達を・・・。
1、 ルベン 優れた威厳と優れた力の持ち主。水のような奔放性。少数派。
2、 シメオン 暴虐性。国中に散らされる。
3、 ユダ 獅子のように獲物によって成長する。王権と指導力。繁栄。自己防衛。
4、 ダン 己の民を裁く。マムシのような狡猾さ。
5、 ナフタリ 牝鹿のような美人系。善良さ。優雅さ。恵みに満ち足りる。
6、 ガド 防衛的。勇敢さ。正義感。最良の地を見つける。
7、 アシェル 王の食卓に美味を供える。穏やかさ。
8、 イッサカル たくましいロバのよう。労働。苦役を強いられる。
9、 ゼブルン 海辺に住む。そこは舟の出入りする港となり、その境はシドンに及ぶ。
10、 マナセ 大自然の祝福。膨大な恩恵。生産の祝福。地の果て果てまで、 国々の民をことごとく突き倒していく進出力。
11、 エフライム 同上
12、 ベニヤミン オオカミのように好戦的。主に愛される者。
このほかに祭祀をつかさどるレビ族がいます。
(ソロモンの後継者をめぐって「イスラエル統一王国」が大分裂。ユダ ベニヤミンの2支族は「南ユダ王国」(首都エルサレム)を樹立 残りのイスラエル10支族は「北イスラエル王国」(首都サマリア)を樹立。北イスラエル王国はBC722年にアッシリア帝国に滅ぼされ、10支族はイスラエルの地から連れさられ、以後行方不明・失われたイスラエル10支族になります。)
+7
-0
-
1196. 匿名 2016/02/26(金) 22:51:24
>>1194さん
日本人のルーツにユダヤ人がという考えはあなただけで無くユダヤの方でも同じ様に考えている方がいらっしゃいます。
紹介しますね。
●ラビ・マーヴィン・トケイヤーは著書『ユダヤと日本・謎の古代史』の中で語ています。
「キリスト教徒たちは日本の空港に着いた時から、全く混乱した違和感を感じているだろうが、ユダヤ人の旅行者に限っては、何か家に戻って来たような親近感があり、国技館で見る相撲の力士が行なう塩を土俵にまく動作にも、奇妙さを感じないのである。ユダヤ人であれば、その意味は即座に理解できるからである。」
「心情的にユダヤ人は、日本人と非常に近いものを持っていると感じ取っている。だから、現在まで書かれた世界史には全く書かれていない何かが、日本人とユダヤ人の間に存在するかもしれないというロマンチックな夢が、ユダヤ人の心に潜んでいるのである。これは神秘的な歴史の謎といえるかもしれない……」
●ヨセフ・アイデルバーグは著書『大和民族はユダヤ人だった』の中で語ります。
「伝統をよく調べてみると、日本人は帰らざるイスラエル10支族の子孫ではないかと思われる。……(中略) 神道という神々の道を勉強し、しばし持者として神社(京都の護王神社)に仕え、私は神社と古代ソロモン神殿の驚異的類似性を知るという、まれな機会を持った。……(中略) 今日、アマテラスオオミカミに馬を捧げる日本の習慣が、古代ヘブライ人が太陽に馬を捧げる習慣からきたものかどうかは知らないが、神道の教義の幾つかはヘブライの古代宗教教義とあまりにも似ているので、この類似性を単なる偶然の一致としてしまうのは難しい。」
このヨセフ・アイデルバーグは、世界中を調査した結果、10支族は日本に行ったことを確信し、以来14年間ひたすらこの問題に取り組んできたといいます。
ユダヤ人言語学者 ヨセフ・アイデルバーグ
●ところで、幕末以来わが国にやって来た外国人(非ユダヤ人)たちの中にも、日本とユダヤとの深い類似を指摘する人物が多くいました。
例えば、1823年に来日した有名なドイツ医師兼博物学者シーボルトもその一人です。彼は5年間日本に滞在しましたが、民族比較論の立場から日本民族のルーツをオリエントの地に求め、ユダヤ人と祖先を同じくする可能性があることを認めていたのです。
●また、明治の初めに来日して約12年滞在したスコットランド人貿易商のノーマン・マックレオドは、1876年に横浜で『日本古代史の縮図』という本を刊行し、アジアの中でも日本人だけが他の民族と非常に異なる風習・文化を持っていると指摘していました。
更にマックレオドは、日本の文化が朝鮮や中国とも異なっているのは、2500年前に古代オリエント地方から東方に追放され、その後歴史から消えてしまった古代イスラエル10支族が、遥か東方の国日本にやって来て住み着いたからではないかと主張しいました。+13
-2
-
1197. 匿名 2016/02/27(土) 01:17:59
>>1196さんありがとうございます
>>1194の二つの族は元は同じ天(アマ)族だったらしく、もっと判りやすくしてみたいと思います(妄想ですが)
●モーセの子孫=天・大和族「龍蛇族」=イザナギ・イザナミ・天照大神
●アロンの子孫=天・出雲族「牡牛族」=スサノオ=鬼
●神の民=縄文人
●炎の蛇=あくまでも妄想なので…言うまい
天照大神とスサノオは兄弟ではとツッコミが入りそうですが、この方がイメージ的にピッタリきます+7
-0
-
1198. 匿名 2016/02/27(土) 01:27:56
>>1195謎解きみたいで楽しいですよね(^^)
12支族の性格おもしろい!
家庭によってはルールが厳しかったり、おおらかだったり、ユーモアがあったりするのと同じなのかな
想像できておもしろいです+11
-0
-
1199. 匿名 2016/02/27(土) 02:20:51
>>1197
その考えも良いんじゃないでしょうか?
日本人は独特の民族ですから色々想像が広がりますよね。
色々と説を投稿していますが楽しんで頂いて嬉しいです。
+8
-0
-
1200. 匿名 2016/02/27(土) 03:06:56
ではここでもう一つ情報を・・・。
ここで出てきている牡牛族に関する情報です。
伊勢神宮にある外宮は豊受大神を奉る宮ですが、王仁三郎氏によれば豊受大神は国祖、国常立大神の別名であるという事ですが、丹後王朝と言われています。丹波・丹後周辺の神社には、この豊受大神を奉る所が非常に多いのです。
伊勢神宮の神官、渡会(わたらい)氏の祖先は乙乃古(うるのふる)命だそうです。シュメールの言葉でウルのフルとは、「ウル(牛)のフル(都)」という意味になります。
気になりませんか??+12
-0
-
1201. 匿名 2016/02/27(土) 09:27:36
>>1200気になります(≧∇≦*)
シュメールにはエリドゥ・ウル・ウルク・ラガシュという都市国家がありましたよね
そのウルが『牛』を意味するとはドキドキ感半端ないです
シュメールでは紀元前3000年頃、銅にすずを混ぜる青銅合金の製造法が発見され、青銅製の武器が作られたらしいのでモーセが示した『青銅の蛇』はその技術で作った剣かなんかだったのでしょうか?+7
-0
-
1202. 匿名 2016/02/27(土) 10:20:02
>>1201
旧約聖書でモーセは神様から「青銅の蛇を造ってさおの上に掲げなさいと」言われ青銅の蛇を造りました。 新約聖書に入ってからこの青銅の蛇はイエスキリストの雛形とされています。
聖書中で蛇は「のろわれた者」という立場にあります。
(創世記 3:14)『神は蛇に言われた,「この事を行なったゆえに,お前は…すべての野獣のうちののろわれたものである。」』
つまり宗教として忌み嫌われるものではなかったのではないのでしょうか?
例えば人を殺すものであるとか・・・。
つまり新約聖書では青銅の蛇であるイエスが一度死ぬ事で平和が訪れる。
武器の無い世界という意味かもしれませんね。+9
-0
-
1203. 匿名 2016/02/27(土) 11:52:53
古代ヨーロッパ人のDNA
ヨーロッパ文化は極めて多様です。それぞれ独特な習慣をもち、比較的狭いけれど、はっきり境界を隔てた地域に隣り合わせに住んでいます。ヨーロッパの発展についてはこれまで理解されてきたいくつかの定説がありますがが、オーストラリアの古代DNAセンターの研究によると、骨の遺伝子マーカーから、4500年前頃にヨーロッパ人のDNAに劇的な突然変異があったことがわかったといいます。
古代人類学者のアラン・クーパー博士によると、何かとんでもなく重大なことが起こったのは確かですが、それが自然の大変動なのか、不可解な事件なのかはわからず、今追跡中だといいます。未知の疫病か、大戦争か、部族間の融合が、ヨーロッパの変則的な過去の鍵を握っている可能性はあります。
+14
-0
-
1204. 匿名 2016/02/27(土) 11:55:46
ダイトン・ロック
米マサチューセッツ州トーントン川の岸辺にある40トンの岩石。わけのわからない文字のような、線画のようなものが刻印されています。1680年にイギリス人入植者が初めてこの石を世に紹介して以来、300年近くにわたって、多くの人がその起源や意味を推測・解読しようとしてきましたが、いまだに謎のままです。
1963年に移動させ、保存されています。学者たちは、岩に刻まれているものは、アメリカ原住民が起源だと考えていますがが、ポルトガル語、中国語、古代フェニキア語という大胆な説もあります。
+11
-0
-
1205. 匿名 2016/02/27(土) 11:59:44
アユードのアルミの楔
1974年、ルーマニアのアユードの東1.2マイル(1.93キロメートル)、ムレシュ川河岸で、楔型の物体が発見されました。地中約10メートルのところから、二体のマストドンの骨とともに掘り起こされたといいます。ハンマーの頭の部分のように見えるこの物体は、薄い酸化物の層に覆われたアルミ合金でできています。これは奇妙です。というのも、アルミが発見されたのは1808年、量産されるようになったのは1885年のことです。しかし、マストドンの骨と同じ地層から発掘されているため、この楔は少なくとも11000年前のものであることになってしまいます。
人類が何千年も前にこのような合金を作ることができたはずはないため、これは、エイリアンが地球にやって来ていた証拠だと信じる人も多いそうです。
+11
-0
-
1206. 匿名 2016/02/27(土) 12:04:28
火星にある黒いシミはいったいどこから来ているのか?
この写真にある火星の黒いシミは、火星が温かくなる時期に突然山頂付近から現れ、水のように山頂を流れ落ちてゆきます。そして、寒い時期に入ると、徐々にその姿を消してゆくそうです。
これを見た科学者たちは初め、氷が溶けて、その水が山頂から流れているのだろう、と言う仮説を立てました。しかし、NASAの火星調査機「マーズ・リコネッサンス・オービター」は水分を観測する事は無かったのです。一体この黒いシミは何なのでしょうか・・・?
+13
-0
-
1207. 匿名 2016/02/27(土) 12:11:27
心肺蘇生法のダミー人形となった女性死体
1880年、パリの川で謎の女性死体があがった。警察がすぐに引き上げ、検死官に渡し、身元を特定するため、検死官はその顔の石膏型を作りました。この石膏型を見た人が何故かその顔を気に入ってしまい、石膏型職人に手渡され、大量生産されました。ヨーロッパ全土へと広がった彼女の顔は数十年後、ある玩具メーカーの目に留まり、彼女の顔は心肺蘇生法に使われるダミー人形となり、さらに広まっていき現在へと至っています。
もしヨーロッパで心肺蘇生法の授業を受けたことのある人は、130年前の彼女と接吻を交わしている事になるのです。ちなみに、彼女は当時16歳だったと言われていますが、彼女が「誰」だったのかは謎のままです。+13
-0
-
1208. 匿名 2016/02/27(土) 14:24:06
Baigong Pipes
中国・青海省にあるBaigong山の山頂には三角形の入り口を持つ3つの洞窟があります。
ここには数百本のパイプのような構造物が点在しているそうです。
パイプは山の奥深くにもあり、また、いくつかは近くの塩水湖にも存在するそうです。
製作者は不明。自然発生的なものという説もあります。
大きいもので直径40cmあり、意図的に配置されているという話も噂されています。
分析では、30%酸化鉄と、大量のシリカ(ケイ酸/酸化シリコン)、酸化カルシウムで構成され、8%は不明となっているそうです。
用途としては、古代の天文学実験室という推論が挙られています。
また、2007年の調査でパイプの一部は高レベルの放射性を持つことが確認されました。
人工物…?
+11
-0
-
1209. 匿名 2016/02/27(土) 14:36:07
発生学円盤(Ancient disc of embryology)
「遺伝子のディスク」とも呼ばれる、南米・コロンビアから出土した円形の石の円盤。
炭分を含む「スレート石」という花崗岩と同程度の硬い石で作られており、直径22cm~27cm、重さは約2kg。
円盤は手で磨き込まれており、ボゴタ大学の地学者による調査では6000年以上前に作られたものと分析されています。
表面には男性の精子から胎児にいたるまでの成長過程、
裏面には細胞分裂の様子や生物の成長過程を思わせるものが段階を分けて描かれており、子供の絵、男女の区別などが見られます。
これらは顕微鏡のない時代に生物の発生・進化の過程が知られていたことを示唆するため、オーパーツという説が挙げられています。
この場合最も疑われるのは製造年代の偽装ですが、最近の調べでその可能性は否定されているそうです。
+13
-0
-
1210. 匿名 2016/02/27(土) 14:53:25
ナン・マトール遺跡(Nan Madol)
ナン・マトール遺跡は、オーストラリア近く、ミクロネシア連邦のポンペイ島にある13世紀~15世紀の遺跡群。
Nan Madolは「天と地の間に広がる空間」を意味します。
1931年に「失われたムー大陸」を著したジェームズ・チャーチワードが、ナン・マトールこそが太平洋上に位置し、高度な技術と権力があったムー大陸(Mu)の聖都であると述べました。
ムー大陸は1万2000年前に突如太平洋の海中に水没した大陸と言われています。
この発言でナン・マトールは世界的に知られることになり、現在でも観光客が訪れる遺跡名所となっています。
ナン・マトールの巨石群が建造されたのはシャウテロール王朝時代であり、
この海域で約1000年かけて完成させたとも、不思議な力により一夜にしてできたとも伝説が残っています。 この海上都市(複数の島々に渡る)の玄武岩巨石群をどこからどのように運び、どのようにして緻密に積み上げたのかは解明されていません。
観光ガイドには外敵からの要塞の目的でこの都市が造られたとも書かれていますが、都市が建造された目的は未だ分かっていません。
+13
-0
-
1211. 匿名 2016/02/27(土) 21:49:09
アブラハムはメソポタミアのウル(現在のイラク南部)で生まれた。
実はアブラハムには兄弟ハラン(モアブ人の祖)がいた。
ウル出身のハランなので…
ウル出ハラン→ウルデハラン→アルデバラン(牡牛座の赤い一等星)→金牛宮(きんぎゅうきゅう)→金の子牛の像?
なんか臭うと思い調べてみました。
イスラエルの民の中にモアブ人の娘達と淫らな行いを始める者が現れた。それだけでなく娘達が崇める神々に犠牲を捧げる儀式にも参加し、異教の神々を拝んでしまった。怒った神はモーセに命じ、異教神『ペオルのバアル』を拝んだ者を殺させた。
イスラエルの者が異教の儀式に耽ると同時に疫病が発生し、死者は24000人に及んだ。
バアルは嵐と雷雨、山岳の神で、慈雨により豊饒をもたらすとされ、「力強きバアル」「雲に乗る者」と形容される。
その図像は二本角のついた山高帽や兜(角は神の象徴)、棍棒(稲妻)と槍(豊饒)を身につけた姿で描かれ、武装して武器を振り上げた姿をとって王権を表すという。
画像は怖いけど、説明文からはスサノオをイメージします
何やら気になりませんか?+12
-0
-
1212. 匿名 2016/02/27(土) 22:03:19
>>1202
イエス・キリストと蛇、意外な関係ですね
キリスト教の方には…この事は言わないでおこう…
(・∀・;)+6
-0
-
1213. 匿名 2016/02/27(土) 22:39:07
>>1211
スサノオ
神名の「スサ」は、荒れすさぶの意として嵐の神、暴風雨や雷の神とする説や(高天原でのスサノヲの行いは暴風雨の被害を示すとする)、「進む」と同根で勢いのままに事を行うの意とする説、出雲西部の神戸川中流にある須佐(飯石郡須佐郷)に因むとする説(スサノヲは須佐郷の族長を神格化したものとする)、州砂(=砂鉄)の王という説から、たたら製鉄の盛んであった意宇郡(おうのこおり)の首長とする説などがあるそうです。
なんだか重なりますよね。
出雲の国と結びつきの強い神様ですが、これらの地域はアマテラスへの献上の草那芸の大刀、大国主命への譲渡した生大刀など日本刀の源流とされる神話があり、古代よりたたら製鉄が盛んだった流れから、現在でも島根県安来市には高級特殊鋼で有名な日立金属安来工場や冶金研究所などが日本刀剣美術協会とともにこの地域で古式にのっとったたたら製鋼を行うことでも有名なんです。
また旧約聖書の著者達から嫌われており、もともと「バアル・ゼブル」(崇高なるバアル)と呼ばれていたのを「バアル・ゼブブ」(蝿のバアル)と呼んで嘲笑したそうです。
新約聖書ではイエス・キリストが悪霊のかしらベルゼブルの力を借りて悪霊を追い払っているとの嫌疑をかけられています。聖書においては異教(他国)の神々は否定的に描かれていることが多いのです。
なのでその様な恐ろしい姿に描かれているんですね。
でもそれだけ協力な力を持った人(人々?)だったということでしょうね。+9
-0
-
1214. 匿名 2016/02/28(日) 00:52:09
>>1213
角、かなり強そうですよね
しかもその起源はかなり古いかもしれませんよ(@ω@;)
ナラム・シン…古代メソポタミアの古アッカド王国第4代目の王(在位前2254~前2218)
彼の名の意味は「シン(月神)の寵児(ちょうじ)」
ナラムシンは、浮き彫りにおいて、角のある王冠を戴いた姿に描かれる。
王の神格化であるが、王が神になったとはいえ神々の最上位にある「運命を定める神々」に加えない。守護神として人間社会の運命を最上位の神々に執りなす神。
初期王朝からアッカド王朝時代まで、王権は王杖で代表された。王杖は、指揮権・統治権などの王の機能を象徴する。
ウル第三王朝時代には、王杖に代えて、王冠が象徴となった。王冠は神たる王を象徴する。
王杖、王冠、王座の三点セットで表現。王座は、神たる王の優越性を象徴する。
三種の神器みたいなの出てきた(汗
シュメールの神々は角のある王冠を頭に戴くので、王たちは角をつけて神の真似をしていたわけですね…
角の話はついでにギリシャ神話のゼウスにもありました
角は強さの象徴と見なされ、特別な力があると信じられる
ゼウスの育ての親はアマルテイア(ラテン語ではアマルテア…アマテラス?!)で、彼女は時に山羊として表現される
アマルテイアが角を持つきっかけとなったのが…
ゼウスは山羊の角を折り、それをアマルテイアに渡して彼女が望んだものがなんでも手に入るよう約束したとされる。コルヌー・コピアイ(cornucopia; 豊饒の角)である。古代の神話によると、角の所有者は多岐にわたる。一般には巨万の富の象徴とされ、また様々な神性や、ナイル川など土地を豊かにする河の象徴ともなる。
角はアイテム的な物らしい(・∀・;)+9
-0
-
1215. 匿名 2016/02/28(日) 01:24:05
ベッドに入る前に。>>1003のピラミッドをかぶる人(神)達について
ピラミッドお帽子の女神イシュタル…こちらの方がピラミッドっぽいです
どうやらこれも角だそうですよ(・∀・;)
古代文明の神は海に沈んだ文明も含めて同じだったかもしれません![歴史のミステリーを語ろう]()
+11
-0
-
1216. 匿名 2016/02/28(日) 01:29:26
>>1214
鋭いですね。
ゼウスに関しては、
ある時ゼウスは浮気した。
地中海フェニキア国の王女、エウロペに一目ぼれをしました。
侍女と共に海辺に遊びにきたエウロペに、純白の雄牛に変身して近づいた。
勝ち気な性格だったエウロペは面白がって雄牛に近づき、大人しくしている雄牛の角に花を飾ったり、撫でたりと楽しんでいた。
そして、背に乗ってみた・・・・と、その途端、雄牛は物凄い速さで駆け出し、
海に飛び込み、泳ぎ、クレタ島へ彼女を連れ去ってしまった。
牡牛は男性の象徴ともされていて力の具現化なのですね。
色々な神話が複雑に絡みそうですね。
+13
-0
-
1217. 匿名 2016/02/28(日) 01:57:17
ではもう一つ気になる情報を。
「ソナカシチ」と「ツヌガアラシト」
「任那」から最初の朝貢のために蘇那曷叱知(ソナカシチ)は、崇神65年に来日し、垂仁2年に帰国しましたが、帰国の際に賜った品物を途中で新羅が奪ったので両国の怨が始まったと伝えられています。
彼は意富加羅国、つまり任那加羅(金官:韓国金海市)から渡来した王子・都怒我阿羅斯等(ツヌガアラシト)と同一人とみる見解があり、「蘇那(ソナ)」は金の国、「曷(カ)」は大または加羅、「叱知(シチ)」は首長の意なので、「鉄(金属)の国を意味する素奈羅(ソナカ)」の中国風の表記と見られているのが一般的です。
そして「金官国(任那加羅)」の「王または王子」という点で「ソナカシチ」と「ツヌガアラシト」の両者は一致するのだと言います。
ではその、「ツヌガアラシト」についても見てみましょう。
『日本書紀』には、別名・于斯岐阿利叱智干岐(ウシキアリシチカンキ)とあり、崇神天皇のとき、天皇に会おうと出雲を経て笥飯浦(敦賀市)へきましたが、崇神天皇が亡くなったのでそのまま留まり、次の垂仁天皇に3年仕えたそうです。
垂仁天皇は、「御間城(崇神)天皇の名をお前の国の名にせよ」と命じ、赤絹を与えて彼を本国へ帰し、これが弥摩那(御間国=任那=ミマナ)という国名の起源となりました。
その後、新羅国の兵が赤絹を奪ったので、以来この両国は恨み合っているのだと言います。
都怒我阿羅斯等(ツヌガアラシト)と 于斯岐阿利叱智(ウシキアリシチ)を比べてみると、「アラシト」と「アリシチ」は本来同じものだったことは一見してわかります。
残る「ツヌガ」と「ウシキ」はすでに「角(ツノ)が」と「牛岐」であるという定説があるので、これだけでも「角がある人」と「牛である人」という風にとれ、「その外観を形容したもの」と見ることができます。
では蘇那曷叱知(ソナカシチ)はどうなるか。
これを日本周辺にある語にあてはめてみると、朝鮮語では「牛」を「ソ」と言うので、「蘇」が「牛」であったとすることができます。
来日した時期を考えるとどうも同一人物ではないかと思われますね。
また牛の角を持つといえば「鬼」が連想されます。
いかがですか?
気になる人物ですよね。+8
-0
-
1218. 匿名 2016/02/28(日) 08:16:56
>>1217
本当にお詳しい…情報ありがとうございます
新たな餌を与えられ食すのに時間が必要です(笑)
このトピが閉じても同様トピがあれば、またお話したいです
トピが立っても気づかない事が多いですが、運良く気付けば嵐が去ったあたりから途中参加でコメントしたいと思います
インスピレーションだけでここまできましたが、高校の時から受けた強いインスピレーションは、
1.エジプト・シュメール・アンコールワット・マヤの遺跡は同じ種類のもの
2.ピラミッドは人間の頭部である
3.神々の統治、ギーザのピラミッドは地図と星図のロゼッタストーン
です。
3については時間があれば意見交換したいです+10
-0
-
1219. 匿名 2016/02/28(日) 09:50:46
コルヌー・コピアイ(cornucopia; 豊饒の角)
角笛に似ています
近代の表現においてコルヌー・コピアイは一般的に、柳の枝を角型に編んだ籠がさまざまな果物や野菜とともに表現される。
角笛や籠に姿を変えて持主が存在するかもしれないです
籠(かご)といえば…カゴメですね
この角は望んだものがなんでも手に入るアイテムなので、欲深い人には最高のお宝です
このお宝を所持していたら命を狙われますね![歴史のミステリーを語ろう]()
+12
-0
-
1220. 匿名 2016/02/28(日) 10:12:26
>>1218
3について他に気になる説を紹介しますね。
最近の調べで、発電所、もしくはエネルギー貯蔵プラントではないかといわれています。
メキシコのテオティワカンの太陽のピラミッドの発掘当時、その頂上で分厚く敷きつめられた雲母の層が発見されています。ピラミッドの地下の部屋には良質の絶縁体である、大量の頁岩スレートが発見されています。また、その近くの小建築物の床にも、2層に敷きつめられた大量で高純度の雲母が発見されています。雲母は高い絶縁性と、高速中性子を通さぬ不透性で知られています。そのため電気の絶縁体や耐火物として、また核反応炉の減速材に使われています。しかも太陽のピラミッドの雲母は地元の雲母ではなく、3200キロ離れたブラジルでとれる雲母をわざわざ使用しています。つまりピラミッドはエネルギーをビン詰めするための人工装置で、エネルギーもれをしないように、大量の石や土砂で造られていて、上と下を絶縁体でふたをされているのです。
太陽のピラミッド
エジプトの大ピラミッドは誘導施設、交信の装置、遮蔽シールド、武器をそなえていたと考えられます。シュメールの古文書によると、エジプトのピラミッドは「ネットを広げる」、「天と地を調べる」、「監視区域全体に方向指示電波を送る」などの表現でひんぱんに示されています。また神々の戦争時、エジプトは「遮蔽物の地」と呼ばれていますし、シュメールの神ニヌルタは「わたしをとらえて殺すために、わたしを追跡して捕まえ、殺すために」ピラミッドの力が戦闘中に使われたと、古文書に記されています。
最近いわれている説は、大ピラミッドがナイル川の水を吸い、そこから水素を取り出し燃やして、火力エネルギーをつくるというものです。というのはピラミッドは石灰岩で出来ていますが、王の間の床、壁、出入り口、切り妻屋根だけは花崗岩で出来ているのです。花崗岩は硬く、伝熱性が高いという性質があります。そのため王の間はオーブンで、その上の重力放散の間はほかの石灰岩が耐えられるよう熱を下げる役割をはたしている、というのです。
たしかに王の間だけ花崗岩を使っているというのはなにか機能的な目的を思わせます。また花崗岩は伝熱性が高いだけでなく、石英結晶を多くふくんでいます。この石英にヒントがありそうです。石英に圧力をかけると電圧が生じることはフランシスヒッチングの研究で知られているからです。約13ミリ大の小さな石英結晶の各面に453キロの力を加えると、なんと25000ボルトの電圧が生じるのです。大ピラミッドの王の間の花崗岩は、あるひとつの重い石だけで70トンあるので、全体としてはかなりの重量の花崗岩があります。ここになんらかの圧力、例えばナイル川の水圧や、水素エネルギーによる圧力をかければ、想像を絶する電気エネルギーが生じることは明らかです。そう考えると王の間が発電室であった可能性はかなり高いと思います
絵の右上に翼のついたピラミッドが見える
なんだかすごいですね。+11
-1
-
1221. 匿名 2016/02/28(日) 16:01:08
>>1220
25000ボルトの電圧って…新幹線を動かせそう(・∀・;)
原発を無くしてピラミッド発電したらいいのに。
ピラミッド恐るべし!
皆さんご存知の通り、ギザのピラミッドはオリオン座の三ツ星ですよね
それを知った時「他の星座もどこかにあるかもしれない」と思いませんでしたか?
そしてふと思ったのです
「もしかしたら世界の地理を星座にしたのかもしれない」と
オリオン座がギザに置かれ、全天の星座も地球に重なる![歴史のミステリーを語ろう]()
+16
-0
-
1222. 匿名 2016/02/28(日) 16:42:20
>>1221の天球儀の点線は”黄道”で天の赤道に対して傾いている
この傾きは黄道傾斜角といって、地球の歳差運動(さいさうんどう)により変化しています。
それにオリオンがギザと合致してないので、もう少し時間をかけて考察していこうと思っています
気になった事(1)
シンガポールのマーライオン
11世紀にマレーシアの王族が対岸に見える大地を目指して航海の旅に出た際、途中で海が激しく荒れ、王族が被っている王冠を海に投げたところ、海は静まり無事にその大地にたどり着くことができた。その時、ライオンが現れて、王族にその大地を治める事を許して立ち去った。マーライオンの頭部はこのときのライオンを表している。
また魚の尾は、古代都市テマセック(ジャワ語で「海」)を象徴している。王族は、その大地を「ライオン(Singa)の都市(Pura)」を意味する「Singapura(シンガプーラ)」と名づけ、マーライオンを国の守り神として祭ったという伝説がある。
先ほどの天球・地球儀でシンガポール付近に「しし座」がきています![歴史のミステリーを語ろう]()
+14
-0
-
1223. 匿名 2016/02/28(日) 17:03:35
>>1222つづきです
そしてアメリカ合衆国やメキシコ付近に「わし座」がきます
アメリカの国章はワシですよね…(関係ないですが、よく見ると菊紋とダビデ星がある!)
この一致は何を意味するのでしょうか?![歴史のミステリーを語ろう]()
+17
-0
-
1224. 匿名 2016/02/28(日) 17:14:39
>>1222
独自の解釈にいつも感心させて頂いてます。
星座占知られる黄道12星座。
これらの星座は、天空でも牡羊座から魚座へと順に円周上に並んでいます。
その円周の中心に、大ピラミッドを置き、ピラミッドから12星座を、観測します。
すると、星座約2万6000年の周期でピラミッドの周りを回っているのです。
ちなみに、ピラミッドの脇に佇むスフィンクスの目線で今がどの星座なのかを知るのだといいます。
そしてスフィンクスですが。
まず、ライオンの体。
これは12星座の中で、獅子座を表しているのだといいます。
そして、この獅子座の対角線上にある水瓶座。
実は水瓶座は、水瓶を持つ人間の姿で表されているのです。
つまりスフィンクスは、獅子座と、みずがめ座を合わせた姿で作られたのです。
12星座が一周するのに要する期間はおよそ2万6000年。
スフィンクスの目線の先に対角線上にある獅子座と水瓶座が来るのは、2万6000年の半分。
つまり、1万3000年ごとということになります。
今から1万3000年前の獅子座の時代。
突然寒冷期が始まり、一部の大陸で、ほとんどの動物が死滅しました。
恐竜の絶滅も、このサイクルにあてはまると言うのです。
スフィンクスが見つめる獅子座と水瓶座の時代には、地球規模の大変動が起きていたのです。
現在、スフィンクスの目線の先にあるのは魚座。
しかし、まもなく水瓶座に変わると言うのです。
世界中に散らばる古代遺跡。
太平洋の上をイースター島を通って南米に上陸。
ナスカ、オリャンタイタンボ、マチュピチュ、クスコ、サクサイワマン、パラトアリ。
そのまま大西洋を渡って、アフリカ。
マリ、タッシリ・ナジェール、シワ・オアシス。
地球を一周し、ギザ。
大ピラミッドを起点に、古代遺跡が一直線上に並ぶのです。
しかも、その円周は、赤道と全く同じ距離。
古代遺跡は、第2の赤道を形作っていたのです。
赤道に垂直な線を延ばすと、どの線も北極点に当たるので、同じように、第2の赤道に垂直な線を延ばしてみましたが、そこは、何もありません。
しかし、その場所にもちゃんと意味はあったのです。
東京工業大学で地球惑星科学を研究する松島助教は、その場所を磁北極と答えています。
方位磁石は常に、N極が北、S極が南を指しますね。
そして、方位磁石のN極が指すその場所が磁北極なのです。
ちなみに磁北極は決まった場所にあるわけではなく、常に不規則に移動しているそうです。
その磁北極について、近年、注目すべき報告が発表されました。
アメリカ大気局・国立地球物理学データセンターによると、1900年、磁北極はカナダにありました。
しかし現在の位置は第2の赤道が示す点とほぼ一致しているといいます。
わずか110年の間に、動きが急速に早まり、第2の赤道が示す点に到達しようとしているのです。
この磁北極が第2の赤道に到達する時、磁石のN極とS極が逆転するのではないかと言われています。
地球の周りには、磁気圏という磁気によるバリアーが存在します。
現代文明はこの磁気圏により繁栄しているといっても過言ではありません。
そのため、磁場が狂うことは、現代文明を一瞬にして崩壊する可能性も示唆しており、巨大地震も引き起こす可能性もあるというのです。
さらに、バリアーが弱まることにより、宇宙空間に存在する放射線や隕石などが地球へ到達することになるとか。
そうなった時、地球は、人類はどうなってしまうのでしょうか。+19
-0
-
1225. 匿名 2016/02/28(日) 17:56:22
>>1222つづき(続投してごめんなさい)
気になった事(2)
新約聖書『ヨハネの黙示録』に登場する獣について
(4:6)より抜粋
御座のそば近くそのまわりには、四つの生き物がいたが、その前にも後ろにも、一面に目がついていた。
↑
”目”は星で、生き物は「星座」ではないかと思うのです
先ほどの天球地球儀を見てみます
・第一の生き物「しし」→東南アジア
・第二の生き物「牡牛」→中東~北アフリカ(リビア含む)
・第三の生き物「人の顔を持つ」これがわからない…
・第四の生き物「わし」→北アメリカ
そんな風に置き換えられるのです
+9
-1
-
1226. 匿名 2016/02/28(日) 18:06:58
>>1224
ありがとうございます!
実は春分点は既に水瓶座になっています(汗
偶然にも昭和の終わりと共にうお座から水瓶座に移ったのでした
そして、南天の星座が一番高くなるのが2510年(494年後)といわれています
その時から徐々に地球に変化があるかも(>ω<)![歴史のミステリーを語ろう]()
+9
-0
-
1227. 匿名 2016/02/28(日) 19:36:13
>>1225
ユニークな考えですね。
・第三の生き物「人の顔を持つ」これがわからない…
人の顔を持つこれは、『ヨハネの黙示録』十二章および十三章に記されていますが、
また、もう一つのしるしが天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。(新共同訳12:3)
とあるので龍ではないですか?
この龍が
わたしはまた、一匹の獣が海の中から上って来るのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。それらの角には十本の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまな名が記されていた。わたしが見たこの獣は、豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に、自分の力と王座と大きな権威とを与えた(新共同訳13:1-2)
わたしはまた、もう一匹の獣が地中から上って来るのを見た。この獣は、子羊の角に似た二本の角があって、竜のようにものを言っていた。この獣は、先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に、致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。(新共同訳13:11-12)
この獣はキリスト教を迫害するローマとローマ軍の象徴であるとされています。「十本の角と七つの頭があった獣」とは、七つの丘や七人のローマ皇帝を指すそうです。
ならば気になるのは龍ですよね。
また場所は幻のアトランティスでは??
あくまで予想ですが・・・。+7
-1
-
1228. 匿名 2016/02/28(日) 20:34:13
>>1227妄想に付き合っていただいて恐縮です…最近は偶然の一致で妄想じゃないかもと少々恐怖を感じています
天・地球儀はまだ完成していないので(しかも2時間くらいで作成した)何ともわかりませんが…仮に新約聖書が編集された時を基準とするならば、現在と大きく変わらないと思っています
●わたしが見たこの獣は、豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に、自分の力と王座と大きな権威とを与えた
・豹=ネコ座→ロシア(ウラル山脈)~カザフスタン~中国(タリム山脈)
・熊=大熊座の足→前足:ロシア(ノボシビルスク)・後足:モンゴル(ウランバートル)中国(長春)
・獅子=獅子座の口→ミャンマーとインドと中国の国境
●もう一匹の獣が地中から上って来るのを見た。この獣は、子羊の角に似た二本の角があって、竜のようにものを言っていた。
・子羊=おひつじ座の角→スペイン南部~モロッコ
・竜=りゅう座→ロシア北東部~アラスカ
>>1224で「水瓶座は人間の顔で現されている」がもしかしたら
第三の生き物「人の顔を持つ」=水瓶座の顔→南米エクアドル海岸付近
・第一の生き物「しし」→東南アジア ⇒ベトナム戦争
・第二の生き物「牡牛」→中東~北アフリカ(リビア含む) ⇒イラク戦争
・第三の生き物「人の顔を持つ」=「水瓶座の顔」→南米エクアドル海岸付近⇒???
・第四の生き物「わし」→北アメリカ ⇒???
第二まではアメリカが起こした戦争ですよね+10
-1
-
1229. 匿名 2016/02/28(日) 20:56:08
>>1227
>ならば気になるのは龍ですよね。 また場所は幻のアトランティスでは??
りゅう座は北極圏にあります。アトランティスって龍がシンボルなのですか?すみません、無知で…
しかしこの天地球儀はギザを基準に考えているので、もしかしたらギザができる前はオリオンの位置は違っていたかもしれないです(^^)でも新約聖書はギザができた後なので、ギザを基準に考えるべきだと思っています
ちょっとこの人頭おかしいって思われそうですが(汗
勝手に動かしてみたら、地理的にフィットする位置があったのです
それが、ヘラクレス=北アメリカです![歴史のミステリーを語ろう]()
+10
-1
-
1230. 匿名 2016/02/28(日) 21:08:46
>>1229のつづきです(写真が一枚しか貼れないので続投します、ごめんなさい)
ヘラクレス=北アメリカにすると、オリオンはインド沖に移動します。歳差運動でもっと下がるのでインド洋の真ん中”レムリア大陸”にきます。
獅子座は太平洋の真ん中”ムー大陸”
そして”アトランティス大陸”のあった大西洋の真ん中にはわし座がきます
マヤ文明があったメキシコにはへびつかい座がきて、ケツァルコアトル(羽毛のあるヘビの姿の神)を連想します
他にもお見せしたいくらい地理的にぴったりくるのです。![歴史のミステリーを語ろう]()
+9
-1
-
1231. 匿名 2016/02/28(日) 21:48:28
古代遺跡一覧>>1227
中々深いですね。
それでしたら一度、世界の古代遺跡一覧を作成してみてその星座と重なる部分を探すというのはどうでしょうか?
もしかすると重なるかもしれません。
他の遺跡も星座を基準に作られているかも?
ただまだ見つかって無い遺跡も有るかもしれませんが・・・。
アトランティスと龍の件ですが海に沈んだ訳ですが海の神はポセイドンですよね。
ポセイドンの鉾には龍が付いています。
またポセイドンには愛人にメドゥーサも居るのです。
あくまで私の意見ですですが・・・。+10
-1
-
1232. 匿名 2016/02/28(日) 22:24:26
12星座・・・。
この12と言う数字にも何か意味があるような気がします。
時間(12時間区切り)
1年(12ヶ月)
1ダース(12)
十二音
十二支(干支)
十二星座
十二宮
十二使徒(新約聖書)
オリュンポス12神(ギリシャ神話)
十二単(日本)
日本神話における十二柱七代の神(古事記)
十二神将(仏教)
冠位十二階(日本)
十二因縁(仏教)
十二直(陰陽)
十二天(仏教)
12という数字に何かあるのでしょうか??+15
-0
-
1233. 匿名 2016/02/28(日) 23:27:52
>>1231
良いアイデアですね、流石です
>>1227の古代遺跡一覧ありがとうございます
教えていただいて助かります(^^)
クリア球を仕入れて、地球儀をトレースして、遺跡を入れて…ワクワクします!5月までには完成させご報告できたらいいなと思います。
インドの72という数字と基準子午線も関係ありそうな予感がするので、それも併せて考察していきたいと思います(これはスルーしてくださいね…陰謀っぽいし、勘なので)+11
-0
-
1234. 匿名 2016/02/28(日) 23:43:09
>>1233
この様な研究は楽しいですよね。
因みにこれらの12星座は、メソポタミア起源で、てんびん座を除けばすべてシュメール時代までさかのぼることができるそうですね。その後、惑星(太陽や月も含む)の通り道にあたるこの場所は重要視され、天体観測もこの黄道十二星座がある黄道帯を中心に行われるようになりました。シュメール→バビロニア→アッシリア→ペルシア→ギリシアと伝来するたびに、いろいろな変化を経てきたものの、遅くともバビロニア時代には現在の12サインに該当する12星座(現在の12星座と同じではないが)が成立していたそうです。
恒星全体は「天の羊の群」
太陽は「老いた羊」
惑星は「老いた羊の星」、星にはみな羊飼いがいる
“ジブジアナ”という明るい星は「天の羊の群の羊飼い」
研究者は、ジブジアナをアルクトゥルスと考えており、もしこれが正しいとすれば、すでに、うしかい座の原型ができあがった、ということになります。
しかしながら、シュメール人もアッカド人も、現在も使われている星座そのものをつくったという直接の証拠がないのが痛いところです。シュメール人によって星座の名前や絵を書かれた粘土板は、今のところまったくといっていいほど見つかっていないからです。しかし、メソポタミアで以降つかわれている星座の名前は、たいていがシュメール語で書かれているそうです。そういうところから、星座をはじめてつくった人としてシュメール人の名前があげられてくるわけです。
ですから、星座の原形をシュメール人がつくり、それに続くメソポタミアの人たち<アッカド・アモリ・アッシリア・カルデア(バビロニア)といった人たち>が、星座として発展・整理していったのではないかと考えるのが自然なわけです。いつの日か、星座の名前が書かれたシュメールの粘土板が発掘される日が来るといいですね。
それにしてもシュメール人凄すぎですよね。+9
-0
-
1235. 匿名 2016/02/28(日) 23:57:54
>>1233
追記です。
他にも星座を基準にしている遺跡を見つけましたのでご報告を。
アンコールワット
カンボジアの有名な遺跡、アンコールワット。
アジア旅行の定番で、12世紀に作られたとされるヒンドゥー教寺院です。
アンコールワットが形成される以前、この地は龍座の形をとって作られ、その後、実際にアンコールワットとして龍座の形に基づいて作られたことがわかっています。
また古代エジプト人は天の川を「空のナイル川」と呼んでいました。そしてギザの3つのピラミッドはオリオン座の真ん中の3つの星を再現していることがわかっています。そのためボーヴァルらは天空(オリオン座と天の川)と地上(ギザのピラミッドとナイル川)の配置が全く同じになるときがあるはず、とコンピューターで調べてみました。すると紀元前2500年は合いませんでしたが、紀元前10500年(12500年前)で完全にピタリと合ったのです。
紀元前10500年の春分の日に太陽が昇る瞬間、りゅう座が真北の空高く横たわっており、そのパターンは、アンコールの主要な寺院とまったく同じ配置になっているそうです。
星座の形を模しているだけでなく、その星座が同じ「紀元前10500年」の時の配置と一致します。
凄くないですか??
+11
-0
-
1236. 匿名 2016/02/29(月) 00:17:14
歴史上の女傑
ゼノビア
3世紀にローマ皇帝の権威が低下した時代に、シリアやエジプト周辺を領土としたパルミラ王国 の女王。「ササン朝ペルシャの侵略からローマ東部属州を護る」という名目で、次々に領土を拡大していきました。
ゼノビアは自らを「エジプトの女王」と称し、「戦士なる美の女王(Warrior Queen)」とも呼ばれました。その後ローマ帝国との争いに敗れ捕虜となりますが、ローマの元老院と再婚し、裕福な暮らしをしたとされています。
+9
-0
-
1237. 匿名 2016/02/29(月) 00:18:20
歴史上の女傑 2
セミラミス
メソポタミア(現在のイラク)北部に興り、世界帝国を築いたアッシリア帝国の伝説の女王。美貌と英知を兼ね備えていたとも、贅沢好きで好色でかつ残虐非道であったとも伝えられ、世界の七不思議の一つ「バビロンの空中庭園」を造らせたのが彼女といわれています。+9
-1
-
1238. 匿名 2016/02/29(月) 00:21:26
歴史上の女傑3
タマル
12世紀にセルジューク朝を駆逐して領土を拡大したグルジア王国の女王。グルジア王国の版図を南カフカース全域にまで広げ、グルジア王国の最盛期を築いています。
歴史上の女傑4
ブーディカ
西暦60年頃、現在のイギリスにあたる土地で、ケルト人イケニ族の女王として君臨。ローマ帝国の侵略軍に蹂躙されたものの、ケルト部族をまとめ上げ、大規模な反乱を起こしました。
各地のローマ帝国植民地を次々に攻略し、ローマ軍第9軍団ヒスパナを打ち負かすなどの戦功を上げ、ネロ帝に軍撤退を決断させるも、ワトリング街道の戦いでローマ軍の反撃を受け敗れました。
+7
-1
-
1239. 匿名 2016/02/29(月) 00:38:48
●わたしが見たこの獣は、豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に、自分の力と王座と大きな権威とを与えた
・豹=ネコ座→ロシア(ウラル山脈)~カザフスタン~中国(タリム山脈)
・熊=大熊座の足→前足:ロシア(ノボシビルスク)・後足:モンゴル(ウランバートル)中国(長春)
・獅子=獅子座の口→ミャンマーとインドと中国の国境
少し外れてはいますが、ほぼ許容範囲内に隕石が落下していました。しかもこの数年のうちに…
・チェリャビンスク
・バイカル湖
・タイとミャンマーの国境付近
なんか怖いです…おやすみなさい(-_-)zzz+8
-0
-
1240. 匿名 2016/02/29(月) 00:48:36
まだこのトピが続いていてすごく嬉しいです!皆さんみたく知識がないので勉強しながら楽しみに見ています(∩´∀`∩)書き込みくださってる方楽しみにしてるのでまだまだお願いします( ˘ω˘ )+19
-0
-
1241. 匿名 2016/02/29(月) 00:54:10
>>1239
素晴らしい分析ですね。
また聞かせて下さい。
お休みなさい。
ヨハネの黙示録の四騎士
白い馬とその乗り手
第一の封印が解かれると、一頭の白馬が出現する。それに乗っている者は弓を持ち、冠が被せられている。
英語ではこの乗り手を「ホワイトライダー」ともいい、侵略戦争を象徴している。
赤い馬とその乗り手
第二の封印が解かれると火炎の如く赤い馬が出現する。それに乗っている者は一本の大剣を持ち、地上から平和を奪う力が与えられている。
この力は人々を互いに殺し合わせるために用いられる。
英語ではこの乗り手を「レッドライダー」ともいい、内戦、内乱を象徴している。
黒い馬とその乗り手
第三の封印が解かれると黒い馬が出現する。それに乗っている者は天秤を持つ。
「四つの生き物」の一体の内から「小麦一ますは一デナリ。大麦三ますも一デナリ。オリブ油とぶどう酒とを、そこなうな」という声が発せられる。
英語ではこの乗り手を「ブラックライダー」ともいう。前述の生き物の声は、この乗り手が象徴する、飢饉を描写したもの。
青白い馬とその乗り手
第四の封印が解かれると青白い馬が出現する。それに乗っている者は四人の中で唯一「死」という名を持つとされる。
その後ろには陰府(原語ではハデス)が付き従う。
英語ではこの乗り手を「ペイルライダー」ともいい、死と荒廃を象徴している。
四人の乗り手たちには、剣と飢饉と疫病と野獣によって地上にいる人間の四分の一を殺害する力が与えられる。
この4騎士も気になりますね・・・+7
-0
-
1242. 匿名 2016/02/29(月) 01:00:13
>>1240
ありがとうございます。
細々とでも続けていきますのでよろしくお願いしますねm(__)m+11
-0
-
1243. 匿名 2016/02/29(月) 07:00:07
>>1240
ありがとうございます(≧∀≦)
妄想が多いですが、お付き合いくださって感謝しています!
昨日の星座の地域を調べながら気がつきました
天地球儀が無くても大まかに星座を示す地域がわかるかもしれません
ノヴォシビルスクやイルクーツクの市章は黒豹でした
東南アジアの国章はライオン(獅子)。その地域の紋章が星座を反映している可能性が出てきました
地球の軌道に干渉する小惑星を”アテン群”などとしますが、ギザのピラミッドやスフィンクスと共に地球にダメージを与える時期を示しているのかと感じました
ついでに気付いたのが…日本の国章が菊紋オンリーなのがシュメール人との関係を物語っているような…モンゴルのウランバートルの市章は鞍馬天狗みたいでヤタガラスを連想します。
↓ノヴォシビルスクの市章![歴史のミステリーを語ろう]()
+8
-1
-
1244. 匿名 2016/02/29(月) 08:59:49
>>1243
ここでお話しのでた八咫烏について。
秘密結社で有名なのは『フリーソーメン』ですが、日本には『フリーメイソン』よりもっと古い歴史をもつ……と言われる、現代につづく世界最古の秘密結社があるそうなんです。
その組織は『八咫烏』と呼ばれています。八咫烏と言えば、初代天皇・神武天皇が東征をする際に、熊野(和歌山)から大和(奈良)へ抜ける道があまりに険しかったことから、古事記によると高御産巣日神より遣わされ先導したとされる伝説の大カラス。
咫とは昔の長さの単位。そのため、1咫(親指と中指とを広げた長さ/約18cm)×8=約144cmの大きさだったのではないかと言われています。他にも特徴として三本足を持っているそうです。
その八咫烏。今では和歌山県にある熊野本宮大社のシンボルとして有名ですね。主祭神・家津美御子大神(現代において正体は素盞鳴尊と言われているが、実のところ正体不明とも言われる神)に仕えているとされています。
始まりは神武天皇が初代天皇に即位するタイミングであったり、聖武天皇の時代であったりとバラバラに言われています。
ちなみに神武天皇即位の時説では、神武天皇よりも先に大和を支配していた物部氏が国譲りをする際、八咫烏となり配下に入ったなんて話があるようです。
ただどちらにせよ共通してあるのは、その存在が「裏天皇である」という説。
八咫烏は最高位の「大烏(通称:三羽鳥)」3名、上位組織の「十二鳥」12名で構成され、その下にも何十名かいると言われています。十二鳥に大鳥が含まれるか、別々なのかは不明だそうです。
まるでユダヤの12支族を連想させます。
大鳥の3人は3人1組で「金鵄」とよばれ、ここで言う「裏天皇」に当たる存在だそうです。金鵄=裏天皇ですね。
金鵄は日本書紀に登場する伝説の鳥。神武東征で神武天皇が長髄彦と戦っている際に天皇の弓に止まり、強烈な光を放ち相手の目をくらまして勝利に導いたとされています。古事記の八咫烏と登場場面がにていることから、この二つの鳥は同一視されることも多いです。
そして、八咫烏はそもそもが「太陽の化身」。体にすると全体が「太陽」、三本の足は左から「人・地・天」の意味を表すと言われています。
そう考えると「八咫烏は天皇=太陽を支える三本の足」ということなのでしょうか。+14
-0
-
1245. 匿名 2016/02/29(月) 09:13:32
>>1232
12は世界共通の運命数といえそうですね
トピズレですが、
「性同一性障害など「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティーに該当する人は全体の7.6%で、13人に1人となりました」
↑遺伝子的にも何かありそうですよね
>>1234
星座を作ったのはシュメール人といわれているんですね
彼らはいきなり現れて既に優れた技術を持っていた…もしかしたら、水瓶時代から始まる獅子時代までの全地球的災害期をどこかに逃れて生き残った人達なのでは?それこそ”ノアの方舟”のように…古代の技術と生物のDNAを保管して…そして獅子座の時代に地上に降り立って、人間と生き物を増やしたのではないでしょうか
>>1235
アンコールも星座を意味するなんて驚きました。インスピレーションも侮れないな…
ギザといっしょで獅子時代「紀元前10500年(正確には紀元前10450年)」(南天の星座が最も低くなる時代)を示していたのですね
もはや陰謀というよりも、『地球の番人』の存在が明らかになってきたのではないかと思います
>>1241
>>1228の第三の生き物「人の顔を持つ」が”かみのけ座”(人の頭部だけの星座)だとしたら=日本になります…私たちに関係する最悪のパターンを合わせて入れてみると…
ヨハネの黙示録の四騎士
第一の封印・生き物…侵略戦争を象徴・ベトナム戦争
第二の封印・生き物…内戦、内乱を象徴・イラク戦争
第三の封印・生き物…飢饉を描写・日本(TPPが関与してくる?)
第四の封印・生き物…死と荒廃を象徴・アメリカ
あるかもしれないですよね(・ω・;)+11
-0
-
1246. 匿名 2016/02/29(月) 09:49:44
ここでアンコールワットがなぜ竜座を模したのかについて。
これはナーガが関係しています。
タイ パルムルン遺跡のナーガ
ナーガとは、
上半身を人間の姿で表し、下半身を蛇として描く構図と用いる例もあるようですが、一般的なものではなく、経典等の記述においては、コブラまたはインドコブラ自体の容姿を思わせる記述としてあり、インドや南伝仏教圏においては純粋に蛇として描かれることの方が多いそうです。東南アジアのインド文化圏では、頭が七つある姿が多い。
釈迦が悟りを開く時に守護したとされ、仏教に竜王として取り入れられて以来、仏法の守護神となっています。特に法華経の会座に列した八大竜王は有名で、その多くがもとはインド神話でも有名なナーガの王(ナーガラージャ Nāga Raja)であったそうです。天気を制御する力を持ち、怒ると旱魃に、宥められると雨を降らす。天候に関して責任感も持っているので、自身の感情を抑えたりもするそうです。チベットでは、樹の枝にも棲むとされている吉兆だそうです。
ここで気になるのは頭が七つですよね。
『ヨハネの黙示録』にも
見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。
明らかに関係有りそうですよね。+9
-0
-
1247. 匿名 2016/02/29(月) 11:17:10
>>1246
ナーガラジャの意味する事は何でしょう?
私の思考が追いついてなくてごめんなさい
実は海蛇(うみへび)座というのがあって、それが蟹座(インド)~獅子座(東南アジア)~乙女座(ニューギニア島)の南方にあります
天地球儀ではスリランカを頭部にしてインドネシアからオーストラリア南部全体をカバーしていて、かなり大きな星座です
この辺りで何か起こるのでしょうか?+8
-0
-
1248. 匿名 2016/02/29(月) 12:05:25
>>1247
ナーガ・ラジャ 《Naga Raja》 出身地:インド
ナーガ・ラジャとはナーガ族の中でも強力な力を持つ者、つまり王族のことをこう呼ぶのです。
それらの中でも著名な者としては、ナーガたちの母神カーリヤ、その息子であり1000の頭とあらゆる魔法の源泉である如意宝珠を持つシェーシャ(アナンタ)、神々とアスラが戦っていた時代から大地を支えているというヴァースキ、賢者カーシャパの息子でクリシュナ神の加護を受けたカーリヤ、干ばつを起こす悪龍ヴリトラなどであります。
もしかしたら大干ばつかも・・・。
+6
-0
-
1249. 匿名 2016/02/29(月) 12:46:11
いつもこのトピを楽しく拝見させて
いただいています。
世界の遺跡を見に行ったり、こういう
ジャンルの本を読んだりはしていたのですが、
更なる知識欲が湧いてきました。
皆さんとてもお詳しいのですが、
史学科などで学ばれたのでしょうか?+15
-0
-
1250. 匿名 2016/02/29(月) 12:52:33
>>1248
大干ばつ(>_<)これは辛いですね…火のように赤い大きな竜ともなれば相当ですよね
ところで先ほどインスピレーションきました!
ヘビはヘルメス(トート)の杖で二重螺旋でデザインされています。それは遺伝子DNAを示すのではないかと…地球規模大災害時(水瓶~獅子の時代)にどこかに逃れていた人々がシュメール人…としましたが、その”どこか”から戻って来る(あるいは行く)道筋を表しているのがヘビ関係の星座なのかと。
そして気になったのが水ヘビ座。これは三角形の上が欠けて”ム”の形になっています。これはシェルターの入口を示しているのでは?
そう考えると三角を作っている星座が気になって…
そういえば前の方で南極で遺跡発見されたみたいなコメントありましたけど、あれってシェルターの入口なのかも。もっとぶっ飛んで考えたらピラミッド王の間は絶縁体でしたよね…あそこもシェルター”アラーラート(アララト山)”なのでは?
天地球儀からヘビ系の星座を抜粋してみました
(ペイントで作成したのでボロいけど、良いアイデアなので次はパワポで作成してみようかな…星座が動かせるし♪)![歴史のミステリーを語ろう]()
+13
-0
-
1251. 匿名 2016/02/29(月) 12:56:01
知識豊富な方がたくさん…!いつも投稿ありがとうございます。
こういうことに興味はあるものの知識は乏しいので
何度も読み返しながら勉強しています。+21
-0
-
1252. 匿名 2016/02/29(月) 12:56:28
>>1249
私の場合は元々歴史が好きだったのですが(古代遺跡です)その中で離れた地域なのに似た様な神話を不思議に思って自分なりに調べ始めたのがスタートですね。
とんでもな説もあると思いますが是非このトピがきっかけになって楽しんで頂けたらうれしいです。
+14
-0
-
1253. 匿名 2016/02/29(月) 13:05:10
>>1250
ありえますよね・・・。
蛇や龍は川の神格化と考えられていますから水=生命の源とも解釈出来ます。
星座の蛇に関するものは非常に重要かもしれないです。
ヘビはヘルメス(トート)の杖で二重螺旋でデザインされています。
これはもしかしたら干ばつと洪水の二面性を表しているのかもしれませんよ。+14
-0
-
1254. 匿名 2016/02/29(月) 13:11:47
>>1249
(・∀・)私はド素人です。
大学は通信教育だし、勉強も得意ではないです。授業中や人と会話している時も白い光が重なって見えるし、言葉を聞くとイメージが頭の中で展開していくので…お勉強できないですね(笑)
本人は自閉症を疑っています。
だけどIQが高いらしく知能テストが終わった後、校長室に呼ばれて「うちの学校に来てくれてありがとう!」と校長に感激の握手をされました。
ところで、さっき>>1250コメする時に、”荒らし警告”が出ました。もしかしたら私は投稿できなくなるかもしれません。被害妄想なら良いのですが「地球の管理人」にとっては知られてはいけない内容かもしれないので(>_<;)+18
-0
-
1255. 匿名 2016/02/29(月) 13:41:59
>>1254さん
気にしなくていいじやないですか。
あなたはあなたです。
私は楽しくお相手させて頂いて感謝していますよ。
色々と投稿していますが、それを見て自分なりに調べたりして知識を深めるのは素晴らしい事だと思っています。
是非また自分の考えを教えて下さいね。
+17
-0
-
1256. 匿名 2016/02/29(月) 13:49:06
>>1251さん
何か知りたい事があれば気軽に書き込んで下さいね。
知りえる範囲でお答えさせて頂きます。
+12
-0
-
1257. 匿名 2016/02/29(月) 14:16:54
異形の者。件くだん
古くから日本各地で知られる妖怪。「件」の文字通り、半人半牛の姿をした怪物として知られています。
その姿は、古くは牛の体と人間の顔の怪物であるとしますが、第二次世界大戦ごろから人間の体と牛の頭部を持つとする説も現れました。
慶応3年(1867年)4月の日付の『件獣之写真』と題した瓦版によると「出雲の田舎で件が生まれ、『今年から大豊作になるが初秋頃より悪疫が流行る。』と予言し、3日で死んだ」そうです。
明治42年(1909年)6月21日の名古屋新聞の記事によると、十年前に五島列島の農家で、家畜の牛が人の顔を持つ子牛を産み、生後31日目に「日本はロシアと戦争をする」と予言をして死んだとあります。
この子牛は剥製にされて長野市の八尋博物館に陳列されたものの、現在では博物館はすでに閉館しており、剥製の行方も判明していません
阪神大震災と東日本大震災直後にも、闇で踊ってる異形の人?の目撃談もあるそうです。
世界で類似しているのがソロモンの魔王72柱のモラクスだと思われます。、
博識伯。36個軍団を指揮する総統でもあるそうです。雄牛の身体に醜い人間の頭を持っていたり、人間の身体に雄牛の頭を持っていたりします。
魔術師にとっては大いに役立つ悪魔で、天文学、占星術だけではなく、宝石や薬草を魔法に利用する方法にも詳しく、その知識を与えてくれるそうです。
また、解剖学の専門家にもしてくれたり、魔術師に使い魔を与えてくれることでも知られています。+10
-0
-
1258. 匿名 2016/02/29(月) 14:22:23
果心居士カシンコジ
筑後の生まれだそうです。大和の興福寺に僧籍を置きながら、外法による幻術にすぐれたために興福寺を
破門されたそうです。その後、織田信長の家臣になりたいという思惑があったらしく、信長の前で幻術を披露して 信長から賞賛されましたが、仕官は許されなかったと言われています。
猿沢の池の水面に笹の葉を放り投げると、たちまち笹の葉が魚になって泳ぎ出した。
上記の術を信用しない男の歯を楊枝でひとなですると、歯が抜け落ちんばかりにぶら下がったそうです。
松永久秀とはとくに親交があり、久秀が「幾度も戦場の修羅場をくぐってきた自分に恐ろしい思いをさせることができるか」と
挑んだところ、数年前に死んだ久秀の妻の幻影を出現させ、震え上がらせたそうです。
豊臣秀吉に召されとき、果心居士は秀吉がだれにも言ったことのない過去の行いを暴いたために不興を買い、捕らえられて磔に処されたといわれています。
しかし、このとき果心居士は鼠に姿を変えて脱出し、それを鳶がくわえてどこかに飛び去ったともいわれています。
古老茶話によると、次のような記述が見られます。
「慶長17(1612)年7月、因心居士というもの、駿府公の御前に出る。
神君むかし御覧あるもの也。いくつになるぞとおたずねこれあるところ、八十八のよし申し上げる」
生没年不明ですが現存していた記録だけが残ります。幻術師+9
-0
-
1259. 匿名 2016/02/29(月) 16:47:18
>>1255さん、ありがとうございます!
豊富な知識で導いてくださり、感謝しておりますm(_ _)m
『ムー』を連想させる南極にある”ム”形の「水ヘビ座」入口…彼らは何らかの理由で地上に出る事ができなかったのかも
>>1253>これはもしかしたら干ばつと洪水の二面性を表しているのかもしれませんよ。
↑
ヒトラーの予言を思い出しました
「とほうもない旱魃や熱波におそわれる国と、寒波や洪水におそわれる国が出る。災害におそわれつづける地域と、楽園のような地域、人っ子一人いなくなる荒地と、無数の人間が鼻をくっつけ合って生きる都会とが分かれる。」
アステカ帝国の伝説
昔、この地には「ケツァルコアトル」という神様がいて、人間達に農耕を教え、全ての文化や知識を与えました。そしてケツァルコアトルは蛇の筏に乗り、海の彼方へ姿を消したのである。去り際の言葉は、
「私は”一の葦の年”に、必ず戻ってくる」
「そして、その年は、人々にとって不幸な年になるだろう」
葦という植物は暑い夏ほどよく成長します。条件さえよければ、地下茎は伸び、適当な間隔で根を下ろし増えていくのです。
”葦の年”とは獅子~水瓶時代で生物が繁殖する事を示しているのでしょう。実際に紀元前10000年頃に農耕が始まっています。獅子時代は氷河期の終わりなので災害などが多発したのでしょう…これが人々にとって不幸な年になるという事ではないのでしょうか。
海の彼方へ帰った神…実際に海の中(シェルター)に帰っていったのかも?
神々の間でよく出てくる『葦』…「人間は考える葦である」としたパスカルは秘密を知っていたに違いない+13
-0
-
1260. 匿名 2016/02/29(月) 18:56:10
>>1259
そうですね。
南極大陸には地下の世界に通じる巨大な穴があるみたいですし、地下都市に帰っていったのかもしれませんね。
謎を解くカギは南極大陸にあるかもしれませんよ。
+14
-0
-
1261. 匿名 2016/02/29(月) 19:28:25
>>1259
マヤ文明について判ってきている事があるのでご報告しますね。
この画像は上空から撮影した、かの有名なカリブ海のベリーズ近海にある水中洞窟、「ブルーホール」です。ブルーホールから採取された鉱物を調査した結果、西暦800年から900年ごろに大規模な干ばつが発生していた事が判明しました。
この時期はちょうどマヤ文明がバラバラに散ったとされる時期です。その後、干ばつは解消されたようですが、そこからまた数百年後に起きた大規模な干ばつによりマヤ文明は完全に滅んだと考えられています。
西暦300年から700年頃、マヤ文明はユカタン半島をその手中に収めていました。この時代のメソアメリカ人たちは驚くべき程高度な技術力でピラミッドを作り、現代でも通用する程の天文学的知識を身に着け、ヒエログリフやカレンダーの作成にも精通していました。
ところが西暦700年頃、その栄光を忘れるかのように文明技術は衰退し、戦争と無政府状態が続きます。近代の歴史学者はこの時代の衰退を木々の減少によって作物が失われた結果であり、かつてマヤ文明の主食となっていたティカルディアという食料が確保できない事によって引き起こされた恐怖の渦によって引き起こされた物だと考えているのです。
2012年にサイエンス誌で掲載されたベリーズ近辺の洞窟の過去の発見によると、約2000年の時を得て出来上がった石筍(鍾乳洞等で見かける下から上へと延びる岩の事)に長い干ばつの記憶が残されていたそうです。
この当時発表された干ばつの記憶の説明について、科学者たちは「 ”熱帯収束体”の変動によるものではないか」と仮説をたてました。
熱帯収束体は地球に存在する気候システムで、大量の雨を熱帯地帯に与え、その代り他の地域から水分を吸収するという気候を引き起こす。夏になるとこの熱帯収束体はユカタン半島に雨をもたらしますが、冬になると熱帯収束体はユカタン半島を越え、より北へと移動します。
科学者たちは「熱帯収束体がマヤ文明衰退と強く関係しており、文明の衰退は熱帯収束体が夏の時期にマヤ文明上空に留まらず、完全に外れてしまった事によって引き起こされたのではないか」と考えたのです。
今回の発表でわかった事は、西暦800年から1000年ごろに干ばつが起きていたと言う科学的事実です。さらに、20年に通常5,6回起こるはずの台風が、この時期には1回か2回程しか起こらなかったという事実も判明しました。
その頃マヤ文明は衰退し、彼らは現在「メキシコ」として知られるチチェン・イッツァへと移住していったのです。更に新たなる事実として、西暦1000年から1100年ごろ(小氷河期の時代)に大規模な干ばつが起こったこともわかりました。これはチチェン・イッツァが滅んだ要因の一つではないかと言われています。
実際大干ばつが起こったみたいですね。+14
-0
-
1262. 匿名 2016/02/29(月) 20:26:46
>>1261
文明の衰退は案外身近なところにあるものですね
スフィンクスを造った年代について
カルナック神殿のスフィンクスが羊の頭部なのは、牡羊座時代(紀元前2330年~紀元前170年)に造られた事を示しています
シンガポールのマーライオンは下半身が魚なので、魚座時代(紀元前170年~1990年)に作られた事を示しています
そしてギザのスフィンクスは獅子座時代に造られたなら紀元前10970年~紀元前8810年、頭部が水瓶座を示しているなら紀元前23930年~紀元前21770年に造られた事になります+13
-0
-
1263. 匿名 2016/02/29(月) 20:30:14
+13
-0
-
1264. 匿名 2016/02/29(月) 21:03:30
>>1262
素晴らしい考察ですね。
ではここで少し趣向を変えて気分転換を・・・
ネイティブアメリカンの教えを。
現代にも通じると思います。
そこにたどりつこうとあせってはいけない。
「そこ」など、どこにもないのだから。
本当にあるのは「ここ」だけ。
今という時にとどまれ。
体験をいつくしめ。
一瞬一瞬の不思議に集中せよ。
それは美しい風景の中を旅するようなもの。
日没ばかり求めていては
夜明けを見逃す。
―――――ブラックウルフ・ジョーンズの言葉
「恐怖そのものに傷つけられることなどあるものか?
あなたが恐怖に動かされなければ恐怖はあなたを傷つけることはできないのだ。
みずから恐怖にのみこまれてしまったら恐怖があなたの主人になる」
あなたが恐怖を支配するか
恐怖があなたを支配するか
いずれにしてもどちらかが主人になる。
―――――ブラックウルフ・ジョーンズの言葉
あなたが本来の自分であること。
宇宙に対してあなたにはそうある責任がある。
自分の本当の姿を思って
あなたがぞっと身震いするなら、
身震いすればよい!
あなたは壊れやしない。
怖れずにはばたけ、
自分自身になれ!
―――――ブラックウルフ・ジョーンズの言葉
唯一の正しい知恵は、人類から遥か遠く離れた大いなる孤独の中に
住んでおり、人は苦しみを通じてのみそこに辿り着くことができる。
―――――カリブエスキモー、シャーマン
一粒一粒の種が目覚め、一匹一匹の動物が産声をあげる。 この神秘な力のお陰で、わしらもまた、生きていく事が出来るのだ。 だからこそ、わしらは隣人達や、近くに住む動物達が、 わしらとまったく同じ権利を持っていて、この大地に住むことを認めてきた。
―――――ラコタ族の首長、シッティング・ブル+16
-0
-
1265. 匿名 2016/02/29(月) 21:13:56
続き・・・
一人でいることと淋しいということはぜんぜん違うのだよ。
一人でいても淋しくなく穏やかな心でいるようになるためには、自分が最良の友と一緒だということを知ればよいのだ。
自分自身と一緒にいて心が安らぎ、自分を愛していれば、決して淋しいことはない。
人は自分自身を愛するようになったとき、初めて他人を愛することができる。孤独の純粋さに触れるには、まず自分を愛することを学ばなければならない。
利己的にならずに自分を愛することができれば、淋しさは存在しない。
自分に対する愛は、また、ほかのすべてのものに対する愛を生み出し、聖なる「ワンネス」の世界に近づけてくれるのだ。
―――――最後のインディアン“ストーキング・ウルフ”の言葉
私は白人を憎んでいるのではないのだよ。白人の考え方や生き方が嫌いなだけだ。
おまえは私の孫だ。白人ではなくて、大地の子だ。肌の色や血がおまえを大地の子にするのではない。おまえを万物と一つにするのは、おまえの心や信念なのだ。私は彼らの無知や破壊を憎むからののしるので、白人という人種を非難しているのではない。
彼らは何も知らないからだ。私の敵は彼らではなく、そのやり方なのだ。私はおまえが彼らのような考え方をしていると思ったことはないよ。
おまえの心はいつでも大地とともに脈打っている。私は誰も憎みはしない。敵でさえもだ。私はこういう人間たちの無知を憎み、ののしるだけだ。私が戦う相手は彼らの無知で、人ではない。白人なら誰でも大地を破壊するわけではないし、先住民がみんな大地を守るわけでもない。
どの人種が悪いというのではない。が、私たちみんなに、無知に対する責任があるのだ。
―――――最後のインディアン“ストーキング・ウルフ”の言葉
この地上で生きているものは、みなものを食べなければならないことを、まず理解 しなさい。
生きるためには大地からのものをもらわなければならない。
どのように してもらうかによって、害悪になるかケア・テーカーになるかが決まるのだ。
自然の恵みを受けるときは、まずそれを賛美し、心で深く感謝しなさい。
私たちが生きるためには、ほかのものの命を犠牲にしなければならないからだ。
自然を破壊するのではなく、自然に利益をもたらすように、心して命をいただきなさい。
未来のことを考えて、子どもや孫にすばらしい財産を残すことだ。
自然の創造物を、もっと立派な形にして後世に残さなければならないのだ。
そうすれば私たちは大地のケア・テイカーとしての運命をまっとうしたことになる。
―――――最後のインディアン“ストーキング・ウルフ”の言葉
ひとびとのこころに 真の平和が宿るまで、
国と国のと間に平和はやってこない。
―――――スー族の格言
知識でなく、知恵を求めよ。
知識は過去の産物だが、知恵は未来をもたらす。
―――――ラムビー族の格言
泣くことを恐れるな。
涙はこころの痛みを流し去ってくれるのだから。
―――――ホピ族の格言
+17
-0
-
1266. 匿名 2016/02/29(月) 21:46:11
続き・・・
神はすべてのものをシンプルに創った。
インディアンの人生はとてもシンプルだ。
わしらは自由に生きている。
従うべきただひとつの法は自然の法、神の法だ。
わしらはその法にしか従わない。
ブラック・ヒルズ(ラコタ族の聖地)の丘がわしらの教会だ。
あんたたちの聖書みたいなものなんかいらない。
風と雨と星がわしらの聖書なんだ。
わしらの聖書はこの世界であり、インディアンはそれを何百年もの間、学んできたんだ。
神が全世界の支配者であり、神が創られたものは、
みんな生きているということをわしらは学んだ。
石だって生きているんだ。
スウェット・セレモニー(清めと祈りの儀式)で石を使うとき、
わしらは石に語りかけ、石はわしらに語り返してくれるんだ。
―――――マシュー・キング(ラコタ族)の言葉
いちばん重要な、最初の平和は、人の魂のなかに生まれる。
人間が宇宙やそのすべての力とのあいだに、つながりや一体感を見いだせたとき、その平和が生まれるのだ。
宇宙の中心にはワカンタンカが住まい、しかもこの中心はいたるところにあって、それはわしらひとりひとりの内部にもある、と理解したときにな。
これこそが真実の平和なのだ。ほかの平和はすべて、この真実の似姿にすぎん。二番目の平和というのは
二 人の人間のあいだに生まれる。そして三番目の平和が、二つの部族間にあらわれる。
しかし、わしがしばしば言うように、人の魂のなかに生まれるものこそが真実の平和なのだから、その平和をまず知っておかない限り、部族間の平和などとうてい実現せぬということを、なによりも理解しなくてはならん。
―――――ブラック・エルク(オガララ・ラコタ族)の言葉
女性が死にたえるまで、部族が征服されることはない。
―――――アメリカ・インディアン女性への賛歌
岩は偶然ここにあるのではない。
木は偶然ここに立っているのではない。
そのすべてを造った者がいる。
私たちにあらゆることを教えてくれる者が。
―――――クロウインディアンの詩
大気はそれが育むあらゆる生命とその霊を共有していることを忘れないで欲しい。
我々の祖父たちの最初の息を与えた風はまた彼の最期の息を受け取る。
――――― シアトルの酋長
あなたが生まれたとき、周りの人は笑って、あなたは泣いていたでしょう。
だからあなたが死ぬときは、あなたが笑って、周りの人が泣くような人生をおくりなさい。
―――――ラコタ族の首長、シッティング・ブル+14
-0
-
1267. 匿名 2016/02/29(月) 22:29:22
>>1262
他の遺跡でも当てはまるものがもっとありそうですね。
+6
-0
-
1268. 匿名 2016/02/29(月) 23:22:39
>>1267
そうですね
ギリシア神話におけるスピンクスは、ライオンの身体、美しい人間の女性の顔と乳房のある胸、鷲の翼を持つ怪物(一部の絵画では尻尾が蛇になっている姿で表される事も)。
乙女座のすぐ下に海へび座があるのでこのスフィンクスが該当します
ということはギリシャ神話のこのエピソードは乙女座時代(紀元前13130年~紀元前10970年)に起きたということでしょうね…ってこのエピソード自体よく知りませんがσ(^_^;
インディアンの優しい言葉に癒されました
ありがとうございます+12
-0
-
1269. 匿名 2016/02/29(月) 23:43:08
>>1268
ではギリシャ神話のスフインクスのお話しを・・・
オイディプスの神話によれば、ヘーラーによってピキオン山に座わり、テーバイの住人を苦しめていました。旅人を捕らえて「朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。これは何か」という謎を出し、間違った者を食べていました。なお、答えずに引き返すことは可能だったそうです。この謎はムーサに教わったとされています。しかし、オイディプスに「人間は赤ん坊の時はハイハイで四つ足、成長して二足、老年で杖をつくから三足だ」と答えられ、岩の台座から飛び降り、海に身を投げて死んだというお話です。
なおこのスフインクスの元ネタはメソポタミアみたいですが。
ちなみに、父は台風の語源となった無敵怪物テュポーン(ガイアの息子でゼウスに匹敵するほど強力)、母は上半身が美女で下半身が蛇の怪物エキドナ(メドゥーサの孫)。
兄弟に地獄の番犬ケルベロスやら、合成獣のキマイラなどがいるそうです。
母親もウミヘビ座と関係ありそうですね。
エキドナ
+11
-0
-
1270. 匿名 2016/02/29(月) 23:52:59
>>1269
>このスフインクスの元ネタはメソポタミアみたいですが。
アラ・マー(笑)
そうなのですか?詳しく教えて欲しいです
o(^-^)oワクワク+8
-0
-
1271. 匿名 2016/03/01(火) 00:43:43
>>1270
お待たせしました笑
ではメソポタミアにおけるスフインクスを・・・
あまり詳しく書かれた資料が見つからなくてすみません・・・。
スフィンクスという名前は「きつく縛る」「絞め殺す者」を意味するギリシア語スピンクスsphink、Sphinxに由来すると考えられています。
恐らくはギリシア神話に登場するスフィンクスのイメージによるものだと思われますが、古代エジプト語の「生ける彫像」を意味する「シェスプ・アンク」に由来するという説もあります。
エジプトではこの怪物は太陽の神ホルスの一面であると考えられ、「ホル・エン・アケト(地平のホルス、墓場のホルス)」「ホル・アクティ(地上のホルス)」などと呼ばれました。他に「ルウティ」などの呼び名もあります。
この怪物の伝承はエジプトを含む中東一帯、そしてギリシアにまで及んでいて、エジプトでは古くから王権のシンボルであり、知恵と力の象徴であり続けました。
人間とライオンと鷲というキマイラ(複合怪物)のような姿をしているのは、恐らく当時崇拝されたものを何らかの理由で一緒にしたものでありましょう。
私たちが知るような姿はメソポタミア(現在のイラク、シリア)で考えられたものです。
ちなみにメソポタミア以外では、人間の頭を持たないタイプもしばしばいて、例えばエジプト中部のカルナック神殿跡では、人間の頭の代わりにヒツジの頭を持つ像が発見されています。
バビロニア神話では光の神マルドゥークに退治される存在としての役割が与えられており、アラビアでは「アブ・ホル(恐怖の父)」などと呼ばれて大変恐れられました。+10
-0
-
1272. 匿名 2016/03/01(火) 01:11:18
>>1271
追記で
光の神マルドゥークに退治される存在としての役割を書きますね。
気になる怪物がまた出てきます。
ティアマト(アッカド語: tiamat)は、バビロニア神話(en)の女神である。
アプスーとティアマトは多くの神々を生みましたが、増えるにつれて増大する、神々の起こす騒ぎに耐えかねたアプスーは、ティアマトに彼らを殺すよう持ちかけました。 しかし、母なるティアマトはそれを拒否。 更にアプスーは計画を悟ったエアの魔術によって眠らされて殺されてしまいます。
ティアマトは、更に続く神々の起こす騒動に耐えていましたが、エアの子であり父をはるかに凌ぐ力を持つマルドゥークの誕生と、アヌによって贈られた4つの風によって遊び、騒がせるマルドゥクに苛立ち、配下の神々の批判もあってついに戦いを決意するのです。
ティアマトは権威の象徴たる「天命の書板」をキングーという神に授けて最高神の地位に据え、更に11の合成獣軍団を創造し、戦いの準備を進めていきます。 後に神々により選ばれティアマト討伐に来たマルドゥクを迎え撃ちますが、マルドゥークの威容を見たキングーは戦意を喪失。 ティアマトは一人でマルドゥークに挑み、彼を飲み込もうと襲い掛かかりましたが、飲み込もうと口をあけた瞬間にマルドゥークが送り込んだ暴風により口を閉じることがかなわなくなったところを、弓で心臓を射抜かれて倒されました。
その後彼女の体は二つに引き裂かれ、それぞれが天と地の素材となったそうです。 彼女の乳房は山になり、そのそばに泉が作られ、その眼からはチグリスとユーフラテスの二大河川が生じたとされます。 こうして、母なる神ティアマトは、世界の基となったそうです。
以前はその姿はドラゴンであると考えられていましたが、神話や関連文献の中にそれを指し示す記述は存在せず、現在では否定されています。ティアマトの姿は明確ではないですが、神話の中では水の姿をしている描写と、動物(おそらくラクダか山羊)の姿をしている描写の間で揺れ動いています。
ティアマトが生み出した11の魔物
ウシュムガル(龍)
ムシュマッヘ(七岐の大蛇)
ムシュフシュ(蠍尾竜)
ウガルルム(巨大な獅子)←これがスフインクスです
ウリディンム(狂犬)
ウム・ダブルチュ(嵐の魔物)
ラハム(海魔)
ギルタブリル(蠍人間)
クサリク(有翼の牡牛)
バシュム(毒蛇)
クリール(魚人間)
+7
-0
-
1273. 匿名 2016/03/01(火) 01:16:38
>>1271
夜中に無理言ってごめんなさいm(_ _)m
お疲れさま&ありがとうございます
神話の世界は奥が深そうですね
自分たちの神を優位にするために相手の神の位を低くするエピソードを創作してそうだし…
全てを鵜呑みにしないよう、多方向から考察しなきゃですね
またインスピレーションの光が差し込みますように
おやすみなさい(-_-)zzz
名前に“角”があるので“件”の話ドキッとしました+13
-0
-
1274. 匿名 2016/03/01(火) 01:32:35
>>1273
探求心を刺激できて嬉しいです。
特にキリスト教は異教神は悪魔として描く事が多いですね(一神教なので)。
ですので比較する場合は多神教が良いと思いますね。
ではおやすみなさいm(__)m
+9
-0
-
1275. 匿名 2016/03/01(火) 09:33:20
“白い死神”
シモ・ヘイヘ
シモ・ヘイヘ(1905年12月17日 - 2002年4月1日)は、フィンランドの軍人。フィンランドとソビエト連邦の間で起こった冬戦争では、ソビエト赤軍から“白い死神”と呼ばれ恐れられました。スナイパーとして史上最多の確認戦果505名射殺の記録を残しています。
狙撃においては、フィンランドが独立後、旧宗主国のロシア帝国が開発したモシン・ナガンM1891を土台に改良したモシン・ナガンM28を使用していました。ヘイヘは身長約152cmと小柄でしたが、120cm以上あるこの銃を手足のように自由に扱ったと言われています。
モシン・ナガンには3.5倍から4倍の倍率を持ったスコープが装着できましたが、ヘイヘはスコープを使用せず、銃身に付いた鉄製の照星と照門のみで狙撃を行ったそうです。これは、猟師時代からの射撃姿勢への慣れと装備の軽量化に加え、スコープのレンズによる光の反射で位置を悟られるのを嫌ったことによります。
狙撃の技術は入隊前に営んでいたケワタガモ猟で培われたものと言われ、これは元猟師だった赤軍のヴァシリ・ザイツェフや、アボリジニーの猟師出身者が多い現代のオーストラリア陸軍SAS狙撃兵などの経歴と共通します。ヘイヘの狙撃は連続的な射撃と精度を両立していたと言われ、狙撃訓練課程では150mの距離から1分間に16発の射的に成功したという逸話が残されています。実戦でも、300m以内ならほぼ確実に敵兵の頭部を狙撃したといいます。
公式確認戦果である505人は世界最多記録として知られますが、このなかには狙撃銃以外の火器による殺害数は含まれていません。サブマシンガンの名手でもあり、“殺戮の丘”の戦闘ではKP31サブマシンガンを用いて、記録では200人以上、非公式なものを含めれば狙撃で殺害した505人よりも多くの敵兵士を倒したと言われています。これらの記録は戦争開始から負傷するまでの約100日間のうちに残されており、1939年のクリスマス直前の12月21日だけでも25人の赤軍兵士を殺害し、クリスマスの夜には通算殺害数が138人に達していたといいます。
冬戦争
冬戦争中のコッラーの戦いにおける丘陵地を巡る戦闘では、ヘイヘを含むフィンランド軍32人が4000人の赤軍を迎撃、拠点防衛に成功し、この丘陵地は“殺戮の丘”と呼ばれました。フィンランド軍は終戦までコッラー河付近の領土を守り抜き、この戦果は後に“コッラーの奇跡”と称されるようになったそうです。
リアルゴルゴ13ですね・・・。+14
-0
-
1276. 匿名 2016/03/01(火) 11:43:59
「濃姫」
戦国時代の英雄・織田信長の正室、いわゆる「濃姫」と呼ばれる女性がいたことは分かっているのですが、彼女がどのような生涯を送ったかは全くの謎です。というのは、濃姫に関する史料がほとんどないのです。
斎藤道三の娘で、織田信長に嫁いだのは分かっているのですが、例えば織田信長が本能寺で死んだとき彼女は生きていたのか、もし生きていたとすればその後どうなったのか分かりません。また「濃姫」というのも「美濃の国の姫」という意味で、本名は分からないというのが定説です。
ちなみに、濃姫について「帰蝶」という名前とされることがありますが、これは『美濃国諸旧記』にそのような表記があるからです。また「帰蝶」は「胡蝶」の誤記(崩して書くと「帰」と「胡」は似ているので)ではないかという指摘もあります。
+12
-0
-
1277. 匿名 2016/03/01(火) 13:07:31
長篠合戦の白装束集団
長篠合戦(長篠の戦い)は1575年の6月29日、三河国長篠城を守る徳川家康の家臣である奥平信昌を武田信玄の息子武田勝頼が攻めたことに端を発する戦いです。
この戦いにより武田家は壊滅的な敗北を喫し、1582年の天目山の戦いにて滅亡をします。この戦いにおいては従来織田信長の「鉄砲三段撃ち戦法」が勝因として語られてきましたが、これは現実には実行不可能な戦術であったとされ、また武田側の騎馬隊の存在すらも史実ではなかったと言われています。
当時の武田軍は大量の火縄銃とそれをあつかう鉄砲隊を組織しており、実際には大規模な銃撃戦が行われたものの数において劣勢であった武田軍が力負けをし、陣形を崩されたということが勝負の決め手となったようです。
さて、この長篠合戦は後に屏風絵の題材となるのですが、この屏風絵には一つ不思議な点があるということが知られています。
それは屏風絵における織田信長の本陣に謎の白装束の集団がおり、しかもその白い袴には六芒星が描かれているというものです。
この六芒星は5世紀から9世紀にかけて大和朝廷において祭祀を司る役目を負い、大きな権力を持っていた忌部氏のものであり、織田家はその忌部氏の子孫であるとされてきたということに由来するのではないかと言われています。
一説によるとこの忌部氏は2000年前に日本にやってきたユダヤ人たちの末裔であるとされ、そのため家紋として六芒星が使用されているとも言われています。
+16
-0
-
1278. 匿名 2016/03/01(火) 18:13:01
>>953
シュメール王名表には、大洪水以前の時代の在位期間が異常に長い
↑クローン技術があったら可能ですよね+8
-0
-
1279. 匿名 2016/03/01(火) 18:55:08
>>1278
確かにあり得そうですね。
まずシュメールの神は二ビルという約3600年周期で太陽系をまわっている惑星にいたといいます。
約45万年前二ビルを覆う大気が宇宙に拡散するという事態が起こります。
彼らは絶滅の危機に見舞われそこで目をつけたのが地球でした。
彼らは地球活動するために地球の生物と自らの遺伝子を組み合わせた新生物アナンヌキを生み出します。
彼らは地球でも王制を整備し都市を完備したワケです。
そして約30万年前に当時地球にいた「猿」と「アヌンナキ」の遺伝子操作を掛け合わせ「人類」をつくったのです。
王制が敷かれたのがメソポタミア。
作り出された彼らが『シュメール人』だったのです。
ちなみ『二ビル』とはシュメール語で“交差する星”という意味を持つそうです。
アヌンナキ(an unna ki )は
an は天、
na は~から(降りる)、
ki は地を意味する。
つまりアヌンナキは「天から降りてきた人々」という意味なのです。
ではここで考古学者セガリア・シッチンがシュメールの古文書を解読した事による事実に基づく仮説です。
★アヌンナキ的人類の作り方★
❶まずアヌンナキの身体からテエマとシルという”ふたつの聖なる物質”が採取する。
・テエマ→”記憶を保存するもの”=”遺伝子”
・シル→”男のアヌンナキからのみ採取しうるもの”=”精子”
❷アヌンナキのテエマとシルを”清められたる容器の中で、猿人の卵子と混ぜ合わせる。
❸受精卵は”清められたる容器”の中から、”鋳型”へと移され一定期間発育。
❹発育させた受精卵を”誕生の女神”の子宮、つまり母体となる女性のアヌンナキの子宮に着床。
うーんなんだかすごい・・・。
聖書にある“人は神に似せて作られた”という表現はアヌンナキが人を自らに似せてつくったと考えれば納得できますよね。
+12
-0
-
1280. 匿名 2016/03/01(火) 18:57:06
>>1277
本当にいますね!
この話になると食いついてしまう(^^;)
百貨店のそごうさんですが…創業者が“十合”さんだそうです
失われた10支族を連想しますよね
そごうのロゴマークは「まるにちきり」。当初そごうが呉服店(十合呉服店) であったころ、織機にちなんでマークとして使ったものです。
この家紋は「立鼓(りゅうこ)」ともいわれ三角形が2つ向き合っていて、重ねたらダビデの星になりますよね!平安時代からある古い家紋で、当時はよく使われたみたいです。
国章や市章に意味があるくらいだから、家紋も同様に“印”かもしれません。
家紋の由来を調べるのも楽しいですよ(^^)![家紋一覧]() 家紋一覧www.morisige.com
家紋一覧www.morisige.com家紋一覧「我が家の家紋」(3720種類)各ページをクリックして下さい。拡大画面になります。P1あ〜い葵・麻・朝顔P2い石・井桁・板屋貝P3い〜う稲妻・稲・イP4う〜お梅・鱗・海老葦・網・粟・庵・筏・錨・石銀杏・井筒・糸巻・稲妻兎・団扇・馬・梅鳥帽子・...
+12
-0
-
1281. 匿名 2016/03/01(火) 19:21:37
>>1280
また喜んで頂きそうな情報を・・・
現在の日本の皇室の公式な紋章は十六菊花紋でありますが、日本の皇室に古くから伝わる紋章の一つに、獅子と一角獣の組み合わせの図柄があるようです。 この写真は、明治時代に来日したスコットランド人、ノーマン・マクレオド氏の本から抜き取った写真を以下に示していますが、旧皇居である京都御所の清涼殿にある天皇の座の前には、獅子と一角獣の像があったようです。(平凡社 世界百科事典)
同じく、獅子と一角獣が盾を支えているデザインです。
盾の内側に12匹の獅子がいますが、これはイスラエル12支族のことを表しているのでしょうか。
そしてこの紋章の頂上にある、ダビデの星(カゴメ紋)を散りばめた、大きな六角形の星
を意味する物は何なのでしょうか。+12
-0
-
1282. 匿名 2016/03/01(火) 20:40:46
>>1281
これは胸高まりますね(☆∀☆)
このデザインは>>1180祭司レビ族の服装 胸当ての飾りと同じデザインですね。上段の4支族がマスに入っていませんよね…これが何を意味するのか気になります。
シンガポールの国章はライオンとトラが向き合っています。ここにもライオンが…
>>1222シンガポールには”ライオン”の神(秘密結社?)が現れています。
ライオン トラ 一角獣(麒麟ーキリン?)…星座とリンクする(トラは無いけどやまねこ座か?)
見えない国境…
私たちの住む世界の国々を表としたら、裏の世界の国々があるのかもしれません
そして裏の世界にも対立する勢力があるかも…?
↓シンガポールの国章![歴史のミステリーを語ろう]()
+14
-1
-
1283. 匿名 2016/03/01(火) 21:09:37
>>1282
対立はありそうですよね。
なんだかワクワクしますね。
以前にも書きましたがユダヤと似てる部分写真を見つけたので貼りますね。
見たら絶対ユダヤと日本の関係を確信しますよ。
●現在でもユダヤ人は祈りの時に『旧約聖書』の言葉を収めた「ヒラクティリー」と呼ばれる小さな小箱を額部分に付けるのですが、これは山伏が頭につける兜巾(ときん)と使用方法が酷似しています。
また、山伏が吹く「ほら貝」の音は、ユダヤ人の祭りに使われる「ショーファー」という羊の角で作った吹奏器とそっくりです。
「ショーファー」を吹くユダヤ人
「ほら貝」を吹く山伏
●古代ヘブライの祭祀レビ族は、みな白い服装をしていた。非常にゆったりとした和服のような服で、そで口には「リンネ」と呼ばれる房が付いていた。もちろん「ヒラクティリー」も使用していた。
彼らの姿は、まさしく神道の神官のような姿をしていたのです。+14
-0
-
1284. 匿名 2016/03/01(火) 23:07:31
>>1283
ショーファーを吹くユダヤ人は近所に居そうな男性ですね(笑)
山伏はレビ族で間違いない(>∀<)
上の方でピラミッドは地球規模災害を逃れるシェルターと仮定しましたよね
>>1121このロシア北方にあるコラ半島で発見されたピラミッド型の遺跡
この辺りが麒麟(キリン)座のシェルターになります
獅子座のシェルターは東南アジアにあるので、日本人はその2ヵ所から来た(あるいはそこで保存されたDNA)とも考えられますよね+9
-0
-
1285. 匿名 2016/03/01(火) 23:43:44
>>1284
素晴らしい推論ですね。
まだ見つかって無いシェルターもきっとありそうですよね。
イースター島のモアイ像は海を背に村を見守っていますが海の方を向いた7体のモアイが内陸部の「アフ・アキビ」にあります。
これは年に2回 春分と秋分の日に 太陽が沈む地点を見つめているのです。
天文学的な信仰を目的に立てられたと言われています。
天体と巨石遺跡の結び付きは強いんですね。
またイースター島の歴史は、4世紀頃マルケサス諸島から流れ着いた人たちがイースター島に住み着いたのがはじまりと言われています。
日本で4世紀頃と言ったら大和朝廷が全国を統一し、古墳が作られる時代です。
そして、7~10世紀頃(諸説あり)から、モアイ像の製作が始まりました。
つまり、日本では聖徳太子が活躍していた頃には、すでにモアイ像が作られていたことになります。
これを考えると、本当にモアイの歴史は古いんですね。
その後、人々は数百年に亘り、平穏にモアイ像を造りながら暮らし、14世紀に最盛期を迎えます。
そして、16世紀から17世紀頃、部族間の紛争が起こり、モアイの破壊合戦が起こったとあるそうです。
有名な伝承がモアイ倒し戦争です。イースター島にはイースター島の歴史は、4世紀頃マルケサス諸島から流れ着いた人たちがイースター島に住み着いたのがはじまりと言われています。
日本で4世紀頃と言ったら大和朝廷が全国を統一し、古墳が作られる時代です。
そして、7~10世紀頃(諸説あり)から、モアイ像の製作が始まりました。
つまり、日本では聖徳太子が活躍していた頃には、すでにモアイ像が作られていたことになります。
これを考えると、本当にモアイの歴史は古いんですね。
その後、人々は数百年に亘り、平穏にモアイ像を造りながら暮らし、14世紀に最盛期を迎えます。
そして、16世紀から17世紀頃、部族間の紛争が起こり、モアイの破壊合戦が起こったとあるそうです。
有名な伝承がモアイ倒し戦争です。イースター島には耳長族と耳短族二つの部族がいて、
耳長族がモアイを作っていた耳短族に無理な要求を行い、
それに反発した耳短族が反旗を翻したのが、モアイ倒し戦争と言われています。
イースター島のモアイ像の大部分が倒れていると言うのは、この戦争があったからだという訳です。
二つの部族がいて、 耳長族がモアイを作っていた耳短族に無理な要求を行い、
それに反発した耳短族が反旗を翻したのが、モアイ倒し戦争と言われています。
イースター島のモアイ像の大部分が倒れていると言うのは、この戦争があったからだという訳です。
イースター島の歴史は、4世紀頃マルケサス諸島から流れ着いた人たちがイースター島に住み着いたのがはじまりと言われています。
日本で4世紀頃と言ったら大和朝廷が全国を統一し、古墳が作られる時代です。
そして、7~10世紀頃(諸説あり)から、モアイ像の製作が始まりました。
つまり、日本では聖徳太子が活躍していた頃には、すでにモアイ像が作られていたことになります。
これを考えると、本当にモアイの歴史は古いんですね。
その後、人々は数百年に亘り、平穏にモアイ像を造りながら暮らし、14世紀に最盛期を迎えます。
そして、16世紀から17世紀頃、部族間の紛争が起こり、モアイの破壊合戦が起こったとあるそうです。
有名な伝承がモアイ倒し戦争です。イースター島には耳長族と耳短族二つの部族がいて、
耳長族がモアイを作っていた耳短族に無理な要求を行い、
それに反発した耳短族が反旗を翻したのが、モアイ倒し戦争と言われています。
イースター島のモアイ像の大部分が倒れていると言うのは、この戦争があったからだという訳です。
耳長族と耳短族ってどんな人達だったのでしょうね?
巨石遺跡の奥は深いですね。
+7
-2
-
1286. 匿名 2016/03/02(水) 01:28:10
>>1285 ありがとうございます!単なる妄想です(汗
耳長族と耳短族→王様の耳はロバの耳 をなぜか連想してしまいました(^^;)
王の耳がロバの耳に変わったことを知ってしまった理髪師が、口どめをされ、苦しさのために森の中の”葦”に向かって「王様の耳はロバの耳」と叫ぶと、葦がその言葉を言うようになる、というところで終わりだが、ミュージカルでは、森の木々がこれを言い、王は木々を切り倒そうとし、これに対して、真実を語るよう王に迫る民衆との間で歌合戦となる。王が負けて、真実を隠そうとした自身を反省したところで、ロバの耳が落ちるというハッピーエンドである。
”葦”が出てきましたね…これも神に関係あるのかしら?
ところで着々と天地図の作成が進んでおります。
聖書に興味がある方は、新約聖書に出てくる獅子・熊・牡牛・ワシ等がどの地域を指しているのか調べてみても良いかもです(但し手作業の為、多少のズレあるのでご了承ください)
このトピが閉じる3月12日までに終わるかどうか…入れるべきだと思う星座があれば教えてくださいね~
おやすみなさい(- -)Zzz![歴史のミステリーを語ろう]()
+13
-1
-
1287. 匿名 2016/03/02(水) 08:47:19
エジプトの星座
古代エジプト人が時間を数える目安にしたのは天の運行です。ほぼ40分置きに地平線から現れる小さな36星座「デカン(decans、十分角)」の動きを追ったのです。36デケード(エジプトでは10日間の意)が続いた後、ちょうど一年になります。これによって、シリウス星が空に現れる時期を見て毎年くるナイル川の氾濫の時期も予言できたとされます。棺の蓋の中からも、デカンの読み取り表も見つかっています。このエジプト人の星時計から昼夜平分ベースの時計を編み出したのが、古代最大の天文学者と呼ばれるヒッパルコ(ギリシア)で、昼夜を各12等分しました。
黄道の南側の星を36のグループに、すなわち10日毎に夜明けに地平線上に現れる星のグループに分割しました。1年の1/36の期間(ほぼ10日強)につき40分づつ前方にずれる。この40分に36(星座)を掛けると1440分になり、一日(60分掛ける24時間)に一致するのです。
+10
-1
-
1288. 匿名 2016/03/02(水) 08:52:09
円の角度はなぜ360度なのか?
はるか昔、円を360度としたのは、約5000年前のメソポタミアのバビロニア人。彼らは月と太陽の動きから、一年は地球が太陽の周りを一周する360日と決め、地球が1日で太陽の周りを回転する角度を1度とした。当時の人たちは月の動き方をみて、30日が1単位で、その12単位が1年であることも知っていたのです。
昔の人は凄すぎます。
+17
-0
-
1289. 匿名 2016/03/02(水) 11:07:24
実は72という数は色んな顔を持つのです(・ω・)
最小のアキレス数(次のアキレス数は108です…72+108=180…180度は地球でいうと裏側を示す)であり、2桁の自然数の中で 60, 84, 90, 96 と並び、最も多くの約数を持つ(いずれも正の約数は12個…また 108 も同じく12個の正の約数を持ち、120 までは12個を超える約数を持つ合成数はない)。
(12という数は人類に無くてはならない数みたいですね)
インドでは還暦の60歳よりも72歳の方がより祝福されるのです
インドは東経72度付近ですが、イギリス・ロンドン郊外の旧グリニッジ天文台跡を通過するグリニッジ子午線を基準としています。これは偶然でなく、意図的に設定されたものかもしれません。
ヒトラーはアーリア人こそが優越民族だと唱えましたがこのアーリア人というのは元々、中央アジアからイラン高原付近に住んでいた遊牧民族です。民族的にはアーリア民族、人種的にはコーカソイド(白人)ですが、ヒトラーが想定していたのはゲルマンやアングロサクソンのようで、インド北部やチベット辺りの民族をアーリア人の祖とみていたようです
インドは人類にとって重要な場所みたいですね(かに座シェルターの人?)
72という数は地球の歳差運動にも深~い関係があります
現在水瓶時代にある春分点ですが、72年で1度移動しています
この72という数字をもっと考察すべきだと思っています
私は自閉症を疑っていると言いましたが、恐らく『論理的なサヴァン症候群』(健常者のように話せます)かもしれません。自分で気付いてしまいました(^^;
実は幽体離脱の経験者なのですが、その時気付いたのが…人間の魂は少なくとも2つ以上が1つの体に入っているということです。幽体離脱の最中に後頭部を上から見ていたのですが、その時見た私は酷いもんで(もう1つの魂が勝手に電話していた)…もうアホとしかいいようがない(チーン)。でも今論理的思考をしている私の方の魂が無くなってしまったら痴呆症や知的障害を発症するかもしれません
エジプトでは”バー”・”カー”など複数の魂が一人の人間に宿るといわれています。これ本当のことだと思います+15
-1
-
1290. 匿名 2016/03/02(水) 11:48:55
>>1289
意味を持つ数字は色々あるでしょうね。
世界の多くの地域では、聖数、忌数、魔法陣など数字に特別な意味があると考える文化伝承があります。
12や24は天体や方位、時間と空間に関係したものに多くみられます。
ここであげる数は数詞ということになるか。数の名称、その用例、意味などを取り上げます。
・「1、2」までは最も原始的な数え方で、他は「たくさん」という意味になるという数の概念が 伝統的生活の少数民族に多くみられるようです。
・0は数学的にはインドで発見されたとよくいわれます。
・1は最小単位だが「唯一」や「一番、ナンバーワンNo.1」は特別な意味を持ちます。
・2は男と女、右と左、陰と陽など「対になる存在」という根源的認識に必要です。
・3は対ではない最小の集まりである。はじめの神々が3人、また3兄弟、3つの道具、 3回の繰り返しなど伝承物語には多くの「3」が存在します。
・4は方位と強く関係する数です。東西南北の4つは二方向と二方向の組み合わせだが 代えられない一組の数です。
四神。4大元素(エレメント)。4大天使。四天王。
・5は片手の指の数。
・7は聖なる数、特別な数とされます。
1週間は7日(唯一神による世界創造)
5惑星と太陽と月をあわせた数(天球上で北極星を中心として動かない特別な星)
ヨーロッパの音階は7つ。虹の7色(*文化で違う)
親の七光(日本)、先祖七代
・8は4の倍数。四方八方の方位。
8 中国で縁起のよい数。物事が開けるらしいです。
8 日本で縁起のよい数。「八」は末広がり
八大竜王(インド)。八卦(中国)。8大天使(ヨーロッパ)。
・9も特別な数としてあつかわれます。
・10は両手の指の数であり、ひとつの集まりの単位でもあります。 多くの文明で10進法にもとづく数詞をもちます。
シャカ(釈迦)の十大弟子。
12は星々や時間、方位と関係する数です。
1年12ヶ月。昼夜各12時間。黄道12星座、十二支、12神将等。1ダース(12個)。
キリストの12使徒。円卓の騎士12人、やシャルルマーニュの12勇士。
24は12の倍数であり、天体・時間・方位と関係する数です。
1日24時間、二十四節気。
・48は24の倍数で、多くの数を表す数である。プトレマイオス48星座
・60は12の倍数。 還暦(12×5)
・72は36の倍数 24の倍数 12の倍数
ソロモン72柱の悪魔
地さつ星 72 (108魔星)
七十二候 (24節気をさらに3つにわけたもの)
・100は10の倍数 10倍
・108は煩悩の数とされる(36×3 インド)。 108魔星(108の悪魔 中国)
・1000は10の倍数 100の倍数 多いことのたとえ
サウザンド thousand 1000 (英語) たくさん A thousand thanks.[ほんとうにありがとう-ていねいな強調]
ミレニアム millennium 1000年。1000年間。千年紀。 1000年で1世紀(ヨーロッパ)
または「千年王国」(キリスト教で、キリストが再臨してこの世を統治するという1000年間。至福千年。千年至福期。)
千世界、三千世界(インド、仏教)
千本桜、針千本、千畳敷、鶴は千年、亀は万年(日本) 千代に八千代に
など、多いですよね。+9
-1
-
1291. 匿名 2016/03/02(水) 13:18:26
バズビーの椅子
1702年、イギリスの北ヨークシャー州、サースク村に住むトーマス・バズビーは 妻の父親を殺害した罪で絞首刑に処され、殺人犯としてその一生を終えました。
彼には生前、長年愛用した椅子が一脚あったそうです。
バズビーの死後このイスは、妻が家財道具を処分した一環で、「バズビー・ストゥープ・イン」というパブに置かれることになりました。
ちなみにこのパブの名前は処刑されたバズビーからつけられたものです。
パブに置かれたこのイスは、それが元殺人犯のものであったことや 持ち主が絞首刑になったこと、このイスには呪いがかけられている などの色々な噂が広まり、酔った勢いで面白がって座る人たちが結構いたそうです。
しかし呪いの噂は本当だったのです。第二次世界大戦中、パブで酒を飲んでふざけて このイスに座った兵士たちは全員戦死しました。その後も噂が噂を呼び、ますます有名になったこのイスは、パブで酒を飲んで気が大きくなった若者たちが度胸試しをするのに格好のネタとなったそうです。
戦後サースク博物館にもうこれ以上、誰も座ることが出来ないように、今では天井からロープで吊り下げられて展示されているます。+14
-0
-
1292. 匿名 2016/03/02(水) 13:21:01
泣く男の子の絵
複数の種類があって何枚も複写されイギリス国内のデパートで簡単に手に入る「泣く男の子の絵」ですがこの絵が イギリス全土を巻き込んだとんでもない出来事を引き起こしました。手に入れた人たちに次々と恐ろしい現象が起きています。
深夜に絵が燃え上がりますそして、焼け跡からこの絵が無事な状態で発見されたそうです。複数の家で・・・
+11
-0
-
1293. 匿名 2016/03/02(水) 13:31:46
写真を撮影されると死ぬと予言された国王
アラビア半島南の石油産出国である、イエメンの国王を務めていたイマーム・ヤフヤー王(1869年 ~ 1948年)。
この、イエメンの国にはある有名な占い師がいました。占い師というより、予言師といってもいいくらいの人物だったそうです。
幼い頃、ヤフヤー王は、この占い師から「決して自分の写真を撮られてはなりません。もし誰かに写真を撮られたら、 あなたは不慮の死を遂げることになるでしょう。」と予言されたそうです。
この予言を完全に信じたヤフヤー王は、これ以降、決して人に写真を撮らせないように最大限の配慮をしていました。その為、国民も、 ヤフヤー王の顔を見たことがなかったのだそうです。
しかしある時、国王に面会を許された、あるイタリア人の画家が、その面会中に国王の顔を完全に覚えてしまい、面会が終わってから 、すぐに国王の肖像画を描きあげてしまったのです。ヤフヤー王にしても、写真は撮られないように注意してはいたものの、絵にまでは考えが及ばなかったのです。
この肖像画は、後にアメリカのリプレーという作家の元に渡り、さらに精巧な肖像画が新聞に掲載されました。
確かに写真ではないですが、絵という媒体を通じて国王の顔は多くの人の目に触れることになってしまいました。この記事が掲載されたのは 1948年2月20日。
そしてアメリカで記事が掲載されたちょうどこの日、全くの偶然か予言通りなのかイエメンにクーデターが起こり、 ヤフヤー王は反乱部隊の手によって殺害されてしまいました。
クーデターは、王位継承を狙う一人の王子の陰謀であり、このクーデターによってヤフヤー王自身と、
16人の息子のうちの3人が暗殺されてしまったといいます。ヤフヤー王殺害のニュースはその日のうちにアメリカに伝わり、 夕刊に記事が掲載されました。
呪いだったのでしょうか??+15
-0
-
1294. 匿名 2016/03/02(水) 14:50:29
>>1292
このページを見ながら寝落ちできませんね(^^;)
皆さん気をつけましょう+12
-0
-
1295. 匿名 2016/03/02(水) 14:59:01
氷河時代の金属容器(Metallic Vase)
アメリカ・マサチューセッツ州で1850年頃に発見された金属の容器。
ドーチェスターにある岩山で建設工事が行われた際、作業の一環で爆破工事を行ったところ、
岩の破片の中から2つに割れた金属が発見されたといいます。
2つの金属はぴったりと合い、鐘状で高さ12cm程度の容器である事が分かりました。
材質は銀を多く含んだ合金で、外側には花柄模様が銀細工で装飾されていました。
金属容器が埋まっていたのは地下5mの礫岩層の部分で、そこは数万年~200万年以上前(氷河時代)の地層だといいます。
銅の精錬は紀元前5500年ごろにペルシャで始まったと言われているので、氷河時代のものなら明らかに時代錯誤遺物となります。+8
-0
-
1296. 匿名 2016/03/02(水) 15:16:10
古代アッシリア遺跡、爆破で全壊か ISが動画公開
イスラム過激派組織「イスラム国(Islamic State、IS)」は11日、イラク北部にある古代アッシリアの都市ニムルド(Nimrud)の遺跡を破壊して爆破する動画を公開しました。
撮影日は不明ですが、同遺跡が全壊した可能性を示唆しています。
ニムルド遺跡はモスル(Mosul)の南東およそ30キロのチグリス川(Tigris River)沿いに位置します。 同遺跡に対する破壊行為は約1か月前に報告されていましたが、被害規模は明らかになっていなかったそうです。
動画の終盤にIS戦闘員の一人が「偶像崇拝を一掃して一神教を伝えられる場所があれば、われわれはいつでも実行する」と述べています。続く映像では、大規模な爆発で茶色の砂ぼこりが大きなきのこ状に立ち上る様子が捉えられているのです。
もうこの建物も粉々にされたのです。
この壁面のレリーフも吹き飛ばされてしまいました。ISILとはなんと愚かで野蛮な集団なのでしょうか。+9
-0
-
1297. 匿名 2016/03/02(水) 16:19:35
>>1296なんてことを…
まさかこの時代の掃除屋?証拠隠滅して、次の葦の時代に備える…だから超古代遺跡の形跡が無いのかもしれない
”聖戦”とか言ってるのも、発達した文明を持つ人類がこの時代に生きていたことを次の葦の時代の人間に知られないようにするためかもしれない…その方が自分たちが神になれ、この文明を未来に届けることができるから…
有識者会議って何なんだって思いませんでした?
もしかしたら”地球の番人”主催の会議かもしれません…今後の世界を裏で操っているかも?
妄想ですが…+12
-0
-
1298. 匿名 2016/03/02(水) 16:50:37
>>1297
もしくはそれに敵対する人達かもしれませんね。
それにしても過去の英知を破壊するなんて本当に愚かで悲しい事です。
一部は大英博物館などに保管されているみたいですが・・・。
凄く悲しい気持ちになりますね。
+11
-0
-
1299. 匿名 2016/03/02(水) 17:55:23
>>1298
そうですね
それにしてもショックです(T_T)
現物を見たかったです
とはいえ外国旅行は怖くて…>>1249さんの勇気、尊敬します+9
-0
-
1300. 匿名 2016/03/02(水) 18:41:55
アステカのカレンダー(Aztec calendar stone)
アステカは、1428年頃~1521年までメキシコ中央部に栄えたメソアメリカ文明の国家。
アステカの遺跡はスペイン人の侵略によって破壊され、わずかに残っているだけですが、
その中でも特に重要な遺物として、1790年に発掘されて以来「科学への桃戦」と呼ばれた太陽の石「アステカのカレンダー」が挙げられます。
円盤の中心にある現在の太陽がさし示す舌、針となる黒曜石のナイフが、
宇宙を形作る4つの運動(ナウイオリン)と一致する時が「第5の太陽の滅亡」といわれ、それは人類の終末を示すとも言われているのです。
カレンダーによればこれまでに人類は4度滅亡しており、5番目にあたる現在の人類滅亡の日は2012年12月23日(書籍によっては21日~24日)と一部で解釈されていました。
本当にもう大丈夫なのでしょうか?
+8
-0
-
1301. 匿名 2016/03/02(水) 18:46:19
ホンス・メスのパピルス(Khonsu-mes Papyrus)
古代エジプトのホンス神殿に由来すると思われる絵図。
「細胞分裂」を描写している部分があるといわれ、オーパーツの1つとして知られています。
細胞は17~18世紀に顕微鏡によって初めて確認され、細胞分裂が観察・報告されたのは1842年なので、
古代エジプトで細胞分裂が知られていたのなら歴史的発見です。
この遺物については、いくつか解説があったので参考に記述していきます。
まず、パピルスは右から左にむけて読みます。
両手を上に広げているのは「百万」=古代エジプトで「無限」を意味するヘフ神。
ヘフ神が手に「アンク」=「生命」を意味する文字をかけている=「永遠の命」を意味するのです。
太陽(ラー)と死後の復活を意味する儀式を行うマアト女神がいます。
赤い矢印で示したのは冥界の神で、冥界で裁かれる描写になっているのです。
青い矢印で示した細胞分裂の上に「アケト」=「地平線の絵文字」が書かれています。
細胞壁に見える部分は両側から二人の女神が水を注ぎ、次に白い服を着た故人がイチジクの樹の女神から乳を飲むシーンがあります。
これらの描写から、死者の書の「太陽(ラー)とともに蘇らん」の呪文の部分と推測されています。
+7
-0
-
1302. 匿名 2016/03/02(水) 18:55:47
マチュ・ピチュ(Machu Picchu)
南米・ペルーの山の尾根、標高2,430mにある15世紀のインカ帝国の都市遺跡。
アンデス文明は文字を持たないため、この遺跡が何のために作られたのか、首都との関係など、その理由は分かっていないそうです。
山裾から遺跡の存在が確認できないことから、しばしば「空中都市」などと称されています。
また、マチュ・ピチュはケチュア語で「老いた峰」を意味する言葉で、本当の都市名ではないのです。
遺跡には3mずつ上がる段々畑が40段あり、3,000段の階段でつながっています。石の建物の総数は約200戸。
建造方法は、石垣をぴったりと重ねて積む方法は石で石を叩いたり、削ったりしたと考えられています。
しかし、マチュ・ピチュの場合は傾斜路を造る余地がないため、どうやって5-10tもある巨石を運んだかは未だ謎であるとされているのです。
以前は「突然人が消えた文明都市」という扱いもあったが、この都市は通常の都市ではなく、王族や貴族のための避暑地としての冬の都(離宮)や田舎の別荘といった種類のもので、住人は最大でも750名しかおらず、雨季や王族が不在の時は、ほんの一握りの住人がいたのみと判明しています(少数の男女の遺体も見つかっている)。
最大の謎として、「なぜこのような急峻な山の上に造ったのか」というものがありますが、今のところ宗教的な理由(太陽が近いなど)が推測されているに過ぎず、解明には至っていません。
+13
-0
-
1303. 匿名 2016/03/02(水) 21:28:54
ソビエトの極秘研究施設(ヴォズロジデニヤ島)
中央アジアのアラル海にあるヴォズロジデジヤ島は、1948年、ソ連がひそかに細菌兵器研究施設を建てるまではただの小さな島でした。
40年間もの間、この研究所では家畜への空気感染を観察する生物兵器の研究がされていました。そこでは炭疽菌や天然痘、野兎病、腺ペストなどの菌が研究されていて、ほとんどのものが遺伝子学的に致命的なものに改造されていました。
1971年、天然痘の菌がアウトブレイクし、島外に放たれ、10人の命を奪ったのです。そして1988年、細菌兵器の計画を必死に隠そうとするソ連は島にある炭疽菌を水で流し土で埋めてもみ消そうとしました。菌は地下水脈を汚染してしまいます。その後、研究所は閉ざされ放置されたままです。
1960年代の灌漑計画以来、アラル海は大幅に干上がり、2001年にはついに陸続きになり、2007年には島の大きさが元の10倍になりました。この事件は環境破壊による悲劇のなかでも最悪のものであす。島ではなく半島になってしまったこの地域は中央アジアの時限爆弾と呼ばれているのです。
+11
-0
-
1304. 匿名 2016/03/02(水) 21:43:00
ニューグレンジ(Newgrange)
アイルランド・ミース州のブルー・ナ・ボーニャ遺跡群にある羨道墳の1つ。
1699年に発見された世界的に有名な先史時代の遺跡の1つであり、アイルランド島で最も有名な遺跡とされます。
紀元前3100年~紀元前2900年の間に作られました。
1年で最も日が短い冬至の明け方、太陽光が長い羨道(玄室に続く通路)に真っ直ぐ入射し、部屋の床を短時間だけ照らすように建設されています。
現在は日の出から4分後に日光が射し込むようになっていますが、地球の歳差に基づいて計算すると、5000年前には日の出と同時に日光が射し込んでいました。
太陽光は、このために考案されたと思われる「ルーフボックス」と名付けられた入り口すぐ上の開口部から射し込みます。
考古学界ではニューグレンジは墓だとする説が優勢だが、天文学や工学、宗教的な施設という説も挙げられており、目的は不明。+9
-0
-
1305. 匿名 2016/03/02(水) 21:53:47
レイライン(Ley Line)
「古代の遺跡には直線的に並ぶよう建造されたものがある」という仮説で、その遺跡群が並ぶ直線です。
レイラインの存在は、1921年にイギリス人のアマチュア考古学者アルフレッド・ワトキンスによって提唱され、著書「The Old Straight Track」によって遺跡の直線的配置性が話題となりました。
地図を開けば確かに遺跡が直線上に並んでいるように見える部分が多くありますが、レイラインを認める動きは学術的には主流とは言えないそうです。
主な理由は、「古代の人々がどうしてそんな直線性を持たせたのか」が不明な事、また、「直線性は偶然に発生したのでは」という疑いに対する解答が得られていない事とされます。
考古測地学を用いて解析すると、レイラインと呼ばれるものは古代人が測量し、所有権を主張するために引いたか、単に一般的な街道を作ったものとも推察できます。
近代的な測量により、「地形」においてもこうした直線性があることも確認されています。
ニューエイジ(新世界主義)の間では、レイラインやレイライン同士の交点は、「風水」「ダウジング」「UFO」のようなものを含む神秘的、超自然的なエネルギーに共鳴する地点だと考える説があります。
+11
-0
-
1306. 匿名 2016/03/02(水) 22:00:06
ローマン・コンクリート(Roman concrete)
「古代コンクリート」とも呼ばれる、ローマ帝国の時代に使用された建築材料。
セメント、および「ポッツォーリの塵」と呼ばれる火山灰を主成分としています。
現代のコンクリートはカルシウム系バインダーを用いた「ポルトランドセメント」ですが、
古代コンクリートはアルミニウム系バインダーを用いた「ジオポリマー」であり、およそ倍以上の強度があったとされています。
例えば、日本のコンクリート建造物の寿命は約50年~100年程度と言われていますが、ローマの「コロッセオ」は2,000年近く経過した現在でも形状を保っています。
また、ジオポリマーで作られたコップはコンクリートの床に落としても陶器のように割れることなく跳ね返るなど、極めて強靭な性質を備えるのです。
ローマン・コンクリートは、ローマ帝国の滅亡後に使用された痕跡はありません。
近年、古代コンクリートは徐々に見直されつつあります。
強度が高く、強度発生までの時間が短いため、軍事面での応用や研究も行われています。
また、鉄道の枕木、下水管、滑走路や石造りの建築物の補修など、広範囲の用途で試験が始まっています。
さらに、現代のポルトランドセメント製造は環境に悪影響で、CO2排出量は産業全体の実に7%に相当しますが、古代コンクリートは環境にやさしい点も注目されているのです。
パンテオン
コロッセオ
現代より優れているなんて凄いですよね。
+18
-0
-
1307. 匿名 2016/03/03(木) 00:26:31
縄文時代で蛇は信仰の対象でした
八岐大蛇の目は「彼の目は赤加賀智の如く」と描写されています
”赤加賀智”とはアカカガシ(赤楝蛇)で、カガシとは日本の古語で「蛇」を意味します…つまり”赤蛇”なのです
赤蛇は胴中央付近の背面の体鱗数は19列。鱗には強いキールがある。キールとは”竜骨”で、船舶の下に配置された水中構造体の名称。
88星座の中には”りゅうこつ座”があり、船の骨組みの形をしたこの星座は主に南半球で見ることができます。歳差運動の水瓶時代(現在)は、この竜骨座が一番高く上る時代です(とはいえ日本では見ることはできません)
>>1227 やっと光が射しました…
1)もう一つのしるしが天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。(新共同訳12:3)
↑この天に現れた「火のように赤い大きな竜」とは歳差運動によりある地点で目視された『竜骨座』の事だと思います。
その後に続く「七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた」は確証が無いので保留にしますが、>>1246さんと同じくインドのナーガ・ラジャを連想してしまいますね
インドといえば、気になる事が…
アナンタ(Ananta)とは、インド神話に登場するナーガラージャの一人。その名は「無際限」または「永遠」を意味する。千の頭をもつといわれる。蛇族の棲むパーターラという地底界の最深部で世界を支えている原初の蛇アーディシェーシャの別名であり、シェーシャが自らの尾をくわえて輪の形になっている状態の時にアナンタの名で呼ばれると言われている。アナンタはこの世が始まる以前、宇宙が混沌の海だった時に、ヴィシュヌがアナンタを船の替わりにして、その上に寝ていたという。そのヴィシュヌのへそから蓮の花が伸びてそこに創造神ブラフマーが生まれ、ブラフマーの額から破壊神シヴァが生まれたとされている。また、この世が終わる時、全ての生物が滅び去った時も、再び世界が創造されるまでの間、ヴィシュヌはアナンタの上で眠り続けるとされる。ヴィシュヌの使いとされる。
この神話に登場する”蛇族”がわかったら「七つの頭と十本の角…」がわかるかもしれません![歴史のミステリーを語ろう]()
+9
-0
-
1308. 匿名 2016/03/03(木) 00:35:42
>>1307ああっ画像が変でした
ごめんなさい…もう寝ます
おやすみなさい(- -)Zzz+4
-0
-
1309. 匿名 2016/03/03(木) 08:19:26
>>1308
いつもユニークな説ありがとうございます。
弾丸が貫通した頭蓋骨の化石(Rhodesian Man With Bullet Hole In The Head)
1921年、アフリカ南部・ローデシア(現:ザンビア)のブロークンヒル鉱山で働いていた労働者が、人間の骨の化石を発掘しました。
化石となった人物の頭蓋骨には、弾丸のようなものが貫通した痕跡が残っていたのです。
化石は分析の結果ネアンデルタール人と同じ種類と判断され、やがてアフリカを代表する化石人類「ローデシア人」と名付けられました。
穴は綺麗でなめらかな状態で、、矢じりや石器などの原始的な武器でつけられた傷、獣に襲われた傷とは考えにくいものでした。
しかし、ローデシア人の化石が埋まっていたのは地下18m、地層は推定10万年前のもので、当然銃火器は開発されていない。
素人考えでは、例えば何らかの自然現象によって高速で飛んできた石ころが頭蓋骨を貫いた…という仮説が思いつくが、定かではありません。
ベルリンの法医学者が調査したところ、高速で発射された物体が貫通した痕という結論が出たという話や、
穴には治癒した痕があるため外傷性のものとは考えにくい、といった話も挙げられています。
+13
-0
-
1310. 匿名 2016/03/03(木) 08:36:33
キエフの宇宙飛行士(The astronaut of Kiev)
キエフは、東欧・ウクライナの首都。
この地で紀元前800年頃から繁栄した「スキタイ文明」は、遊牧民の文明でした。
その遊牧民の1つ、カヤポ族の遺物とされるものがオーパーツと呼ばれています。
アルタイと呼ばれる地域の凍った墓の中から見つかったのもで、材質・大きさは不明。
紀元前700年前のものと推測されていますが、紀元前2000年頃という説もあります。
「宇宙飛行士」または「ロボット」にも見えるとして、海外のページでも多く紹介されています。
+12
-0
-
1311. 匿名 2016/03/03(木) 08:47:32
>>1307で図らずもアイヌ人と足利氏のルーツがわかったかもしれませんね
画像も変でしたが、文字も間違ってました…画像内の蛇は”ヤマカガシ”です。
ヤマカガシ(山楝蛇、赤楝蛇、Rhabdophis tigrinus)は、爬虫綱有鱗目ナミヘビ科ヤマカガシ属
ここで訂正します
そして間違いもう一点…竜骨座が南天で一番高く上るのは牡羊時代~魚時代(紀元前2330年~1990年)でした。期間的には4320年間という事になります
インドでは60進法が用いられ、
4320÷60=72
72という数字は期間を現し、竜骨座起源の人(神)達の時代だったのかもしれません
ちなみにこの60進法は紀元前3000年~紀元前2000年の頃から、シュメールおよびその後を継いだバビロニアで用いられましたので、シュメール起源であることは明らかですよね
この時代はこの支族が支配するとかいう談合があったのかもしれません
画像の矢印は歳差運動による今後の星座の上下の動きを表しています
星々は海に浮かぶ小船のように波に揺られているのです![歴史のミステリーを語ろう]()
+9
-0
-
1312. 匿名 2016/03/03(木) 08:48:50
サントリーニ島のアクロティリ遺跡(Acroteri on Santorini Island)
サントリーニ島はエーゲ海南部に位置するギリシャ領の島で、断崖の上にある白い建物群などは有名な観光地となっています
島内の南部ではヨーロッパで最も古い文明の1つといわれるミノア文明の大規模な港湾都市遺跡「アクロティリ遺跡」が発見・発掘されており、その高度さから、古代ギリシャの哲学者プラトンが伝える「一夜で沈んだ高度な文明社会」という「アトランティス大陸伝説」のモデルではないかとして有名になりました。
本島であるティーラ島(サントリーニ島)は紀元前1628年頃、海底火山の爆発的噴火(ミノア噴火)によって島の半分が吹き飛んだともいわれる惨状にみまわれました。
この爆発的噴火はエーゲ海一帯に惨禍をもたらし、プラトンが提唱したアトランティス伝説の内容に大きな影響を与えたといわれています。
また、幻の大陸アトランティスのもう1つの有力なモデルが、南にある「クレタ島」で、ここでも本島と共にミノア文明(クレタ文明とも呼ぶ)が栄えていました。
ミノア文明の背景を明らかにするには「線文字A」(別項目参照)の解読や、宮殿の情報の整理、聖域などについての更なる発見が必要とされていて、今も研究が続いています。
サントリーニ島。観光地で有名ですよね
+8
-0
-
1313. 匿名 2016/03/03(木) 09:11:20
>>1307
88星座の中には”りゅうこつ座”があり・・・
このりゅうこつ座の意味が何かありそうです。
ほ座のδ星とκ星、りゅうこつ座ι星とε星を結ぶと十字架の形になるので、これらの星たちはみなみじゅうじ座と見誤りやすい。このためこの4星を「ニセ十字」と呼ぶ。またニセ十字とみなみじゅうじ座の間に「Diamond Cross」というアステリズムを有する。これは、θ星とβ星を結んだ縦線とυ星とω星を結んだ横線を組み合わせたものである。
「ニセ十字」何か深い意味ありそうですが・・・。
また1756年出版の、フランス科学アカデミーの1752年版『紀要』に収められたニコラ・ルイ・ド・ラカーユの星表の中で、アルゴ座の一部分の名称として Corps du Navire (船体) と書かれたのが始まりです。ラカーユ死後の1763年に出版された星表 Coelum australe stelliferum では、Argûs in carina (アルゴの竜骨) とされました。アルゴ座はあまりに巨大すぎたため、1922年に国際天文学連合が現在の88星座を定めた際に3つに分割されました。りゅうこつ座は、このアルゴー船の「竜骨」の部分に相当します。
Corps du Navire (船体) も本当の意味を考えてしまいますね。+6
-0
-
1314. 匿名 2016/03/03(木) 09:42:24
ソ連が生んだ史上最強の女スナイパー「リュドミラ・パヴリチェンコ」
1941年6月、ドイツのソ連領侵攻が開始されたとき、24歳のリュドミラ・パヴリチェンコはキエフ大学で歴史を学ぶ学生でした。看護師になるという選択肢を拒否し、当時はまだ珍しかった女性でありながら従軍するという道を選びました。赤軍には2,000人の女性狙撃手がいましたが、生き残ったのは500人のみです。彼女もその内の1人で、第二次世界大戦では敵スナイパー36人を含む、確認戦果309射殺という記録を残しました。終戦後、外交宣伝の一環としてカナダとアメリカに赴任し、アメリカ大統領に招かれた最初のソ連人となったそうです。
凄い女性ですね。
+9
-0
-
1315. 匿名 2016/03/03(木) 10:10:56
>>1311
60進法の計算違っていました!これは関係ないかもです(>ω<;)
本当にごめんなさいm(_ _)m
そんな赤っ恥を晒したところで…しばらく黙々と仕事や天地図作成したりします
たくさん情報をありがとうございます
このトピが永遠に続いて欲しいと思いました+14
-0
-
1316. 匿名 2016/03/03(木) 10:16:05
>>1313
(≧∀≦)クー そそられる~+6
-0
-
1317. 匿名 2016/03/03(木) 10:18:02
ハンス=ウルリッヒ・ルーデル(Hans-Ulrich Rudel)
ハンス=ウルリッヒ・ルーデル(Hans-Ulrich Rudel, 1916年7月2日 – 1982年12月18日)は、第二次世界大戦中のドイツ空軍の軍人(航空機操縦員、幕僚将校)。
まずは彼の戦績
・出撃回数 2530回
・被撃墜回数 30回
・戦闘による負傷 5回
・ソ連軍によってかけられた賞金 10万ルーブル
戦果
・戦車519輌
・装甲車・トラック800台以上
・火砲(100mm口径以上)150門以上
・装甲列車4両
・戦艦1隻(マラート)
・嚮導駆逐艦1隻
・駆逐艦1隻
・上陸用舟艇70隻以上
・航空機9機(戦闘機 2、爆撃機 5、その他 2)
戦友らの証言によれば、ルーデルは仲間たちの評価を上げるために、自らの戦果を他人の戦果として申告させていたといいます。
この証言に従えば、実際の戦果は公式記録より多い事になります。
また彼は、負傷した際も病院からこっそり抜け出しては出撃し戦列に紛れていたため、実際に挙げた戦果はさらに多かったものと思われます。
また、右足を切断するというパイロット生命に関わる事態が起こったことで、退院後、部隊に戻ってからは航空団司令として地上勤務に就いていると上層部には思われていました。そのため、部隊を率い4月から終戦までに30輌以上の戦車を確実に破壊したと言われる戦果も、公式戦果として認められているのは3輌のみだそうです。
逸話
飛行中に敵の対空砲で撃たれ片足が吹っ飛んでしまったそうです。後席のガーデルマンに「足が無くなってしまった」と言ったら「そんな事は無いでしょう。足が吹っ飛んだら、話なんかしていられるもんですか。そんな事より左翼が燃えてます。不時着しましょう」と返されたそうです。何事もなく不時着したそうですが・・・。
当然、病院送りになったのですが、見舞い客が訪れると珍しく泣いていました。流石に片足になったら辛いのだろうと友人たちが慰めの言葉をかけると「もう二度と高飛びも出来ないしスキーもできないが、まだ一本残っているから脚の方はどうでもいい。しかしこの祖国の危機にイワンどもの戦車をしばらく撃破出来ないのが悔しい」という事だったそうです。そして実際に六週間後、鋼鉄製義足を装着して復帰復活しました。その後、入院していることになっていたルーデルは書類を偽造して出撃し、やっぱり相変わらずソ連戦車部隊に急降下爆撃を仕掛け続けたといいます。
凄すぎます・・・+12
-0
-
1318. 匿名 2016/03/03(木) 15:28:19
バルト海の海底に沈む物体(Baltic Sea anomaly)
UFOのようにも見えるし、スターウォーズの「ミレニアムファルコン」に似ている謎の構造物。もとはと言えば2011年6月にスウェーデンのダイバーによって水深90メートル付近で発見されたものです。直径はなんと60メートルもあるという巨大な物体。とんでもなくでかい物体で謎に包まれていました。
イスラエルの研究者の発表によると、この構造物にはリモナイトやゲータイトなどの金属も見つかっているのだといいます。つまり自然では形成されない人工物である可能性をにおわせているのです。しかし別の科学者によるとそれら金属は、付近の地質学上自然形成はあり得るとし、両者の言い分は平行線を保ったままです。
さらにストックホルム大学の海洋地質学者の話によると、この物体付近に花崗岩を発見。そこから得られた情報によるとこの建造物は14,000年前から存在するのではないかと推測されています。
14,000年前というと地球は氷河期だったのですが、その際バルト海は海岸線が遠のいていたので昔の人でも十分この物体を加工できる状況にあるとしています。
人工的なものなのかそれとも自然なのか議論が分かれておりますが、人工物だった場合目的は何であるかが今度は気になるところですね。
+11
-0
-
1319. 匿名 2016/03/03(木) 17:02:50
ヨハン・ライヒハート
ドイツ最後の死刑執行人。
生涯で3,165人の処刑に携わり、詳細な記録を残し、処刑者数ではフランス革命で約2,700人を処刑したシャルル=アンリ・サンソンをも上回り、公式の死刑執行人としては史上最多です。
1893年、ヨハン・ライヒハートはバイエルン王国、ヴェルト・アン・デア・ドナウ(ドイツ語版)のヴィヒェンバッハで生まれました。ライヒハート家は8世代にわたる死刑執行人の家系であり、叔父のフランツ・クサーヴァー・ライヒハートなどを始め、多くが同様に死刑執行人であったそうです。
ライヒハートは死刑執行の依頼を受けた人数が莫大であったにも関わらず、執行手順を非常に厳しく守ったそうです。黒い手術着に白いシャツ、白い手袋それに黒い蝶ネクタイという、ドイツの伝統的な死刑執行人の服装を着ました。そして、助手と共に罪人の体を固定すると、苦痛を与えないよう速やかに首を切断したそうです。彼の仕事はポーランドとオーストリアを含む占領されたヨーロッパの多くの地域で行われました。
1949年、西ドイツにおいて死刑廃止のため、最後の死刑囚である強盗殺人犯に対するギロチン刑を行いました。死刑廃止後も彼は嫌われ、孤独な人生を歩んだそうです。また、息子のハンスは父の職業との関係から結婚に失敗して、1950年に自殺しました。
1972年、バイエルン州ミュンヘン北東近郊のエルディング(ドイツ語版)にあるドルフェンにて孤独に死んだそうです。
仕事とはいえ人から嫌われ可哀想ですね・・・+13
-0
-
1320. 匿名 2016/03/04(金) 06:44:01
天地図を作成してる時、ちょっと気になることがありました
意見をお聞きしたいのですが…その事は画像化しなければ説明できないので…
説明するための星座を天地図に入れてからコメントさせてください(・_・;)
仕事もあるので思うように天地図が進みませんが、今日中にはコメしたいです!+6
-0
-
1321. 匿名 2016/03/04(金) 09:13:13
>>1320
了解です。
楽しみにしときますね。
ハリカルナッソスのマウソロス霊廟(Mausoleum at Halicarnassus)
ハリカルナッソスのマウソロス霊廟は、古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つ。
ハリカルナッソス(現:トルコの港湾都市ボドルム)にありました。
カリアの王マウソロスとその妻アルテミシアの遺体を安置するために造られた霊廟。
マウソロスの死から3年後の紀元前350年に完成したといわれています。
妻アルテミシアは霊廟建設の費用を全く惜しまなかったそうです。
彼女は当時最も優れた建築家と芸術家を連れてくるためギリシアに使いを送り、2人の一流建築家と4人の高名な彫刻家が造営に参加しました。
王の死から2年後、アルテミシアも後を追うようになくなったのです。
伝説によれば、彼女は夫マウソロスの遺灰をワインに混ぜて飲み、悲しみのうちに息絶えたといわれています。
この伝説から、アルテミシアは献身的な妻の象徴にもなっています。
霊廟は1856年に、書物でおおよその位置を把握していた大英博物館の考古学者チャールズ・ニュートンによって発掘されました。
+10
-0
-
1322. 匿名 2016/03/04(金) 09:17:01
トロイアの木馬(Trojan Horse)
ギリシア神話に登場する装置。「トロイの木馬」とも言われます。
木馬の中に人が隠れることができるようになっており、トロイア戦争においてトロイア(イーリオス)を陥落させる決め手となりました。
古代都市イーリオスは長く神話上のものと思われていましたが、19世紀末、ハインリッヒ・シュリーマンによりトロイア一帯の遺跡が発掘されました。
現在では第7層がトロイア戦争のあったと伝えられる時期(紀元前1200年中期)であると考えられています。
トロイア戦争にまつわる叙事詩の全てが架空のものではないとすれば、その中心はやはりイーリオスの破壊と考えられます。
都市が火災に見舞われたことは考古学的に間違いないですが、それが侵略によるものかどうかは、可能性としてはかなり高いものの推察の域を出ません。
また、神話において戦争の勝敗を決定づけた「木馬」はまだ見つかっていません。
トロイアの木馬が神話をドラマチックに見せるための空想だったのか、それとも実在した装置だったのかは、未だ不明です。
+11
-0
-
1323. 匿名 2016/03/04(金) 09:33:10
バビロンの空中庭園(Hanging Gardens of Babylon)
バビロンの空中庭園は、古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つ。
名前からは重力に逆らって空中に浮かぶ庭園のようなイメージが浮かぶが、実際は高台に造られた屋上庭園でした。
現在のイラク・バグダード郊外にそれらしき遺跡が残っています。
紀元前600年頃に新バビロニアの王ネブカドネザル2世が、砂漠の国に輿入れするのを嫌がった王妃アミュティスを慰めるため、バビロンに庭園を建造したとされています。
宮殿の中に作った高さ25m・5段の階段状になっているテラスに土を盛り、水を上まで汲み上げて下に流し、樹木や花などを植えたそうです。
あまりの大きさのため、遠くから見ると空中に吊り下げられているように見えたといいます。
水を汲み上げる方法については、らせん水揚げ機などの説がありますが完全には分かっていません。
紀元前538年のペルシアによる侵略で破壊されたといわれています。
+8
-0
-
1324. 匿名 2016/03/04(金) 09:35:51
バビロンの城壁(Walls of Babylon)
バビロンの城壁は、古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つ。
しかし「バビロンの空中庭園」と混同されたためか、後世には七不思議入りしておらず、代わりに「アレクサンドリアの大灯台」が入れられています。
新バビロニア王国の首都バビロンを取り巻く城壁で、高さ約90m、厚さ約24m、総延長は数十kmにおよび、100の門と250の塔をそなえていたとされています。
有名なものに、北域に位置する8番目の門「イシュタル門」があります。
城壁は二重になっていて、「生命の樹」という不老不死になる力を持つ木を王が探しに行くために、門を開ける儀式があるそうです。
また、その時に壁の間をシルシュ(聖獣)が走っているといわれます。
イシュタル門
+10
-0
-
1325. 匿名 2016/03/04(金) 09:38:42
エフェソスのアルテミス神殿(Temple of Artemis at Ephesus)
エフェソスのアルテミス神殿は、古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つ。
紀元前7世紀~紀元3世紀にかけてエフェソス(現在のトルコ)に存在した、狩猟・貞潔の女神(後に月の女神にもなった)アルテミスを奉った総大理石の神殿。現在は原形をとどめていません。
最初の神殿は紀元前700年頃の物で、キンメリア人によって破壊され、紀元前550年頃にリディアの王によって再建されました。
紀元前356年に放火で再び失われ、紀元前323年に三度建てられました。
異なる記述も多々ありますが、プリニウスによれば、神殿は広さ縦115m、横55mで、高さ18mの柱127本からなっていたそうです。
1863年から大英博物館の考古学探検隊がエフェソスの発掘を続け、7年後ついに深さ4m半の泥の中から神殿跡を発見しなした。
+11
-0
-
1326. 匿名 2016/03/04(金) 09:46:03
オリンピアのゼウス像(Statue of Zeus at Olympia)
オリンピアのゼウス像は、古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つ。
紀元前435年に、古代の高名な彫刻家ペイディアスによって建造された天空神ゼウスの彫像。
主に古代オリンピックにおける奉納競技の本尊とされていたといわれます。
紀元前5世紀頃、オリンピアに「ゼウス神殿」が建造され、ゼウス像はこの神殿の奥に収められました。
座像でありながら全長は約12mもあり、紀元前1世紀頃の地理学者ストラボンは「もしゼウス像が立ち上がったら、屋根を突き抜けてしまうだろう」と記述しています。
西暦394年、ゼウス像はオリンピアからビザンツ帝国に移されました。その後の消息は不明ですが、おそらく焼失したものと考えられています。
1958年にゼウス像の建造に使用されたと考えられる工房が発見され、この発見によってゼウス像の全容の解明が進められました。
+10
-0
-
1327. 匿名 2016/03/04(金) 09:49:02
ロードス島の巨像(Colossus of Rhodes)
ロードス島の巨像は、古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つ。
紀元前3世紀頃にリンドスのカレスによってエーゲ海のロードス島に建造された、太陽神ヘーリオスをかたどった彫像(コロッソス)。
全長は34m、台座まで含めると約50mになり、ニューヨークの自由の女神像に匹敵する大きさだったそうです。
巨像が完成したのは着工から12年後の紀元前284年とされています。
58年後の紀元前226年にロードスで地震が発生、巨像は膝から折れて倒壊しました。
巨像は800年間にわたってそのまま放置され、残骸を見物するために多くの人が訪れたそうです。
西暦654年、ムアーウィヤの軍がロドスを征服し、イスラム教徒で偶像崇拝を禁じている彼らは巨像をスクラップにしました。
結果、現在では巨像はカケラも残っていません。
巨像のイメージは港口をまたぐ姿勢とされていますが、これは1つの伝説が元になっており、本来の姿は分かっていません。
+13
-0
-
1328. 匿名 2016/03/04(金) 09:52:36
アレクサンドリアの大灯台(Lighthouse of Alexandria)
古代ギリシアの数学者・フィロンが選んだ「世界の七不思議」の建造物の1つに加えられていますが、
彼は自分の国の不思議を考慮しなかったため、実際には七不思議に含まれていません。
紀元前3世紀頃にエジプト・アレクサンドリア湾岸のファロス島に建造された灯台。「ファロス島の大灯台」とも呼ばれます。
灯台の高さは約134mで、当時は地球上で最も高い人工物の一つでした。
建材には大理石が用いられ、頂点には鏡が置かれました。日中はこれに陽光を反射させ、夜間は炎を燃やして反射させていたそうです。
796年の地震で大灯台は半壊し、その後の1303年と1323年の地震で完全に崩壊。
1480年頃、残骸を利用して要塞が建造され、大灯台は完全に消滅しました。
1994年にダイバーによって遺構が発見され、衛星調査でさらに解明が進むことになります。
また、戦時には鏡の反射光を敵の船めがけて照射し、船が海岸に到達する前に燃やすことが出来たという伝説があります。
+10
-0
-
1329. 匿名 2016/03/04(金) 10:36:23
カッパドキアに新たな地下都市
トルコの世界遺産カッパドキアで、過去最大とみられる地下都市が見つかりました。
場所はこの地方の中心都市ネブシェヒルの市街地。丘に建つ城の地下に、入り組んだトンネルと部屋が発見されました。発掘調査されたのはまだ一部ですが、その規模と構造はこれまで最大とされてきたデリンクユの地下都市を上回るとみられます。
カッパドキアはトルコ中央部に位置し、妖精の煙突と呼ばれる奇岩や洞窟の教会、さらには数多くの地下都市で知られています。火山灰が堆積してできた柔らかい岩石や凝灰岩を削り出してつくった地下都市は250 余りあり、侵入者から逃れるための隠れ場所だったとされます。
発見のきっかけは、市の住宅建設プロジェクトでした。2013年、ネブシェヒルの城を取り囲むように建っていた低所得者向け住宅を解体していた作業員たちが、地下への入り口を発見。
その先にはトンネルと部屋が網の目のようにつながっていました。
市は建設プロジェクトを中止すると、考古学者や地球物理学者による調査を開始。
2014年に居住空間や調理場、ワイン醸造所、礼拝堂、階段などから成る多層構造の地下都市を発見しました。石臼や石の十字架、陶磁器といった遺物からは、ビザンチン期からオスマン帝国の支配下に置かれるまで、ここが実際に使用されていたことがうかがえます。
地下都市のエリアマップ
カッパドキアといえば核爆発で出来たガラスや痕跡が沢山見つかっているそうですが、核シェルターだったとか・・・。
+11
-0
-
1330. 匿名 2016/03/04(金) 11:34:44
>>1321さんと皆さん お待たせしました>>1320です…こっちが気になるので仕事は後回し(笑)
実は星座の中に最近作られたものがあるのです。なので神話がないのです(例外はありますが)
>>1313さんの通り、星座が分割されたり消されたりしています。ニコラ・ルイ・ド・ラカーユも気になりますが(調べたら報告したいです!)、17世紀初頭にペトルス・プランシウスが作った6星座を先に報告します
《ペトルス・プランシウスの6星座》…と勝手に名前をつけてみる
1)麒麟(キリン)座
2)一角獣座
3)雄鶏(おんどり)座…現在は無い星座(天地図のピンク〇の辺り)
4)ヨルダン座…現在は無い星座(天地図の薄紫:山猫座・小獅子座・猟犬座に分割?)
5)チグリス座…現在は無い星座(天地図の黄色:小狐座を通る)
6)スズメバチ座(蜜蜂座・キタバエ座)…現在は無い星座(天地図のオレンジ色:牡羊座の角の一方)
3)失われた星座とも呼ばれるヨルダン座
ヨルダン川の事であり、中東の国際河川で「下降する川」を意味します。『新約聖書』によれば、洗礼者ヨハネがイエス・キリストに洗礼を授けたのがヨルダン川であったとされています。エジプトの聖マリヤ(聖母マリアとは関係ないとされる…?)は伝承舞台がヨルダン川です。彼女の伝承は、エジプトに生まれ12歳で両親の元を離れアレクサンドリアに赴き、以降17年間糸紡ぎ職をしながら肉欲目当てで無報酬で男達と寝ていて貧しい生活をしています。十字架挙栄祭の日に見えざる力によって聖堂に入れなかった彼女は、涙を流して生神女の庇護を願う祈りを捧げて聖堂に入る事が出来、十字架も目にする事が出来たといいます。ヨルダン川の向こう岸に行けば平安を得られるであろうとの啓示を得た彼女はそこの荒野で47年間、修行生活をしていました。永眠し修道司祭ゾシマにより埋葬される際マリアの足元に大きなライオンが現れ硬い地面を掘り埋葬するとライオンは荒野の奥へ帰って行ったそうです。
ヨルダン川はこの伝承を示しているのかもしれません…小獅子が近くに(足元?)あるし…
称号まで全て含めて記述される場合、エギペトの克肖女(聖)マリヤとも呼ばれる。克肖女(こくしょうじょ)とは「肖を勝ち得た女」との意味で、肖とは日本正教会においてアダムとエヴァ(イブ)によって曇らされた神の似姿を指す漢字として用いられる。
女性の聖人が「克肖」の称号が用いられる場合には克肖女(こくしょうじょ)と呼ばれ、男性の聖人の場合には克肖者(こくしょうしゃ)と呼ばれる。本記事内に登場していた修道司祭ゾシマもまたパレスティナの遁世者克肖(聖)ゾシマと呼ばれる。すなわち克肖者・克肖女は「神に似た人間の本来の姿を回復した聖人」を意味することとなる。
これって神に似せて作った人間のことですよね?つまりは古代の人間(神)の遺伝子を強く持つ人間ですよね?
ヨルダン座はフリーメイソンの蛇のバッチ(ユーラシア大陸に蛇が横たわっている)の蛇の位置にも近いものがあります
![日本が蛇に呑み込まれ始めた?〜なわ・ふみひと]() 日本が蛇に呑み込まれ始めた?〜なわ・ふみひとwww.h2.dion.ne.jp
日本が蛇に呑み込まれ始めた?〜なわ・ふみひとwww.h2.dion.ne.jp日本が蛇に呑み込まれ始めた?〜なわ・ふみひと帰還船[HOME] > [なわのつぶや記(復刻版)] > 日本が蛇に呑み込まれ始めた? 2005年4月18日(月)・22日(金)掲載文を再編集しました。 以下は当サイトの「フツーの人が書...
”失われた星座”と呼ばれることからも”失われたイスラエル10支族”を連想してしまいます
もしかしたら10支族の旅路なのかもしれません
6)スズメバチ座は元々ミツバチ座と呼ばれていたものが、蠅(ハエ)座になったそうです。この星座の連星が新星爆発を起こし(1991年ハエ座新星)、一方はブラックホールの可能性があります。水瓶時代の幕開けに新星爆発+ブラックホールだなんて…寒気がします
しかもこの星座の位置は、
●もう一匹の獣が地中から上って来るのを見た。この獣は、子羊の角に似た二本の角があって、竜のようにものを言っていた。
この位置ですから…
長くなり申し訳ありません
調べていくうちに、『キリスト教星図』の存在と、その観測地が”喜望峰(ケープタウン)という事がわかりました
他にもヨハネス・ケプラーやニコラ・ルイ・ド・ラカーユなど各国の天文学者が関与している事も…
気になりませんか?![歴史のミステリーを語ろう]()
+9
-1
-
1331. 匿名 2016/03/04(金) 11:55:05
>>1330ですが、ごめんなさい
ヨルダン座はこうでした![歴史のミステリーを語ろう]()
+12
-0
-
1332. 匿名 2016/03/04(金) 12:20:49
>>1330
非常に気になりますね。
まず天の川やヨルダン座の様な川を表すものは蛇や龍と同じと考えてもいいような気がします。
まず、新約聖書以前と以後は分けて考えた方が良いですよね。
新約聖書では他の宗教の神は全て邪教とされていますから・・。
スズメバチ座は元々ミツバチ座と呼ばれていたものが、蠅(ハエ)座になったそうです。
ハエと言えばハエの王を連想しますよね。
ベルゼバブ、ベールゼブブとも表記される。新約聖書にもその名がみえる。この名はヘブライ語で「ハエの王」を意味する。
本来はバアル・ゼブル (בַעַל זְבוּל)、すなわち「気高き主」あるいは「高き館の主」という意味の名で呼ばれていた。これはおそらく嵐と慈雨の神バアルの尊称の一つだったと思われる。 パルミュラの神殿遺跡でも高名なこの神は、冬に恵みの雨を降らせる豊穣の神であった。一説によると、バアルの崇拝者は当時オリエント世界で広く行われていた、豊穣を祈る性的な儀式を行ったとも言われる。
しかし、イスラエル(カナン)の地に入植してきたヘブライ人たちは、こうしたペリシテ人の儀式を嫌ってバアル・ゼブルを邪教神とし、やがてこの異教の最高神を語呂の似たバアル・ゼブブすなわち「ハエの王」と呼んで蔑んだという。これが聖書に記されたために、この名で広く知られるようになった。
とあります。
明らかにキリスト教による悪意が有りますよね。
そう考えると失われた星座こそ大切なものを表している様な気がします・・・。
また星座の元になる星々にもそれぞれ意味があります。
例えば。
かに座(蟹座、キャンサーCancer)
カニ:ギリシャ ヘラクレスがヒドラと戦った時、ヘラが応援に遣わしたが踏み潰されたカニ。
4等星までの星しかない星座だがプレセペ星団がある。プレセペは「飼葉(かいば)桶」の意。
プレセペ星団は、中国では積尸気(せきしき、積上げられた死体からのぼる燐気)といわれる。
天秤座(てんびん座、ライブラ)
てんびん:ギリシャ 乙女座(バルゴ)の女神が死者の心臓と羽のペンを比べ善悪を裁く天秤
てんびん:メソポタミア 死の天秤
ペルセウス座
β星 恒星アルゴル
アルゴルの名はアラビア起源でラス・アル・グル(デーモンの頭の意)
(ペルセウス座の、メデューサの首にあたる)
※アルコールと語源同じ
リリス:ヘブライの占星術師たちに呼ばれた名
ロシュ・ハ・サタン(サタンの頭):ヨーロッパでもリリスとしてみるときに呼ぶ
カプト・ラールウァエ(幽霊の頭の意):ヨーロッパ
ツァイ・シー(積尸、積上げられた死体の意):中国
星座の中の星も重要な気がしませんか?+8
-0
-
1333. 匿名 2016/03/04(金) 12:25:52
>>1331
ヨルダン座ってもしかすると日本人の先祖が渡ってきた経路かもしれませんね。
なんとなくですが笑
+11
-0
-
1334. 匿名 2016/03/04(金) 12:56:12
>>1332
Away in a manger かいばのおけで(クリスマスキャロル)
かいばのおけでねている
やさしいかおのイエスさま
つきほし 空にかがやき
平和なすがた見守る
かちくの声でめざめても
なかない強いイエスさま
わたしがねむるときにも
守ってください朝まで
すべての神のこどもを
めぐみと愛でみたして
永遠までもみくにで
ともに住まわせてください
「かいばのおけで」
リビングプレイズ 211番
作詞 不詳
作曲 James R. Murray
訳詞 吉倉英基
『飼い葉の桶で(かいばのおけで) Away in a manger』は、キリストの降誕(こうたん)を題材にした賛美歌。
初出は1885年。ルター派の日曜学校(Sunday School)で用いる教科書の中で最初に登場した。作曲者は、ジェームズ・マレイ(James R. Murray/1841–1905)。タイトル表記は、「まぶねの中で」、「神の御子イエス」など様々見られる。
「飼い葉(かいば)」とは、牛や馬などに与えるエサ用の牧草・干し草・わらのこと。ルカ福音書によれば、キリスト降誕の際、宿屋が混んでいたために通常の寝室には泊まれず、イエスを飼い葉桶に寝かせたとされている。こうして、「飼い葉」はイエス・キリストの降誕(誕生)を祝う記念日であるクリスマスには欠かせないテーマの一つとなっている。
なんかありますね…+7
-0
-
1335. 匿名 2016/03/04(金) 13:09:32
>>1332 いつでも名前のついた星を示せるように天地図を作っています(^^)v
小さな文字でいれてみますね!
>>1330が長い文章で消えたらいけないと読み返す時間が無かったので…
3)失われた星座とも呼ばれるヨルダン座 →4)でした
さらに、エジプトのマリアのところで
ヨルダン川はこの伝承を示しているのかもしれません…小獅子が近くに(足元?)あるし…
としましたが、バッチリ大人の獅子座が下にあるではないですか!
…でもヨルダン川(エジプトのマリア)の下半身に小獅子がある意味って…獅子の子供ができたってことを示しているのでは…そして日本列島を通過している意味は…?
ドキドキします(≧ω≦)=3+9
-0
-
1336. 匿名 2016/03/04(金) 13:21:14
>>1334
讃美歌は裏の意味が有りそうですよね。
その意味を伝承している人々がいそうです・・・。+11
-0
-
1337. 匿名 2016/03/04(金) 13:43:20
>>1335
星座は単体で作られたのではなく、歴史や重要な民族の秘密が隠されているのかもしれませんね。
調べれば調べるほどドキドキしますね。
+9
-0
-
1338. 匿名 2016/03/04(金) 15:18:33
追加情報
エジプトのマリアが聖堂で十字架を目した直後、ヨルダン川の向こう岸に行けば平安を得られるであろうとの啓示を得た。彼女は、ヨルダン川に赴いて顔と手を洗い、丸木舟でヨルダン川の向こう岸に渡った。その後47年間、荒野で修行生活をしていた。着物は擦り切れて失われ、食物は荒れ野の貧しい食べ物に頼っていた。情欲にも焦がされたが、それらとも精神的に闘っていた。
これらの話に彼女が聖書の句を引用しながら話すのを聞き、修道司祭ゾシマが「母よ、どこでそのような言葉を学ばれたのですか」と尋ねると、彼女は一切それらの言葉を学んだことも聞いた事は無いと答え、ただ全知全能の神は人にあらゆる事を教えられます、と微笑んで答えた。
>>1330~ここまでのコメント+追加情報で導き出される答えは…
エジプトのマリアは神の遺伝子が強く出た女性で、修道院に目をつけられて『獅子族の王』との子供をインドのマッディヤプラデシュ近郊で作った。これまで同じような事をしても思うような子供が現れなかったが、その中で唯一無二のイエス・キリストが誕生した。
マリアは荒野に埋葬され、イエス・キリストの子孫は朝鮮半島から日本列島へと渡り北上して二手に分かれた。一方はユジノサハリンスク経由で樺太(カラフト)へ、もう一方は北方領土からカムチャッカへ…。
というところでしょうか?
今、気になっていること…
日本ではロマと呼ばれるジプシー(ジプシーは差別用語)について
ジプシー(gypsy)は、一般にはヨーロッパで生活している移動型民族を指す民族名。転じて、様々な地域や団体を渡り歩く者を比喩する言葉ともなっている。外名であり、当人らの自称ではない。
1427年にパリに現れた彼らは、「自分たちは低地エジプトの出身である」と名乗った。ここから「エジプトからやって来た人」という意味の「エジプシャン」の頭音が消失した「ジプシー」 (Gypsy) の名称が生じたと言われる。ジプシーの居住圏は西洋だけにとどまらない上、生活様式は日本ではむしろサンカに近い。
サンカは、日本の山地や里周辺部で過去に見られたとされる不特定の人々を指す言葉である。その指し示す範囲は広く、回遊職能民であったり特殊な窃盗団など、時代や立場によって定義や趣旨も大きく変わり、語義を明確にすることは難しい。
「山窩」、「山家」、「三家」、「散家」、「傘下」、「燦下」(住む家屋を持たず傘や空を屋根とする屋外に住む存在という意味)などと表記される。「ポン」、「カメツリ」、「ミナオシ(箕直)」、「ミツクリ(箕作)」、「テンバ(転場)」など、地方によって呼ばれ方も違う。(それぞれの呼称は、「ホイト(陪堂)」、「カンジン(勧進)」など、特定の芸能を指す言葉と併用されることも多い。)
定住ではないため拠点(天幕、急ごしらえの小屋、自然の洞窟、古代の墳遺跡、寺等の軒先など)を回遊し生活しており、人別帳や戸籍に登録されないことも珍しくなかった人々であったとされている。
「サンカ」という言葉は、江戸時代末期(幕末)の広島を中心とした中国地方の文書にあらわれるのが最初である(ただし、それよりもさかのぼるとする意見もある)。幕末期においては、サンカの呼称は西日本に限られたとされている。
第二次世界大戦前の時代において、「サンカ」の語が漢字表記「山窩」として一般に広く知られるようになったのは、サンカ小説によって流行作家の地位を確立した三角寛(僧名は釈法幢)が発表した一連の作品群によるところが大きい。
明治時代にはサンカと呼ばれた不特定の層は徐々に元の生活圏に近い集落や都市部などに吸収されたと考えられる。
《古代難民説》
サンカ(山人)は、原日本人(あるいは縄文人)であり、ヤマト王権により山間部に追いやられた異民族であるとする説や、古代出雲との関連性が指摘されることもある。
《中世難民説》
動乱の続いた室町時代(南北朝、戦国時代)の遊芸民、職能集団を源とする仮説。起源を比較的古くまで求めることが可能な言葉である「三家」、「三界」、「坂の者」などを根拠とする。喜田貞吉の研究が代表的である。語源を探る上で説得力を持つが、江戸時代末期の中国地方の文書にあらわれた「サンカ」との因果を検証することが困難である。
《近世難民説》
江戸時代末期の飢饉から明治維新の混乱までの間に山間部に避難した人びとが多数を占めるであろうという考察。サンカに関する記述が、近世末になって、天保の大飢饉が最も苛酷であった中国地方で登場することから、沖浦和光が主張している。
サンカを山岳信仰や密教における山伏や、経済的な互助組織である無尽講などと関連づけた創作や論文体の物が読み物として流通した。
「ジプシー」+7
-0
-
1339. 匿名 2016/03/04(金) 15:24:14
>>1338のつづき…途中で切れました(汗
「ジプシー」が日本に渡って「サンカ」になったのでしょうか…
もしかしたらイエス・キリストの子孫は彼らなのかもしれません+7
-0
-
1340. 匿名 2016/03/04(金) 17:14:49
>>1338です…驚いたのが、
「サンカ」という言葉は、江戸時代末期(幕末)の広島を中心とした中国地方の文書にあらわれるのが最初
という事です。
という一文。
私事で申し訳ないのですが、実は先祖がその文書作成に関わっていたかもしれません…ヤバイ(汗
元々は大田原氏に縁がある家系なので、関東出身という事になります
しかも家紋が”そごう”さんとほとんど同じ”立鼓(輪子)…紡績具で、紡錘 (つむ) に取り付け、調べ糸をかけて回転させるもの”→エジプトのマリアは糸紡ぎ職をしていた→まさか…
このインスピレーションは断片的な先祖の記憶なのでしょうか…![歴史のミステリーを語ろう]()
+13
-0
-
1341. 匿名 2016/03/04(金) 19:04:45
>>1340
「サンカ」ですか。
この人達は謎が多いですよね。
しかし居たのは確実に確認出来ますよね。
流浪民ですが言われれば確かにジプシーの様ですね。
ネイティブアメリカンの様でもありますが・・・。
日本から北米に流れて行ったのかも・・・。
そごうのマークずらすと六芒星になりますね笑
サンカの人々
+13
-0
-
1342. 匿名 2016/03/04(金) 20:22:43
>>1341
>そごうのマークずらすと六芒星になりますね笑
↑
そうですよね(^^;)
渡来系民族だと思います…冗談でハーフって言っても疑われないので
まぁそれは置いといて(気になりますが)天地図作成に励みますね(^^)+10
-0
-
1343. 匿名 2016/03/04(金) 21:15:44
>>1342
頑張って下さいね。
楽しみにしてます。
+11
-0
-
1344. 匿名 2016/03/04(金) 22:38:26
見て下さる方がまだいらっしゃるみたいなので頑張って投稿させて頂きます。
曜変天目茶碗
天目茶碗は、「天目釉」と呼ばれる鉄釉(薬品)をかけて焼かれた陶器製の茶碗。
曜変天目茶碗は天目茶碗のうち最上級とされるもので、世界で3点(或いは4点)しか現存していません。
その全てが日本にあり、3点が国宝、1点が重要文化財に指定されているそうです。
いずれも中国・南宋時代の作とされますが、作者は不詳。
ある時期、建窯でわずかな曜変天目茶碗が焼かれ、それから二度と焼かれることは無く、なぜ日本にだけ現存したのかなど、多くの謎が残っています。
漆黒の器であり、内側には星の様にもみえる青・群青・銀・黄色などの玄妙な光沢・色彩を呈する大小の斑文が散らばり、斑文の周囲は藍や青で、角度によって虹色に光彩が輝き、「器の中に宇宙が見える」とも評されています。
現在、技術復元への努力が一部の陶芸家によって続けられています。
(2002年に陶芸家の林恭助が再現に成功したという記述があるものの、曜変の条件に沿うものは現在でも国宝の3点のみとされています)
+9
-0
-
1345. 匿名 2016/03/04(金) 22:42:58
北宋・汝窯の青磁
「青磁」(せいじ)は、紀元前14世紀頃の殷(中国)を起源とする青磁釉を施した磁器、または炻器。
特徴的な青緑色は、素材に含まれる酸化第二鉄が、高温の還元焼成で酸化第一鉄に変化する事で発色すします。
メノウを混ぜ込むことで、淡いピンク色になる事もあるそうです。
「汝窯」(じょよう)は、北宋時代に青磁を焼いた河南省清涼寺の窯。
汝窯の青磁は最高級品として知られ、澄み切った青空のような色彩(「天青色」とも表現される)をしています。
高麗の滅亡後、職人の多くが海外に流出、あるいは白磁の製造に切り替えるなどしたため技術が失われました。
現存数は少なく、どれも非常に高価ですがが、復元への試みがなされています。
ちなみに、ガンダムでマ・クベがいいものだと言った「北宋の壷」は商品化しているそうです笑(約4万円)
+9
-0
-
1346. 匿名 2016/03/04(金) 22:51:19
ローマ水道(Roman aqueduct)
紀元前312年~西暦200年代にかけて、古代ローマで建築された多数の水道。
これらの水道は古代の土木建設で最も偉大な業績の1つであり、古代ローマの滅亡後1000年以上、これに匹敵するものは作られなかったそうです。
現代でもこの水道は多くの都市で実用に供され、2000年以上も水を供給し続けています。
都市ローマ内の水道は合計350kmになり、ほとんどは地下を流れていて、例えば動物の死骸が原因の腐敗を避けることができ、敵の攻撃からも守られました。
水道は非常に精巧に作られており、厳密な許容誤差内で建築されていた(1kmあたり約34cmの誤差)。また、重力を利用した効率も良さも挙げられます。
ローマ市で供給された1日の1人当たりの水量は約1000Lで、現代の東京都民の水使用量233Lを遥かに凌ぎます。
また、「サイフォン」と呼ばれるパイプの圧力を利用して水を上昇させており、現在の水力技術も上下水道で同様の技術を使用しています。
施設を構成する建造物には、連続アーチ構造の水道橋、不純物を沈殿除去する沈殿池、末端の分水施設などがありました。
これらの施設には石やレンガの他、強度の高いローマン・コンクリートも使用されています。
偶然の故障やメンテナンスに対応するため、地下の導水渠には一定の間隔でマンホールが設けられていました。
ローマ帝国の滅亡で、ローマ水道は敵により徐々に破壊されていき、その他の水路もメンテナンス不足により故障し、水道技術は大幅に衰退・停滞したそうです。
+10
-0
-
1347. 匿名 2016/03/04(金) 22:54:40
ペルーの農業用水路(Irrigation in Peru)
南米・ペルー北部、標高2,750mの山に囲まれた盆地に、カマハルカ(Cajamarca)という都市があります。
カハマルカから約20kmの地点に巨大な岩が乱立する「クンベ・マヨ」(Cumbe Mayo)という場所があり、
ここには岩に掘り込まれた精緻な水路があります。
この水路が作られたのは紀元前900年頃とされ、当時はプレ・インカ文明が繁栄していました。
水路の長さは合計20km以上で、コース上にある巨石には30cm程度の鋭利な切断面があり、それが岩盤の中を100m以上伸びていて、途中で直角に曲がっています。
この切り口は刃物を使っても作れないといわれ、レーザー光線のようなものが使用されたかもしれないという説があります。
また、水路の中には幅が20~30cm且つ深さが約2mある個所もあり、機械を使ったのではないかともいわれます。
機械やレーザーを用いる技術があればこのような原始的な水路を作らないとも思えますが、詳しい加工方法は不明なままです。
+11
-0
-
1348. 匿名 2016/03/04(金) 23:14:16
歴史ミステリーにはまってしまい、毎日楽しみにしています。
全くの無知なので、すごく勉強になりますし、知れば知るほど面白いです。+15
-0
-
1349. 匿名 2016/03/04(金) 23:21:01
>>1348
ありがとうございます。
少しでも楽しんで頂けて嬉しいです。
+5
-0
-
1350. 匿名 2016/03/05(土) 00:01:55
>>1342ですが…どうしても気になって(ーωー;)
ベルベル人のハーフに似ていると言われます
もし私がエジプトのマリアの子孫だとしたら、彼女はベルベル人の子孫かもしれません
ベルベル人はモロッコに多く、”牡羊座”と”ハエ座”にあたります
画像はベルベル人とアイヌ人の民族衣装ですが、どことなく似ているような…![歴史のミステリーを語ろう]()
+14
-2
-
1351. 匿名 2016/03/05(土) 00:07:06
>>1348
ありがとうございます(^∀^)
私も無知なんですよ>>1349さんの導きでインスピレーションを得ています+8
-0
-
1352. 匿名 2016/03/05(土) 01:12:51
1240です(^∀^)皆さん相変わらず書き込みありがとうございます!あと少しでトピが終わってしまうのがとても寂しいです(´・・`)それまでにまた皆様の推測など新たな発見楽しみにしております!
書き込みくださってる方お疲れ様です(∩´∀`∩)+8
-0
-
1353. 匿名 2016/03/05(土) 01:17:47
>>1350
確かににていますよね。
琉球の人とアイヌの方も非常に似てますよね。
ユダヤ人が日本に来た時一緒に来たのかもしれませんね。
”牡羊座”と”ハエ座”にあたります
気になるのは牡羊といえばソロモンの霊72人の中に羊の頭を持つ悪魔がいます。
バラム(バラン) Balam
グリモアの伝統におけるデーモン。ソロモンの霊72人の一人でもある。 3つの頭をもっていて、1つは人間、残りは獣だという。 エノクのデーモンでもあり、その記述では牡牛と人間と牡羊の頭で、燃え上がる目、蛇の尾をもち、猛り狂う熊に乗り手首に鷹をとまらせてあらわれる。
過去と未来のすべての知識を与えてくれるという。
とあります。
ハエ座といえばベルゼバブ
ベルゼバブ ベルゼブブ Beelzebub
蝿の王の姿であらわされる。デーモン全ての君主に与えられた名のひとつだという。 ギリシアのデーモン学者プセルスによればヘブライのベルゼブル(天の神)が歪められて(おもしろく転訛されて) ベルゼブブ(糞山の王)になったという。
バールゼブブ(高い館の王)との表記をとる説もあるが、それではソロモン王のこととされかねないので、ユダヤ人が 蝿の王にしたという説がある。
とあります。
星座の中には悪魔と共通のものが沢山あるのがなんだか気になります・・・。+10
-0
-
1354. 匿名 2016/03/05(土) 02:19:07
>>1240さん応援ありがとうございます(^^)
>>1353さん( ・_・;)ですよね…
バラム…
“バラン”といえば牡牛座のアルデバランがリビアの“ベッテ山”にきています
尻尾が蛇→牡羊の頭→牡牛の頭→オリオンの頭
これは…
神のDNA→モロッコ人→リビア人→エジプト人
という民族のルーツと移動を意味しているかもしれません+10
-1
-
1355. 匿名 2016/03/05(土) 02:52:58
>>1354
そう思ってしまいますよね。
悪魔と言うのが裏に凄く深い意味が有ると思ってしまいます。
悪魔を調べると複合された動物が非常に多いのが気になってしまいます。
キリスト教徒から見た異教徒の事を表している様な気がします。+12
-0
-
1356. 匿名 2016/03/05(土) 03:51:40
>>1355
キメラみたいな悪魔はキリスト教が暗号のように使っているのではないでしょうか
何がしたいのかと考えたら、恐らくDNAを追跡しているのだと思います
その民族DNAの行いが悪かったらハエにされたりとか(^^;
そういえばエジプトの人は「我々はオリオンから来た」としているけど、天地図でのオリオンなのかもしれません。人類誕生の地と一致していますし…
おやすみなさい(- -)Zzz
↓天地図の北アフリカ~中東~ユーラシア下部の拡大図です。文字まで大きくなって見づらいかもしれませんが…![歴史のミステリーを語ろう]()
+10
-0
-
1357. 匿名 2016/03/05(土) 08:48:45
>>1356
かなり完成が近づいてきましたね。
楽しみです。
では趣向を変えて良く知ってるけど意味を知ると怖い話を
「かごめかごめ」の意味
かごめかごめ (籠女籠女…籠を抱えたような女性=妊婦) 籠の中の鳥は (お腹の中の赤ちゃんは) いついつ出やる (いつ産まれるのだろうか) 夜明けの晩に (悪阻あるいは陣痛で意識が朦朧としている最 中に) 鶴と亀が滑った (お腹の赤ちゃんは流産してしまった) 後ろの正面だあれ (後ろにいるのは、この世に生を受けられなかった水子の怨霊)
別には・・・
かごめ かごめ (囲め囲め、あるいは屈め屈め) 籠の中の鳥は (複数の人間によって作られた輪の中にいる人 は/神仏の力によって守られた、全くの無抵抗な 状態にある人は) いついつでやる (いつになったら憑霊し、神の言葉を発するの であろうか、あるいはとても神聖である) 夜明けの晩に (トランス状態において) つるつる つっぱいた (神がサッと入った=乗り移った)
+5
-0
-
1358. 匿名 2016/03/05(土) 08:51:48
続いて
『赤い靴』
一
赤い靴 はいてた 女の子
異人さんにつれられて
行っちゃった
二
横浜の 埠場(はとば)から
船に乗って
異人さんにつれられて
行っちゃった
三
今では 青い目に なっちゃって
異人さんの お国に
いるんだろう
四
赤い靴 見るたび 考える
異人さんに
逢うたび考える
この唄には「岩崎きみ」という女の子のモデルがいたのです。野口雨情が札幌で新聞記者をしていた頃に、偶然隣家に住んでいたのが「きみ」の実母だったのです。大人の世界の複雑な事情によりアメリカ人に預けたきり、会えないでいる、と。なんと切ない話なのでしょう。野口雨情は実母の話をもとに唄を作りました。
その後、五年の歳月をかけて「きみ」を追い掛けた人がいました。文筆活動に入る前、雨情と同様に新聞記者であった菊池寛です。その内容とは…「きみ」は三歳の頃、アメリカ人宣教師夫妻の養女となりましたが、渡米を前に結核にかかり、孤児院に預けられます(当時六歳)。病気と闘いながら孤児院で三年の月日を過ごし、遂にアメリカの地を踏むことなく、九歳でこの世を去りました…「きみ」の実像に迫った菊池は、一九七九年に「赤い靴はいてた女の子」という題で本を出版したのです。このことは、ご記憶に有る方もいらっしゃるかもしれません。これをきっかけに、本来の母子が再会できなかったことに対する悲哀・同情も多数寄せられ、現在では全国数カ所に歌碑や像が建てられています。+10
-0
-
1359. 匿名 2016/03/05(土) 09:14:37
「ハイサイおじさん」を知ってますか?
ハイサイおじさんという歌の背景には実際にあった凄惨な事件が元になっているとのこと。
かなりショッキングな事件ですので気を付けて下さい・・・
この「おじさん」は喜納家の隣人でしたがが、妻が精神に異常をきたし実の娘(7歳)の首を切り落とし鍋で煮るという事件を起こし村八分同然となり、以前から交友のあった喜納家に酒を無心に来るようになったそうです。この孤独なおじさんに歌を作ってあげようと思い立った昌吉が初めて作詞作曲したのがこの「ハイサイおじさん」です。NHJ Music Storeでは「おじさんのモデルはもともと校長先生にまでなった優秀な人だったが、沖縄の戦乱の中でアル中になり狂ってしまった実在の人物である。そんな彼を少年時代の昌吉は沖縄の伝統的共同体のやさしい眼差しで歌っている」と解説があります。また平成23年7月9日付朝日新聞朝刊土曜版be「うたの旅人」において、二面に渡りハイサイおじさんの詳細が掲載されていますが、こちらでは校長だったというのは虚言で戦前は遊郭で働く馬子だったことや、妻の狂気の原因が、おじさんの酒量が増え戦災でホームレスとなった女性達を家に連れ込むようになったことにあったなど細かい事情が説明されています。
おじさんが帰宅すると娘の足が毛布から出ている、触ると冷たい、どうしてこんなに冷たいのかと毛布をめくると頭部がない。
この事件を最初に目撃した近所のおばさんがひどいショックで一年後に死亡。
妻は「自分の子どもなんだから食べてもいいでしょう!」収容されるが後年自分のしたことの恐ろしさに堪えきれず自殺。
良く高校野球で沖縄の高校の応援歌になってますが・・・
+10
-0
-
1360. 匿名 2016/03/05(土) 14:09:28
>>1356
完成間近と思わせといて…実はまだ半分しか星座が入っていません
(^^;
このトピが閉じる前に(完成していなくても)載せますね
この天地図はあまり出回らない方が良いと思うので、また同様のトピが立ち、閑散とした頃に完成版を載せます!
+10
-0
-
1361. 匿名 2016/03/05(土) 15:25:43
>>1360
頑張って下さいね。
楽しみにしてます(^^)/
アコースティック・キティー
アコースティック・キティー(英語:Acoustic Kitty)とは、1960年代にCIAがネコをスパイ活動に利用しようとした計画です。
この計画で使用されたネコには、小型マイクと電池、さらに尻尾部分にはアンテナが埋め込まれました。
また、ネコが注意散漫になること(任務を忘れネズミを追いかけてしまう等)を防ぐため、ネコにはあらかじめ、空腹を感じなくするための手術が施されました。
訓練・手術等に費やした諸費用は、約1,000万ドルだったといわれています。
最初の任務は、ワシントンD.C.ウィスコンシン大通りにあったソビエト連邦大使館近くの公園で行われました。
任務の内容は、ベンチに座っている二人の人物の会話を盗聴してくる、というものでした。
しかしネコは放たれた直後、通りがかったタクシーに轢かれ死亡したそうです。
結局この計画は失敗に終わり、予算をただ浪費しただけだと結論付けられました。
目標のすぐ近くから放たれた場合には一定の成功をみたものの、実際の諜報活動において工作員が目標の至近距離までネコを連れて行くのは困難であり、あまりにも実用性に欠けると判断されました。
最初に気づきそうですが・・・。
真面目に研究しているのが笑っちゃいますね。+12
-0
-
1362. 匿名 2016/03/05(土) 16:05:38
デオンという男、あるいは女
18世紀のフランスの外交史上に不思議な人物がいる。その名をシャルル・ジュヌヴィエーヴ・ルイ・オーギュスト・アンドレ・ティモテ・デオン・ド・ボーモンといいます。この人は、生涯の前半は男性として、後半を女性として生きたといわれています。
女装させて8歳まで女の子として育て、その後も女装を好み、世間から少女として扱われることに喜びを感じるようになったデオンは、その美貌からルイ15世が、ぞっこん惚れ込んだといいます。この国王はデオンのその女装と美貌を外交に利用しようとしました。
27歳のデオンは完璧な女装をしてリア・ド・ボーモンという女性の偽名でロシアに渡りました。そしてロシアのエリザベータ女帝に近づき、 密かに情報をルイ15世に送っていました。当時、デオンの存在は一部のモノをのぞいてはフランス政府ですらその存在が隠されていたといいます。
そして二度目にデオンがロシアに渡った際は、女装せずに普通に男性としていました。今度はデオンはボーモンの兄であるという触れ込みで、 周囲の人々をごまかしたといいます。
その後フランスに帰国したデオンは、男性として軍隊生活を送ります。デオンの武勇は多く、フェンシングの達人でもあったそうです。
また一方で、デオンの外交手腕は確かなものであったらしく、全権公使を任ぜられ英国に渡りました。英国の社交界にも顔を出し、 しばしば女装で現れて英国社交界を混乱させたといいます。
英国社交界に入り浸るようになったデオンは、英国王のジョージ三世の妃と懇意になります。ある日、一夜を共にしたことが一部の 人間に知れてしまったというのです。すぐさま帰国しなければ命が危ない。だがフランス政府はこのときとばかり、 帰国の引き換えとしてデオンがスパイ生活で得た数々の機密文章の提出と、死ぬまで女性の姿でいることを条件として出しました。
なるほどデオンが女性を押し通せば、妃との男女の関係が無かったことになります。しぶしぶデオンはこのことに従います。
帰国したあとのデオンは、デオンの性別に興味を持つ多くの大衆に絶大な人気があったといいます。
またデオンは時としてフェンシングの剣を握り、スカートをまくしあげて決闘をおこなったと伝えられています。
デオンが死亡した時には、医者がその死体を見分し、男性らしからぬ胸のふくらみと、小さな男性器をみつけたと伝えられています。+8
-0
-
1363. 匿名 2016/03/05(土) 20:56:42
オルメカ
オルメカ(Olmeca)とは、紀元前1200年頃から紀元前後にかけ、先古典期のメソアメリカで栄えた文化、文明です。アメリカ大陸で最も初期に生まれた文明であり、その後のメソアメリカ文明の母体となったことから、「母なる文明」と呼ばれます。
オルメカとは、ナワトル語で「ゴムの国の人」を意味し、スペイン植民地時代にメキシコ湾岸の住民を指した言葉です。巨石や宝石を加工する技術を持ち、ジャガー信仰などの宗教性も有していました。その美術様式や宗教体系は、マヤ文明などの古典期メソアメリカ文明と共通するものがあります。
オルメカの影響は中央アメリカの中部から南部に広がっていましたが、支配下にあったのは中心地であるメキシコ湾岸地域に限られました。その領域はベラクルス州南部からタバスコ州北部にかけての低地で、雨の多い熱帯気候のため、たびたび洪水が起こりました。しかし、河川によって肥沃な土地が形成され、神殿を中心とした都市が築かれたのです。
オルメカの文化は、出土するさまざまな石像に現れています。人間とジャガーを融合させた神像は、彼らにジャガーを信仰する風習があったことを物語っています。祭祀場では儀式としての球技が行われ、その際には人間が生贄として捧げられました。また、絵文字や数字を用い、ゼロの概念を持つなど、数学や暦が発達していました。+9
-0
-
1364. 匿名 2016/03/05(土) 21:09:39
ネムルト山(ネムルト・ダウ、ネムルトダーゥ、トルコ語: Nemrut Dağ)
コンマゲネ王国の王アンティオコス1世が紀元前62年に建てた、王自身の座像を含む8 - 9 m の巨大像が並ぶ巨大墳墓があるとされていますが、現在でも埋葬施設が発見されていません。この事から現在でも、宗教上の儀式を執り行う場として機能していたとする説と、王自身がそこに永眠することを望んだ墓所とする説とが対立していますが、結論は出ていません。
直径152 m、高さ49mの頂上部には、王の座像のほか、2羽の鷲、2頭のライオン、様々なギリシャ神話やペルシャ神話の神々の像などが並んでいます。神像にはゼウス=オロマズデス(ゼウスとアフラマズダが同一視された神)、アポロ=ミトラス、ヘラクレス、テュケ(ギリシャ神話の女神でコンマゲネ王国の守護神)などが含まれています。いずれの像もギリシャ的な顔の造形と、ペルシャ的な服装・髪型の双方の特徴を備えています。また、山頂部は小石が積み上げられていますが、この小石は像を作った際に出た石材の破片を再利用したと見られています。
+9
-0
-
1365. 匿名 2016/03/05(土) 21:15:28
ヌビアのピラミッド
ヌビアのピラミッドはナイル川流域の「ヌビア」地域に栄えたクシュ文明の遺跡。エジプトのピラミッドの影響を受けています。
現代ではスーダン領となっているヌビア地域では古代に3つのクシュ文明が栄えました。最初はケルマに都し(B.C.2600-1520)、つぎにナパタ(英語版)(B.C.1000-300)、最後にメロエを都とする王国 (B.C.300–A.D.300) が成立しました。
ケルマはヌビア文明で最初の中央集権国家であり、その建築様式や埋葬形式はヌビア土着のものでありました。ナパタとメロエは北方の強大なエジプト王国により文化的、経済的、政治軍事の側面でも大きな影響を受けました。やがてエジプトの強力なライバルとなったクシュはついに第25王朝でエジプトを征服、ナパタの王はファラオとして君臨しました。
ナパタのエジプト統治は比較的短命で、B.C.656年のアッシリアの侵攻により終焉を迎えました。しかしナパタに与えた文化的な衝撃は巨大であり、ナパタの後継王朝であるメロエにおいてはピラミッド建築が爆発的に増加することになったのです。+9
-0
-
1366. 匿名 2016/03/05(土) 21:22:21
ペトラ(アラビア語: البتراء)
紀元前1200年頃から、エドム人たちがペトラ付近に居住していたと考えられています。エドム人たちの詳細は不明です。 (旧約聖書の創世記第36章からの文書データによると、アブラハムの孫・エサウ系の子孫と、その地のセイル(セラ) 山地に先住していたホリビとセイルの子孫らとの一部混淆による人たちであろうと推定されます。)
紀元前1世紀ごろから、エドム人達を南へ追いやったナバテア人達が居住しはじめる。ナバテア人はアラビア付近の貿易を独占。それにともないペトラも古代ナバテア人の有力都市として栄えました。
紀元前64年から紀元前63年ごろ、ナバテア人はローマの将軍、ポンペイウスにより、その支配下におかれます。ローマは、ナバテアの自治は認めたものの、税を課した。また砂漠から進入してくる異民族の緩衝地帯としました。また、ローマ風の建築物の造営がこのころ始まりました。
紀元後105年に、ローマ皇帝トラヤヌスが反乱を起こしたペトラを降伏させ、106年には、ペトラとナバテア人はローマのアラビア属州として完全に組込まれました。
インディ・ジョーンズ 最後の聖戦に登場しましたね。+8
-0
-
1367. 匿名 2016/03/06(日) 01:22:20
>>1366 遺跡を巡る旅に出ている気分でリフレッシュします(^^)ありがとうございます
天地図はあと30星座で星座の入力は完了です!…と言っても南極が省略されているので、そこまでは無いですけど♪
だけど天地図に遺跡を入れたり、ニコラ・ルイ・ド・ラカーユを調べたり、聖書の検証をしたりとやりたい事がたくさんです(^^;幸せです(笑
作成途中ですが天地図の拡大図(ユーラシア~アメリカ)です![歴史のミステリーを語ろう]()
+10
-0
-
1368. 匿名 2016/03/06(日) 01:44:32
>>1367
随分進んできましたね。
非常に楽しみにしてますので頑張って下さいね。
+5
-0
-
1369. 匿名 2016/03/06(日) 07:51:35
>>1368
はい(^_^)/励みます
星座が反転になっていますが、天の星々をそのまま地上に貼り付けたのでそうなっています
神の視点ですね…天使が地上に舞い降りた、的な
あとM3等の記号は星雲・星団・銀河などです
Mは“メシエ”と読みます…メシエとはシャルル・メシエ(Charles Messier 、1730年6月26日 - 1817年4月12日)は、フランスの天文学者。『メシエカタログ』の作成者ですが、これは裏で糸を引いている組織がありそうです。メシエ…“メシア(救世主)”というくらいなので…近くに重要な修道院があるかもしれません
地球に接近する小惑星はその軌道要素からアポロ群、アモール群、アテン群の3つに大別されます。そのため、地球近傍小惑星はアポロ・アモール・アテン型小惑星、AAA天体と呼ばれることもあります
このことからキリスト教やバチカン、エジプト(神官)が関与していることがわかるのです+9
-0
-
1370. 匿名 2016/03/06(日) 08:38:48
>>1369
1775年、ジェローム・ラランドによってかんししゃメシエ座(監視者メシエ座)という星座が設定されたことがあるが、現在は用いられていない。
と有りますし気になりますよね。
指紋照合システムのきっかけ
一見、同一人物に見えるこの2人の男性は、なんと同じ名前を持ち、同じ刑務所に送られたのです。しかし、刑務所に入る前まで、2人は他人同士だったといいます。この出来事がきっかけで指紋というシステムが導入されました。+13
-0
-
1371. 匿名 2016/03/06(日) 11:35:48
嵐警告きた(T_T)もうコメできないかも
結構いいとこ突いていたのかもしれません+11
-0
-
1372. 匿名 2016/03/06(日) 11:46:06
大丈夫ですか?
心配です・・・+9
-0
-
1373. 匿名 2016/03/06(日) 11:50:12
ギルガメシュ叙事詩(Epic of Gilgamesh)
古代メソポタミアの文学作品。叙事詩(じょじし)。
実在した可能性のある古代メソポタミアの王ギルガメシュを巡る物語。
主人公のギルガメシュは、紀元前2600年頃にシュメールの都市国家ウルクに実在したとされる王で、
後に伝説と化して物語の主人公になったとも考えられています。
最古の写本は紀元前2000年初頭に作成された「シュメール語版ギルガメシュ諸伝承の写本」。
また、シュメール語版の編纂は、紀元前3000年頃まで遡る可能性が極めて高いといわれます。
これだけ古いので、様々な文献に影響を与えたとされており、例えば旧約聖書の「ノアの方舟物語」は「ウトナピシュティムの洪水神話」が元になったという説、
ギリシャ神話の物語の中に、これが原型と考えられているものがある、といった話があります。
古代以後長い間忘れられていましたが、最初の粘土板写本が発見された1853年(聖書との類似性の発見は1872年)以後の文学作品にも大きな影響を与えました。+7
-0
-
1374. 匿名 2016/03/06(日) 12:20:06
>>1372閉め出された(/_;)
仮説の答えに辿り着いたというのに+8
-0
-
1375. 匿名 2016/03/06(日) 12:59:24
>>1374
大丈夫ですか・・・
応援してます。+9
-0
-
1376. 匿名 2016/03/06(日) 13:15:53
>>1375
ありがとうございます!!+6
-0
-
1377. 匿名 2016/03/06(日) 13:23:55
キープ(Quipu/Khipu)
インカ帝国で使われた紐に結び目を付けて数を記述する方法。
キープはケチュア語で「結び目」を意味します。
紐の結び目の形で数を表現するため、「結縄(けつじょう)」とも呼ばれます。
紐は二本撚り以上になっており、さまざまな形の結び目がついています。
下がり紐は3本ほど~2000本近いものまであり、細い補助紐がつけられる場合もあるそうです。
レイランド・ロックの研究によって、十進法を用いていることが判明しました。
キープは単なる記号以上の複雑な体系を持ち、「言語情報」を含んでいることが近年の研究によって明らかにされています。
王や役人は人民の統治に必要な情報などをキープに記録し、その作製および解読を行うキープカマヨックと呼ばれた役人がいました。
インカ帝国には「キープを教える専門の学校」が存在し、交叉型の分類、集計の混じった情報を扱うこともでき、数学的思考を可能としました。+7
-0
-
1378. 匿名 2016/03/06(日) 13:28:52
ロンゴロンゴ(Rongorongo)
イースター島で19世紀に発見された、文字とも原文字とも見られる記号の体系。現在も解読されていない。
イースター島の土着語であるラパ・ヌイ語で「暗誦、朗誦、詠唱」を意味します。
ロンゴロンゴが「文字」であることが証明されれば、人類史上において数少ない、独自に発達した文字体系の一つであることになります。
19世紀後半に、ロンゴロンゴの記された24の文字板(木片)が収集されましたが、風雨による損傷や、破損、焼失部分のあるものも多かったそうです。
これらは現在世界各地の博物館に分散しており、イースター島に残っているものはないとされます。
1870年代、島の先住民にこれを読むことが出来た人がほとんど残っていなかったことから、極少数の集団しかこれを読み書きすることができなかったと思われます。+11
-0
-
1379. 匿名 2016/03/06(日) 14:29:37
>>1370
かんししゃメシエ座(かんししゃメシエざ、監視者メシエ座、Custos Messium)、または、見張り人メシエ座(みはりにんメシエざ)は、現在は使われていない星座の1つ。現在のカシオペヤ座の北側の部分、きりん座とケフェウス座の間に設けられた。
↑
グリーンランドですね
先住はイヌイット(本国のデンマーク人に対する意味での先住民族はカラーリットであるが、彼らの入植はグリーンランド史においては比較的浅い方である。アメリカ先住民(インディアン)に近縁と思われる入植者の波が数度にわたってあり、その後アイスランドのヴァイキングが、最後にカラーリットが入植した)
北グリーンランドはカーナーク(英語版) Qaanaaq(旧:トゥーレ Thule)とノード Nord
南グリーンランドはナルサルスアーク(英語版) Narsarsuaq
”ナルサルスアーク”はアーク(正教会においては、聖櫃とは聖人の不朽体が納められた、装飾された箱である)の事でしょうか?
トゥーレとは「世界の最果て」を意味します。古代エスキモーと現代グリーンランドのイヌイットの祖先の民族は、トゥーレの伝説から名前を取ってトゥーレ族 (Thule people) と名付けられました
そしてグリーンランドの横の島は「アイスランド」でスコットランド・ゲール語では「 Innis Tile 」、つまり文字通り「トゥーレの島」と言います
インドとモロッコの子孫はヨルダンを通り、カムチャッカ→アラスカ→カナダ→グリーンランド→アイスランドに辿りついたのかもしれません
これが私の答え…妄想ということで+7
-0
-
1380. 匿名 2016/03/06(日) 15:15:42
>>1379
”ナルサルスアーク”
10世紀に赤毛のエリック(ヨーロッパ人初のグリーンランド入植者)が同地に移住。
とありますね。
この赤毛のエリックはエイリーク(赤毛のエリック)と呼ばれるノルウェー人はノルウェー,次いでアイスランドから追放され,982年(981年説もある)にグリーンランドを発見し,南西岸に定住した。ノルウェーやアイスランドからの植民を迎えるとともにグリーンランドの西岸を北上し,西へ向かってバフィン島や,さらにノバ・スコシア(カナダ南東部)などに達した。…
なんだか深い意味がありそうですね。
アークが眠っている場所なのかも・・・。
+7
-0
-
1381. 匿名 2016/03/06(日) 16:30:01
お城にはトイレがなかった
戦国時代に建てられたお城にトイレがないことをご存知でしょうか?
唯一、姫路城天守のみ、地階にトイレがあるのですが、これも1度として使われた形跡がなかったといいます。
なぜなのか?鋭い人は、お気づきかと思いますが、当時は、水洗トイレなど存在せず、トイレは不衛生でした。ほおっておけば、ハエやらバイ菌やらがウジャウジャ・・・。だから疫病などの蔓延を防ぐ為に、お城にトイレはあえて作らなかったのですね。
籠城中などの為に、姫路城天守では作られたようですが、使用することはなかったようです。
とはいえ、昔の人だって出るもんは出る!それをどうしていたかというと、オマルを使っていたようです。その排泄物は、毎日、毎日、中身を城外へ捨てていました。
しかも、なるべく遠くまでいって捨てろ!と厳しい掟を作っていた城もあったようで、捨てる人は大変だったでしょうね。
水洗トイレに感謝です。+13
-0
-
1382. 匿名 2016/03/06(日) 16:35:06
国家「君が代」の由来
我が国の国家である「君が代」。この君が代は、平安時代前期の古今和歌集におさめられた歌が元となっています。
「わが君は、千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」
意味は「私の大切なあなた どうぞ千年も万年も 小石があつまり大きな岩となり、そこに苔が生えるほど末永くお元気でありますように」といった歌です。
この歌は、やがて現在の「君が代」と同じ歌詞になり、おめでたい時に歌われたり、歌舞伎、浄瑠璃、物語などでも取り上げられるなどして庶民に定着していました。
幕末になると、開国した日本は外交儀礼の際、軍楽隊が演奏する為の国家の必要性がでてきて、遂に日本にも国歌が誕生することになります。そして明治13年に「君が代」が日本の国家として選ばれ、洋楽風に編曲したものが公表されました。
国家「君が代」について、日本国憲法では、「君」を日本国及びに日本国民統合の象徴である天皇を指すとし、君が代の歌に関しては、我が国の末永い繁栄と平和を祈願したものと解釈されています。
ちなみに、この「君が代」作者(作詞家)は不明です。
オリンピックやサッカーの試合でよく耳にする「君が代」。元は、平安時代につくられた歌だったんですねぇ。+12
-0
-
1383. 匿名 2016/03/06(日) 16:36:50
実は江戸時代には○○藩という言い方はなかった!
映画やドラマ、小説や教科書にまで使われている「○○藩」という言い方。しかし、これ、実は江戸時代には○○藩という呼び方はなかったという事実をご存知でしょうか?
この藩という名称が使われるようになったのは、大政奉還の翌年のこと。
御存知のように、その後すぐに廃藩置県によって藩は県に変わってしまうので、実際には殆ど使われてはいない。
では、江戸時代には金沢藩、米沢藩などどのように呼ばれていたのか?当時は、○○領という呼び名や加賀国金沢や出羽国米沢といった○○国○まるという言い方が一般的だったようです。
とはいえ、○○領といわれるより、現在では○○藩といったほうがピンとくるので映画やドラマでは藩の名称を使っているのでしょう。+10
-0
-
1384. 匿名 2016/03/06(日) 16:40:46
殺人を犯して逮捕!平賀源内の悲惨な最期とは?
平賀源内は、医学、蘭学を学び、文芸、芸術の世界でも才能を発揮した多才な人物でした。
「土用の丑の日」というキャッチコピーを生み出したのも平賀源内です。
そんな、平賀源内ですが、その最後は悲惨なものでした。殺人事件の犯人として獄中で亡くなってしまうのです。平賀源内にいったい何が起きたのでしょうか?
平賀源内が亡くなる1779年。彼は引越しをしました。その引越しした家というのが、以前切腹した浪人が住んでおり、次に住んだ住人も悪事が見つかり死罪になったという曰く付き物件です。
しかし、科学者である平賀源内は、その不吉な家に値段が安かったという理由で引越しをします。
その家が本当に祟られていたのか、どうか分かりませんが、後に平賀源内はその家で殺人を犯してしまうのです。
平賀源内が起した殺人については、いくつか説があるのですが、有力といわれるものを紹介します。
ある大名が別荘の修理を町人に依頼します。しかし、その町人よりも平賀源内の方がはるかに安い値段で修理ができるといいます。結局大名は、平賀と町人とを共同で修理にあたらせることにするのですが、仲たがいしていても仕方がないということで平賀源内の家で町人を呼んで宴会を開くこととなります。
町人は、平賀源内に「なぜ、あんな安い見積もりで修理ができるのか?」と問いますと平賀源内は、その修理の計画書を町人に見せます。これはスゴイ!と驚く町人。それを見た平賀源内も満足顔です。しかし、翌朝起きてみるとその計画書が消えている!町人が盗んだに違いないと思い込んだ平賀源内は、逆上して町人を殺してしまったというのです。
その後、平賀源内は1779年。11月21日に江戸小伝馬町の獄中に入り、約1ヵ月後に破傷風となって亡くなってしまいます。
エレキテルで有名な平賀源内。しかし、彼の最後は悲惨なものでした。
+13
-0
-
1385. 匿名 2016/03/06(日) 16:42:46
○○万石とか言うけど、それって現在の金額にするとどれくらい?
よく、100万石、200万石の大名などと言われますが、なかなかピンときませんね。○○万石って、いったい現在の金額に直すとどれくらいなのでしょうか?
江戸時代は長期にわたり繁栄したので一概にはいえませんが、一般的に1石=金1両=10万円ほどといわれています。
つまり、100万石の大名ならば年収がおおよそ1000億円ということになります。
とはいえ、そのすべてが大名の年収になるかといえば、そうではなく、そこから家臣の給料や土木工事などの国役や軍役、さらには参勤交代で江戸に行かなければならない・・・と出費も多かったようで、石高の少ない大名では、財政逼迫が常だったようです。
しかも、米などは種類や年により価値も変わってきますので、教科書や参考書などでは、○○万石=○○円などといった表記はしないのが普通です。+10
-0
-
1386. 匿名 2016/03/06(日) 20:12:41
天地図はかなりヤバかったみたい…PCが完全シャットアウトです(T_T)
なのでここで終わりです。
ごめんなさいm(_ _)m
トゥーレ協会
正式名称を「トゥーレ協会・ドイツ性のための騎士団」といい、鉤十字(ハーケンクロイツ)と剣をシンボルマークとした秘密結社であった。
ナチ神秘主義者は、トゥーレやヒュペルボレイオスがアーリア人の古代起源だと信じていた。ウィルヘルム・ダーム(ウィーンの医者)は次のように記している。「トゥーレ協会の名は、神話のトゥーレ、つまり消滅文化である北欧のアトランティスからとった。トゥーレに住む超人の民族は、魔力を通じて宇宙と繋がっていた。彼らは20世紀をはるかに上回る精神的・技術的パワーを持っていた。この知識をもって祖国を救い、新しく北欧・アーリア・アトランティックの民族を生み出さなければならない。新しいメサイアが現われて、人々を目的地へと導くだろう。」
アトランティスはモロッコのアトラス山脈に関係ありそうです
考えてみたら、アメリカなのにインディアンなわけは、その起源がインドだったからなんですね
たくさんの情報をありがとうございます
ではまた(^^)/~~~+14
-0
-
1387. 匿名 2016/03/06(日) 20:59:23
>>1386
とても残念です・・・
またどこかでお話しできたら良いですね。
お疲れさまでしたm(__)m
+13
-0
-
1388. 匿名 2016/03/06(日) 21:04:29
まだ見て頂ける方がおられるみたいなので頑張って投稿したいと思います。
古墳を作るのにかかる費用ってどれくらい?
かつて、大手建設会社の大林組が大仙古墳の建設費を見積もったことがあります。
大仙古墳は、ちょっと前まで仁徳天皇陵といわれてた古墳で現存する世界最大の面積を誇るお墓です。全長486m、高さ35m!
この古墳を造るのにかかる費用は、現在の技術、ブルドーザーやトラック、コンピューターを駆使し、20億円!期間は2年半。また、1万5000個の埴輪も制作するとなるとプラス16億。しめて36億円也~。
また、大林組によると現在の技術を使用せず、古墳を作るとなると、費用は796億円。期間は15年8ヶ月。埴輪には別途60億円。856億円もの費用がかかるとの計算でした。
850億ものお墓を建設できる人物となると、現在では・・・。日本でもかなり有名な会社の社長なら作れますかねぇ?+16
-0
-
1389. 匿名 2016/03/06(日) 21:09:55
369年 日本は朝鮮半島の一部を支配していた?
1910年から35年間、日本が朝鮮を植民地としていたのはご存知かと思います。豊臣秀吉の時代にも朝鮮に出兵していますね。
ですが、それよりずっと前、369年に日本は朝鮮半島南部の一部である任那(みなま)という地域を支配し、その一国である安羅という場所に日本府を置いていたというのは知らない人も多いのではないでしょうか?
時代は、ヤマト王権の時代です。日本書紀によれば、ヤマト王権は神功皇后摂政49年(369年)に朝鮮に出兵し任那を征服しました。そして、その後、新羅に奪われるまでのおよそ200年間、ヤマト王権はその地に任那日本府を置いたと書かれています。
しかし、よくよく調べてみれば、当時、まだ日本という国名は存在していなかったはずなんですよね。それなのに何で「日本府」という名称が使われているの?これは、日本書紀の創作なんじゃないの?と疑問の声も出ておりました。
でも、実は、日本書紀だけでなく、中国や朝鮮の史書にもヤマト王権の朝鮮半島への進出を示す史料は存在しているんですね。また、日本特有の前方後円墳が朝鮮半島にも存在していることや高句麗の王の業績を称えた石碑に「海を渡ってきた倭が百済や新羅を破って臣民とした」と書かれていることからも、現在ではヤマト王権と関わりをもった集団が任那にはいて、軍事的、経済的にヤマト王権は一定の影響力を持っていたことは間違いないのではないか?とする歴史家の方が多いようです。+9
-0
-
1390. 匿名 2016/03/06(日) 21:39:00
相撲のルーツとは?
相撲のルーツとは、紀元前23年にまでさかのぼります。
大和国にタイマノケハヤという力持ちで有名な男がいると聞いた垂仁天皇は、出雲の国からノミノスクネという人物を呼び寄せ、力比べをしてみろ!とすすめます。
しかし、この戦いは、現在の相撲というよりは、K1のようになってしまったようで、なんと蹴り合い!勝者は、出雲の国のノミノスクネで相手のわき腹と腰骨を蹴り砕いて勝利したと言われています。しかも、相手のタイマノケハヤは、この戦いで亡くなってしまっている・・・。
これが、日本書紀に記されており、とても相撲とは言えないものの、一般的に相撲のルーツだったといわれます。
その後、ノミノスクネは、タイマノケハヤの持っていた所領を貰い受け、垂仁天皇に仕えることになりました。
ちなみに、このノミノスクネは、当時、天皇の后が亡くなった際に、それまであった天皇陵に人が生き埋めにされるといった風習をなくし、埴輪を使おう!と提案した人物だとも言われています。+13
-0
-
1391. 匿名 2016/03/06(日) 21:42:13
昔の人は肉をほとんど食べなかった!
日本にて牛肉を食べる習慣が始まったのは明治の初頭。それ以前の日本では、猪や鹿の肉以外はほとんど口にしなかったといいます。
これは、海に囲まれた日本が動物性たんぱく質を魚介類でほとんどまかなえた為、危険を犯す動物の狩猟おり安全な魚介類の採取にたよる傾向にあった為とまた仏教の影響も強いようです。
日本では、古来、家畜の習慣がなく狩猟で得た肉はよいが、家畜を殺して食べるという行為には嫌悪感があったようです。ちなみに聖武天皇の時代には家畜を殺すことを禁止しています。
また、7世紀後半の天武天皇の頃には、犬、猿、牛、馬、にわとりの肉を食べることが禁止されたりしています。
日本人の獣肉の消費量が魚肉を上回るのは第二次世界大戦後の高度成長期以降からです。我々、日本人が肉を食べ始めたのって、ほんと最近からなんですねぇ。+10
-0
-
1392. 匿名 2016/03/06(日) 22:20:49
足利尊氏の肖像画は別人だった!
足利尊氏といえば、かつては京都国立博物館に所蔵された黒馬にまたがる有名な肖像画のイメージが強かったのですが、どうもこれが別人だったというからビックリ!
教科書にも載っていた足利尊氏の肖像画。それは、鎧を着て馬にまたがり、兜はかぶらず、ざんばら髪。鞘に収めず、刀をそのまま肩に担ぎ、背負った矢の一本が折れているという、かなりのアウトローの出で立ち・・・。
実は、これ足利尊氏じゃありませんでした。と、いわれて見てみれば確かに将軍というよりは、特攻隊長といった感じですね。
この足利尊氏といわれてきた肖像画。近年、研究が進み、馬具や武具をみると「輪違」といわれる紋が描かれていることがわかり、これは高師直(こうのもろなお)のものではないか?と言われ始めました。高師直とは、足利尊氏の側近で、南北朝の動乱の中で、数々の武功を納めた勇猛な武将。
この高師直の最後は、足利尊氏と尊氏の弟、直義とが権力抗争を繰り広げていた際、直義側の武将、上杉能憲により襲われ殺されてしまうのですが、その時の場面を描いたとすれば、折れた矢など納得がいきますね。
ちなみに、こっちが本物じゃない?といわれているのが等持院にある木像。かわいい顔してますね。
+8
-0
-
1393. 匿名 2016/03/07(月) 09:00:19
縄文式土器の文様の謎
縄文式土器といえば、名前の由来ともなっている「縄」でつけた「文様」がついている土器ですね。
当時、このような装飾をおどこしていた土器は世界的にも珍しいのですが、この文様はただ装飾のためだけにつけられた訳ではないようです。
縄にて文様をつける意義のひとつが、耐久性を高めること。
土器の形をつくり、熱を加えて土器を完成させるのですが、その粘土の中に空気が入っていると焼くときに破裂してしまったり、出来上がってからすぐに割れてしまったりするそうです。そこで、焼く前に縄でグイグイ押し付けて空気を抜くわけですね。しかも、デザインにもなるので一石二鳥という訳です。
また、滑り止めにもなるという効果が期待できます。これは、なんとなくわかりますよね。重いものを持ち上げる時にツルツルでは滑ってしまう。しかも、動物や魚を煮込むために使われていた訳ですから、手にも土器にも脂がついており、滑りやすかったでしょう。
縄文土器は実用性とデザインを兼ね備えた優れた土器だったのですねぇ。+13
-0
-
1394. 匿名 2016/03/07(月) 09:01:56
弥生時代の弥生ってどっからきたの?
縄文時代は縄文、つまり「縄」でつけられた「文様」の入った土器が見つかったので縄文時代。これは、意味がわかります。しかし、弥生時代の弥生って?
弥生といえば、3月のことですが、これと関係が?
実は、3月とはまったく関係なく、これ地名なんです。
弥生式土器が見つかったのが明治17年のこと。この弥生式土器の発掘場所が東京都文京区弥生町だったので弥生式土器となり、この土器が使われえていた時代、紀元前5世紀ごろ~3世紀ごろまでを弥生時代と呼ぶようになったのです。
もし、歌舞伎町で見つかっていたら歌舞伎式土器、歌舞伎時代と訳わからなくなっていた?かもしれませんねぇ。+9
-0
-
1395. 匿名 2016/03/07(月) 09:23:09
アダムのカレンダー
南アフリカの山全体に数千ものストーンサークルが散在しています。
アダムのカレンダーは、これらの遺跡の中で最も有名なものだと考えられています.
南アフリカのムプマランガにあり、いくつかの根拠によって75,000年前に作られたとされる直径30mのストーンサークルが立っています。
石はすべてドロマイトで、重さはそれぞれ5トンにもなり、離れた場所から輸送されてきたと言われています。
この遺跡は、太陽の動きを追跡するために配置され、岩の上に影を落とすところから、それにふさわしくアダムのカレンダーと名付けられました。これは背の高い中央の一枚岩から横の平らな石の上に、沈む夕日の影が動いていくことでカレンダーとして今でも完璧に動作します。
様々な天文的配置がこの遺跡で確認されていて、もしかしたら完全に機能的でほとんど手付かずに残された世界唯一の巨石カレンダーかもしれません。
天文学者のBill Hollenbachによってオリオン座の上昇に基づく計算が完了し、この遺跡が少なくとも75,000年前のものであると示唆されました。2009年6月には、オリオン座が「地平線と水平」ということだけでなく、遺跡で見つかった「ドレライトの侵食」にも基づいてさらなる計算が行われ、少なくとも160,000年前のものだと示唆されました。
160,000年前は・・・
頭脳の大きい、口腔咽頭が発達した現在の人類が誕生したのが20-15万年前と考えられます。
本当に巨石建造物なんて作れたのでしょうか??
特筆すべきは、アダムのカレンダーの周囲に金が非常に豊富だということです。
シュメール人の神、アヌンナキがニビル星から金を求めて、初めて地球のアフリカ大陸に降り立ったのは、今から約44万年前でした。
まさかこの遺跡は・・・。
+8
-0
-
1396. 匿名 2016/03/07(月) 17:30:09
摂政という職は現在も残っている!
摂政とは、天皇の代わりに政治を行う人のことですね。聖徳太子が推古天皇の摂政になったので何となく分かりますが、でも摂政の他にもたしか天皇の代わりに政治を行う人がいます。関白、院政。
ちょっと、話はそれますが、この摂政と関白、院政って何が違うのでしょう。知っておくとテストでも役に立つかもしれませんので見ておきましょう。
摂政(せっしょう) 天皇が女性だったり子供だったりした場合に代わりに政治を行う。
関白(かんぱく) 天皇が大人であっても代わりに政治を行う。通常は摂政がそのまま関白となることが多い。
院政(いんせい) 元天皇が政治を天皇の代わりにそのまま政治を行う。
つまり、摂政は天皇が女性だったり子供だったりした場合に政治を行う職のことです。聖徳太子も推古天皇が女帝天皇だった為、摂政となり政治を行いました。
関白は、天皇が成人していても代わりに政治を行う職のこと。9世紀の後半頃から、藤原氏による摂関政治(摂政、関白による政治)が始まります。藤原氏は、一族の娘を天皇と結婚させて、生まれてきた子供を天皇とし、天皇が子供の頃は摂政として、天皇が成人した後も関白として政治を行いました。
そして、9世紀の後半から始まった藤原氏による摂関政治も11世紀後半、藤原氏の后に子が出来ず、藤原氏の血をほとんでひいていない天皇が即位します。これをきっかけに、再び天皇に政治の権利が戻ってくるのです。そして、天皇を引退し上皇、またその上皇が出家して法皇となってからも政治を行うようになったのです。これを院政といいます。
話をもとに戻しますが、関白や院政は現在では必要ないので事実上なくなりました。しかし、摂政は残っています。将来、まだ幼い天皇が即位する可能性もありますし、また天皇がご病気などで長期入院となった場合などには、その期間、摂政に任命された方が天皇の代わりを務めます。
聖徳太子の時代から続く職がまだ残っているってちょっとすごいですよね。+7
-0
-
1397. 匿名 2016/03/07(月) 17:36:56
小野小町は絶世の美女!分かっているのはそれだけ・・・
歌人であり、絶世の美女だったといわれる小野小町(おののこまち)。しかし、彼女の正体は多くの謎に包まれています。
ただ、美女であったというのは、信憑性が高く、紀貫之(きの つらゆき)は古今和歌集(こきんわかしゅう)の中で、
「小野小町は古へ衣通姫(そとおりひめ)の流なり。あはれなるようにて、つよからず。いはば、よき女の悩めるところにあるに似たり。つよからぬ女の歌なればなるべし」
衣通姫とは、古事記に登場する伝説の美女ですので、その美女を引き合いに出しているくらいだから、やはりかなりの美女であったのでしょう。
さらに、小野小町の歌で有名なものもあります。
「花の色はうつりにけりないたずらに わが身世にふるながめせしまに。」
この歌で、小野小町は自身を花にたとえて、若い頃は花のように美しかったが、年と共に衰えてしまったと言っています。つまり、自他共に認める美女だったということですね。
しかし、この小野小町は、遣隋使で有名な小野妹子(おののいもこ)の子孫であるといわれていますが謎も多い女性です。
まず、いつ生まれて、いつ亡くなったのかが定かではない。大体、825年~900年ごろを生きた人物ではないか?といわれていますが、決定的な史料などは見つかっていません。
また、小野小町という名前も本名ではないらしい。当時、「町」とは、後宮に仕えた女性を意味していると言われており、小野小町は姉と共に宮仕えしていた為、妹の小野小町の方が「小町」といわれるようになったとも言われています。
さらに、小野小町の祖父は、あの空海とならび称された小野篁(おののたかむら)という歌人であり学者だった人物だといわれていますが、この人物が生まれたのは802年なので小野小町が活躍したであろう時代とズレが生じます。
となると、家系図が事実と違うのか?或いは、やはり小野小町の生没年がズレているのか?現在残された史料からでは、小野小町が美女であったということくらいしか分からないようです。+7
-0
-
1398. 匿名 2016/03/07(月) 17:40:41
「いろはにほへと」は誰が作ったのか?
「いろはにほへと」は、「あいうえお」のようなものですが、この「いろはにほへと」に意味があるのはご存知でしょうか?
いろはにほへと(色は匂へど) ちりぬるを(散りぬるを)
わかよたれそ(我が世誰ぞ) つねならむ(常ならむ)
うゐのおくやま(有為の奥山) けふこえて(今日越えて)
あさきゆめみし(浅き夢見じ) ゑひもせす(酔ひもせず)
香りよく咲く色とりどりの花もいずれは散ってしまうもの。この世は、誰にとっても永遠ではない。無常の有為転変(ういてんぺん)迷いの山を今日乗り越えれば、儚い夢を見ることも、現世に酔いしれることもないだろうに。
と、いった意味です。
これは、仏教の教えを表しており、それを47文字を重なりあわぬようにひとつづつ使い、意味のある文面に仕上げています。
この作者は古くから空海ではないか?と言われ続けてきましたが、その説も怪しいようです。
空海の時代には「あ行にある『え』=eと「や行の『え』=jeを別の音として区別されていました。しかし、いろは歌にはそれがない。また、「いろは歌」のような今様形式の歌も空海の時代には存在しなかったとも言われています。
現在では「いろはにほへと」=空海ではなくなってしまっていますが、では誰が作者なのかと聞かれれば・・・。
謎です。
しかし、少なくとも「いろは歌」の作者は空海の没後100年たった頃だという説が有力なようです。+7
-0
-
1399. 匿名 2016/03/07(月) 17:43:53
平清盛の両親ってだれ?
平清盛といえば、武士として始めて太政大臣となり、政界のトップに立つと日宋貿易などで財力を蓄え栄華の限りを尽くした人物ですね。
この平清盛、長いこと公家が政界を牛耳ってきた時代に、武士として異例の出世を果たしていきます。父親の平忠盛は、朝廷の警護役でありましたが、それほど身分が高いわけではない。それなのに、清盛は12歳で中央政治に参加し、49歳で太政大臣に登りつめます。
なぜ、そのような出世を果たすことができたのか?これには、清盛の出生に秘密があると古くから言われてきました。
平清盛の父親は、平忠盛。母親は不明となっています。これほどの有力者で母親が不明というのもおかしな話ですが、実は父親も忠盛ではないという噂が当時から流れていたようです。
「平家物語」には次のように書かれています。
~忠盛が仕えていた白河上皇には、祇園女御(ぎおんのにようご)という愛人がいました。ある夜、上皇が怪しい人影を見つけます。側近のものが「鬼がでた!」と騒いだので上皇は「ならば、殺してしまえ」と即座に命じますが、忠盛は冷静に「殺す前に私が鬼の正体を確かめてまいりましょう」と人影に近づいていきます。すると、その正体は、鬼どころか老僧でした。上皇は「大変な間違いをするところだった」と胸を撫で下ろし、忠盛に褒美として祇園女御をめとらせた~
といいます。この時、すでに祇園女御は身ごもっており、それが平清盛。つまり、清盛は白河上皇の子であったというのです。
ただし、これには疑問も出てきます。本当に祇園女御が清盛の母親だったとするならば、出産当時の年齢はおおよそ40歳以上。当時としては、かなりの高齢出産です。まぁ、無理ではないですけど、信憑性に欠けるなぁ。といったところだったのですが、近年になり新たな発見がなされます。
滋賀県の古宮(このみや)神社から見つかった「仏舎利相承系図(ぶつしゃりそうしょうけいず)」という文書によれば、祇園女御には妹がおり、その妹もまた白河上皇から寵愛を受けていた。その妹は懐妊の後、忠盛に授けられた。と書かれていたのです。
つまり、平清盛の父は、白河上皇であり、母は祇園女御の妹ということになります。
その後、祇園女御の妹は早くに亡くなってしまったことから、清盛は祇園女御の手によって育てられたというのが現在、もっとも有力な説です。
なるほど、これなら平清盛の異例の出世にも納得がいきますね。+9
-0
-
1400. 匿名 2016/03/07(月) 20:35:48
元号っていつから始まった?
日本最初の元号は、「大化の改新」で有名な「大化」です。この日本の元号は中国の制度を真似て作られました。皇極天皇4年のを大化元年としたのは始めです。
天武天皇の晩年にあたる686年の「朱鳥」という元号を堺にして、その後いったん元号は中断しますが、701年の大宝律令によって、「公式な文章には元号を用いるように」と定められてからは、現在にいたるまで継続的に元号は続きます。
とはいえ、現在のように天皇が代わるごとに元号もかえるという方式は、明治に入ってから・・・。
それ以前は、今のように天皇の交代により元号をかえることもありましたが、大きな災害があり、それを断ち切るために元号をかえたり、占いなどでその年には大きな事件や災害が起きるとされる年などには、元号をかえて運気を呼び戻すなどの理由で元号をかえることもありました。+6
-0
-
1401. 匿名 2016/03/07(月) 20:38:05
竹取物語は中国からのパクリ?
かぐや姫で知られる「竹取物語」は日本人なら知らない人はいないと言えるほど有名なお話ですが、この竹取物語は作者が不明であることでも有名です。
平安時代初期に書かれたと言われる、この「竹取物語」ですが、実は近年、中国の四川省に伝わる「斑竹姑娘(はんちくくうにゃん)」という物語が竹取物語にそっくりであることがわかりました。
中国の物語でも、やはり主人公は竹から生まれる美しい娘であり、5人の青年に結婚を申し込まれます。そして、かぐや姫から無理難題を言われるというところまでそっくりです。
ただし、この中国版かぐや姫も正確にいつ、誰が作ったお話なのか分からず、実際のところ日本の「竹取物語」が先でそれが中国に伝わったのか?または、中国のかぐや姫が先でそれが日本に伝わり、誰かが編集して物語を作ったのか?意見の分かれるところです。
しかし、中国の「斑竹姑娘」では竹を割るのがおじいさんではなく、若い青年でラストシーンではその青年と竹から生まれた美しい娘は結ばれるというハッピーエンド。ちょっと、日本のかぐや姫とは違っています。
かぐや姫の作者は誰なのか?いつ作られたものなのか?永遠に謎のまま。
・・・それも、またミステリアスで素敵なのかもしれません。+11
-0
-
1402. 匿名 2016/03/07(月) 20:41:23
源義経はイケメン!?
(戦国時代か江戸時代に書かれただろうとされる義経、あまりハンサムじゃない・・・)
源義経といえば、ドラマや映画では、二枚目俳優が演じ、浮世絵などでも美男子として描かれることが多いですね。
でも、本当に義経は美男子だったのでしょうか?
実は、義経が生きていた時代に描かれた肖像画などは残されていないのです。
では、なぜ美男子説が現れたのか?『源氏盛衰記』には「色白にて容貌優美、進退優なり」と書かれています。『義経記』でも「きわめて色白く、かね黒に眉細くつくりて・・・、楊貴妃ともいいつべし」と書かれているのです。女性のように色白で少女マンガに出てくるような美男子を想像させられますね。
しかし、一方で平家側が出陣の前に指揮を高める場面では、「色白うちいさきが、むかばのことにさしいでてしるかんなるぞ」、色白で背が低い出っ歯と義経をけなして士気を高める場面があります。
幸若舞の『笈さがし』にも「向歯反って・・・」という記述があるので義経の前歯が大きかったのかもしれませんね。
ちなみに、義経の母親は常盤という1000人の中から選ばれた美女であったといいます。兄の頼朝も結構イケメンですしね。義経が美男子であったという可能性は高いんじゃないでしょうか?+10
-0
-
1403. 匿名 2016/03/08(火) 00:39:32
たった10年で捨てられた都、長岡京のなぞ!
早良親王を祀った崇道天皇社(奈良市西紀寺町)
710年に遷都された平城京。794年に遷都された平安京は学校でもしっかり習い有名ですが、784年に遷都された長岡京は教科書でも詳しく触れられてはおらず、その為、桓武天皇は平城京から平安京へと都を移したと記憶している方も多くいるでしょう。
しかし、実際には桓武天皇は平安京に都を移す10年前に平城京から長岡京へと都を移し、その僅か10年後に長岡京を捨て、平安京へと都を移しております。
桓武天皇は、なぜ、たった10年で長岡京を捨てたのか?
もっとも、有名で興味深い説が「怨霊が怖かった」という説です。
長岡京へ都が移されてまもなく桓武天皇の優秀な部下であった藤原種継(ふじわらのたねつぐ)という人が暗殺されてしまいます。この種継という人は長岡京遷都プロジェクトの推進派だった為、犯人は遷都反対派の仕業であろうと大伴継人、佐伯高成らと共に桓武天皇の弟である早良(さわら)親王までもが捕らえられます。しかし、早良親王はこれを完全否定。無実であると訴えて絶食までし、淡路への流罪の途中で衰弱し死んでしまうのです。
その後、桓武天皇のまわりで恐ろしい災いが続きます。
まず、夫人の藤原旅子が病死。続いて生母の高野新笠が死亡。ついには、皇太子の安殿親王までもが重病となってしまいます。その間、長岡京は2度も洪水に襲われ、飢饉や疫病が発生。さすがに、ここまで不幸が続くのはおかしい。これらは、早良親王の祟りではないかと噂がたつようになるのです。
そして、桓武天皇は呪われた長岡京を捨て、平安京へと都を移します。しかし、それでも異変が収まることはなく、都を移す直前に安殿天皇の妃である藤原帯子が急死してしまいます。
実際、桓武天皇が本当に早良親王の怨霊を恐れて、都を移したのか?それとも2度も洪水に襲われるような場所をお金と労力を裂いて再建させるより、新しい都を開いたほうがいい、と判断したのか?その辺りは謎です。
しかし、実際、桓武天皇は早良親王の霊を沈めるための儀式を行ったり、早良親王の霊を沈めるための寺を建てたりと怨霊を恐れていたことは事実のようです。
+7
-0
-
1404. 匿名 2016/03/08(火) 09:19:55
(・ω・)テステス+4
-0
-
1405. 匿名 2016/03/08(火) 09:56:15
あ PC復活しました(^∀^)タダイマー
ところで…また妄想です(^^;もう全て妄想という事で。
南極で見つかった遺跡はちょうど”ハエ座”にあたります。はモロッコにある”キタバエ座”はアトラス山脈付近…これがシェルターかも?”ハエ”は人を遠ざけるために付けた名前だったみたいです
こうなると「浦島太郎」の竜宮城も存在するかもしれません。浦島太郎はシェルターでコールドスリープから目覚めて帰ってきたから時間が過ぎていたんですね(300年どころじゃないかも?)…キリストも本当に復活するかもしれません
”メシア”とはヘブライ語で「聖油を注がれた者」を意味します。これは原油が関係ある?…原油が枯渇した空間をシェルターとし、優れた民族を枯葦時代(葦が枯れる水瓶~乙女時代と仮定)の災害から守るというプロジェクト(汗…私は大賛成ですよ、このプロジェクトは。ただし、ジェノサイド(集団虐殺)は駄目です
グリーンランドは、島内のほとんどの土地が厚い氷に覆われており、地下資源の採掘が困難であった。しかし、地球温暖化の影響で少しずつ氷が溶解しており、今後採掘のスピードが速まると予想される。グリーンランドの地下には中東地域に匹敵する量の原油が存在するとされており、地下資源収入が経済的にグリーンランドを支え、デンマークからのグリーンランド独立が容易になるとも指摘される。
↑既に原油は急ピッチで取り出されているかも…米の原油増産と関係あるかもしれません(ガソリン価格の下落)。そして米は優先的にシェルターに入ることができ、忽然と人々は消えるわけです(→>>1245ヨハネの黙示録の四騎士:第四の封印・生き物…死と荒廃を象徴・アメリカ)
天地図の貼付は控えますが、中国地方~九州北部に星が密集しています。これは広島・長崎を示しているのではないかと思います。つまりは全てシナリオ通り…
※妄想です+9
-0
-
1406. 匿名 2016/03/08(火) 11:35:38
>>1405
お帰りなさい(^^)/
心配してました。
また楽しみにさせて頂きます。
なんだか悲しい未来しか見えないですね・・・。+8
-0
-
1407. 匿名 2016/03/08(火) 11:58:29
元寇で「神風」は2度も吹かなかった?
元の皇帝・フビライハンは、東アジアへの支配を拡大する中、東の島国、日本も征服しようと考えておりました。そして、遂に1274年。元は総勢4万もの兵を引き連れ日本を襲ってくるのです。これに、日本軍は激しく抵抗。日没と共に元軍は船に引き上げがた、その夜、突如襲った台風によって元軍は大被害を受けあえなく退却となります。
そして、7年後の1281年。今度は14万もの兵を率いて元軍は再び日本侵略の為、攻めてきます。しかし、今度は日本軍も準備万全。博多湾に石で塀を築くなど防御は十分。さらに、日本軍の武士たちは必死に勇戦し、元軍の上陸をこばむ。そうして、元軍が海上にとどまっているところに再び、台風が襲い、2度目の襲来も見事に撃退!
日本は『神風』によって、大国、元の襲来を拒み独立を保つことができた。
・・・と、長い間言われ続けてきましたが、最近では日本を救った『神風』は、2度も吹かなかったいう説が有力となってきております。
1度目の元寇(文永の役)で元に加勢した高麗の史書には、確かに「夜中に強い風が吹き、船や兵に大きな損害が出たので退却を余儀なくされた」とあります。しかし、元の史書によれば、「日本軍は思ったより手ごわく、こちらにも被害が大きい上に、矢も尽きてしまったので協議し、いったん退却することにした。」というのです。
もし、元の史実が正しければ、最初の元寇では『神風』は吹かなかったということになります。
いくらなんでも本州に攻め込んで僅か1日で矢が尽きるというのはおかしいようにも思えますが、近年の解釈では、最初の元寇は日本の侵略が目的ではなく、元の力を見せつけてその後の外交を有利に進めるがための攻撃だったのでないか?その為、日本を征服するほどの武力も持ち合わせておらず、思いのほか日本の武士達が手ごわかったこともあり、僅か1日で引き上げるしかなかったのではないか?という説が有力視されているようです。
ちなみに、2度目の元寇(弘安の役)では、日本の記録にも『神風』が吹いたと書かれており、弘安の役の時に台風が元軍を襲ったのは間違いないようです。
『神風』が2度も吹いたかどうかは定かでありませんが、当時の日本の武士達が命を懸けて戦ってくれたお陰で今の日本があるのは間違いありません。
現代に生きる我々も、未来の日本人に感謝される日が来るのでしょうか?・・・と考えさせられます。+6
-0
-
1408. 匿名 2016/03/08(火) 12:02:58
足利義満は暗殺されていた?
足利尊氏の孫であり、11歳の若さで室町幕府の3代将軍となった足利義満。
南北朝といわれる、2人の天皇が存在した時代をひとつにまとめ上げ、金閣寺を建てたことなどが有名ですね。
この足利義満の死は、義満にとって実にタイミングが悪く、暗殺説も古くから疑われています。
その暗殺説の理由が足利義満は天皇になろうとしていた。そして、実際、かなり近いところまでいっていたという事実です。義満が、いよいよ息子を天皇の座につけようという時に急死です。
う~ん。タイミングが良すぎる・・・。
だれかが、天皇家のっとりを食い止めようと暗殺したとしても不思議ではありません。
足利義満は、1394年に将軍の座を長男、義持に譲り、自身は太政大臣に昇進しました。武家として最高位の征夷大将軍と公家として最高位の太政大臣をともに務めたことになります。さらに、半年後には、太政大臣をやめ、今度は出家して宗教界をも手中に収めようと考えます。
また、足利義満は1401年は遣明使を派遣しますが翌年、明から「日本国王源道義」という返書をもらっています。道義とは出家した義満の法名です。明から国王としての返書を貰っていたのです。
時、義満の権力がいかに大きかったかがわかるエピソードです。
あの有名な金閣寺の造りにもメッセージが含まれていると囁かれています。金閣寺の造りは1階が公家の好んだ寝殿造り。2階が武家造り。3階が禅宗仏殿造りとなっています。これは、俺は公家よりも武士よりも天皇よりも偉いんだぞ!という義満のメッセージだともいわれます。
このように当時大きな権力を握っていた足利義満。1408年4月25日には、自身の息子の元服の儀を宮中で行うのですが、この時、「うんげん緑」といわれる天皇と上皇のみしか座ることを許されないといわれる畳を用意させ天皇、上皇と同じ作法で対面しました。いよいよ、息子を天皇にし、自身は上皇として君臨するという筋書き通りにことは進んでいくのです。
しかし、息子の元服の儀から2日後の4月27日。足利義満は、病に倒れ、5月6日には急死してしまいます。通説では、風邪をこじらせ急性肺炎になったといわれていますが、なにしろタイミングが良すぎる。
天皇家を守ろうと誰かが義満に毒を盛り暗殺したと言う方が納得がいくといったところです。
とはいえ、現在、足利義満が暗殺されたという証拠は出てきておりません。ただ、タイミングが良すぎるだろ!というだけです。外傷などもなく、4月27日から徐々に弱っていった様子も伺えることから暗殺であったとしたら毒殺という説が一般的です。
死後、足利義満は朝廷から太上法王の称号を送られますが、これは周りからの説得もあり息子の義持により辞退しております。ホント、もう一歩で天皇の位というところまできていたようですね。
+7
-0
-
1409. 匿名 2016/03/08(火) 12:05:39
弁慶って実在したの?
軍記物語の「義経記」では、準主役級の扱いを受け、現在でも人気の高い弁慶。しかし、この弁慶は本当に実在したのでしょうか?
伝えられるところでは、弁慶は紀伊熊野別当、湛増(たんぞう)が二位大納言の娘を強奪して産ませたのが弁慶だといいます。母の胎内に18ヶ月もとどまり、生まれた時にはすでに髪は肩まで伸び、歯も生えそろっていたそうです。
その後、弁慶は元服を迎える前に比叡山に預けられますが、乱暴がすぎて追い出されます。
そんな乱暴者の弁慶は、京で1000本の太刀を奪おうと悲願を立てて、道行く人を襲い999本まで集めます。そして、残りあと1本というところで京の五条大橋を笛を吹きながら歩いてきたのが牛若丸こと義経です。巨漢の弁慶は、牛若丸に襲い掛かりますが、牛若丸はひらりひらりと攻撃をかわし、弁慶を負かせてしまいます。そして、弁慶は牛若丸の家来となることを決意するのです。
弁慶は、義経の忠実な家来として活躍し、平家討伐でもその力を発揮。義経の兄、頼朝の怒りを買って義経一行が奥州へと逃げる際も大活躍をします。安宅の関所で義経の正体が見破られそうになるという大ピンチの時、弁慶は白紙の勧進帳を読み上げ見事そのピンチを乗り越えてみせるのです。力だけでなく、頭も切れたのですね。
そして、衣川の合戦にて、義経を守るために敵の矢を全身に受け、立ったまま息絶えたのが弁慶の最後だといわれます。
こられのエピソードは感動を呼び、義経同様に人気の高い弁慶ですが、なんだかフィクションぽいのも事実。本当に弁慶という人物はいたのでしょうか?
結論を言ってしまうと「いた」ようです。
歴史書の「吾妻鏡」に弁慶の名前は2ヶ所でてきます。都落ちする義経一行の中には確かに「弁慶法師」の名前が出てきますし、また別の箇所にも「武蔵坊弁慶」の名がでてきます。
弁慶にまつわる多くのエピソードは、「義経記」を元にされたもので、史料としての信憑性は低いというのが定説ですが、エピソードがどこまで本当だったのかはさておき、弁慶という人物は間違いなく実在したようです。
+8
-0
-
1410. 匿名 2016/03/08(火) 12:15:47
>>1406ご心配おかけしました。ごめんなさい
そうですね…H・G・ウェルズが1930年に予言したとされる「世界はこうなる」の和訳本出版の際、「日本人は知らない方がいい」という言葉は「髪の毛座」の事(広島・長崎)の事を言っていたのかもしれません(この予言の事はよく知りませんがσ(^_^;)
過去に氷河期があったことは事実で、私達は生き延びる努力をする権利があるのです。これは個人の力ではどうにもならない事で、当然シェルターの切符を奪い合う争いが起きます
日本人の中にも(上層部)シェルターに入る人はいるでしょう。でもシェルターでは和を重んじ、争うことのない心優しい人(或いは個人を超えた視点を持つ人)でなければ人類を未来に繋げる事はできないと思います
しかしシェルターに入れなかった組も負けてはいませんよ
だってシュメール神話には『神と猿の遺伝子をかけあわせた』としていますから…賢い人類は生き延びるでしょう…争わず、奪わず、助け合い、なんとしても生き延びましょうね!
妄想ですが…ね(^^)+9
-0
-
1411. 匿名 2016/03/08(火) 12:53:24
>>1410
お互いを尊重するのは大事ですよね。
今の世界情勢を見ると悲しくなりますが・・・。
素晴らしい未来が有るといいですね(^^♪+7
-1
-
1412. 匿名 2016/03/08(火) 14:52:21
源頼朝や平清盛。
姓と名前の間につく「の」って何の意味が?
源頼朝や平清盛、また藤原道長など姓と名前の間に「の」が付く人と足利尊氏や織田信長、徳川家康のように「の」が付かない人との違いは何でしょう?
簡単に言ってしまうと源や平、藤原のように「の」が付くものは天皇から与えられた「氏(うじ)」といわれる公式なもので、「の」が付かないものは自分が支配していた領地や地名などからとった日常的に使う「苗字」です。
つまり、源頼朝なら「天皇から授かった源の血筋を引く頼朝です」という意味。
徳川家康も源氏の流れを汲んでいることになっていますから、本当は「源朝臣(みなもとのあそん)徳川家康」です。
しかし、なぜ、源や平などの氏が使われなくなってきてしまったかというと、平安末期ごろでは同じ姓の人間が増えすぎて紛らわしくなってきてしまいます。「源さ~ん」って呼ぶと10人くらいが一斉にこっち向いちゃうような感じですかね?
また、武士の力も強くなり、天皇との主従関係も薄れてきたことから、平氏の中からは「織田」「北条」。源氏では「徳川」「足利」などの苗字を日常的には使う人が多くなってきた訳です。
ですから、徳川家康も公式の場では「源朝臣(みなもとのあそん)家康」とちゃんと「氏」を入れてサインしています。
しかし例外もあり。豊臣秀吉(とよとみひでよし)。この豊臣は本来、天皇から与えられた氏なので「とよとみのひでよし」というのが正しいはずなのですが、時代的に徳川家康や織田信長などすでに「氏」での呼び名が薄れてきてしまっていた為に「とよとみひでよし」と「の」を省いて読むのが一般的です。+6
-0
-
1413. 匿名 2016/03/08(火) 14:54:15
初めて切腹した人ってだれ?
初めて切腹した人物でといわれているのは、988年に切腹した藤原保輔(やすすけ)という人物だといわれています。彼は、事件を起して捕まり自分の腹を切り裂いて自殺したのですが、それが歴史上初めての切腹だといわれます。
そして、腹を十字に裂いて、古典的な形式である切腹をして見せたのが、「義経記」に残る佐藤忠信の壮絶な最後です。このホームページはお子様も見ている可能性があるので、これ以上書きませんが、そりゃもう壮絶だったそうです。
この佐藤忠信という人は、源義経(牛若丸)の家来でしたが、ついに義経も自害するときになり、どのような最後を見せればいいのか?と付き添いの人に聞いたところ、「佐藤忠信の死に様は、人々が褒めておりました。」と答えたことから義経もやはり切腹をして見せたといいます。
そして、この切腹という方法が武士における栄誉ある自害として定着していき、鎌倉時代では、武士の自害といえば切腹というのが当たり前になっていったようです。鎌倉幕府が滅亡した際、元執権の北条高時も切腹して最後を遂げましたからね。
さらに、豊臣(羽柴)秀吉により、切腹は進化していきました。秀吉が信長の家臣として中国地方への侵攻に出ていたころ、三木城攻め、鳥取城攻め、備中高松城の水攻めの際、秀吉は、城主が切腹すれば、兵の命は助けてやるというパターンを編み出します。これにより、切腹が単なる自害から責任をとるという方法へとかわっていきます。
江戸時代になると切腹は儀式化していきます。白い着物を着て、背後には刀を持った介錯人・・・。映画やドラマで出てくる”あれ”ですね。また法律でも切腹が刑罰のひとつとして定着していくことになるのです。+3
-0
-
1414. 匿名 2016/03/08(火) 18:23:38
武田信玄の死因はなんだったのか?
武田信玄といえば、甲斐の戦国武将であり、21歳の時に父親である信虎を追放し家督を相続。その後は、勢力を拡大しながらも志半ばで倒れ、その死は、3年もの間隠され続けたといいます。
その武田信玄の死因については、よくわかっていなく、いろいろな説があります。
鉄砲に撃たれて、それが原因で亡くなった。結核の病だったなどなど・・・。
近年、興味深い説として有力視されているのが、胃がん説です。
武田信玄の侍医である板坂法印(いたざか ほういん)という人が信玄の病は膈の病であるといっていてという記述が「甲陽軍艦」から見つかりました。
膈の病とは、胃や食道に食べ物が停滞して、むせる、吐くなどの症状が出るといいますので、胃がんであった可能性が高いというのです。
まぁ、同じような症状で胃がん以外も考えられるのでしょうが、少なくとも武田信玄の死因は、病気であったようです。
愛知県新城市、野田城近くには、信玄が狙撃されたとされる場所に石碑が立ち、看板も掲げられていますが、この信玄狙撃説創作の可能性が高いようですね。
甲斐の虎と恐れられた武田信玄は、1573年に亡くなり、敵に彼の死を知られるのを恐れ、3年もの間、その事実は隠され続けました。信玄の墓は甲府市岩窪町、また和歌山県高野山、愛知県福田寺などに存在します。
+4
-0
-
1415. 匿名 2016/03/08(火) 18:25:13
武田騎馬隊はポニーで戦っていた?
戦国最強とまでいわれた武田軍の騎馬隊。映画やドラマなどで見る武田騎馬隊のイメージでは、隊全員が馬にまたがり、華々しく活躍する画が浮かんできますが、実は、想像しているよりずっと小さな馬で戦っていました。
武田軍の乗っていた馬は木曽馬といわれる馬だということがわかっています。木曽馬の体高は130センチ~140センチほど。ちなみに、サラブレッドは150センチ~160センチ。ポニーとは体高147センチ以下の馬をいうらしいので、ポニーに乗って戦地に向かっていた訳ですね。映画などで描かれる大きな馬にまたがった集団とはかなり違ったイメージです。しかも、走る速さは、子供が走るのと同じぐらいだといいます。
実は武田騎馬隊というのは、武田軍の軍記「甲陽軍鑑」にも武田騎馬隊の記述は出てきません。たしかに、武田氏は、馬牧場を信州諏訪に所有していましたが、どうやら軍全員が馬で攻めるといったいわゆる武田騎馬隊の存在はなかったようです。
あくまで、馬と歩兵が一体となって攻めるといった一般的なスタイルを武田軍もとっていたようですね。
ちなみに、戦国最強の武田騎馬隊が壊滅したとされる長篠の戦。織田・徳川の連合軍は、馬防柵を全長2キロにもわたり作り上げ、繰り返される武田騎馬隊の攻撃を鉄砲隊によって退けたとされていますが、実際に主戦場となった地形をみると起伏があり、馬で攻めるにはちょっと不向き。また、武田軍の武将が亡くなった場所には石碑が建てられていますが、その石碑も馬防柵とはちょっと離れた場所に点々と残されています。騎馬隊が馬にまたがったまま、鉄砲隊によりその場に倒れていった訳ではなく、多くの武将たちは、鉄砲隊の前に負傷したところを追撃にあい殺された可能性が高いようですね。+5
-0
-
1416. 匿名 2016/03/08(火) 18:32:47
>>1410
>シェルターでは和を重んじ、争うことのない心優しい人(或いは個人を超えた視点を持つ人)でなければ人類を未来に繋げる事はできないと思います
↑おそらく選別する時が来るのでは…?
閻魔大王や『死者の書』に記されている事が起こるのでしょうか+8
-0
-
1417. 匿名 2016/03/08(火) 18:46:12
>>1416
『死者の書』
心臓(イブ)を天秤にかける死者の裁判の章は有名である。真理の女神マアトの羽根(真実の羽根)と死者の心臓がそれぞれ秤に乗っており、魂が罪で重いと傾くようになっている。秤の目盛りを見つめるのは冥界神アヌービスで、死者が真実を語れば死人はオシリスの治める死後の楽園アアルへ、嘘偽りであれば魂を喰らう幻獣アメミットに喰われ二度と転生できなくなる、とされる。
ですね。
ここでも天秤が出てくるのが気になりますね。
また幻獣アメミットは
頭は鰐、鬣と上半身が獅子、下半身は河馬のものになっているそうですね。
+5
-0
-
1418. 匿名 2016/03/08(火) 20:26:04
山本勘助は実在したの?
山本勘助といえば武田信玄の軍師として知られる人物ですが、その実像は謎だらけです。
実際、山本勘助は昭和に入るまでは架空の人物では?と考えられていました。そもそも、山本勘助は武田家の軍法などを記した「甲陽軍鑑」で重要な役目を果たしていますが、この史料の信憑性が疑わしいと考えられており、また山本勘助の名が武田信玄の家臣の中にない。
山本勘助は、「作り上げられた理想の軍師」といった見解が昭和に入るまで続いていました。
ところが、昭和44年、武田信玄が市河藤若に宛てた書状が見つかり、その中に「山本菅助」という名が出てきたのです。名前の漢字がちょっと違うのですが、当時は漢字表記が現在ほど重視されていなかったので、それほど不自然でない。
これにより、山本勘助は実在した!と決定づけられます。
容貌は色黒であり、戦場で手足が不自由になったという山本勘助。その最後は、1561年の川中島の合戦だったといわれますが、生まれに関しては1493年、1506年などの説があります。
また、山本勘助は軍師として伝えられていますが、山本勘助が軍師だったとは「甲陽軍鑑」にも書かれていない。ただ、”軍配鍛錬の者”とあり、川中島の合戦では「啄木鳥の戦法」を進言したことから軍師だったのだろうと憶測できるというだけ。
歌舞伎などで山本勘助を軍師として演じているので、すっかり軍師として定着してしまっていますが、実際に軍師という立場にあったのか?そこは、諸説分かれる所です。
+3
-0
-
1419. 匿名 2016/03/08(火) 20:26:13
山本勘助は実在したの?
山本勘助といえば武田信玄の軍師として知られる人物ですが、その実像は謎だらけです。
実際、山本勘助は昭和に入るまでは架空の人物では?と考えられていました。そもそも、山本勘助は武田家の軍法などを記した「甲陽軍鑑」で重要な役目を果たしていますが、この史料の信憑性が疑わしいと考えられており、また山本勘助の名が武田信玄の家臣の中にない。
山本勘助は、「作り上げられた理想の軍師」といった見解が昭和に入るまで続いていました。
ところが、昭和44年、武田信玄が市河藤若に宛てた書状が見つかり、その中に「山本菅助」という名が出てきたのです。名前の漢字がちょっと違うのですが、当時は漢字表記が現在ほど重視されていなかったので、それほど不自然でない。
これにより、山本勘助は実在した!と決定づけられます。
容貌は色黒であり、戦場で手足が不自由になったという山本勘助。その最後は、1561年の川中島の合戦だったといわれますが、生まれに関しては1493年、1506年などの説があります。
また、山本勘助は軍師として伝えられていますが、山本勘助が軍師だったとは「甲陽軍鑑」にも書かれていない。ただ、”軍配鍛錬の者”とあり、川中島の合戦では「啄木鳥の戦法」を進言したことから軍師だったのだろうと憶測できるというだけ。
歌舞伎などで山本勘助を軍師として演じているので、すっかり軍師として定着してしまっていますが、実際に軍師という立場にあったのか?そこは、諸説分かれる所です。
+1
-1
-
1420. 匿名 2016/03/08(火) 20:30:44
2回投稿してしまいました・・・
戦国時代、遺体の処理はどうしていたのか?
戦国時代は、基本的には戦場において、戦死者がでた場合は、上官がその遺体を回収し、費用は主家が負担し葬るというのが理想とされていました。
しかし、現実的に、そうすることはなかなか難しかったようです。
大阪冬の陣・夏の陣では、家康からの許可を貰い受け、大阪の富豪が戦場の後片付けをかってでています。これは、死体の処理をする代わりに、武具や武器をこっそり貰うよ。と、いう暗黙の了解があったようです。
小さな合戦では、戦国の武士道にならい遺体を回収し手厚く葬るということもあったようですが、大きな合戦になると武器や武具を貰う代わりに遺体を処理するといった現在で言う業者のような手が入ることが多かったと思われます。
合戦場となった付近の僧侶や農民が遺体の埋葬することもありました。その際も武具や武器の剥ぎ取りなどがなかったということはないでしょう。
城下周辺の合戦では、遺体はしっかり埋葬されることが多かったようですが、山野での戦となると遺体から衣類や武器は剥ぎ取られ、そのまま放置されることも少なくなかったようです。
+2
-0
-
1421. 匿名 2016/03/08(火) 21:43:49
ねずみ小僧は実在した?
大名屋敷に盗みに入り、その奪った金を貧しい人に分け与えたとされる「ねずみ小僧」。
このねずみ小僧は、江戸時代の後半に実在した人物で名前を次郎吉といいます。
ねずみ小僧が盗みに入った武家屋敷は71ヶ所。そのうち大名屋敷は21ヶ所。盗んだ金の総額は1万2000両だといいます。
ぬずみ小僧は、本当に盗んだ金を貧しい人々に分け与えたのか?
捕まったねずみ小僧こと次郎吉の取調べに当たった町奉行、榊原主計頭(かしわばら かずえのかみ)が「盗んだ大金はどうした?」と聞いたところ次郎吉は「すべて、ギャンブルで消えた」と答えたそうです。
つまり、盗んだお金を貧しい人々に分け与えたというのは、フィクッションで実際は、自身の遊びの為に大金を使ってしまった訳ですね。
では、どうしてねずみ小僧をヒーローのように扱うようになったかというと。
実際、ねずみ小僧は、大名や武家屋敷ばかりを狙って盗みに入っていました。これは、商人の家では警備が厳重である反面、武家屋敷ではいったん入ってしまうと警備があまく盗みに入りやすかったからだといいます。
武家屋敷では、あまり警備を厳重にしてしまうと、幕府に謀反の疑いをかけられかねないなどの理由があり、また盗まれたのを気付いても大名には面子があり、おおやけにはできなかったなどの原因があげられるようです。
このように、武家屋敷や大名屋敷ばかりを狙って盗みに入るねずみ小僧を人々は、汚い金を溜め込んだ大名らの家に盗みに入り、その金を貧しい人々に配っているヒーローなのではないか?とねずみ小僧が捕まる9年ほど前から噂が流れていたといいます。実際は、ギャンブルに使っていたのですけどね。
それらの噂を元に歌舞伎などでもねずみ小僧が演じられるようになり、現在でも舞台やアニメ、映画などにねずみ小僧はヒーローとして取り上げられているのです。
+3
-0
-
1422. 匿名 2016/03/08(火) 22:22:26
>>1417素晴らしい!
>『死者の書』
心臓(イブ)を天秤にかける死者の裁判の章は有名である。真理の女神マアトの羽根(真実の羽根)と死者の心臓がそれぞれ秤に乗っており、魂が罪で重いと傾くようになっている。秤の目盛りを見つめるのは冥界神アヌービスで、死者が真実を語れば死人はオシリスの治める死後の楽園アアルへ、嘘偽りであれば魂を喰らう幻獣アメミットに喰われ二度と転生できなくなる、とされる。
また幻獣アメミットは
頭は鰐、鬣と上半身が獅子、下半身は河馬のものになっているそうですね。
↑
天秤座はフィジー共和国=裁判所
古代エジプトはオリオン座の三ツ星とその南側をサフと呼び、「オシリス」と同一視した。古代メソポタミアのシュメール人はより広い(現在のオリオン座に近い)星々を「アヌの真の羊飼い」と呼んだ。
天地図では中部アフリカのヴィクトリア湖とその南側(タンザニア)=楽園アアル=天国
さらに「カバ座」もあります。「りゅう座」付近にあるとされる、このカバの姿をした神は「トゥエリス女神」。ロシア→アラスカ・カナダに渡っている=幻獣アメミットに喰われ二度と転生できなくなる=地獄
気になったのは、ナイル川の増水期に供え物をトゥエリス女神に捧げる習わし(1961年にアスワンハイダムが完成するまで続いた)です。真の供え物はアラスカ方面に行く人間だったのでは…?
この土地がグリーンランドに近いことも気になります。イエス様が飼い葉桶(プレセペ星団のこと:中国では積上げられた死体の中という意味)で眠っている…もしかしたらシェルターだと思っていたのは、原油製造装置だったとか?原材料は人間…おそろしや…
※日本国の原油の消費量を死体数で換算してみると、1人当たりひと月で9.7人分の死体の原油を消費していることになります
↓![世界を「数字」で回してみよう(12) 環境問題:石油は本当に枯渇するのか? (3/5) - EE Times Japan]() 世界を「数字」で回してみよう(12) 環境問題:石油は本当に枯渇するのか? (3/5) - EE Times Japaneetimes.jp
世界を「数字」で回してみよう(12) 環境問題:石油は本当に枯渇するのか? (3/5) - EE Times Japaneetimes.jpあと10年、あるいは条件によってはあと5年で石油は枯渇する――。そのようなデータが飛び交っていますが、果たしてこれは本当なのでしょうか。今回は、筆者が常々疑問に思っていた、「石油は本当に枯渇するのか」について数字を回してみようと思います。
+5
-0
-
1423. 匿名 2016/03/08(火) 22:53:36
>>1422
なんだか色々繋がってきますね。
怖くなってきます。
原油ですか・・・。
そうですね。
原油も良く判らないみたいですね。
原油が出来るもっとも有力なものが、植物プランクトンなどの死骸が海底や湖底に沈み細菌によって分解されて腐敗植物となり、地殻変動で地下深くに埋没し高い地熱と圧力を加えれて原油に変化する、という説。
一般的に広く知られています。
ただこれが正しければ、産地によって成分の変化が起きてもいいものですが、世界中どこで採れる石油も成分が同じなのです。
不思議ですよね・・・。+6
-0
-
1424. 匿名 2016/03/09(水) 01:04:22
>>1423
本当に怖いです(>ω<)
そういえば、獅子時代とか乙女時代とかの星座時代は必ず午年(うま年:日本の十二支)で始まり、巳年(へび年)で終わるのです。水瓶時代は1990年に始まり、午年です(前年は巳年です)
世界の終末を告げるのは”馬”でしたよね…
北欧神話も見直す必要がありそうです
”ラグナロク”と呼ばれる世界の終わりの日や、”ユグドラシル”、”アースガルズ”、アース神族が重要な問題や会議があるとそこに集う”イザヴェルと呼ばれる平原”(出雲?)。ニヴルヘイムへ落下したという”イズン”という女神。もっと調べたら真実に辿り着くと思います
次回の課題になるかもしれませんが…
やはり神話が重要な情報源です>>1423さんの原点ですね(^^)
おやすみなさい+7
-0
-
1425. 匿名 2016/03/09(水) 02:25:25
>>1424
”ラグナロク”ですか。「神々の黄昏」ですね。
では長いですが・・・。
『新エッダ』より
『新エッダ』第一部『ギュルヴィたぶらかし』第51-53章によれば、ラグナロクが起こる前にまず風の冬、剣の冬、狼の冬と呼ばれるフィンブルヴェト(恐ろしい冬、大いなる冬の意)が始まります。夏は訪れず厳しい冬が3度続き、人々のモラルは崩れ去り、生き物は死に絶えます。
太陽と月がフェンリル(狼の姿をした巨大な怪物)の子であるスコルとハティに飲み込まれ、星々が天から落ちる。大地と山が震え、木々は根こそぎ倒れ、山は崩れ、あらゆる命が巻き込まれ、あらゆる命が消えてしまいます。ヘイムダル(北欧神話の光の神。「白いアース」とも呼ばれる)は、世界の終焉を告げる為に角笛ギャラルホルン(アースガルズの門番であるヘイムダルが持つ角笛で、ラグナロクの到来を告げるという)を預けているミーミルの泉へ向かいます。最高神オーディンはミーミルの元へ駆けつけ、助言を受けます。
この日には全ての封印、足枷と縛めは消し飛び、束縛されていたロキ(悪戯好きの神。その名は「閉ざす者」、「終わらせる者」の意)やフェンリル、ガルム(北欧神話に登場する番犬)などがアースガルズ(アース神族の王国)に攻め込む。巨蛇ヨルムンガンドが大量の海水とともに陸に進む。その高潮の中にナグルファル(巨大な船。ムスペルが所有する)が浮かぶ。舵をとるのは巨人フリュムである。ムスペルヘイム(世界の南の果てにある灼熱の国)のスルト(北欧神話に登場する巨人。名前は「黒」または「黒い者」)が炎の剣を持って進む。前後が炎に包まれた彼にムスペル(巨人の一族である。 南にある火の国「ムスペル」に住んでいるとされる)の子らが馬で続く。ビフレスト(神々が地上からアースガルズへとかけた虹の橋)は彼らの進軍に耐えられず崩壊します。
神々と死せる戦士たち(エインヘリャル)の軍は皆甲冑に身を固め、巨人の軍勢と、ヴィーグリーズ(神々と巨人との最終決戦(ラグナロク)が行われる場所とされている)の野で激突する。オーディンはフェンリルに立ち向かうもののフェンリルに飲まれて死ぬ。オーディンの息子ヴィーザル(北欧神話の神の一人。その名は「森」、あるいは「広い場所」)が、フェンリルの下顎に足をかけ、手で上顎を押さえてその体を切り裂き、父の仇を討つ。トール(神々の敵である巨人と対決する戦神「雷神・農耕神」)はヨルムンガンドと戦い、ミョルニル(神トールが持つ鎚(ウォーハンマー))で殴りつけて倒すが、毒を喰らい相打ちに終わります。テュール(軍神。勇敢な神とされる)はガルムと戦うが相打ち。ロキとヘイムダルも相打ちに倒れる。フレイ(フレイヤの双子の兄。 神々の中で最も美しい眉目秀麗な豊穣の神)はスルト(ムスペルヘイムの入り口を守る炎の巨人)と戦い善戦するも武器を持っていなかったため打ち倒される。
スルトの放った炎が世界を焼き尽くし、九つの世界は海中に没します。闘いの後、大地は水中から蘇りバルドル(北欧神話の光の神)、ヘズ(盲目の神。バルドルの弟で、オーディンの息子)は死者の国より復活する。オーディンの子ヴィーザル()、ヴァーリ(司法神の一人)、トールの子モージ、マグニ、さらにヘーニル(アース神族の一人である。その名前は「番人」「射手」)らも生き残り、新たな時代の神となる。彼らはかつてアースガルズのあったイザヴェル(アースガルズがつくられる神話上の場所)で暮らします。
天にあるギムレー(「火に対して保護された場所」の意味)という、太陽より美しく黄金より見事な広間には、天地を滅亡させる炎も届かない。ここに、永遠に、善良で正しい人が住むのである。さらに、ホッドミーミルの森(en)だけが焼け残り、そこで炎から逃れたリーヴとリーヴスラシル(ラグナロク(世界の破滅)の後、再び人類をふやすように定められた人間の男女。この二人がラグナロク後の世界の人類の祖となったとされる)という2人の人間が新しい世界で暮らしていくものとされている。ホッドミーミルの森とは世界樹ユグドラシル(世界を体現する巨大な木であり、九つの世界を内包する存在とされる)の別称であるとされる。太陽が狼に飲み込まれる前に産んでいた美しい娘が、母を継いでその軌道を巡り、新しい太陽となります。
+5
-0
-
1426. 匿名 2016/03/09(水) 03:59:41
続き
九つの世界
九つの世界(ここのつのせかい)は、北欧神話に登場する世界の総称で9つあり、3つの層に分かれていいます。第一層と第二層とは、虹の橋(ビフレスト)によって結ばれていいます。
ユグドラシル
ユグドラシル(世界を体現する巨大な木、世界樹)は、九つの世界に根を張り、3つの魔法の泉がある
ミーミルの泉(ミーミスブルン)・・・知恵と知識が隠されているとされており、賢い巨人ミーミルが所有している
ウルズの泉(ウルザブルン)・・・運命の女神、ノルンたち(ノルニル)の一柱で、三姉妹の長女ウルズ(「編む者」「織姫」を意味するが、のちに「運命」「宿命」「死」を意味する)に由来し、泉水は強力な浄化作用を持っている
フヴェルゲルミル・・・ニーズヘッグ(蛇、この蛇はラグナロクを生き延びるとされている。『巫女の予言』第66節に、終末の日に翼に死者を乗せて飛翔する黒き龍として登場する。)が棲んでいるとされる
第一層
アース神族(最高神オーディンを長とする神々の系統)の国アースガルズ
ヴァルハラ・・・主神オーディンの宮殿。古ノルド語ではヴァルホル(Valhöll、戦死者の館)
妖精の国アルフヘイム
ヴァン神族(一群の神々である。その名前は「光り輝く者」を意味する。豊穣と平和をつかさどる。ニョルズ、フレイ、フレイヤが所属していた神族である。)の国ヴァナヘイム
第二層
小人(ドワーフ)の国ニダヴェリール
黒い妖精の国スヴァルトアールヴヘイム
人間の国ミズガルズ
巨人の国ヨトゥンヘイム ウートガルズ・・・「ヨトゥン」と呼ばれる霜の巨人族と丘の巨人族が住む国
ウートガルズ・・・ヨトゥンヘイム(巨人の国)にある都市。ウートガルザ・ロキが治めている。
ガストロープニル・・・ヨトゥンヘイムの砦、その城門はギフとゲリという番犬が守っている。
スリュムヘイム・・・巨人スィアチの館である。その名前は「轟く家」("crash-home")、「雷の鳴る家」("Thunder Home")、「騒がしい家」("noisy-home")を意味する。
第三層
氷の国ニヴルヘイム ・・・ロキの娘ヘル(老衰、疾病による死者の国を支配する女神)が投げ込まれた場所
ギンヌンガガプ(ニヴルヘイムとムスペルヘイムを分ける亀裂)
死の国ヘルヘイム・・・ロキの娘・ヘルが治め、ユグドラシルの地下にあるといわれる死者の国
炎の国ムスペルヘイム・・・世界の南の果てにある灼熱の国、ムスペルと呼ばれる巨人が住み、スルトという巨人が入り口を守っている
ギンヌンガガプ
となっているそうです。+4
-0
-
1427. 匿名 2016/03/09(水) 08:09:55
参勤交代の目的は大名の財力を減らすことではなかった!
3代将軍・家光が1635年に発した武家諸法度において制度化された参勤交代。かつては、この参勤交代における幕府の目的は「大名の財力を減らすこと」とされていましたが、現在、多くの歴史研究家の方の認識はちょっとこれとは違うようです。
家光の時に発せられた武家諸法度(寛永令)を見てみますと、
「従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。」
と書かれています。これは、「最近では従者の数が多くなり、出費がかさみ領地や領民の負担となっている。今後は、ふさわしい人数に減らしなさい」ということです。
参勤交代は、実は制度化される以前から将軍に対する礼儀として大名達は行っていたんです。それが制度化されたのが1635年の武家諸法度から。
その武家諸法度では、参勤交代について”人数をふさわしい数に減らしなさい”と記しています。
大名の財力を減らすことが目的であったのならば、参勤する人数を減らしなさいとは書きませんね。
つまり、参勤交代は結果として大名の財力を減らすことになりましたが、それが目的とするのは間違えというのが現在の考え方です。
参勤交代の目的は、将軍と大名との「主従関係の維持」と考えるのが正解でしょう。
+3
-0
-
1428. 匿名 2016/03/09(水) 08:13:31
日本刀の切れ味・一本の刀でどれくらいの人が斬れた?
時代劇では、日本刀を片手にバッタバッタと悪人を斬り捨てていくシーンが最大の見せ場ですね。しかし、日本刀って本当にそんなに人が斬れるものなのでしょうか?刃こぼれとかしないのでしょうか?
幕末に刀の試し切り役で死刑執行人も兼ねていた山田浅右衛門という人物が、一本の刀で何人くらいの斬れるかという記録を残しています。
ちょっと、恐ろしいですが、これによると有名な職人の作った名刀ならば13人。
まぁ、実戦では、当然、刀と刀がぶつかり合ったり、甲冑に当たったりする訳ですから、すぐに刃こぼれしてしまう場合も多いでしょうから、もっと数字は少なくなるかもしれません。
人によっては、日本刀は2~3人も斬れば刃こぼれして、使い物にならなくなるといいます。
しかし、山田浅右衛門が残した記録は首を斬っての数字。太い骨の部分を斬って13人ということであれば、戦闘のプロである武士なら骨まで斬るようなことはしないでしょう。刀の性能を熟知し、刀の消耗が最小限で抑えられる斬り方をしていたはず。また、人を斬ると脂身や血で斬れなくなるといわれていますが、これもある程度高級な日本刀ならば、そのようなこともないそうです。なれば、2~3人というのは、ちょっと少ない。一流の剣士であれば10人ほどは斬り倒すことができたと推測できます。
+3
-0
-
1429. 匿名 2016/03/09(水) 08:16:58
老将・鬼庭良直(おにわよしなお)
主君を守るため、73歳という老体に鞭打って戦場に出た老将、鬼庭良直。この鬼庭良直は、高齢で重い甲冑など身に着けることが出来なかった為に水色の法被に黄色の綿帽子を被って出陣したといいます。もはや、死など微塵も恐れず、死に場所を戦場でと決めた男の中の男!!!
鬼庭良直は、伊達政宗の父、輝宗に仕えておりました。その輝宗が、二本松城主・畠山義継(はたけやまよしつぐ)に殺害されてしまいます。父の仇と立ち上がった政宗。鬼庭良直は、この時すでに隠居していましたが、世話になった輝宗の仇討ちとあらば・・・と、73歳という高齢にも関わらず、刀をとることを決意します。
とはいえ、二本松城も守りは堅く、そうそう落とすことはできません。そんなこんなをしている内に二本松城を支援するために連合軍が結成され3万もの大軍で攻めてきます。ちなみに、政宗軍の兵は7000ほど。4倍以上の兵力です。
鬼庭良直は、政宗より授かった金色の采配を手に60騎の兵を引きつれ勇敢に戦います。そして、敵兵を200余りも討ち取り、最後は戦場にて壮絶な最後を迎えることになりました。
齢70を過ぎて、伊達家のために戦地に赴いた鬼庭。その功績をたたえ、政宗は良直の妻に隠居領分の知行を与えたといいます。
+4
-0
-
1430. 匿名 2016/03/09(水) 10:03:47
>>1426
うん、わかりません(^^;)
星と関連付けたらわかるかもしれません…そういえば、北欧神話には”セイズ”なるものが出てきます
「セイズ( seiðr )」の語源は不明である。
古代北欧の文献や魔法に関する伝承では、誘引の紐の使用がセイズに関わりがあると示唆されており、それによれば誘引は、セイズの施術の要素の1つである。 しかし、もしセイズが「糸巻の護符」に関連するのなら、亜麻や羊毛を紡ぐ際に使う道具である糸巻棒が、セイズの術に関連すると思われることの説明になる。
↑「糸巻の護符」…マリアの輪子ならば聖書(星座)に関わる
さまざまな学者がセイズについて検証し、そのうちの幾人かは、術者による幻想的な旅という文脈から、セイズとはシャーマニズムであると主張したとされます。…だけど、日本人なら星図を連想しますよね。どうやら天地図と関係ありますね。
(私事ですが、輪鼓(糸巻き)の家紋を持つ私は運命を感じます。ちなみに御船千鶴子は輪鼓紋です…さらにもう一つの家紋は茗荷紋―出口王仁三郎と同じでした…やっぱりそっち系かもしれません)
紀元前の北欧神話でセイズは、オーディンとフレイアの両神に関係があった。 オーディンは戦争と詩文と魔術の神であり、フレイアはヴァン神族の一人で、アース神族にセイズの慣習を教えたと信じられている。
北欧神話は星座との関連が薄そうなので、別の切り口を見つけないと…宿題ですね!
私は昨日の原油製造器の衝撃が抜けません(;ω;)
エジプトやマヤでは死んだ王がカヌーに乗せられるのですが、その時の従者が「犬(犬頭の神)」「鳥(鳥頭の神)」「猿(猿頭の神)」(桃太郎伝説と同じ)。猿はトト神ですがデンデラ黄道帯で照らし合わせて調べようと思います。+6
-0
-
1431. 匿名 2016/03/09(水) 11:11:42
>>1430
中々それぞれの神話の真実を読み取るのは難しいですね・・・。
でもおぼろげながら関係が有りそうな気がします。
大変ですがお互い頑張りましょう(^^)/
+4
-0
-
1432. 匿名 2016/03/09(水) 13:44:42
>>1431
はい(^^)
幻獣アメミットをデンデラ黄道帯で確認したら、アラスカ・カナダではなかったです
竜座の反対側…つまりグリーンランド~アイスランド~スカンジナビア半島でした![歴史のミステリーを語ろう]()
+4
-0
-
1433. 匿名 2016/03/09(水) 13:48:59
>>1432ですが、画像が見えにくくてごめんなさい(・ω・;
これでどうかな?![歴史のミステリーを語ろう]()
+5
-0
-
1434. 匿名 2016/03/09(水) 14:38:34
>>1433
判りやすいですね。
ありがとうございます。
近くに気になる星座がありますね。
てんびん座(古代エジプトの『死者の書』(ペレト・エム・ヘルゥ)で死者の魂の善悪を判定する)
蟹座β星(かに座で最も明るい恒星。3.520等星。アラビア語で「終り」と言う意味を持つ)
双子座(弟がポリュデウケース兄はカストールポリュデウケースは神であり不死だったが、カストールは人間で、死ぬ運命にあった)
死の匂いがしますね・・・
+3
-0
-
1435. 匿名 2016/03/09(水) 15:56:14
影武者は実在したのか?
「影武者 徳川家康」隆慶一郎作の小説で有名な影武者。原哲夫さんの漫画でもお馴染みですね。
しかし、この影武者という役割は戦国時代に存在したのでしょうか?
実は、当時の資料や記録を見ても「影武者」という呼び名は出てきません。まぁ、影武者の存在が世間に知れれば、意味が無くなってしまいますから当たり前といえば当たり前ですね。
とはいえ、影武者のような働きをした人物は資料に残されています。
武田信玄の影武者です。信玄は、1573年に亡くなっていますが、遺言で「私が死んでも3年間は、その死を隠し通せ」といい残したといいます。信玄が死んだとわかれば、敵が一斉に攻めてくる恐れがあったからです。
とはいえ、3年もの長い間、信玄が顔を見せないとなれば、疑うものも出てきます。見舞いと称して北条氏政などは部下の者を信玄の下へ向かわせ様子を探らせもしました。そこで、影武者となったのが、信玄の弟である信綱。信玄のふりをしてやり過ごしたというエピソードが残っています。
この信綱の話が元になり、黒澤明監督は映画「影武者」を撮影したといわれています。
また、毛利元就の家臣、渡辺通という人も元就が身につけていた甲冑を身にまとい、身代わりになって亡くなったという話も残されています。写真がない当時では、武将といえど、顔はさほど知れわたっっておらず、甲冑さえ着てしまえばうまくだませたのでしょうね。+4
-0
-
1436. 匿名 2016/03/09(水) 15:58:45
元禄時代の財政再建政策
5代将軍綱吉の時代。幕府は、10万両もの赤字を抱えていたといわれています。
これには、色々な複合的要因が考えられますが、その理由として綱吉をはじめ、大奥の女性達が当時は贅沢をしていた為と綱吉の母親、桂昌院が寺院の建立、再建などに財を惜しまなかったなどの理由があげられます。また、綱吉は将軍になる前から家人を幕府に入れていたため人件費が増加したこと、さらには幕府の安定期に入っていた元禄では、都市が発展し物価の上昇を引き起こしたことなども考えられます。
10万両もの赤字を抱え幕府も指をくわえてみていただけではなく、当然政策を打ち出します。
新しいお金を大量に作り出したのです。現在の日銀も同じようなことをしていますが、当時の政策はちょっと違います。
新しいお金には金や銀の純度を減らしたのです。つまり、金や銀の純度が高い古いお金を回収して、純度の低い新しいお金を出回らせた訳ですね。当然、幕府には純度の高い古いお金が集まり、金や銀が大量に手に入る仕組み!!!これにより、幕府に450万両あまりが手に入ったといわれます。
この政策を打ち出したのは萩原重秀(はぎわら しげひで)という人で後に勘定奉行に抜擢されています。
しかし、当時は富士山噴火などの災害などにより出費も多く、抜本的な財政復興とまではいかなかったようです。
+4
-0
-
1437. 匿名 2016/03/09(水) 16:18:23
>>1434
死の匂い…辛いですね
行き詰ったので、しばらく仕事しつつ瞑想します(・ω・;)
+5
-0
-
1438. 匿名 2016/03/09(水) 16:21:46
ゴルナヤ・ショリア遺跡
ロシア・シベリア南部の山岳地帯ゴルナヤ・ショリアは美しい山が連なっている穏やかな場所ですが、そこで発見された巨石遺跡は群を抜いた大きさなのです。
今まで過去最大と言われていた古代文化遺産はユネスコ登録されている「レバノンのバールベック」で、石の重量は推定800トンといわれています。
しかし、この「ゴルナヤ・ショリアで」1番大きいものはその3倍以上、つまり、2400トンくらいではないかといわれているのです。
ちなみにピラミッドの平均石重量は2.5トン、イギリスのストーンヘンジは50トンです。
謎は深まりますが、一番古い巨石で、1万年よりは新しいそうです。それでも紀元前3000年頃に始まったとされる古代エジプト文明よりも、遙か昔ということになります。
まだ発見されたばかりで調査は進んで無いようですが、一体だれが作ったのでしょうか?+5
-0
-
1439. 匿名 2016/03/09(水) 16:23:21
>>1437…の前に
インドのパタン郊外、北西部に位置する 7 層の壮大な階段井戸ラーニキ・ヴァヴ―別名女王の階段井戸。発見当時、大きさ、彫刻モチーフの出来、保存状態の美しさで人びとを驚かせました。2014年、グジャラート州パタンのラーニキ・ヴァヴ[女王の階段井戸]という名称で世界遺産に登録されました。
これ、気になります![歴史のミステリーを語ろう]()
+6
-0
-
1440. 匿名 2016/03/09(水) 16:48:07
>>1439
ラーニキ・ヴァヴ[女王の階段井戸]ですか。
これも気になる所がいっぱいですね。
ラニ・キ・ヴァヴにはヴィシュヌ神とその化身の姿の彫刻がたくさん施されているみたいですね。
このヴィシュヌ神は4本の腕を持ち、右にはチャクラム(円盤、あるいは輪状の投擲武器)と棍棒を、左にはパンチャジャナ(法螺貝)と蓮華を持つ男性の姿で表されるそうです。そのためチャトゥルブジャ(4つの武器を持つ者)という称号も持っています。
ヴァーハナ(乗り物)はガルダと呼ばれる鳥の王で、鷲のような姿をして描かれたり、鷲と人を合わせた様な姿で描かれるそうです。
タイの国章のガルダ
宇宙が出来る前にヴィシュヌは竜王アナンタの上に横になっており、ヴィシュヌのへそから、蓮の花が伸びて行きそこに創造神ブラフマーが生まれ、ブラフマーの額から破壊神シヴァが生まれたとされています。
そのヴィシュヌをたくさん彫刻しているなら重要な意味があるのでしょうね。+3
-0
-
1441. 匿名 2016/03/09(水) 17:27:33
>>1440
ありがとうございます(^^)
階段井戸はインドにたくさんあるみたいですね
これって、井戸にしては大きいし…怖くないですか?
インドは蟹座。プレセペ星団が(今回の?)飼い葉桶を意味しているから、もしかしたらここは…(汗)
今終末の飼い葉桶はこちらになります、みたいな気がしてなりません
( ・_・;)
生成期間も必要だから、数カ国が当番制で廻しそうです
ヴィシュヌが左手に持っている棒付の球体が天地球儀に思えてなりません。それに、ヘソや額から生まれるってクローンですよ、それは
えげつない話でごめんなさいm(_ _)m
インパクト大で頭から離れません+5
-0
-
1442. 匿名 2016/03/09(水) 18:31:18
>>1441
かなりこのラニキ・ヴァヴは不可解ですよね。
11世紀頃に王の追憶と名声のために造られたのに、1980年代後半に発見されるまで水没していました。
寺院としての役割も担っているはずなのに・・・。
隠さなければいけない理由でもあったのでしょうか?
深読みしてしまいますね。+4
-0
-
1443. 匿名 2016/03/09(水) 19:20:18
>>1441
りゅう座(トゥバン)で気になる事を発見したのでご報告を・・・
りゅう座α星…4等星であり最も明るい星ではないですが、紀元前2790年頃から、その前後数百年にわたって北極星の役割を果たしていた星で、 一説によるとその当時は、少なくとも現在の約2倍の光度(2等級)があったといわれています。
この恒星が第一星とされたのは、天文学の前身であり現在も使用されている占星術が成立したのが約5000年前のメソポタミアであることと関係があると思われます。
りゅう座に何か重要な事が隠されている気がして仕方ありません・・・。
また他の星も
りゅう座ζ星…アラビア語でハイエナという意味のアル・ディーバ(Al dhi'bah)という固有名を持つ。またこの星は青色巨星であり最期には超新星となり、中性子星やブラックホールを残すと考えられている。
りゅう座η星…アラビア語で「2匹のオオカミ」という意味のアルディバイン(Aldhibain)という固有名を持つ。
りゅう座ι星…アラビア語で「雄のハイエナ」を意味する al-dhīkh に由来する。
りゅう座χ星…バテンタバン・ボレアリスという固有名もあり、これはアラビア語の بطن الثعبان (baţn al-thubān, 竜の腹)に由来する。
りゅう座ψ星…アラビア語で「2匹のオオカミ」または「2匹のジャッカル」を意味するAdh-Dhi'banという言葉に由来する
気になる星だらけです。りゅう座+4
-0
-
1444. 匿名 2016/03/09(水) 21:36:59
日本を離れたフランシスコ・ザビエルのその後
フランシスコ・ザビエルは、日本に始めてキリスト教を伝えた人物ですが、彼がその後、どうなったのかは、あまり知られていません。
フランシスコ・ザビエルは、インドで布教していた際、アンジロー(ヤジロー)という日本人と出会いました。それがきっかけとなり1549年、アンジローの案内で日本の鹿児島についたフランシスコ・ザビエルは日本での布教を始めます。
ザビエルは、九州から大阪、京都にまで布教活動をこなし、2年3ヶ月の月日を経て、日本を去ることとなります。
日本を去ったザビエルは、ゴアに帰任しますが、今度は中国での布教に赴きます。そして、1552年12月3日、粗末な住居で布教に励んでいたザビエルは病死するのです。
彼の片腕は、ローマに送られ今も大切に保管されています。このザビエルの片腕は、戦後、日本でも公開されたことがあるとのことです。
ちなみに、このフランシスコ・ザビエルの肖像画。これは、フランシスコ・ザビエルを想像して後に書かれたものであり本当は、肖像画のような変な髪形じゃなかったんじゃないか?ともいわれています。もし、フッサフサだったら、カッパのような髪型で伝えられたザビエル。・・・ちょっと可愛そうですね。+6
-0
-
1445. 匿名 2016/03/09(水) 23:19:55
>>1443グッジョブです(^^)b参考になります
>>1442
ラニキ・ヴァヴがあるグジャラート州パタンは東経72度でした
インドという国は”72”という数字を重視しています。東経72度なのは偶然ではなく、そうなるように本初子午線を決めたのではないかと思ってしまう…だとすると世界的に重要な場所ということです。この遺跡はかなり重要だと思います+5
-0
-
1446. 匿名 2016/03/09(水) 23:42:03
>>1445
参考になって良かったです(^^)/
絶対隠さなければならない理由があったんでしょうね・・・。
+5
-0
-
1447. 匿名 2016/03/10(木) 08:56:49
赤穂浪士
赤穂浪士といえば、四十七士というのが一般的ですよね。討ち入りした浪士の数が47人だった為に映画や小説、漫画などでは四十七士が定説となっています。
しかし、実は、本当に47人だったのか?本当は46人だったのか?はっきりとしていないんです。
赤穂浪士が江戸郊外の吉良邸に討ち入りしたのは、元禄15年(1702年)の12月14日の深夜。ですから、かつては必ず年末になると赤穂浪士の討ち入りを描いたドラマ(忠臣蔵)がどこかの局で放送していました。
しかし、実際の赤穂浪士はドラマとは違い、バラバラの服装でバラバラに集まった後に表門と裏門に分かれて侵入しています。
この時の討ち入りが47人であったというのですが、これは竹田出雲によってかかれた『仮名手本忠臣蔵』が四十七士としていたから、その後の作品でも当たり前のように47人となってしまったのです。
しかし、出雲が四十七士としたのは、外題をつけるにあたって47人であれば「いろは」の47文字と同じなので「仮名手本」という外題をつけることができ、都合がよかったためといわれています。46人では、なかなかかっこいい外題が思いつかなかったんでしょうね。
とはいえ、46人の浪士ははっきりしていますので46人は間違いなく討ち入りしています。問題なのが47人目の寺坂吉右衛門(てらさか きちえもん)。
赤穂浪士は討ち入りを果たした後、現在の勝鬨橋(かちどきばし)あたりで勝どきをあげ、その後、浅野家(赤穂藩藩主、この人が吉良上野介といろいろあって自刃に追い込まれたため、仇討ち事件の始まりとなった)の菩提寺である泉岳寺(せんがくじ)に向かい、墓前に報告を済ませると浪士たちは自首しました。
しかし、寺坂吉右衛門は、泉岳寺に着くまでにはいなくなってしまっています。もし、討ち入り後に姿を消したのであれば、討ち入りは47人であったことになりますが、討ち入り前に逃げてしまっていたとすれば討ち入りは46人となります。
なぜ寺坂吉右衛門は姿を消したのか?最近では、討ち入り後に密命を受け姿を消した寺坂吉右衛門の姿を描いた作品なども制作されています。この人だけは、足軽の身分でしたからね。まぁ、皆と違って別の命を受けたとしてもありえない話ではありませんね。+4
-0
-
1448. 匿名 2016/03/10(木) 08:58:46
原爆の候補地の第一目標は京都だった!
太平洋戦争中、アメリカでは原爆をどこに落とすか?を決めるための会議が開かれます。この候補地として挙げられた第一目標が実は京都であったといわれています。
アメリカ軍としては、原爆の破壊力を見るには、100万以上の人口がおり、まだ本格的な爆撃を受けていない場所を探していたようです。しかも、京都には天皇の都。御所があり、ここに原爆を落とせば日本人に与える心理的ダメージは計り知れない。戦争を終わらせるためにはココしかないと軍部では訴えます。
しかし、この案は最終的に却下されることになります。
「天皇を神として崇拝している日本人にとって、ここに原爆を落としたならば日本人に遺恨の念を植え付け、戦後日本を占領する際にうまくいかなくなるどころか、アメリカよりもソ連になびく可能性がある。」と、考えられたようです。
よく、京都は重要文化財や寺院仏閣が多いから空爆を受けなかったといわれていますが、原爆の候補地に挙がったところをみると、そうとも言い切れないようです。また、歴史研究者の方の中には、原爆の候補地であったからこそ、空爆を避けてきていたと考える方もいます。+5
-0
-
1449. 匿名 2016/03/10(木) 10:34:49
一昨日のニュースで気になったのが、
「2016年3月6日、中国北京市門頭溝区の潭柘寺で「ネコ住職」の呼び名で親しまれたシロが亡くなった」
京華時報によると、シロをめぐっては、ネット上で、寺はお布施を入れる「功徳箱」を置くなど金もうけに利用する一方で十分に世話をしていなかったなどと批判の声が上がっていた…そんなニュースでしたけど、これって世界中に知らせるニュースでしょうか?
不審に思い少し調べてみると、中国の習近平国家主席の『白猫黒猫論』がありました
「白猫(韓国)であれ、黒猫(北朝鮮)であれ、ネズミを捕る(中国のいいなりになる)のが良いネコだ」
これにより、”白猫が死んだ”とは韓国が無くなったという事で、韓国が米側についたという事ではないかと思うのですが、どうでしょうか
それから、日本の十二支神話でネズミに騙されてネコは十二支に入れてもらえませんでしたよね
この十二支にまつわる話は、中国・モンゴル・中央アジア・ロシア周辺にも伝わっており、そのほとんどが「猫とねずみが敵対することになった十二支の話」か、「ねずみが牛にくっついて行って一番になる十二支の話」なのです。
この牛は、牛頭天皇…?
北欧神話に出てくるねずみはラタトスク(Ratatoskr、「走り回る出っ歯」の意)。世界樹ユグドラシルに住んでいるといわれる栗鼠(リスだったのね…)。ラタトスクはユグドラシルの梢に住んでいる鷲(フレースヴェルグ)と、根元に住んでいるニーズヘッグの間で交わされる会話を中継しており、この2匹の喧嘩を煽り立てている。あまりよく思われていませんね(汗
芋づる式に気になる事が出てきます
牛頭馬頭(ごずめず)とは、仏教において地獄にいるとされる亡者達を責め苛む獄卒で、牛の頭に体は人身の姿をした牛頭と、馬の頭に体は人身の姿をした馬頭をいう。牛頭馬頭という呼び方からわかるように、牛頭と馬頭はセットで語られることが多い。仏教の経典では『大仏頂首楞厳経』第8、『十王経』などにその語の使用例が確認でき、牛頭鬼馬頭鬼(ごずき-めずき)、牛頭獄卒馬頭羅刹(ごずごくそつ-めずらせつ)とも表記される。中国では牛頭馬面(ごず-ばめん)とも呼ばれており、地獄の様子を描写した民間の書籍や変文ではこちらも広く使われている。
日本でも地獄の登場する説話や、地獄の様子を描いた『六道輪廻図』、『六道道』、『十王図』、『地獄草紙』などの絵画にその姿が決まって描かれてもおり、馴染みも多い。
牛頭、馬頭の他にも、鹿、虎、獅子、猪といった動物の頭を持つ仲間も存在する。
↑
”六道輪廻”だとか”十王”が出てきてイスラエルを連想します
それに動物たちも神話と関連がありそうですよね+7
-0
-
1450. 匿名 2016/03/10(木) 11:15:10
>>1449
仏教は気になる事が多すぎますよね。
十二神将も干支ですもんね。
+4
-0
-
1451. 匿名 2016/03/10(木) 13:06:09
>>1449
、”白猫が死んだ”とは韓国が無くなったという事で、韓国が米側についたという事ではないかと思うのですが、どうでしょうか
そうですね。
在韓米軍との軍事演習の件では北朝鮮よりも中国の方が脅威ですしね。
特に中国が気にしているのは米軍による韓国の(THAADミサイル配備)でしょうね。
これは
THAADミサイル(終末高高度防衛ミサイル、英語: Terminal High Altitude Area Defense missile, サードミサイル)は、アメリカ陸軍が開発した弾道弾迎撃ミサイル・システム。当初は、戦域高高度防衛ミサイル(英語: Theater High Altitude Area Defense missile)と呼ばれていた。
これは北朝鮮というよりも中国の核に対するものと言われていて、中国としてはのど元にくさびを打たれる事になるので嫌がっているのでしょうね。+4
-0
-
1452. 匿名 2016/03/10(木) 13:46:48
>>1451
その通りですね…ってよく知らないけど言ってみる
(-ω-)フムフム
米vs中国…この対立の根源は何なのでしょう?
実は猫の親玉は米だったりして。13番目のユダ…+5
-0
-
1453. 匿名 2016/03/10(木) 14:46:25
>>1452
ありえますね・・・+3
-0
-
1454. 匿名 2016/03/10(木) 19:11:09
まんが日本昔話のエンディングに、特別な意味が込められてるという説が気になります。
![本当は怖い?『人間っていいな』に隠された裏の意味]() 本当は怖い?『人間っていいな』に隠された裏の意味on-linetrpgsite.sakura.ne.jp
本当は怖い?『人間っていいな』に隠された裏の意味on-linetrpgsite.sakura.ne.jpまんが日本昔ばなしの『にんげんっていいな』に隠された意味について、謎解きをします。その裏には、仁徳天皇条の『雁の卵の話』に関わる「後の雁が先になる」という言葉や、菟道稚郎子との話が浮かび上がります。そして、でんでんでんぐり返ってバイバイバイ・・・...
>このように考えて行くと、「人間っていいな」というタイトルの裏には、、、
>あなたが、獣と化すのなら、666でバイバイバイ。
>あ~、自分は獣じゃなくて、人間で良かった。。。
>・・・そう言う意味が隠されているんじゃないでしょうか?
アニメの製作者の中に、預言者のような人物がいたのでしょうか…?+7
-0
-
1455. 匿名 2016/03/10(木) 19:54:30
>>1454
深い意味があるのですね・・・。
江戸時代の天皇の生活って?
江戸時代の天皇は、どんな生活をしていたのでしょう?「禁中並公家諸法度」により江戸幕府からの支配を受けていたことは教科書で習っていますけど、大政奉還がもたらされるまでの間は、教科書に殆ど天皇の名は出てきませんよね。
江戸時代の天皇は、幕府から禁裏御料3万石を寄進されていました。ん?たった3万石・・・。少ない・・・。
そうなんですね。3万石じゃ、小大名クラスです。しか~し!天皇には、特権があったんですね。
普通、大名なら家臣に払う給料のほか、江戸への参勤交代やら自腹を切っての土木事業やらを行わなければならなかったんです。もう、それだけで財政はギリギリです。
ですが、天皇の臣下には、禁裏御料とは別にお給料が払われるので天皇はぜんぜん痛くない・・・。しかも、もちろん参勤交代もないし、大名のように幕府の命令で土木事業など行う必要もないんです。
もう、3万石はほとんど好きに使っていいんですね。
おぉ、江戸時代の天皇って大名に比べるとラッキーな生活してたんだねぇ。なんて、簡単に考えちゃダメですよ。天皇は国民のために祭事を行うという役目があります。江戸時代も現在も同じです。国民の生活を思いお祈りを捧げてくださっているんですよ。+5
-0
-
1456. 匿名 2016/03/10(木) 19:55:50
日本で最初のクリスマスっていつ?
本来、キリスト教国でもないのに、日本ではクリスマスを盛大に祝います。お寺のお坊さんですら、クリスマスはケーキを食べている人も多いのでは?まぁ、楽しいのでいいのですが、日本で最初のクリスマスっていつ行われたのでしょう?
それは、1552年にまでさかのぼります。
場所は、現在でいうと山口県。当時の山口地方は、キリシタン大名である大内義隆が治めており、キリスト教の布教が自由で非常に盛んでした。
この頃、すでにフランシスコ=ザビエルは日本を離れていましたが、後を継いだトルレスという人が山口や大分で布教活動に励んでおり、山口にて日本初の教会を建設することが許されていました。
この教会建設を記念して、山口にてクリスマスを祝う行事が行われたといいます。
その後、山口では、大内家が衰え、毛利元就が治めるようになってからは、キリスト教は衰えることになるのですが、日本で始めてのクリスマスは山口県からだったのですねぇ。+6
-0
-
1457. 匿名 2016/03/10(木) 19:58:57
炭酸飲料が日本に伝わったのは江戸時代!
皆さんがよく飲むでありましょう、炭酸飲料。実は、すでに江戸時代に炭酸飲料は日本に伝わっておりました。
1853年のこと。横須賀の浦賀にペリー率いる黒船が来航したのはご存知でしょう。
その時、ペリーが持参していたのが炭酸レモネード。
当時の日本人は、炭酸レモネードの栓を開けた際の「ポンッ」という音を銃の音と聞き間違い、びっくりして刀に手をかけたという話も残っています。
これが、日本における炭酸飲料の始まりといわれています。+5
-0
-
1458. 匿名 2016/03/10(木) 21:45:38
カルナック列石
カルナック列石は、フランス・ブルターニュ地方最大の巨石遺構で、巨大なメンヒルが総延長およそ4kmにわたり数列に並んでいる三つの列石群からなります。
紀元前5000年あるいは、紀元前3000年から紀元前2000年頃に造られたとされれますが、その目的は精霊や巨人が建てたとする伝説の他、戦士の墓、種族の記念碑、天文学上の目的等、あるいは生命の起源と関連付けたようなオカルト系学説など諸説があり、はっきりしていません。
スコットランドの巨石遺構研究者のアレクサンダー・トム(英語版)が提唱した古代の天文学装置であるとする説や、ヘルムート・トリブッチの提唱した蜃気楼の観測所であるとする説などが主流です。
カルナック列石に関連のあるとされる古墳が近辺に多く見られ、聖ミシェル古墳などが知られています。
+5
-0
-
1459. 匿名 2016/03/10(木) 22:30:47
妄想地図ができました(ー∀ー)=3![歴史のミステリーを語ろう]()
+8
-0
-
1460. 匿名 2016/03/10(木) 22:31:45
詳細1![歴史のミステリーを語ろう]()
+8
-0
-
1461. 匿名 2016/03/10(木) 22:32:19
詳細2![歴史のミステリーを語ろう]()
+8
-0
-
1462. 匿名 2016/03/10(木) 22:32:57
詳細3![歴史のミステリーを語ろう]()
+8
-0
-
1463. 匿名 2016/03/10(木) 22:33:37
詳細4![歴史のミステリーを語ろう]()
+8
-0
-
1464. 匿名 2016/03/10(木) 22:34:55
以上、妄想地図でした(^^)+7
-0
-
1465. 匿名 2016/03/10(木) 22:52:10
>>1464
素晴らしいです。
お疲れさまでした。
見るだけで妄想が広がりますね(^^)/
+6
-0
-
1466. 匿名 2016/03/10(木) 23:08:31
>>1465
ありがとうございます(^^)約束は守るのです
やはり南極が気になりますね…羅針盤・ポンプ・コンパス・定規・望遠鏡・顕微鏡・鳳凰などは最後に入れたのですが、新しい星座の中でもこれらは道しるべ的な存在で注目していただきたいです+7
-0
-
1467. 匿名 2016/03/10(木) 23:14:03
>>1466追加で、風鳥座も気になります。
南極中央は省略されているので見えにくいですが、孔雀の方を指し示しています+6
-0
-
1468. 匿名 2016/03/10(木) 23:41:40
>>1466
南極に有るアルゴ座(巨大な船)を「とも座」・「ほ座」・「りゅうこつ座」の3つ、あるいは「らしんばん座」を加えて4つに分割されていますね。
巨大な船・・・。
ノアの箱舟でしょうか?
特にりゅうこつ座はι星とε星を結ぶと十字架の形になるので、これらの星たちはみなみじゅうじ座と見誤りやすい。このためこの4星を「ニセ十字」と呼ぶそうです。
うーん。
気になります・・・。
+5
-0
-
1469. 匿名 2016/03/11(金) 00:28:42
>>1454「人間っていいな」…おもしろいですね
私も解釈が脳内スパークしたのですが、えげつないバージョンなので控えます(笑
獣の数字”666”ですが、算木で表すと Τ⊥Τ
合体させると”鳥居”になりますよね。”獣”といえば十二支…まさか?!
>>1468
アルゴ座はデンデラ黄道帯で牛が乗っていました
牛頭族に関係ありそうですよね
トピが閉じる日が近いので(12日夕方?)、寂しいです
おやすみなさい(--)Zzz+6
-0
-
1470. 匿名 2016/03/11(金) 02:26:04
もうすぐこのトピも終わってしまいますね(´・・`)すごく寂しいです
皆さん知識豊富で今まで見ておりましたが、少しずつですが勉強させていただいてました!遺跡、最座、神話、色々な関係などすごく興味深く、どこから勉強していいものか( ˙-˙ )歴史に疎いので次お会いできる時までに少しでも知識が増えてればと思います。とりあえず日本の事をしるのに古事記を読みましたが他わかりやすい資料さいとなど教えて頂きたいです(´・×・`)+9
-0
-
1471. 匿名 2016/03/11(金) 06:46:04
>>1469さん
妄想です(ついに名前になった!)
私は聖書も古事記も日本書紀も北欧神話も…何もかもまともに読んでおりません(^^;)
ただ、小説は読みます。ムーも少々…言われてみれば真面目に取り組んだほうが良いかもですね!
フィクションも捨てたもんじゃないですよ
「王様の耳はロバの耳」でもわかりますが、真実を伝えようとしている人がいるのです。裏に隠された共通の出来事を追えば、真実にたどり着くかもしれません。+6
-0
-
1472. 匿名 2016/03/11(金) 08:00:21
>>1471ですが、間違えてました(>>1469は自分のコメだし)
>>1470さん宛てのコメントです(^^;)+5
-1
-
1473. 匿名 2016/03/11(金) 08:18:02
>>1471
返信ありがとうございます*(^o^)/*裏に隠された共通の出来事!確かにそうですね(∩´∀`∩)私も童謡、昔話、小説なども見てみます!まだトピが続く限り色んな憶測など楽しみにしております!+5
-0
-
1474. 匿名 2016/03/11(金) 10:00:31
もう少しで終了ですが、ラストスパートで頑張りたいと思います。
みなさんと出会えた事が1番の宝物ですね。
西郷隆盛の銅像が連れている犬って?
明治31年、12月18日。上野山王台にすえられた西郷隆盛の銅像が初めてお披露目となりました。この銅像を制作したのは高村光雲という人。
しかし、高村光雲は困り果てます。西郷隆盛に関しては、まったく写真が残っていない。いったい、顔をどうすればいいのか?そこで、光雲は肖像画や西郷隆盛の弟を参考に苦心してイメージを膨らませます。
そして、現在のみなさんの知るあの西郷隆盛の顔が出来上がる訳です。しかし、銅像の除幕式に参列して西郷隆盛の奥さんは「うちの人はこんな顔じゃなかったですよ。」と不満の声を漏らしたというからあまり似ていなかったようです。
そして、西郷隆盛の銅像が連れている犬。これは、生前の西郷隆盛がウサギ狩りを好んでいたことにちなんでいます。
西郷隆盛は、ウサギ狩りの時に2.3匹の犬を連れ狩に出ていたといいます。その中でもメス犬の「ツン」という犬を可愛がっていたことから、あの西郷隆盛の銅像が連れている犬は「ツン」をモデルにしているといわれることも多いのですが、実はそうでもないようです。
当初、光雲が制作した犬の像は、耳が垂れていました。しかし、実際、西郷隆盛が連れていた犬は、耳がピンと立っていたという証言があり、その後、別の彫刻家がつくった犬と替えられています。しかし、「ツン」がメスだったのに対して、差し替えられた犬は「オス」。これまた、「ツン」とはかけ離れている・・・。
実際、西郷が可愛がっていた「ツン」をモデルに制作しようとしたのに史料不足でそうなってしまったのか?そもそも、別に「ツン」をモデルにして制作した訳ではないのか?その辺は分かりませんが、まぁ西郷隆盛の銅像がつれている犬は愛犬「ツン」とは違うものになってしまったようですね。西郷さん自身も顔ぜんぜん違うので合っているのはもはや名前だけ???
+10
-0
-
1475. 匿名 2016/03/11(金) 10:02:00
二宮金次郎(二宮尊徳)ってどんな人?
以前は、どこの小学校にでもあった二宮金次郎の銅像。現在では、「歩きながら本など読んだら危ないじゃないか!」といった話も出てきて、座りながら本を読む二宮金次郎の銅像なども登場しているそうです。もっともな、意見ですが、ちょっと残念な気もしますね。
この二宮金次郎って勤勉で有名ですが、どんな生涯を送っていたのでしょう。
二宮金次郎は1787年に現在の神奈川県の農家で生まれます。幼少時に川の氾濫により親の田畑が無くなってしまいます。その後、金次郎14歳の時に父親を失い、2年後には母親も死去。その後、金次郎は叔父の家で育ちます。
二宮金次郎は、夜に勉強するのは油の無駄だと叔父に怒られますが、それならばと自身で植えた菜種からとれる油で火を灯して勉強したといわれています。また、田植え後に落ちている稲を拾い集めて、自分の田に植え米を収穫したという逸話も残っています。
その後、二宮金次郎は、小田原藩の家老・服部家に奉公し、その子弟が通う学校にお供するのですが、そこでも金次郎は、中からもれてくる先生の授業に耳を傾け勉強しました。
そうして勉強を重ねた二宮金次郎は、奉公先の服部家の財政立て直しを頼まれ、見事成功!その才を認められた二宮金次郎は現在の栃木県各地でも所領の再建などを頼まれ成功させていきます。
この二宮金次郎の財政再建の方法は報徳仕法(ほうとくしほう)とよばれ、多くの賛同者が生まれました。
ちなみに二宮金次郎は子供時代の名前です。本来は、二宮金治郎というらしいのですが、二宮金次郎のほうが有名ですね。ちなみに、大人になってからは、二宮尊徳となりますが、この尊徳も「そんとく」という送り仮名が一般的ですが、本来は「たかのり」と読むそうです。
+8
-0
-
1476. 匿名 2016/03/11(金) 10:46:01
>>1470
歴史に興味を持って頂いて嬉しいです。
![日本神話の簡単な流れをまとめました | 知っているようで知らない日本書紀・古事記を紐解こう]()
日本神話の簡単な流れをまとめました というサイトに判り易く書かれていますのでのぞかれてはいかがでしょうか。+9
-0
-
1477. 匿名 2016/03/11(金) 10:50:15
>>1474
皆さんと出会えたことが宝物(´;ω;`)素敵ですね!いつも沢山の投稿ありがとうございます!ラストスパート最後まで楽しみに見ております!
イルミナティトピが無くなった時も寂しかったですがこのトピも終わるのが寂しい(´・・`)また次もどこかで会えるといいです
+11
-0
-
1478. 匿名 2016/03/11(金) 10:51:39
>>1476
わざわざサイトの貼り付けありがとうございます!少しずつでも知識を増やしていきます!+7
-0
-
1479. 匿名 2016/03/11(金) 11:28:12
七つの大罪
七つの大罪(ななつのだいざい、ラテン語: Septem peccata mortalia、英: Seven deadly sins)は、キリスト教の西方教会、おもにカトリック教会における用語。ラテン語や英語での意味は「七つの死に至る罪」ですが、「罪」そのものというよりは、人間を罪に導く可能性があると見做されてきた欲望や感情のことを指すもので、日本のカトリック教会では七つの罪源(ななつのざいげん)と訳しています。
七つの大罪とそれに比肩する悪魔と動物
大罪 対応悪魔 動物
傲慢(高慢) ルシファー(ベリアルとする説がある) グリフォン、ライオン、孔雀、蝙蝠
憤怒(激情) サタン ユニコーン、ドラゴン、狼、猿
嫉妬(羨望) レヴィアタン マーメイド、蛇、犬、猫
怠惰(堕落) ベルフェゴール(アスタロスとする説がある) フェニックス、熊、牛、驢馬
強欲(貪欲) マモン ゴブリン、狐、針鼠、烏
暴食(大食) ベルゼブブ ケルベロス、豚、虎、蝿
色欲(肉欲) アスモデウス サキュバス、山羊、蠍、兎
これに対する形で7大天使がいます。
ミカエル
ガブリエル
ラファエル
ウリエル
等の四大天使(ウリエルについては異動もある)に三体の天使を加えたものが基本で、その三天使は教派や聖典ごとに異なります。
『エノク書』 - ラグエル、ゼラキエル、レミエル
『ディオニュシオス文書』 - カマエル、ヨフィエル、ザドキエル
教皇グレゴリウス1世時代のカトリック教会 - サマエル、オリフィエル、ザカリエル(※さらにウリエルがアナエルと入れ替わることがある)
東方正教会 - セラフィエル、イェグディエル、バラキエル(※さらに「イェレミエル」(ウリエルと同体とされることもある)を加えて八大天使とすることもある)
コプト正教会 - スリエル、サラティエル、ザダキエル(※さらにウリエルがアニエルと入れ替わる)
その他の聖典などではメタトロン、サンダルフォン、ラジエルといった全く別の天使が入ることもあります。
7つの大罪における動物と星座の関連が有るような気がします。+6
-0
-
1480. 匿名 2016/03/11(金) 13:01:30
孔子の身長は2m以上もあった?
中華戦国時代の前夜に活躍した孔子(前551頃~前479年)の身長は「九尺六寸」。時代により、尺の長さは変わるので正確な寸法は出せませんが1尺を22.5cmと換算すると、およそ2m16cm!元横綱の曙さんが2m3cmですし、ジャイアント馬場さんだって2m9cmなのでそれより大きいということになる!
また、外見については、上半身が長く、下半身が短い・・・。背中が曲がり、耳は後ろの方についていた、などの記述が残っております。
当時の中国での男子平均身長は七尺ほど(154~160センチほど)だったといいますので平均より背が高かったことは間違いないでしょうが、史記により伝えられている九尺六寸というのは、少し大げさでしょうね。
+8
-0
-
1481. 匿名 2016/03/11(金) 13:04:00
シルクロードはいつ作られた?
シルクロードといわれ、始めに頭に思い浮かぶのが「西遊記」という人も多いことでしょう。その「西遊記」に登場する三蔵法師にはモデルになった人がいました。玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)という人です。この玄奘三蔵というお坊さんは、629年にインドへ向かい、645年にインドから中国へと戻ってきました。「西遊記」では、その旅をモデルにお話を作られています。その旅をした道がシルクロード。
では、この玄奘三蔵が活躍した時代がシルクロードの成立の時代かというとそうではありません。
ちょっと、話がずれますが、「シルクロード」と命名されたのは、19世紀の末、ドイツの地理学者リヒトホーフェンが発表した「中国」全5巻の中で中国とヨーロッパを繋ぐ中央アジアの道をシルクロードと名づけたのが始まりだと言われています。
話を元に戻して、シルクロードの成立の時期ですが、紀元前139年に前漢の武帝は、北方の遊牧民に対抗するため、張騫を西方の大月氏のもとに使いを出したとされています。これにより、前漢の使者が現在のアフガニスタンにあった大月氏国に行ったことが分かります。これにより、それまで未知であった西の情報が東に伝えられ大規模な国交が始まりシルクロードの開拓が本格化されていったといわれています。
しかし、その時代がシルクロードの始まりかといわれると・・・。別の資料からは、紀元前1000年ごろには、すでに中央アジアに遊牧民が広がっていたことから、彼らは長距離の交易を行っていたこともわかっており、この頃、どのくらいの規模かは不明ですが、すでにシルクロードの元になる道は出来ていたのではないか?と予測もできます。
+6
-0
-
1482. 匿名 2016/03/11(金) 13:07:17
万里の長城は秦の始皇帝が造り上げたものじゃない?!
あの果てしなく伸びた、レンガ造りの塀を誰もが一度は写真やテレビで見たことがあるでしょう。
秦の始皇帝は、あれほどのものを何もない所から造り上げたと思われている方も多いかとは思いますが、実は始皇帝は元々あった長城をくっつけて長くしたに過ぎません。
秦の始皇帝が生きた戦国時代には、各国がみな、警戒すべき国境に長城を築いていました。その後、始皇帝は見事、中国を統一。そして、不要となった国内の長城は取り壊し、燕、趙、秦に元々あった長城を連ねて万里の長城を築き上げ、匈奴から攻撃に備えたのです。
ちなみに、当時の万里の長城は山では石を積み上げ、平地は、土を固めた簡単なものでした。今の立派なレンガ造りの長城になったのは、明の時代(15世紀~16世紀ごろ)になってから。
現在、テレビや写真で見ている、あの万里の長城は実は、始皇帝時代のものではなく、明の時代に完成された姿なのです。
とはいえ、始皇帝時代に造り上げた、万里の長城建設の大工事もすさまじかったといわれ、その為に民衆の不満が高まり、反乱が起きて秦の国が滅ぶきっかけの1つとなったと言われています+7
-0
-
1483. 匿名 2016/03/11(金) 13:13:15
サンタクロースにはモデルになった人物がいた!
クリスマスといえばサンタクロースを思い浮かべる人は多いでしょう。でも、なぜキリストが生まれたとされる12月25日にサンタクロースが子供たちにプレゼントを配るようになったのでしょう?
サンタクロースには、モデルとなった人物がおりました。4世紀、司教をしていたセント・ニコラスという人です。
あるとき、セント・ニコラスは町に貧しくて3人の娘たちをお嫁に出せないという人がいることを知ります。心優しい、セント・ニコラスは夜中に頭巾とマント姿で名を告げることもなく、窓から金貨の袋を投げ入れてあげました。その金貨の袋は偶然、暖炉の側に吊るしてある靴下に入ったそうです。
その後、セント・ニコラスはキリスト教の重要な人物の1人となり342年12月6日になくなります。
時は過ぎ、12世紀のフランス。偉大な彼、セント・ニコラスの亡くなった日の前日にあたる12月5日に修道女たちが夜中にこっそり、貧しい人々の家に食べ物などを送る風習がでてきます。この風習が世界中に広まると、やがて12月5日ではなく、クリスマスの日に贈り物を贈るように変わっていったのです。
貧しい家に金貨を送ったセント・ニコラス。その時の彼の姿が頭巾をマントをしていたことから、みなさんの知るサンタクロースの姿ができ、その金貨が偶然、暖炉側に吊るしてあった靴下に入ったことからプレゼントを靴下の中に入れるようになったのですね。
また、セント・ニコラスという名前。彼のこの名前がなまり、セントニコラス→サンタクロースとなりました。
オランダ語が訛って聖ニコラスがサン・ニコラース→サンクト・クラウス→サンタクロースとなったと言われています。
サンタさんの衣装やプレゼントを入れる靴下にもちゃんとした理由があるのですね。
セント・ニコラスさんの名前は日本では、それほど有名ではありませんが、その優しき行いは今も受け継がれているのです。
+8
-1
-
1484. 匿名 2016/03/11(金) 18:05:56
「赤ずきんちゃん」や「白雪姫」はグリム兄弟が考え出したものではない!
日本でも馴染みの深い「グリム童話」(正式には『子供と家庭のメルヒェン集』)ですが、こららの物語をすべてグリム兄弟が考え出したお話だと勘違いされている方も多いでしょう。
実は、この「グリム童話」は、グリム兄弟がドイツのあちこちを回り、昔話を聞いて書物にまとめたものなのです。
つまり、もともとあったお話をグリム兄弟が(多少手を加え?)文章にしたものが「グリム童話」な訳です。
グリム兄弟にお話を提供した人々が誰なのか?はっきりしたことは分かっていませんが、「グリム童話」の中の作品の多くの部分が、グリム兄弟の身近にいる人々から提供されたものであることが明らかになっています。
ちなみに、「赤ずきん」や「白雪姫」はグリム童話に先行して発表されたフランスのペローの童話集にも登場しております。(ちょっと内容は違うようですが・・・)
グリム兄弟は童話作家だと勘違いされることも多いのですが、実は彼らは言語学者でありドイツ文学者。童話作りは本職ではないのです。
+7
-0
-
1485. 匿名 2016/03/11(金) 18:08:26
アメリカ大陸を始めて発見したのはコロンブスではない!
1492年。コロンブスがアメリカ大陸発見は有名な話であり、学校でも習います。しかし、コロンブスが始めてアメリカ大陸を発見した訳ではありません。
さかのぼること、500年前。西暦1000年といわれています。ヨーロッパ人のレイフ・エリクソンという人が仲間と共にアメリカ大陸に到着しています。
彼らは、ブドウが実り、川にサケが泳ぐ豊かな土地を発見し(アメリカ大陸の北東部、ニューファンドランド島辺りと思われる)、そこで越冬したと言われています。翌年、レイフらは帰国し、その後アイスランドの人の北アメリカへの殖民が始まりました。
現在までに、エリクソンらが残していった糸車、鍛冶屋の跡なども発見されており、国際歴史公園として世界遺産に認定されております。
しかしながら、アイルランド人の北アメリカへの移住は結局のところ失敗に終わり、現在では、このレイフ・エリクソンのアメリカ大陸発見よりも歴史的に重要な意味を持つ(ヨーロッパ諸国のアメリカ進出のきっかけとなった)コロンブスのアメリカ大陸発見を重要視し学校などでは教えているのです。
ただし、コロンブスが始めてアメリカ大陸を発見したとは教えていないはず・・・。
レイフ・エリクソンの名は、教科書に注釈ですら出てきませんので、ヨーロッパ人で始めてアメリカ大陸を発見したのはコロンブスだと思われがちですが、実はその500年も前にすでに大陸に到着していた人物がいたのです。+9
-0
-
1486. 匿名 2016/03/11(金) 18:15:03
>>1479
カテゴリー参考になります(^^)
日本神話も勉強して、次回お話するときに備えたいです
ありがとうございます
生物の生存をかけた争いは絶えることがありません
歴史を正しく認識し、理解することで戦争は減るかもしれないと思いました
多くの情報をいただいて、とても感謝しております。完全に歴史に目覚めました(笑)
そして私の妄想にお付き合いいただき、ありがとうございました
時間の許す限り、よろしくお願いします
m(_ _)m+6
-0
-
1487. 匿名 2016/03/11(金) 18:39:52
>>1486
忘れられたり勝者によって変えられたり、隠されたりした歴史を考えるのはとても大切だと思います。
興味を持って頂けた事だけでも投稿した意味がありました。
ありがとうございますm(__)m
+6
-0
-
1488. 匿名 2016/03/11(金) 19:26:27
秦氏の謎
秦氏の来日は、公式記録(日本書紀)によれば、応神天皇の283年に弓月君が百済から127県の1万8670人を連れて、 日本に来たといいます。
弓月君の名前は、新撰姓氏録では融通王と呼んでいるそうで、 天山山脈の北にあるバルハシ湖に流れるイル川の上流にあった弓月国の「ヤマトゥ」から来たらしいのです。
この「ヤマトゥ」の近くに「ハン・テングリ(Khan Tengri)山」という山があって、 この山が「天狗」のルーツではないかと言われています。
応神天皇の283年の弓月君(融通王)の来日の前に応神天皇の父とされる仲哀天皇の199年に、 融通王の父である功満王(弓月の王)が日本を公式訪問したという(新撰姓氏録)。
佐伯好郎博士の研究によれば、弓月国(Kung-Yueh)は小国であるが、 キリスト教王国であったそうです。
当時の中国は、後漢(25~220年)の時代だったと思われますが、 上図でもわかるように弓月国あたりまで勢力を伸ばしており、 後漢の弓月国への圧迫や万里の長城の苦役の強制があったと思われます。
そこで、弓月国の人々(秦氏)は、満州を経て朝鮮に逃げたらしいのですが、 朝鮮でも迫害を受けて、日本に来てやっと、日本の天皇に助けられたのです。
秦氏が日本の天皇のために献身的に尽くした割には、それに対する政治的地位などの 報酬はなかったようですが、その理由は上記のせいかも知れません。
秦氏は、短期のメリットしかない政治的地位よりも、長期的な価値のある ビジネス的な特権(養蚕業やその流通の独占など)を望んだのではないでしょうか。
これは、弓月国の人々(秦氏)が信ずるキリスト教は、景教(ネストリウス派)であったでしょうから、 彼らは迫害を受け続ける歴史だった生活の知恵なのかも知れません。
そして、日本の天皇家だけには迫害を受けなかったことが、 彼らの意識を貫いていたでしょうし、もしかしたら天皇家のルーツかも知れないし、 いずれにしても日本人の文化や考え方のルーツであることは確かです。
日本へ渡ると初め豊前国(福岡県東部、大分県北部 )に入り拠点とし、その後は中央政権へ進出していったそうです。
大和国のみならず、山背国葛野郡(現在の京都市右京区太秦)、同紀伊郡(現在の京都市伏見区深草)や、河内国讃良郡(現在の大阪府寝屋川市太秦)、摂津国豊嶋郡など各地に土着し、土木や養蚕、機織などの技術を発揮して栄えました。
秦氏は相模原にも上陸し、現在の秦野市の地域に入植してその名を現在に留めています。
秦氏が創建に関係した主な神社・寺院
神社松尾大社
伏見稲荷大社
木嶋坐天照御魂神社(蚕の社)
大避神社 - 兵庫県赤穂市坂越にあり、秦河勝を祀る。対岸の生島には秦河勝の墓がある。
敢国神社
寺院
広隆寺+5
-0
-
1489. 匿名 2016/03/11(金) 20:54:04
ザビエルも困った「キリスト教」の矛盾を突く日本人
日本の各地でザビエルは布教するのですが、
出会った日本人が彼に決まって尋ねた事があります。
それは、「そんなにありがたい教えが、なぜ今まで日本にこなかったのか」ということでした。
そして、「そのありがたい教えを聞かなかったわれわれの祖先は、
今、どこでどうしているのか」ということだった。
つまり、自分たちは洗礼を受けて救われるかもしれないけれども、
洗礼を受けず死んでしまったご先祖はどうなるのか、
やっぱり地獄に落ちているのか・・・・・
当時の日本人はザビエルにこういう質問を投げかけた。
元来、キリスト教においては、洗礼を受けてない人は皆地獄ですから、
ザビエルもそう答えました。すると日本人が追求するわけです。
「あなたの信じている神様というのは、ずいぶん無慈悲だし、無能ではないのか。
全能の神というのであれば、私のご先祖様ぐらい救ってくれてもいいではないか」
ザビエルは困ってしまいまして、本国への手紙に次のように書きました。
「日本人は文化水準が高く、よほど立派な宣教師でないと、
日本の布教は苦労するであろう」と。当時の中国にも、韓国にも、
インドシナにもこうしたキリスト教の急所(?)を突くような人間はいなかったわけです。+8
-1
-
1490. 匿名 2016/03/11(金) 21:06:10
息抜きに小ネタを・・・
坂本龍馬は武器商人だった
坂本龍馬が設立した海援隊という組織は日本初の商社であり、武器弾薬を倒幕陣営に輸出していました。
現代でいう死の商人といわれている人ですね。
肉じゃがはビーフシチューの失敗作
東郷平八郎が外国で食ったビーフシチューを日本でも食いたいとゴネる
↓
レシピなんて知らないので材料だけ教える
↓
「何で味付けるんだよ」と言いながらも結局醤油で仕上げる
↓
何か違うけど(゚д゚)ウマー だそうです笑
首相官邸が出来た訳
初代総理大臣の伊藤博文は女遊びしすぎて破産 。
首相の家がないというのはヤバいということで首相官邸ができたそうです。
日本で初めて鉛筆を使ったのは伊達政宗
日本で初めて眼鏡をかけたのは徳川家康
日本で初めてパンツをはいたのは豊臣秀吉
時代劇「水戸黄門」で退治した今までの悪代官の数を合計すると、江戸時代のすべての代官を合計するより全然多い・・・。
慶応大学創設者の福沢諭吉大先生は禁酒中に「ビールは酒じゃねえよ」と言って
毎晩ビールを飲んでいたそうです。
枕草子で有名な清少納言は股間を丸出しにして女であることを証明したことがある
寛仁元年(1017年)、朝廷での勤めを引退し出家して尼になった清少納言は兄(清原致信(きよはらのむねのぶ))の家に身を寄せていました。その年の3月、兄と敵対する源頼光が暗殺者を送り込み一家を斬殺。男と勘違いされた清少納言は暗殺者達に殺されそうになったため、自ら股間を丸出しにし女であることを証明、窮地を脱したそうです。
裏話でした笑+8
-0
-
1491. 匿名 2016/03/11(金) 21:21:27
なぜ日本は鎖国したのか?
九州の戦国大名達が、戦争でさらった敵国の人間を、布教に来ていたキリスト教団体にダース売りしていたのです。
売られた日本人は、そこから奴隷売買ネットワークに乗って世界中に渡っていきました。
豊臣秀吉 の側近、 大村由己(ゆうこ) は、平戸に行った時の記録として、そこにいたポルトガルの輸送船が何百人かの日本人を手足を鎖で繋いで、船底に押し込んでいる様子を記録しています。
これを知った豊臣秀吉は、ツバ飛沫を飛ばしながら バテレン追放令 を発布。その後の 鎖国 への流れと繋がっていくのです。
日本人はよく働くので奴隷としてのコストパフォーマンスは高い。
凶暴なので、男は多少敬遠され気味でしたが、それでも重宝されたそうです。
大規模に プランテーション経営 をしていた インド では、ポルトガル人より 日本人奴隷の方が多かった という記録もあります。
当然、マニラーメキシコ航路で中南米にも渡っていったそうです。
中南米に、いくつかの記録が残っています。
アカプルコ 。
1597年に、ポルトガル商人の奴隷として、 ガスパール・フェルナンデス 、 ミゲル 、 ベントゥーラ という3人の日本人奴隷が渡っている記録があります。
アルゼンチンのコルドバ 。
日本人奴隷売買の証書が残っている。
1596年、 フランシスコ・ハポン(多分、フランシスコ会の日本人程度の意味かと)という日本人が、ディエゴ・ロッペス・デ・リスボアという奴隷商人から、ミゲル・へローニモ・デ・ポラースという神父に800ペソで売られたというもの。
このフランシスコ・ハポンは、奴隷生活の中で現地の言葉を習得し、自分が奴隷ではないと主張して訴訟を起こしました。
その結果、解放されることとなったそうです。
ブラジル。
歴史書のいくつかに、中国人や日本人の女性だけを満載したポルトガル船がアカプルコに向かっていた記録があるそうです。
酷い話ですよね・・・。
+8
-0
-
1492. 匿名 2016/03/12(土) 09:51:20
ではいよいよ最終日
最後までお付き合い願います
キリストが生まれたのは西暦1年でも12月25日でもない!
西暦とはキリスト教をひらいたイエスの誕生の年を1年とし、12月25日にイエスは生まれたと思われている方も多いと思われます。しかし、実はイエスの生年月日については、新約聖書などにも記されていないことから、かなりあやふやらしいのです。
そもそも西暦とは、530年頃、神学者ディオニシウス・エクシグスによって考え出されました。彼は、新約聖書の文章からイエスの生まれを計算。しかし、現在ではその計算は間違いであるという見方が一般的となっています。
また、12月25日の誕生についても、イエスの生まれた日が正確にわからない為、本来、冬至祭であった12月25日をイエス・キリストの誕生日として祝うようになったのではないかと言われています。
では、イエスの本当の生年月日はいつなのか?色々な説がありますが、興味深い説をいくつか・・・。
新約聖書の中にある「ベツレヘムでキリストが誕生した直後、誰も見たことのない星が西の空に輝き、3人の賢者にイエスの生誕を知らせキリストのもとへと導いた」という文に天文学者が注目。
この「見たことのない星(ベツレヘム星)」の正体とは紀元前7年に起きた土星と木星の異常接近であり、両惑星が重なり合って明るく見えたのではないか?というのです。土星と木星の異常接近は非常に稀であり、これならば「誰も見たことのない星が現れ・・・」という記載にも納得がいき、ベツレヘム星の正体がこの天体現象だとするならばキリストの生まれは紀元前7年9月15日ということになります。
いやいや、、このベツレヘム星とは紀元前2年6月17日の木星と金星が重なり明るく見えた現象であり、キリストの生まれは紀元前2年6月17日だという説。或いは紀元前12年のハレー彗星がベツレヘム星だという説など・・・。
また、他にも「大規模な人口調査が行われた年にキリストがベツレヘムで誕生した」という記述から大規模な人口調査が行われた西暦4年がキリストの生まれた年だという説もあります。
しかしながら、現在までイエス・キリストの正確な生年月日はわかっておりません。イエス・キリストに関する新たな資料でも見つからない限り永遠に謎のままなのかも・・・。
ただし、クリスマスはキリスト教やそうでない人にとっても特別で大切な日であることには変わりありません。ちなみに、クリスマスツリーのテッペンにつける星。あれは、キリスト誕生の日に輝いたベツレヘム星をイメージして付けるらしいですよ。
+6
-0
-
1493. 匿名 2016/03/12(土) 09:58:08
中国「Chaine」の語源って?
Chaineの語源は、秦の時代にあります。秦は紀元前221年に戦国時代を終わらせて中華を統一しました。
初めて中国を統一した秦が「Chin」。これを語源として、中国は「Chane」。漢民族は「Chainese」となったのですね。
+6
-0
-
1494. 匿名 2016/03/12(土) 10:03:21
コペルニクスが始めて地動説を唱えたわけじゃない
コペルニクスといえば地動説。地動説といえば、コペルニクスというくらい地動説を始めて唱えたのは、コペルニクスだと思われている方も多いと思います。
しかし、このコペルニクスが始めて地動説を唱えた訳では実はありません。
地動説は、ギリシア時代からすでにありました。天文学者のアリタルコスという人は太陽中心説を唱えていますが、この人が亡くなったのは紀元前230年。そして、コペルニクスが地動説を発表したのは1543年です。かな~り古くから実は太陽の周りを地球が回っているんじゃない?という考えはあったようです。
しかし、当時は、まだ太陽中心説を決定付ける証拠を提示することはできない。中世になっても、カトリック教会がアリストテレスの天動説を指示し、地動説を弾圧していた為になかなか地動説が世にでることはありませんでした。
とはいえ、天文学が進むにつれ天動説では合理的に説明が付かない惑星の動きなども発見されていきます。
そして、1543年ついにコペルニクスによる地動説の発表です。
このコペルニクスが書いた自署のなかでも、ちゃんとアリタルコスの地動説が紹介されています。
つまり、最初に地動説を唱えたのはコペルニクスではありませんが、ちゃんと本として出版したのがコペルニクスということになります。
ちなみに、じゃ、ガリレオガリレイは何だ?と思われる方もいると思いますが、ガリレオはコペルニクスの地動説をより決定的なものにした人です。+7
-0
-
1495. 匿名 2016/03/12(土) 10:08:58
1776年アメリカ独立は嘘?
1776年7月4日にアメリカは独立宣言を出し、現在でもアメリカでは7月4日を独立記念日としています。
しかし、アメリカの独立が正式に列強国に認められたのは、パリ条約によって・・・。つまり、1783年9月3日のパリ条約終結で初めてアメリカの独立が世界的に認められたわけです。
この辺りは実に微妙なのですが、「独立しま~す!」って宣言した時よりも支配していた国が支配権を放棄した時を独立記念日としている場合も多い。
となると厳密にいえばアメリカの独立は1776年の7年後の1783年9月3日ともいえるわけですね。
まぁ、独立宣言を出した1776年7月4日がアメリカ独立革命の始まりともいえますのでアメリカに住む人々にとっては、この日の方がパリ条約によってイギリスから独立を勝ち取った日よりもインパクトが強かったんでしょうね。
+3
-0
-
1496. 匿名 2016/03/12(土) 10:14:22
ヒトラーとアインシュタイン、そして原爆との関係
アインシュタインといえば、相対性理論で有名ですね。彼が、特殊相対性理論と光粒子仮説を唱えたのが1905年。なんと、アインシュタイン26歳という若さのころでした。
このアインシュタインがユダヤ人であったことも有名ですね。1933年にはヒトラーがドイツの首相となりユダヤ人を徹底的に迫害していきます。これに対して、当時アメリカに渡っていたアインシュタインは帰国拒否宣言を行い、ヒトラー政治への抗議をしました。
アインシュタインが自らの身を案じて、帰国拒否宣言を出したと思われがちですが、その頃は、まだユダヤ人虐殺などは行われておりませんでした。それどころか、あれほど酷い虐殺を行うなど誰も想定していない頃。アインシュタインは、自らの身の安否というより、やはり、ヒトラーへの抗議の為の帰国拒否だったと思われます。
アインシュタインは、その後、ロンドンに落ち着き、1937年に再びアメリカへ戻ります。そして、ドイツが原爆開発に着手したとの情報を得て、アメリカ大統領ルーズベルトに原爆製造を進言する手紙に署名をしました。ドイツには、核分裂を発見したハーンや優秀な物理学者ハイデルベルクがいます。そのドイツが原爆開発に乗り出したと聞き強い危機感を抱いたのでしょう。
とはいえ、アメリカの核は、ドイツの核に対する抑止力の為であり、ドイツはもちろんのこと、まさか日本に原爆を投下するなどとは、当時の科学者たちは想像もしていなかったといいます。しかし、結局、原爆は広島、長崎に投下され、アインシュタインらは大きな衝撃を受けたそうです。
その後、アインシュタインは、晩年平和活動に力を注ぎ、日本にも訪日しています。
+8
-0
-
1497. 匿名 2016/03/12(土) 10:38:32
海の王者・ラピタ人
ラピタ人(英: Lapita)は、人類史上初めて遠洋航海を実践し、太平洋の島々に住み着いたと思われる民族です。
1952年、ニューカレドニアで発見された土器が「ラピタ土器」と命名されたことから、この文化がラピタ文化と呼ばれるようになりました。
彼らは3300年ほど前にニューギニアの東の島々から旅立った人々で、ポリネシア人の祖先ですが、多くの謎に包まれています。
タロイモなどを栽培する農耕民族でもあり、海洋活動に特化した文化を持っていました。
航海術を駆使してわずか500年ほどの間に、バヌアツ、ニューカレドニア、フィジー、トンガやサモアの島々に拡散し、ラピタ文化を広く展開しました。
ポリネシアの島々の人々は、何千キロも海洋を隔てているにもかかわらず、互いによく似た言語を話すことで知られています。
また長い間土器を持たなかった太平洋地域にあって、高度な技術「ラピタ土器」を残したラピタ人はアジア人とポリネシア人をつなぐミッシング・リングとして注目を集めています。
また六分儀、クロノメーター、方位磁針といった航法器具を用いずに、数千キロメートルに及ぶ遠洋航海を行っていたと考えられています。
遠洋航海に乗り出す船は、星・星座や太陽、月などの天文現象と、風や波、雲、鳥、海の色などの自然現象を最大限に利用したのである。とくに船の針路や島の方位を示す星座コンパスには500以上の星・星座が使われ、その出没位置などから方位を定め、船を導いたとされます。
およそ3300年前にビスマルク諸島へ突如として出現し、西ポリネシアのサモアまで一気に拡散したラピタ人ですが、その後およそ2500年前までにその痕跡を消してしまいます。
興味深いのは、彼らは、ある時から土器を作るのをあっさりとやめてしまったこと。だから今、ラピタ土器を作っている島はどこにもないのです。
彼らはどこから来てどこへ行ったのでしょうか?
+4
-0
-
1498. 匿名 2016/03/12(土) 11:26:04
>>1492
とうとう最終日ですね*\(^o^)/*最後まで沢山の投稿ありがとうございます!!このトピが終わるまで楽しませていただきます( ˘ω˘ )+4
-0
-
1499. 匿名 2016/03/12(土) 12:23:53
参加することに意義があるってどゆこと?
オリンピックのたびに引用されたり、学生時代には部活などの活動でも一度は耳にしたことがあるでしょう。
「参加することに意義がある」
この言葉は、近代オリンピックをひらいたフランスのピエール・ド・クーベルタンの言葉です。
近代オリンピックの第1回は1896年アテネにて行われます。当時は、世界中で植民地の争奪戦が激しさを増していた頃。1893年にはハワイ革命、1894年には日清戦争、スペイン・モロッコ紛争。1895年、イタリア・エチオピア戦争、キューバ暴動。1896年イギリスのスーダン遠征・・・。
そこで、スポーツを通じ世界に平和を訴えようと古代オリンピックを復活させることになったんです。
しか~し!各国は自国の威信をかけメダルを争うばかり・・・。
1908年の第4回オリンピック(ロンドン)では、綱引き競技にてアメリカチームが運動靴で参加しているにも関わらずイギリスチームがスパイクを履いていたことでアメリカは試合をボイコット。これが始まりとなり、陸上男子800メートルではアメリカの選手がイギリスの選手を押した押さないで乱闘にまで発展しそうに・・・。
これを見たクーベルタンが演説のなかで語った言葉が
「勝つことではなく、参加することに意義がある」
だったのです。
現在では、いろいろな意味での解釈がありますが、オリンピック本来の意義を見失い、争う状況を見て発せられた嘆きのような言葉だったんですねぇ。
ちなみに、クーベルタンは「参加することに意義がある」の後に「美しく負けるのも大切である」と述べています。
考えさせられますねぇ。
+6
-0
-
1500. 匿名 2016/03/12(土) 12:26:15
大西洋無着陸飛行を最初に成功させたのリンドバーグじゃない
1927年5月20日~21日でリンドバーグは大西洋を飛行機で無着陸飛行を成功させました。これにより、25000ドルもの賞金を獲得!地位と名声を得ることになったのです。
しかし、リンドバーグが始めて大西洋無着陸飛行を成功させた訳ではありません。リンドバーグの飛行よりも8年前。1919年にアメリカのオールコックとブラウンの2人がニュージーランドからアイルランドまでの飛行に成功しております。これは、なんと飛行機が発明されてから、たった16年後のこと。
大西洋無着陸飛行に始めて成功したのは、実は、この2人なのです。
では、なぜリンドバーグが彼らよりも有名になってしまったのかというと、リンドバーグは何とたった1人で大西洋を無着陸で飛行して見せたからです。
パイロットが2人いれば、仮眠をとり、休息をとりながら飛行を続けることは出来ますが、リンドバーグは33時間29分ものあいだ一睡もせずに飛行機を操縦し続けたのです。
僅かな操縦ミスが命取りになるような状況でリンドバーグは33時間半も眠ることなく飛行機を飛ばし続けた訳ですから、その集中力と忍耐力は凄すぎる!
当時の人々は、無謀とも思える彼の挑戦に息を呑んで見守り、見事成功した瞬間には歓喜の声を上げたことでしょう。
感動的なリンドバーグの大西洋無着陸飛行は映画などにもなり、あまりにも有名になってしまったことから、リンドバーグが始めて大西洋無着陸飛行を成功させたと誤解されることも多いのですが、実は始めて大西洋無着陸飛行を成功させたのはオールコックとブラウンなのですよ。
+6
-0
コメントを投稿する
トピック投稿後31日を過ぎると、コメント投稿ができなくなります。関連トピック
関連キーワード
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する

 出典:blog-imgs-42.fc2.com
出典:blog-imgs-42.fc2.com