-
1. 匿名 2024/03/01(金) 15:23:10
■生産者が倒産する未来も
■流動食給食
ここで考えたいのは「なぜ、死亡事故が起きた場合に問題視される食材と問題視されない食品があるのか」ということである。
厚労省が運営するe-ヘルスネットが食品ごとの窒息危険度を掲載しているが、餅の危険度は段違いである。「1日1億回国民が食べたと仮定した場合の事故発生件数」を表す「一口あたり事故頻度」を見てみよう。なお、必ずしも死亡事故ではない。
餅:6.8~7.6
ミニカップゼリー:2.3~5.9
飴類:1.0~2.7
こんにゃく入りミニカップゼリー:0.14~0.33
パン:0.11~0.25
肉類:0.074~0.15
魚介類:0.055~0.11
果実類:0.053~0.11
米飯類:0.046~0.093
こんにゃく入りミニカップゼリーは様々な自治体が注意喚起をして、子供や高齢者は食べないよう指導しているというのに、餅の50分の1ほどの0.14~0.33。メーカーはサイズを小さくしたりハート形に代えたり、子供と高齢者が苦しむ顔を蓋に掲載して×印をつけるなど対策を施した。だが、餅は毎年のようにお雑煮で食べられて正月に高齢者が多数死亡する。各地の名物で納豆餅やらずんだ餅などもある。
■本質的な問題は食べ方
そもそも、本質的な問題は食材にあるのではなく、食べ方にあるのだ。慌てて食べるから喉に詰まらせるのだ。余裕を持って食べるべく、給食の時間を延ばしてもいいではないか。或いは高齢で咀嚼能力が低下している場合だ。それはこんにゃくゼリーしかり、餅しかりである。種なし巨峰の皮を勢いよく押し、口の中に吸い込んでも危険だ。+174
-6
-
22. 匿名 2024/03/01(金) 15:27:41
>>1
統一教会が自民党に作らせたこども家庭庁が子供一人当たり634万円もの予算を毎年食い散らかしていて日本人は窒息しそう![]()
+36
-4
-
35. 匿名 2024/03/01(金) 15:29:11
>>1
今の日本では過保護性免疫不全症候群が大量発生していて、賞味期限でしか食品を食べていいかどうかの判断が出来ない子供や、この事件のように何かを食べると喉に詰まって死ぬんじゃないかと、超神経質に子供に過敏・過保護になる親が多いのが問題だわ。+22
-6
-
65. 匿名 2024/03/01(金) 15:34:36
>>1
食べ方に問題あるけど
実際、給食で事故が起きたら学校とか担任の責任になるからね。
親が責任持って指導するのが前提だけど、学校給食では指導が必要な危険がある食材は提供しないでいいような。+5
-3
-
112. 匿名 2024/03/01(金) 15:51:41
>>1
うずらの卵が悪いわけじゃないし、好物だったから給食の八宝菜はうずらを大事に食べたよ+5
-2
-
115. 匿名 2024/03/01(金) 15:53:35
>>1
他職種、介護職だけど、できるなら危ない食材は避けたいと思ってしまう。
事故起きた時の大変さを知ってるからさ、あえてうずらの卵出さなくてもいいかなと。
いろんな食材を食べることは大事だけど、リスクは減らしたいな。+3
-2
-
118. 匿名 2024/03/01(金) 15:55:18
>>1
子供のために増税だ!![]()
+0
-3
-
152. 匿名 2024/03/01(金) 16:20:03
>>1
うずらは窒息を起こしやすい食材と、小児学会は言ってるらしいね。確かに大きさといい、形状といい、ツルッと入ってしまえば軌道が塞がれそう。
それに低学年はちょうど歯が生え変わる時期で、痛くて噛みにくかったりするかもしれないよね。+9
-1
-
175. 匿名 2024/03/01(金) 16:47:15
>>1
> 本質的な問題は食材にあるのではなく、食べ方にあるのだ。
給食の時間をもっと長く取る。それだけで解決じゃん+0
-0
-
198. 匿名 2024/03/01(金) 17:39:32
>>1
蒟蒻畑は加工品だから改善の余地はあったけど、他のは切り方変えるとかしかないかもね+1
-0
-
211. 匿名 2024/03/01(金) 18:19:54
>>1
こうやって考えると…マンナンライフは頑張ってるよね
あれはぶっちゃけ幼児に食べさせた方が悪いって話になるのに+16
-0
-
216. 匿名 2024/03/01(金) 18:47:05
>>1
子を亡くした親御さんには悪いけど蒟蒻ゼリーに関してだけは理不尽な八つ当たりだと思ってる
凍らせて丸ごと与えて喉に詰まらせて亡くなったのがメーカーのせいってどうなの+7
-3
-
218. 匿名 2024/03/01(金) 19:06:02
>>1
運転する人のミスで交通事故が起こったら車を作った会社が悪いわけではないのと同じだと思う+1
-2
-
220. 匿名 2024/03/01(金) 19:27:03
>>1
どんどん食べられるものが減っちゃうね+3
-2
-
255. 匿名 2024/03/02(土) 13:35:50
>>1
マイナス覚悟だけど、危険な食材は一人ひとり目の届かない学校や保育園の給食では出さないでほしい。
危険が伴う食材はしっかり見られる家で与えるから。自分がいない時に事故が起こるほど無念なものはない。+2
-2
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する



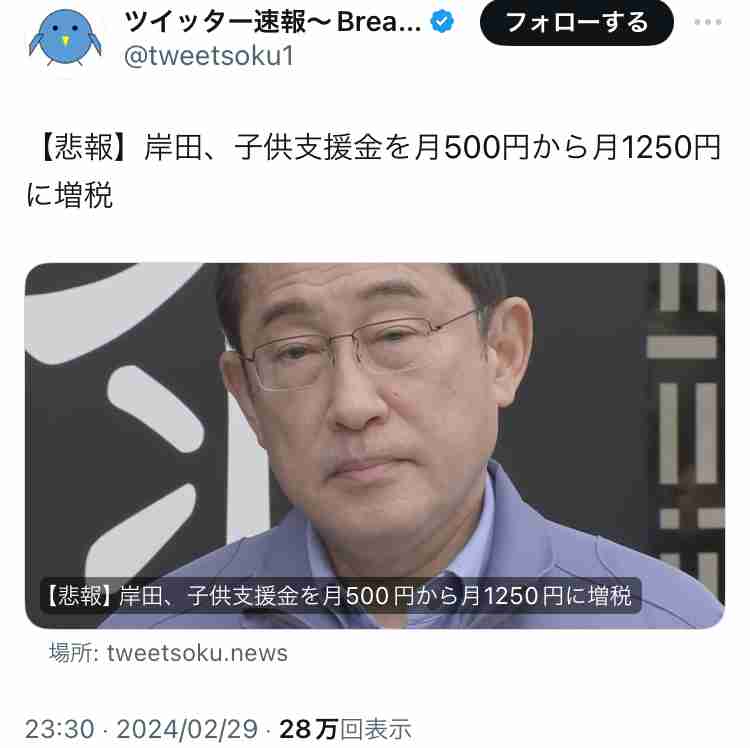
…メディアも重大事故としてこの件を扱っているが、いきなりこの対応になるのは極端ではないか。もちろん、児童が命を落としたことは痛恨事であり、二度と同じ事故が起きないよう対策を徹底すべきだろう。ただ、うずらの卵は給食で何十年にもわたって採用され続け、小学生の遠足の弁当にも多く使われてきた。それが2024年、この事故が1例あっただけで、「うずらは危険」という空気感が一気に生まれてしまった。せめて学年別で使う食材を変える、といった柔軟な対応もできたのでは……。本稿では【悪者にされる食品】【悪者にされない食品】について考えてみる。